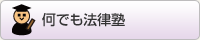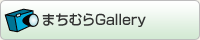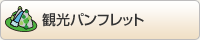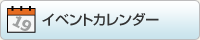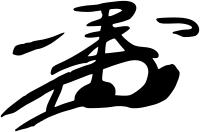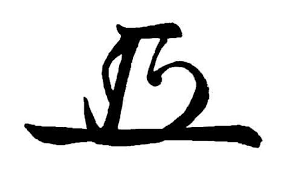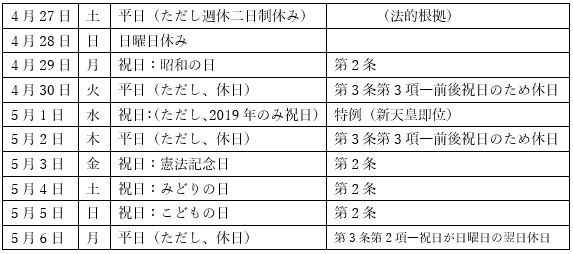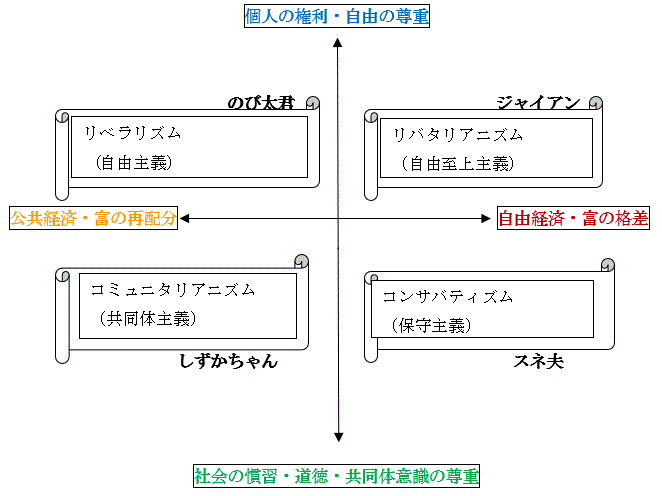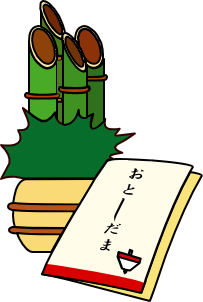.
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
<問題>
地方税の督促状などの文書について、納税者からすると郵便ポストに知らないうちに郵送されており、他の郵便物と一緒に間違って破棄したりする危険性があるのですが、重要な書類を普通郵便で送付すること自体問題ではないでしょうか。
仮に、納税関係の種類だけでなく、役所からの水道料や下水道使用料などの督促状なども普通郵便で送付されることがあるのでしょうか。
≪解説≫
1.地方自治体が納税者等に普通郵便で書類を送付した場合に、普通郵便では実際に宛名人へ到達したかどうかの記録は残りませんし、把握することもできません。そういう場合には、郵便を受けたとされた本人は、問題文のように自分で誤って破棄している場合でも、「自分はそのような郵便は受け取っていないし、そのような文書は見ていない。大事な文書であれば、書留郵便か配達証明郵便で送るべきだろう!」と抗議してくると思われます。
ただ、実際には、本当に郵便が届いていない場合(郵便窃盗事故、郵便廃棄隠匿事故等)もあり得ますし、そもそも送っていないという可能性もあります。そういう争いを生じさせる書類郵送の方法はいかがなものか、と思われる一般市住民は多いだろうと思われます。
2.納税関係書類の送付が通常の取扱いによる郵便で行われた場合については、地方税法第20条第4項及び第5項の定めがあります。
[地方税法第20条]
1 地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)又は還付に関する書類については、その住所、居所、事務所又は事業所に送達する。
2~3(省略)
4 通常の取扱いによる郵便又は信書便により第一項に規定する書類を発送した場合には、この法律に特別の定めがある場合を除き、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物(第二十条の五の三及び第二十二条の五において「信書便物」という。)は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
5 地方団体の長は、前項に規定する場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、宛先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。
県税事務所の納税通知事務を例にあげて、簡単にこの条文の内容を説明しますと、
「一般の郵便で税金に関する書類を送った場合は、『通常到達すべきであった時』にその書類が届いたと推定する。ただし、この規定を使うためには、県税事務所は税金に関する書類の名称・送付先の氏名・宛先・発送年月日を確認できる記録を作っておかなくてはならない」とされています。
つまり、県税事務所が納税通知書や督促状の発送時に、送り先や発送日の記録を残しておけば、宛先である納税義務者に実際に届いているかどうかに係わらず「通常到達すべきであった時」、例えば普通郵便で発送し宛先が同じ県内なら(常識的に考えて)発送から2~3日程度後には発送先へ到着したとみなしてよく、だから、費用の安い普通郵便で送ってよい、という理解がなされています。
そして、このような定めがある以上は、納税義務者が「いや、本当に届いていないんだ」と主張するためには、納税義務者の側が引越しや郵便事故等で届かなかったことを立証しなくてはいけないのです。
このような法律の定めをした理由は、一つは、納税通知などの多数の者への通知について、行政上の手続きの軽減と費用負担軽減を図る趣旨があり、もう一つは、そもそも税を納めるのは国民・住民の義務であり、本来は通知がなくても国民のほうから納めるべきものであるという税に関する理念があるのだろうと思われます。
3.それでは、税関係書類ではなく、それ以外の公文書、公的な通知書の送付の場合にも、普通郵便やはがきによる送付で良いのでしょうか?
私が行政の法律相談等の際に個人的に認識できた範囲では、水道料金や下水道料金の支払通知書は、「はがき」で行われているようですし、公営住宅の延滞家賃の督促も「普通郵便」で行われているのではないかと思います。行政処分通知書を普通郵便で送付している例もあったかと思います。
実は、地方自治体の事務手続きとしての書類の送達については、地方自治法第231条の3第1項、第2項、第4項に次のような定めがあり、地方税の規定を準用しています。
「1 分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。」
「2 普通地方公共団体の長は、前項の歳入について同項の規定による督促をした場合には、条例で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。」
「4 第一項の歳入並びに第二項の手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。」
この規定によれば、書類の送達に関する地方税法第20条第4項、第5項の適用があるのは「分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入」という「債権」の「徴収・還付」に限られるということになります。
(1)「分担金」とは、特定の事業により特定の利益を受ける受益者に経費の分担を求めるもので(地方自治法第224条)、下水道事業負担金(都市計画法第75条)などがあります。
(2)「使用料」とは、公の施設(地方自治法第244条)の利用の対価であり(地方自治法第225条)、下水道使用料(下水道法第20条)などがあります。
なお、水道使用料は、水の売買代金としての私債権であり(東京高裁平成13年5月22日判決、最高裁平成15年10月10日判決)、使用料としての公債権ではないとされ、普通財産の使用(公営住宅の使用許可)の対価も契約による賃料債権(私債権)であり(最高裁昭和59年12月13日判決)、使用料としての公債権ではないとされています。
公立病院の診療代金請求権も、同様に私債権であるということになります(最高裁平成17年11月21日判決)
(3)「加入金」とは、慣習により公有財産の使用権(入会権等)を有しており、新しく使用を許されたものに対して「特別の使用権付与の対価」として一時的に賦課するものを言います(地方自治法第226条、第238条の6第2項)。
(4)「手数料」とは、特定の者のためにする事務又は役務の提供の反対給付としての金銭であり(地方自治法第227条)、身分証明書や印鑑登録証明書の発行手数料等などがあります。
(5)「過料」とは、行政上の義務違反者に対して制裁として科せられる行政秩序維持のための制裁であり、地方自治法第14条第3項は、「普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる」と定めています。この規定は、平成11年の「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」によって加えられたものです。さらに、同法第228条は、「詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者については、条例でその徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する規定を設けることができる」とし (第3項)、かつ、「分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関しては、次項に定めるものを除くほか、条例で五万円以下の過料を科する規定を設けることができる」としています (第2項) 。(これらの規定は、いずれも過料を科すには、条例の定めを要するものとしていますが、以上のほかに、同法第15条第2項は「普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる」と定めていて、規則の制定は、首長の権限に属する事務であるので(同法第15条第1項)、その点において、条例に定める過料と規則に定める過料と所管の線引きがされることになりますが、過料の徴収等の手続きには差異はありません。)
(6)「普通地方公共団体の歳入」とは、「会計年度ごとの一切の収入」を意味し、地方税、分担金、使用料、加入金、手数料、過料、地方債、地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、財産売払収入金、他会計からの繰入金」が含まれるとされています。
この解釈として、①普通地方公共団体の歳入となるものであれば、その債権は公法上の債権であろうが、私債権であろうが、その徴収手続には、到達推定規定(地方税法第20条第4項、第5項)の適用があるとする見解と、②到達推定が働くのは地方自治法第231条の3の公法上の債権の例に示されるものに限定され、私債権については到達推定は認められないので、私債権の送達には配達証明を付するなどが必要であるとする見解もあるのですが、私見としては、地方公共団体が一括送付を必要とする事情は、公法上の債権であろうが、私債権であろうが変わらないことから、前者の見解(私債権でも歳入として調定されれば到達推定が働く)でいいのではないかと考えます。
しかし、歳入に全く関係しない「行政処分の通知」や「監査手続きでの監査請求人への通知」等については、その到達の有無について争いが生じた場合に、到達推定規定は全く働かないので、相手方住民に到達したということを行政側が立証しなければいけません。
従って、このような書類の送付方法としては、その到達を直接立証できる、「配達証明郵便」又は「直接の交付」(受取書受領)によって行わなければならないだろうと考えています。
4.到達推定規定の適用に関する判例
地方自治体の歳入債権の徴収文書を普通郵便で送付した場合には、規定上「到達の推定」があるだけであり、推定である以上は、納税義務者から、その推定を破る証拠が提出されると、「到達していない」と認定される場合もあるということになります。
例えば、本人への未到着以外に、近隣全体に郵便物未到着例が多く発生していたとか担当郵便局員が未配達隠匿していたというような事実が立証される場合などが考えられます。
そのような観点で、問題となった事例の判決がWeb上で二例紹介されていましたので、引用しておきます。
○東京地裁平成27年4月28日判決(判例集登載なし―(情報提供:株式会社ロータス21)
非居住者である原告が指定した納税管理人の住所に納税通知書が到達しなかったことを理由に、原告がY区に対し納税通知書の送付が前提となる督促処分の取消しを求めた事案において「自己への書籍が配達されなかったという出来事の他に、自己の住所に郵便物などの不達(誤配など)が相当数発生していたと認めるに足りる証拠はなく、地方税法第20条第4項の推定を覆すに足りないので、送達があったものと判断する。」
○東京地裁平成27年4月23日判決(判例集登載なし―情報提供:株式会社ロータス21))
納税通知書の不達で期限内納付ができず延滞税が発生したとして、原告がY市に対し延滞税の還付を請求した事案において、「地方税法第20条第4項の推定規定によれば、送達の立証義務は徴収者が負うものではなく、納税者である原告において、近年の郵便物の不配事件の発生の事情や納税通知書が送られていれば納税しない理由はないという事情は、本件納税通知書に関し郵便事故が発生したことを伺わせるほどのものとは言えないので、送達があったものと判断する。」
5.結論
<問題>への回答としては、「重要な書類を普通郵便で送付すること自体問題ではないでしょうか。」については、問題がないとは言えませんが、郵便が着いたかどうかについては、地方自治体が法的に救済される場合があります。
「仮に、納税関係の種類だけでなく、役所からの水道料や下水道使用料などの督促状なども普通郵便で送付されることがあるのでしょうか。」については、普通郵便でなされる例が多いと思います。その場合にも郵便が着いたかどうかについては、地方自治体が法的に救済される場合があります。
以 上
学校の先生は私生活上の不祥事を起こすと、厳しい処分を受けちゃうのですか?~学校教職員の不祥事とその責任の重さについて~
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
(問 題)
学校の音楽の先生Xは音楽作成ソフトウエアを無断複製してインターネット上で販売したことから、警察が学校や自宅を捜索する事態となり、刑事問題になりました。
先生Xは、先生を辞めなくてはいけなくなるのでしょうか?
(事案の概要)
①Y公立中学校の音楽教諭X(管理職ではない)が、
②生活費の不足を補うために、
③著作権法違反であることを認識しながら、市販の音楽作成ソフトウエアを無断で複製し、インタ―ネットオークションで複製品60本を販売し30万円の利益を得た。(本件非違行為)
↓↓
④その結果、警察によるX教諭宅、学校のX使用パソコン等の捜索が行われた。(この点は報道されていない)
⑤Xは著作権会社に謝罪し被害弁償の申出をした結果、示談金170万円(推定損害348万円)で和解した。
⑥著作権会社は、上記示談により、Xを宥恕する旨の上申書を検察庁に提出し、検察庁は著作権侵害罪につき、不起訴処分にした。(担当検事は不起訴処分とした際、Xに対して教員を続けることができるように勇気づける言葉を贈った)
⑦処分行政庁は、本件非違行為につき、Xを懲戒免職処分にし、処分行政庁によりXの懲戒免職処分が公表されたことで報道機関により報道された。
理由
a 教職員は髙倫理と廉潔性が求められる。重大な非違行為である。
b 本件非違行為は他人の財産権を侵害する金銭窃盗と罪責が近似しているので、窃盗犯罪に準じて厳しい処分となる。
*窃盗罪法定刑「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(刑法第235条)
*著作権法違反「10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金又は併科」(著作権法第119条第1項)
⑧XはY人事委員会へ不服申立をし、Yの知事に対する審査請求を経て、懲戒免職処分取消訴訟を提起した。
(参照判例:札幌高裁判決平成28年11月18日-判例時報2332号-90頁、判例地方自治418号50頁)
○著作権法に違反するソフトウエアの無断複製及び販売行為を反復継続した公立学校教員に対する懲戒免職処分及び退職手当等の全部を支給しないこととする処分について、当該非違行為は極めて重大であるとまではいえず、その動機をもって極めて悪質であるともいえない等として、社会観念上著しく妥当性を欠き、処分行政庁がその裁量権の範囲を逸脱した違法なものとされた事例。
(解 説)
1.公務員の場合の解雇(免職)と労働契約法
公務員も憲法上の労働者であるのですが、公務員の勤務関係(労働関係)は、「契約」ではなく「任用」関係であり、労働契約に関する労働契約法は適用されません(労働契約法第22条第1項)。
2.懲戒処分の位置づけ
(1)民間労働者に関しては、労働契約上の付随義務である企業秩序遵守義務があり、その違反になる労働者の行為等については、使用者は就業規則の定めるところにより、制裁としての懲戒処分をすることができるとされています。ただし、その懲戒処分も使用者が自由に行えるものではなく、懲戒処分が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には、懲戒権を濫用しているものとして懲戒処分は無効となります(労働契約法第15条)。
(2)公務員の場合は、地方公務員法の定めがあり「公務員としてふさわしくない非行がある場合に、その責任を確認し、公務員関係の秩序を維持するために課される制裁」として任命権者に懲戒権限が認められています(地方公務員法第29条、最高裁判例昭和52年12月20日)。ただし、その懲戒処分も任命権者が自由に行える(自由裁量)ものではなく、懲戒権の行使が「社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合」に限り違法となるとされています。
判例上、公務員に対する懲戒処分の適否については、「公務員の場合には,懲戒処分として戒告,減給,停職又は免職の処分をすることができるところ,職員が懲戒事由に該当する場合に,懲戒をするか否かの判断及び懲戒をするときはどのような処分を選択するかの判断は,内部の事情に精通し,平素から職員の指揮監督の衝に当たる懲戒権者の裁量に委ねられていると解するのが相当であって,懲戒権者は,懲戒をするか否か及び懲戒をするときはどのような処分を選択するかを,懲戒事由に該当する行為の原因,動機,性質,態様,結果,影響等のほか,当該職員の上記行為の前後の態度,懲戒処分等の処分歴,選択する処分が他の職員ないし社会に与える影響等の諸般の事情を総合的に考慮し,その裁量的判断によって決定することができるというべきである。したがって,懲戒権者がその裁量権を行使してした懲戒処分としての免職の処分の適否を裁判所が審査する場合,裁判所は、懲戒権者と同一の立場に立って,懲戒をすべきであったか否か及び懲戒をすべきであったときはどのような処分を選択すべきであったかについて判断した上,その結果と免職の処分とを比較して,その適否を論ずべきではないのであって,懲戒権者がその裁量権を行使してした免職の処分は,それが社会観念上著しく妥当を欠き,懲戒権者が,その裁量権の範囲を逸脱し,又はそれを濫用してしたものであると認められる場合に限り,違法となるというべきである(最高裁判所昭和52年12月20日第三小法廷判決・民集31巻7号1225頁、最高裁判所平成2年1月18日第一小法廷判決・民集44巻1号1頁参照)。」としています。
3.私生活上の非行を理由とする懲戒処分の可否について
本件は,Xの職務外の私生活上の非行(音楽教育を離れて,私生活上の生活費不足を補うためにソフトウエアの違法複製を自宅パソコンを介してインターネットオークションで販売していた)が懲戒処分対象行為であるが、職務上の行為とは言えないことから、そもそも職務上で要求される義務違反(懲戒処分対象行為)になるのかどうかが問題となります。(なお、販売行為の違法性については、公務員においては、営利目的事業の兼業禁止の地方公務員法第38条違反も考えられますが、著作権侵害罪としての刑事処罰性に準じた違反のほうが強いので、後者のみの非行を問題にしているようです。)
(1)民間労働者の場合には、会社の社会的評価に重大な悪影響を与えるような従業員の行為については、それが職務遂行とは直接関係のない私生活上で行なわれるものであった場合でも、これに対して会社の規制及び懲戒権を及ぼすことができます。ただし、その行為により「会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に評価される場合」でなければならないとされています。
(2)公務員の場合には「公務の円滑な運営の確保と並んでその廉潔性の保持が社会から要請ないし期待されていることから,一般企業(民間企業)の従業員と比較して,より広くかつより厳しい規制が課されている」(最高裁判決昭和49年2月28日:国鉄中部支社事件判決)として、職務と関係のない純然たる私生活上の行為についても厳格な規制(懲戒処分対象性)が及ぶこととなっています。少なくとも、非違行為と職務や地位との関連性が強い事例では懲戒免職処分の有効性は認められる場合が多く、関連性が少ない事例の場合には、懲戒処分の程度は低くなるという関連性において、総合判断されるという立場になろうかと思われます。
4.本件判決の分析(札幌高裁判決平成28年11月18日-判例時報2332号-90頁)
まず、本件一審の判決(札幌地裁平成28年6月14日判決)は、「本件免職処分及び本件退職手当支給制限処分は、いずれも処分行政庁がその裁量権の範囲を逸脱し又はそれを濫用してした違法なものではなく、適法な処分である。」としていますが、本件高裁判決(札幌高裁平成28年11月18日判決判例時報2332号-90頁)は、結論としては、「懲戒処分の裁量権の範囲を逸脱しており、懲戒免職処分は違法である」としています。その理由は次のとおりです。(なお、本高裁判決の上告審(最高裁判決平成29年6月13日)は上告を棄却しており、本高裁判決の結論が確定していますので。高裁判例を引用しておきます。)
(1)指針基準の尊重と公平性の観点
懲戒処分として、戒告、減給、停職又は免職の処分のうち、免職を選択したことが、その裁量権を逸脱し、又はそれを濫用したものであるかについて検討するが、
その判断は、処分行政庁が自ら定めている原判決別紙の懲戒処分の指針によることが、平等取扱いの原則(地方公務員法第13条)及び公正の原則(同法第27条第1項)に照らして相当である。
(2)著作権法違反(無断複製販売)と窃盗との対比(指針基準の準用の適否)
懲戒処分の「指針」は、金銭事故(公金又は学校徴収金の横領・窃取)及び他人の財物の窃取の量定について免職を基本としているところ、処分行政庁は、本件非違行為が他人の財産権の侵害である金銭事故や窃盗に近似するとの評価のもとに、刑法等での量刑(*窃盗罪法定刑「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(刑法第235条)、*著作権法違反「10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金又は併科」)と比較するなどした上で、本件免職処分をしたものであり,適法である旨主張している。
しかしながら、本件非違行為についての処分行政庁の上記評価は誤ったものである。
窃盗は、行為の反道義性、反社会性が国民一般に認識されている最も典型的、古典的な自然犯であるのに対し、本件非違行為は、産業政策的な目的で保護されているソフトウエアに対する侵害行為であることからすると、その性質は大きく異なっている。(すなわち、ソフトウエア(プログラム)についての著作権法違反の罪は、いわゆる法定犯として、著作権法において、産業政策的な目的から、保護すべき著作権の内容や範囲及び著作権侵害となる行為が規定されており、著作権法の保護の対象となったのも昭和60年の改正法によってであり、その内容は今後も変更されることが予想されるものである。背景にはデジタル技術の発展による複製の容易化とインターネットの普及があるが、後者にはネットにおける自由を求める運動もある。また、ソフトウエアの使用は、通常、複製作業を伴うものであり、複製物の所有者は同法第47条の3の定める範囲で適法に複製することもできる。違法コピーの存在は、かねてからの社会問題であるが、ソフトウエアの提供者において、市場占有率の確保などのためにコピーを許容している場合もある。このような性質の違いから、一般に、行為者にとって、ソフトウエアの違法コピーは、窃盗とは罪悪感に質的相違があると考えられ、また、社会的非難の質と程度にも大きな相違がある。)
そして、侵害に対する救済も民事的救済が中心であり(同法第112条以下)、刑罰は親告罪とされており(同法第123条第1項、第119条)、刑事裁判における著作権法違反の罪に対する実際の量刑も、窃盗のそれよりも相当軽いのであり、これは両者の罪質の違いに起因するものなのである。
以上によれば、
著作権法違反に該当する本件非違行為をした控訴人の懲戒処分をするにあたって、懲戒処分の指針における金銭事故及び窃盗の量定が免職処分を基本としていることを参考にするのは相当でないというべきである。
(3)本件行為の性質及び態様
本件非違行為は、控訴人が適法に購入した本件ソフトウエアを自宅のパソコンで複製して販売したというものであって、その手口は稚拙なものであるということができる。また、本件非違行為は、被害者と直接相対せず、自宅で簡便に行うことができるものであることから、罪の意識が低くなりがちな性質を有するといえる。
また、本件行為は、興味本位で、インターネットのオークションサイトに本件ソフトウエアを出品したところ、売買取引が成立したことから、本件非違行為を開始し、その後は、生活費の不足分等を稼ぐという目的から、本件非違行為を継続したものであり、営業目的や遊興費を稼ぐ目的等と比べると、その利欲目的は強固なものとはいえず、本件非違行為の動機をもって極めて悪質であるということはできない。従って、重大な非違行為であるとはいえるものの、極めて重大な非違行為であるとまではいえない。
(4)本件行為の結果ないし影響
① 著作権法違反の被害者であるB社との間で、B社に示談金として170万円を支払う旨の示談を成立させてこれを全て支払い、B社が明確に宥恕の意思を表明し、告訴しないことを明らかにした結果、犯罪として起訴されるには至らなかったことからすると、
本件非違行為の結果を重大であるとまでいうことはできない。
② 教職員である控訴人が本件非違行為をしたことによって、被控訴人の地方教育行政に対する社会の信頼が低下したことは否定できない。
しかしながら、
控訴人は管理職ではない一般教員であり、本件非違行為については職務外の行為であり、控訴人は逮捕されておらず、処分行政庁が、本件免職処分をした後に、本件免職処分とその理由となった本件非違行為を公表したことを受け、北海道新聞ほかの新聞各紙が本件免職処分とその理由となった本件非違行為について報道するまでの間、報道機関によって報道されることはなく、広く一般に知られることはなかった。そして、本件免職処分後になされた報道も、処分行政庁が同時期にした他の懲戒処分と併せて報道するものであり、本件免職処分についての記載は簡略なものであった。また、控訴人は、本件免職処分がなされるまでの間、児童生徒に対する指導を継続したが、上記中学校で混乱が起きることはなく、その指導に特段の支障は生じなかった。
したがって、
中学校の教員である控訴人が本件非違行為をしたことによって、被控訴人の教育公務員が遂行する地方教育行政に係る職務に対し、児童生徒やその保護者、地域社会を初めとする社会全体が有する信頼が著しく低下したと認められない。したがって、本件非違行為の社会的影響が重大であるということはできない。
(5)結論
以上の事情を併せ考慮すると、本件免職処分は、社会観念上著しく妥当性を欠き、処分行政庁がその裁量権の範囲を逸脱したものというべきである。
したがって、
本件免職処分は、違法であり、取り消すべきである。
5.まとめ
一般的に、公務員の私生活上の犯罪行為は、民間会社の社員の場合よりも厳しく懲戒される場合がありますが、この判例のとおり、懲戒免職や懲戒解雇処分のように労働契約を一方的に終了させるような厳しい懲戒の場合には、犯罪行為の悪性の実態や社会への影響力等の具体的な事情を詳細に検討することが求められており、「私生活上の不祥事でも、学校の先生だから厳しく処分されて当然だ。」というように、単に公務員であるということをもって厳罰に処するという考え方は改める必要があると思われます。
以 上
<お正月と法律>年末年始挨拶回りについて
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
官公庁や会社では、年末の御用納め(仕事納め)や新年の御用始め(仕事始め)に際し、挨拶回りをする恒例行事があります。盛装をして関係機関や取引先などに挨拶をして回るというものですが、私が大学を卒業して就職した昭和の時代には、御用納め日も御用始め日も「半日勤務体制」になっており、挨拶回りを終えた後に、昼食時から宴会的な雰囲気の中で更に年末年始の挨拶を受けた経験をしております。
その後半世紀の時を経て、年末年始の挨拶回りについては、官公庁でも会社でも、お祝いの宴会気分の催しとして過ごすこともなく、通常の「平日勤務体制」が定着した様子が見受けられます。ある調査結果によると、昨今「働き方改革」が叫ばれる中、業務の効率性を重んじる傾向も高まっており、年末年始の挨拶回りを必要だと考えている人は全体の約22%にとどまっており、反対に不要だと考えている人は全体の約20%、あまり必要ではないと考える人も含めると約43%の人が必要性を感じていないという結果が出ているようです。
1.年末年始挨拶回りは「業務」か?
年末年始の挨拶回りについて法律的に検討してみますと、それはそもそも業務なのか、業務を免除された個人的な行為なのか?業務ではないとしたら、年末年始の挨拶回りをすることは職務専念義務に反しないか?という問題があります。
業務性の有無は、公務災害の対象になるかどうかという問題に影響します。また、職務専念義務違反としての懲戒対象になるかという問題も生じます。公務災害の点で、仮に、「年末年始の挨拶回り」を本来の公務と全く関係のない他業務に従事するために職務専念義務免除がなされていると考える場合は、年末年始の挨拶回りの際に当該公務員が事故に遭っても公務災害の対象にならないのではないかという疑問が生じます。
「年末年始挨拶回り」をする場合には有休休暇を取るように指導していたような職場で、個人的に「年末年始挨拶回り」をしていた場合は、業務ではないという解釈になるでしょうが、「年末年始挨拶回り」が従来から恒例行事として行われている職場においては、「業務」(「業務としての外出行為」又は「業務に付随する行為」も含む)として黙認されているものと考えるべきだと思います。
その意味では、「年末年始挨拶回り」を黙認している職場においては、「年末年始挨拶回り」は「業務」であり職務専念義務違反ではなく、もし職務専念義務違反免除であったとしても「業務に付随する行為」であるため、年末年始挨拶回りの際に事故に遭った場合は公務災害の対象になると考えます。
2.年末年始挨拶回りの公用車又は社用車運転手の待機時間は休憩時間になるか?
上司が年末年始挨拶回りに公用車又は社用車を使用する場合、その車の運転手は、上司が挨拶回りを順次行っている間、1時間程度待機する場合もあるでしょうし、各訪問先で数10分程度ずつ待機する場合もあるでしょう。そのような場合の待機時間は、運転業務そのものを行っていないので、労働法上は、「休憩時間」ということになるのでしょうか、という問題もあります。
(1) 労働時間とは
労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことを指し(最高裁第1小法廷判決 平成12年3月9日)、例えば、待機時間(手待ち時間)のように、使用者の指示があれば直ちに作業に従事しなければならず、そのような作業場の指揮監督下に置かれた時間は労働時間となります。
(2)待機時間は、労働時間か?
労働時間として必要な「指揮命令下にあるか否か」は、主に「場所的な拘束性の有無」、「職務内容による拘束性の有無」で判断されますが、場所的な拘束性の点でみると、一定の駐車場内で1時間以上も待機している場合には、上司の挨拶回りの場所との拘束性もあまりなく、自動車に鍵をかけて自動車から離れて過ごすことも可能なことから、場所的拘束性はあまりないと判断されるでしょう。一方、挨拶回りの場所へ移動して待機する場合には、路上に駐車させて車の中にとどまっていなければならないという意味で場所的拘束性はあるということになるでしょうし、職務的拘束性の点からすれば、挨拶回りをしている上司の指示や乗車指示に応じて運転する態勢でいることが要求されていれば、職務内容による拘束性が認められることになるでしょう。
(3)類似判例―大分地裁判決 平成23年11月30日 労判1043号54頁
この判例は、タクシー運転手がタクシーに乗車して客待ち待機をしている時間を労働時間と認定した判例です。上司の年末年始挨拶回りに公用車又は社用車を使用して運転手が上司の指示で挨拶回り先へ移動し待機している場合と同様の待機態勢と評価できる判例です。この判例は次のとおり判示しています。
(判旨)「労基法上の労働時間とは,労働者が使用者の明示または黙示の指揮命令ないし指揮監督の下に置かれている時間をいい,原告X1ら(運転手)がタクシーに乗車して客待ち待機をしている時間は,これが30分を超えるものであっても,その時間は客待ち待機をしている時間であることに変わりはなく,被告Y社(タクシー会社)の具体的指揮命令があれば,直ちにX1らはその命令に従わなければならず,また,X1らは労働の提供ができる状態にあったのであるから,30分を超える客待ち待機をしている時間が,Y社の明示または黙示の指揮命令ないし指揮監督の下に置かれている時間であることは明らかであり,仮に,Y社が30分を超えるY社の指定場所以外での客待ち待機をしないように命令していたとしても,その命令に反した場合に,労基法上の労働時間でなくなるということはできない。」
3.最後に
この拙稿を読んでいただく頃には、皆さんは年末年始の挨拶も終わられていることでしょう。新年を迎え、挨拶回りを終え、また新しい気分で仕事に邁進していきましょう。
ちなみに我が事務所では、私が昭和時代の御用納め等を経験した関係上、仕事納め日は午前中の半日勤務として、昼食会終了後の帰宅は自由としており、正月1週間程度のお休みをいただいた上で、新年の仕事始め日は昼食会でスタートするという昭和の方式を採っております。
以 上
(論考)国際連合とロシア連邦のウクライナ軍事侵略について
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
12月を迎え、1年を終えようとしていますが、今年はコロナ禍の年であったという他、2月のロシア連邦のウクライナ(共和制国)軍事侵略を契機に、ウクライナ支援とプーチン大統領非難の1年になったように思います。
今年の10月14日に講演をする機会があり、講演の冒頭の“掴み”として、「10月14日は何の日か知っていますか?」という問いから始め、次のような話をしました。
「一般的には“鉄道の日”とも言われていて、今年は鉄道開通150周年ですかね。ウィキペディアで、「10月14日 何の日」で調べてみたら、こんな記載がありました。~~「10月14日は、グレゴリオ暦で年始から287日目(閏年では288日目)にあたり、年末まであと78日ある。」・・・・確かにそうですよね。正しすぎて何とも言えない気分になりました。
その他に、1つ気になる記載がありました。~~「ソビエト連邦でフルシチョフが追放された日」なんだそうです。1964年(昭和39年)10月14日に、ニキータ・フルシチョフが、ソビエト連邦中央委員会第一書記を事実上追放されて失脚し、ブレジネフ、コスイギン体制になった日のようです。アメリカのケネディ大統領との間で核戦争のキューバ危機を生じさせたフルシチョフが追放され失脚した日なので、それと同じ日の今日、ウクライナ侵略での核戦争の危険を生じさせたウラジミール・プーチンが追放され、失脚するといいなあと個人的に考えたりしましたが、現段階ではそのようなニュースは残念ながら無いようですね。
最近少しずつ寒くなってきていますが、寒くなるとスーツを着る時期がきているなあと思うわけで本日私もスーツを着ています。スーツの“裏地(うらじ)”をみると、なぜか、いつもわがままプーチン大統領のことを想像しちゃうんですよね。・・・裏地見る・・・ウラジミール・プーチンだから・・・。あ、ここも私なりのプーチン批判に同調してもらって、笑ってもらうところでした。」
私の真意はプーチン大統領批判なので、笑おうにも笑えないような“掴みの話”になってしまいましたが、講演聴講者からは、かすかな笑い声をもらうことができました。
そこで、批判をする以上は自分自身でも調べておこうと考え、プーチン大統領批判と同時に、国際連合の安全保障理事会常任理事国5か国の一つであるロシア連邦の軍事侵略を国際連合がなぜ防ぐことができなかったのかという点を調べてみました。
1 国際連合の結成の経緯
連合国(the United Nations)は、第二次世界大戦からの米英を盟主とした戦勝国クラブ(会員制の集まり)であり、1945年(昭和20年)4月25日から6月26日にかけて、日本又はドイツ(ドイツは会議中の5月7日に降伏したが、日本は降伏前である。)に宣戦している連合国50か国の代表がサンフランシスコに集まり、国際連合設立のためのサンフランシスコ会議を開き、1945年(昭和20年)6月26日、50か国が国際連合憲章に署名して会議は終結しました。この50か国には、既に降伏したイタリアやドイツ、降伏前の日本は含まれていません。
その後、アメリカ、イギリス、フランス、ソ連、中華民国及びその他の署名国の過半数が批准した1945年10月24日に、国際連合(United Nations、第二次大戦の連合国(米英仏ソ中)が安全保障理事会の拒否権を有する常任理事国を構成する。)が正式に発足しました。
従って、国際連合は、英語名が「United Nations」とされ、連合国の英語名「the United Nations」と全く同じ表記であることから分かるように、第二次世界大戦の連合国の団体であることを特徴としており、連合国による平和秩序維持を目的としている国際団体であることが分かります。
2.国際連合の敵国条項(Enemy Clauses)の問題点
(1)国連憲章第53条第1項前段では地域安全保障機構の強制行動・武力制裁に対し国際連合安全保障理事会(安保理)の許可を取り付けることが必要であるとしています。
しかし、第53条第1項後段(安保理の許可の例外規定)は、「第二次世界大戦中に連合国の敵国だった国」が、戦争により確定した事項を無効に、又は排除した場合、国際連合加盟国や地域安全保障機構は安保理の許可がなくとも、当該国に対して軍事的制裁を課すことが容認され、この行為は制止できないとしています。
(2)この国連憲章第53条を形式的に解釈すると、現在、日本と中国との間には尖閣諸島をめぐる領土問題がありますが、仮に、日本の尖閣諸島の「実効支配」が「旧敵国による侵略政策の再現」とみなされるようなことになったら、中国は、国連の「敵国条項」(第53条1項後段)のもと、平和的解決も話し合いもせずに日本に対して軍事的制裁を下すことができるという条項になります。つまり「敵国条項」がある限り、尖閣諸島がどちらの領土なのかという議論も話し合いもせずに、日本に対して問答無用で武力攻撃できてしまう危険性をはらんでいるのです。
(3)日本政府の見解では、「敵国」は、第二次世界大戦中に国連憲章の署名国のいずれかの敵であった国(=第二次世界大戦で「連合国」と対峙した「枢軸国」とも呼ばれています。)とされており、日本、ドイツ、イタリア、ブルガリア、ハンガリー、ルーマニア、フィンランドがこれに該当すると例示しています。1995年(平成7年)の第50回国連総会にて、憲章特別委員会による「敵国条項」の改正削除が賛成155、反対0、棄権3で採択され、同条項の削除が正式に約束されましたが、未だに「敵国条項」は削除されていません。但し、「敵国」に該当する全ての国がその後国際連合に加盟しており、国連憲章制定時と状況が大きく変化したため、国連憲章第53条と第107条は事実上死文化した条項と考えられています。
(4)なお、「敵国条項」を実際に国連憲章から削除するには、「敵国」であるとされている7か国(日本・ドイツ・イタリア・ブルガリア・ハンガリー・ルーマニア・フィンランド)以外の加盟国のうち3分の2の国が、国内で煩雑な手続きを進め、議会の承認を得る必要がありますが、該当7か国以外の国からすると、「すでに事実上死文化している条文を変更・削除したからといって何も変わらないだろう」という認識に過ぎず、削除しなくても国連活動には支障はないからという考え方で、それぞれの国で国内議会の議決手続きを積極的に取り上げていないため後回しになっている、というのが実情のようです。
(5)今回のロシアによるウクライナ侵略では、プーチン大統領から「ネオ・ナチズム勢力の排除」という言葉が出てきたりしています。これは、旧ドイツのヒトラーのナチズムに通じるということで、かかる勢力は、この「敵国条項」に該当するという解釈で、安保理の許可がなくとも、「ネオ・ナチズム」国(ウクライナ)に対して軍事的制裁を課すことが容認されこの行為は制止できない、と解釈しているのではないかと思ったりしています。しかし、戦後のウクライナ国がネオ・ナチズムの国家であるというような評価は、世界のどの国も世界の誰もがしていないことは明らかですので、プーチン大統領がこのような解釈をしているとすれば悪意の曲解と非難せざるを得ません。
3.安保理常任理事国5か国一致の原則と理事国排除の可否
今回のロシア・プーチン大統領のウクライナ軍事侵略は、国連憲章第53条第1項前段違反の行為になります。地域安全保障機構の強制行動・武力制裁に対しては安保理の許可を取り付けることが必要であるとされているにも関わらず、安保理の許可を得ないままで行っているからです。
このような国連憲章違反国に対する国連憲章上の排除措置というものがあるのでしょうか。この点については、ロシアが連合国の5大国として、拒否権を持つ安保理常任理事国であることから大きな制約があります。
(1)拒否権を持つ常任理事国に関する定めは、次のとおりの定めになっています。
記
〇憲章 第5章 安全保障理事会 第23条
「1 安全保障理事会は、15の国際連合加盟国で構成する。
中華民国、フランス、ソヴィエト社会主義共和国連邦、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国は、安全保障理事会の常任理事国となる。総会は、第一に国際の平和及び安全の維持とこの機構のその他の目的とに対する国際連合加盟国の貢献に、更に衡平な地理的分配に特に妥当な考慮を払って、安全保障理事会の非常任理事国となる他の10の国際連合加盟国を選挙する。」
〇憲章 第27条
「1 安全保障理事会の各理事国は、1個の投票権を有する。
2 手続事項に関する安全保障理事会の決定は、9理事国の賛成投票によって行われる。
3 その他のすべての事項に関する
安全保障理事会の決定は、常任理事国の同意投票を含む9理事国の賛成投票によって行われる。但し、第6章及び第52条3に基く決定については、紛争当事国は、投票を棄権しなければならない。」
〇憲章 第108条
「この憲章の改正は、
総会の構成国の3分の2の多数で採択され、且つ、
安全保障理事会のすべての常任理事国を含む国際連合加盟国の3分の2によって各自の憲法上の手続に従って批准された時に、すべての国際連合加盟国に対して効力を生ずる。」
〇憲章 第109条
「1 この憲章を再審議するための国際連合加盟国の全体会議は、総会の構成国の3分の2の多数及び安全保障理事会の9理事国の投票によって決定される日及び場所で開催することができる。各国際連合加盟国は、この会議において1個の投票権を有する。
2 全体会議の3分の2の多数によって勧告されるこの憲章の変更は、
安全保障理事会のすべての常任理事国を含む国際連合加盟国の3分の2によって各自の憲法上の手続に従って批准された時に効力を生ずる。」
(2)拒否権を持つ安保理常任理事国の排除の限界(不可能)
国連憲章第27条により、安保理常任理事国は手続事項を除く全ての事項に関する安保理の議案への拒否権を持ち、安保理常任理事国のうち1か国でも反対すれば、議案は成立しない仕組みになっています。また、国連憲章第108条により、安保理常任理事国は国連憲章の改正に対しても拒否権を持ちます。
今回のロシアに対して、アメリカ、イギリスを中心とした自由主義陣営国家は、令和4年3月2日に「ロシアによるウクライナ侵攻を非難する決議」を国連総会で賛成多数(賛成141か国。反対はベラルーシ、北朝鮮、エリトリア、ロシア、シリアの5か国、棄権は中国やインドなど35か国)で採択しました。3月24日に「ロシア軍のウクライナからの即時完全無条件撤退を求める決議」を国連総会で賛成多数(賛成140、反対5、棄権38、無投票1)で採択していますが、総会決議に法的拘束力はないため、ロシアは何ら従っていません。
そこで、国際連合としては、安全保障理事会においてロシアに対する軍事手続等の決議を行うことも検討しますが、肝心なロシアが拒否権を行使できる仕組みのため功を奏しないことは明らかですし、安保理常任理事国を定める国連憲章からロシアを除く(除名又は権限停止等も含む)とする憲章改正や、拒否権を認める国連憲章を拒否権なしの制度にする改正を国連総会で3分の2の多数で採択しても、各国の批准手続きでは3分の2の多数国の中に安保理常任理事国を含む必要があり、ロシアが批准しなければその憲章改正総会決議は法的効果が生じません。そのため、国連多数国は個々の国の経済制裁的対応以外には具体的方策が取れず、ロシアのプーチン大統領の野蛮な軍事侵略を事実上許してしまっている状態になっています。
4.最後に
このような、野蛮かつ横暴な軍事侵略を阻止できないような安保理常任理事国が拒否権を持つ仕組みは廃止されるべきではないか?という意見があります。
しかし、この拒否権制度は、ある大国が世界各国から批判されている場合に、旧国際連盟のときのように当該大国が国際連合を脱退して戦争状態になることの反省から、常任理事国に拒否権を与えることで国際的協議機関でもある国際連合を脱退せずに、拒否の態度を示しながらも協議を続けてくれるという平和的解決状況を作ることができるという役割も果たしている面があります。
国際法という法の世界は、そもそも法的強制力をもっておらず、多数国による政治的圧力・制裁以外には「戦争」という武力行使でしか解決できない限界があるなかでは、根気強く協議を続け説得をすることを最終解決とする手法であることは強く理解しておく必要があると思います。
以 上
「現金支払い」と「電子マネー(又はクレジットカード)による支払い」
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
テレビコマーシャルで、オダギリジョーさんの八百屋さんが外国人客から「カード支払いOK?」と聞かれて、「NO、NO!(うちは現金のみだ)」と対応したところ、外国人客が「じゃあ~いいですう~~~。」と言って去っていくという、モバイル決済サービス「エアペイ(Air PAY)」のCMがありました。このCMの意味は、「そもそも、現金払いのみだけの店でも問題はないのだろうけど、これからの世の中は、キャッシュレス支払いが増大して、現金支払いだけだとお客は離れて行って、経営的には損をしますよ。モバイル決済サービス「エアペイ(Air PAY)」を取り入れましょうね。」ということを示しています。
それでは、逆に、現金支払いは人手を経ていてコロナ禍の時代には感染防止の観点から望ましくないし、売上金を店舗内で保管する状態は店舗強盗等に対しての防備策も必要になるなどの理由で「店が『現金不可(電子マネーのみ)』という支払い条件を店頭に表示」して、現金支払いを拒否する方法を取った場合には、法律上何か問題があるでしょうか?
1.キャッシュレス支払いの急激な増大
近年、世界のIT化の促進もあって、日本でも現金を使わないキャッシュレス化が進んでいます。キャッシュレス支払いは、店にとっては、釣り銭を準備する必要がなく、レジ打ち作業を省力化でき、売上額とレジ内の現金を照合する「レジ締め」も不要になることで、客へのサービスに専念できるという利点があり、顧客にとっては、クレジットカードでの支払いでポイント付与等のサービスがあるということで、多くの人たちが利用するようになってきています。
また、2020東京オリンピックで来訪した外国人客への対応のため、政府が事業者店舗等へのキャッシュレスのレジ機器の導入を補助したことで、キャッシュレス支払いが可能な店舗が増え、更に、令和2年にパンデミックとなったコロナ禍対応策と相まって、人手を経た貨幣・金銭の授受による感染防止策としても有効な方策であるとされたことから、急激に増大してきています。
「飲食代金は、現金払い」「持っている現金以上は飲まない。食べない」を鉄則としている齢70歳近くの私でさえ、最近は、電子マネーカードを1枚所持している状況です。
2.「完全キャッシュレス」店舗の出現
貨幣が使えない機器が日本社会に出現した例としては、NTTから「テレホンカード専用」の公衆電話機器(MC-5APN公衆電話機、MC-5BPHN公衆電話機)が出現してきたときに「あれ?現金が駄目なの?」と思ったことがありました。最近では、京都大学吉田キャンパス(左京区)前に、令和3年6月にオープンした「PIZZA(ピッツァ)百万遍」(まき窯で焼き上げるナポリピザのテイクアウト専門店)で、「現金のお取り扱いはございません」と表示され、「完全キャッシュレス」として決済はクレジットカードのほか、JR西日本のICカード乗車券「ICOCA(イコカ)」、スマートフォン決済サービス「PayPay(ペイペイ)」など30種類が使用できるとの案内をしているニュースがありました。
3.「現金支払い拒否」の法的問題点
「現金支払い拒否」の店舗については、キャッシュレスカードを持たない高齢者や、親の了解を得ないとキャッシュレスカードを作れない未成年者は、全く利用できないという事態が生じます。実際に、先のピザ専門店においても今まで時々利用していた高齢者や未成年者が利用できなくなったという意見が出たそうです。
ところで、「現金のお取り扱いはございません」との表示を見て、それを承知の上で商品を購入した人に関しては、双方の合意の下で現金以外のキャッシュレスの方法で支払いをするとの契約をしたということで問題は生じないと思いますが、表示が不明瞭又は小さい表示で気づきにくい場合には、法的な問題が生じるのではないかと思います。
ピザ専門店ではなく、食料品、医薬品などの生活必需品の取扱店が、「現金のお取り扱いはございません」との表示をした場合を想定してみてください。
「現金のお取り扱いはございません」とのお店の表示について問題を分析してみます。
4.「現金支払い拒否」の法的問題点の分析
(1) 現金通貨の強制通用力について
日本銀行法第46条では、日本銀行券が法貨として無制限に強制通用力を有することが定められ、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第7条では、貨幣については「額面価格の二十倍まで」に限り、法貨として強制通用力を有することが定められています。紙幣の場合には、千円札だけで何十万円もの買い物をして支払いができるのですが、貨幣の場合には、1種類の貨幣は20枚までしか受け取ってもらえないことがあるということです。この定めを「法貨(現金通貨)の強制通用力」と言います。
強制通用力というのは、「金銭債務について債務を消滅させる効力(債務免責力)」と「債権者に受領させる効力(受領強制力)」を意味します。
キャシュレス決済というのは、この現金通貨ではなく、預金通貨(口座振替、クレジットカード、ネットバンキング等により預金金額で支払うもの)と電子通貨(プリペイカード等による電子マネー金額で支払うもの)で行う支払いを言いますが、この預金通貨や電子マネーの支払いは、「貨幣」ではなく、「貨幣単位」を移転することによって一定額の給付を実現する履行手段にすぎず、強制通用力を認められている「法貨(現金通貨)」ではありませんので、双方で支払方法としての特約を結ぶか、又は最低限、債権者の同意を得る必要があります。
預金通貨や電子マネーは、円で表示される金銭債務について「債務免責力」を有する点では現金通貨(法貨)と同じなのですが、「受領強制力」を有していない点で法貨である現金通貨とは異なり「自由通貨」の範疇に属するものなのです。
(2) アメリカ合衆国内での動き
キャッシュレス払いが先行しているアメリカ合衆国において、2020年1月23日、「ニューヨーク市議会が、市内のレストランや小売店が現金での支払いを拒否し、クレジットカード払いなどに限ることを禁止する法案を、賛成43反対3の圧倒的賛成多数で可決した」というニュースがあります。ニューヨーク市の発表によると、全体の11%の世帯が銀行口座を持たず、21.8%の世帯は口座を持っていても小切手による支払いや銀行以外の金融サービスを利用しているとの統計結果から、全ての人に現金支払いの利便性を維持する必要があるということのようです。既にサンフランシスコ市とフィラデルフィア市が同様の法律を定めているようです。
(3) 日本の場合の現時点での結論
日本では、法定通貨の現金を支払いの最終手段として常に通用するように国家が国民に強制できる「強制通用力」が法律で規定されているのですが、他方、アメリカ合衆国内の例のように「現金支払い拒否」を禁止する法律を定めているわけでもありません。
そこで、「現金支払い拒否」に関する法的論点として整理すると、「強制通用力を有する現金通貨の支払いを債権者・債務者の双方の合意のもとで排除することは、契約自由の原則から許容されるものかどうか」という問題点に集約できるのではないかと思います。
この点、契約自由の原則は、法律の強行法規に反しない限度で認められるにすぎませんので、現金通貨の強制通用力が法律で規定されている点を踏まえると、店舗が現金での代金受け取りを拒否することは違法であり、新たにキャッシュレス禁止法を成立させる必要はないようにも思えます。
しかし、現金での代金受け取りを拒否するかどうかという問題は、契約当事者の債権者と債務者との双方が本来契約で自由に定めることのできる決済方法に関することにすぎないので、「契約締結の自由」が、現金の強制通用力に優先するとみなされるのではなかろうかと考えます。
日本の民法第402条第1項で「債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができる。ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない。」と定めており、支払いに関する現金通貨を選択できる約定が許されていることからすると、受領強制力を有する日本の現金通貨の使用を全面的に排除して預金貨幣や電子マネーを使用する特約も有効とされていることになるので、「店舗が「現金お断り」という貼り紙を店頭に掲げて、「現金支払い拒否」の意思表示をすること自体は何ら違法ではないということになります。
ただし、そのことを前提にしても、契約自由の原則として「現金お断り」「現金支払い拒否」が相手方との合意があれば可能であるというだけですので、そのような表示を了解した上で顧客が商品を購入したり飲食したりすることが必要であり、当初述べたように、店舗の表示が不明瞭で又は小さい表示で気づきにくい場合には、表示に気づかなかった顧客が現金で支払いたいという申出に対しては現金支払いの強制通用力が適用され、店舗側は受取拒否ができないという結果になるという点だけは、留意しておくべきでしょう。
以 上
相続財産についての情報と個人情報保護
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
○ 田舎で長寿を全うした甲爺さんには、2人の子供(娘乙、息子丙)がいました。娘乙は甲爺さんの近くに住み甲爺さんの老後の面倒を看ていましたので、甲爺さんの年金預金(A銀行通帳)も甲爺さんの依頼で出し入れを手伝っていました。甲爺さんは自筆遺言証書で「預金の4分の3を娘乙が相続する。4分の1を息子丙が相続する。」と遺言していましたが、都会に住む息子丙は、遺言書は娘乙が偽造したものではないかと疑い、遺言書の印鑑とA銀行届出印鑑を比較しようと考え、甲爺さんの相続人として、A銀行に対して、甲爺さんの銀行取引印鑑届出書の情報開示請求をしたところ、A銀行は「死者の情報であり、請求者の相続人丙の個人情報ではないので開示できない。」と拒否しました。A銀行の取扱いは正しいのでしょうか。
○ 解 説
1.甲爺さんの遺言書の意味(なぜ、娘乙に預金を全部あげなかったの?)
銀行預金だけが相続財産で、相続人が乙・丙の2人の場合には、法定相続は乙が2分の1、丙が2分の1となります。ところが、遺言書では乙が4分の3、丙が4分の1になっています。
仮に「乙が預金を全部相続する」という遺言だったらどうなるでしょう?
この場合、乙が預金全額を相続することは難しくなります。息子丙も相続人ですので、遺留分として一定の権利が認められています(改正民法第1042条)。息子丙は遺留分4分の1(法定相続分の2分の1)が認められますので、息子丙が娘乙に対して、遺言内容を知ったときから1年の間に遺留分侵害額を請求できることになっており(改正民法第1047条、第1048条)、結局は娘乙が4分の3、息子丙が4分の1を取得することになります。
甲爺さんの自筆遺言は、息子丙の遺留分は保証してあげようという法的に公平な遺言なのだろうと思われます。
2.甲爺さんの銀行の印鑑届書は、死者の個人情報?相続人が相続で引き継いだ個人情報?
(1)情報公開法(情報公開条例)と個人情報保護法という法律があります。情報公開法(平成13年4月1日施行)又は条例は、国や地方自治体等の行政機関が保有する情報を開示する手続きを定める法律であり、個人情報保護法(平成17年4月1日全面施行)は、国・地方自治体以外の民間企業においても、その保有する個人情報は適式に取得・管理・利用されなければならないとする法律です。(但し、令和4年4月に国の行政機関の保有する個人情報保護法と一元化され、国の行政機関での個人情報についても規定されており、令和5年5月には地方自治体の個人情報保護条例とも一元化されることになっています。)
この情報公開法と個人情報保護法の二つの法律では、「個人情報」は、行政機関においては公開・開示しなくても良いとされ(情報公開法第5条第1項第1号)、当該個人においては、自分の個人情報については開示請求権を持ち、管理している取扱事業者は個人情報開示義務を負うとされています(旧個人情報保護法第28条第1項、第2項)
(2)死者の個人情報について
甲爺さんの銀行への印鑑届書は、甲爺さんが銀行預金取扱いに使う印鑑の印影や住所・氏名が載っている文書です。「個人情報」の定義としては、「氏名、性別、生年月日等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表すすべての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれ、暗号化等によって秘匿化されているかどうかを問わない。」(個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン(PDF) p2)とされていますので、「甲爺さんの個人情報」であることは間違いありません。
問題は、旧個人情報保護法第2条に「この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。」と「生存する個人に関する情報」に限定されている趣旨です。「死者の個人情報」については、個人情報保護法は適用されず、死者の遺族を含めて誰も開示請求できないということが前提になっている点です。
他方、民法で相続制度を定めており、民法896条では「相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」としていますので、相続人は被相続人である死者の権利義務の一切を承継するのであるから、本来被相続人(甲爺さん)が有していた「自分(甲爺さん)の個人情報開示請求権」という権利も相続人(娘乙や息子丙)が承継しているということになるのではないかという疑問も生じます。
この点は、民法第896条但書「ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」と定めている点の適用の有無(甲爺さんの個人情報開示請求権は一身専属の権利なのかどうか)が検討される余地があります。
3.判例を紹介しましょう
この事案に関する判決としては、第1審判決は、「甲の印鑑届書の情報は、請求者息子丙の個人情報ではない。」としてA銀行の勝訴、しかし、第2審判決は、「死者(甲)に関する情報と他の情報(丙の他の個人情報)を容易に照合することにより特定の丙個人として識別することができる場合には、当該情報は、当該個人(相続人丙)に関する情報ということができる」としてA銀行は敗訴しました。
第1審判決と第2審判決が異なる中で、上告審の最高裁判決は「(息子丙が)相続人等として本件預金口座に係る預金契約上の地位を取得したからといって、(甲の)印影は、相続人丙とA銀行との銀行取引において使用されることとなるものではない。また、本件印鑑届書にあるその余の記載も、相続人丙とA銀行との銀行取引に関するものとはいえない。甲の印鑑届書の情報は、請求者息子丙の個人情報ではない。」として第1審の結論を支持しました。
各判例の詳細は以下のとおりです(第一法規判例データベース利用)
(1)岡山地方裁判所平成28年10月26日判決―金融法務事情2123号67頁
① 本件印鑑届書記載の情報は、本来、既に死亡したB(設例での甲爺さん)に関する情報であるところ、死者に関する情報であっても、それが同時に生存する個人に関する情報でもあると認められる場合には、法2条1項の「生存する個人に関する情報」に当たるといえる。そこで、どのような場合に死者に関する情報が同時に生存する個人に関する情報でもあるといえるかが問題となるところ、原告は、この点に関し、死者の財産に関する情報であれば、当該財産を相続した相続人の情報にも該当する旨主張する。
しかし、法は、個人情報取扱事業者が個人情報を取扱うことによる本人の権利利益の侵害の危険性や本人の不安等を取り除くことをその目的にしており、法の目的に照らせば、法が保護しようとする個人の権利利益とは本人の人格権的権利に由来するものと解され、本人の財産権行使等の便宜を図ることはその本来の目的ではないと解するのが相当である。
したがって、生存する個人が、現に自己に帰属する財産権の行使のために必要ないし有用な情報であれば、それが本来は死者である被相続人に由来する情報であっても、直ちに生存する個人(相続人)に関する情報に当たると解するのは相当でない。そして、法の目的からすれば、生存する個人に関する情報といえるためには、当該情報の取扱いによって個人の権利利益を侵害する可能性がある情報、すなわち、当該情報によって生存する個人それ自体を識別することができる情報である必要があると解すべきである。
② 本件印鑑届書には、Bの住所、氏名、生年月日、連絡先電話番号、開設日の年月日及びBの印鑑が表示されているところ、これらの情報からBを識別することはできるものの、これはB個人にかかる情報であって、これから原告を識別することはおよそ不可能であるといえる。原告は、戸籍等の資料を合わせれば、本件印鑑届書記載の情報をもって、原告を識別することが可能である旨主張するが、戸籍等の資料を合わせても、本件印鑑届書が原告の相続した預金債権に係るものであることが認識できるにすぎず、本件印鑑届書記載の情報それ自体から、直ちに原告個人(設例の息子丙)が識別できるとはいえない。
したがって、本件印鑑届書記載の情報は、法2条1項に定める「生存する個人に関する情報」に当たらないというべきである。
③ 以上によれば、本件印鑑届書記載の情報は、個人データ、ひいては保有個人データに当たらず、原告(設例の息子丙)の法25条1項に基づく開示請求(本件印鑑届書の写しの交付請求)は理由がない。
(2)広島高等裁判所岡山支部平成29年8月17日判決―金融法務事情2123号65
① 死者に関する情報であっても、当該情報が、死者が死亡時に有していた財産に関する情報である場合には、当該財産が相続人や受遺者に移転することにより、当該情報も相続人や受遺者に帰属することになり、これを相続人や受遺者に関する情報ということを妨げる理由はない。また、当該情報に死者の氏名等が明示されていることにより、その氏名等と夫婦や親子という身分関係に関する情報や遺言に含まれる相続人や受遺者の情報とは容易に照合することができるから、それにより特定の相続人や受遺者を識別することができることも明らかである。のみならず、前記のような死者に関する情報が不適切に管理されて、無用の情報が流出すること、又は、必要な情報が提供されないことは、死者に関する情報と他の情報を容易に照合することにより識別することができる特定の生存する個人の権利利益が適正に保護されないことを招き、このような結果は、法の目的に反するものといわなければならない。
そうすると、死者に関する情報は、同時に、当該死者に関する情報から識別することができる特定の生存する個人にとって、法にいう個人情報として、法による保護の対象となるべき情報であると解するべきである。
このように解することは、平成15年5月21日の参議院の個人情報の保護に関する特別委員会での附帯決議6項(死者に関する個人情報の保護の在り方等について交わされた論議等これまでの国会における論議を踏まえ、全面施行後3年を目途として、本法の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること)の趣旨にも適うものである。
以上のとおりであって、法の文理解釈からしても、また、死者が死亡時に有していた財産に関する情報が、相続人や受遺者にとって適正に管理されるべき情報であって、法による保護の対象になるべき情報であると解するべき目的解釈からしても、当該情報は、法にいう個人情報(生存する個人である相続人や受遺者に関する情報であって、当該情報に含まれる被相続人の氏名等と他の情報と容易に照合することができ、それにより相続人や受遺者を識別することができることとなるもの)と認められる。これは、当該情報が相続人や受遺者において具体的に有用か否かによって左右されるものではない。
② 被控訴人は、死者に関する情報が、生存する個人に関する情報に当たるのは、当該情報によって当該相続人を識別することができる場合に限ると主張する。
しかし、既に説示したとおり、法のいう個人情報は、他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含むのであるから、死者に関する情報に相続人や受遺者の氏名等が明示されている場合のみのならず、死者に関する情報と他の情報を容易に照合することにより識別することができる特定の個人がある場合には、当該情報は、当該個人に関する情報ということができる上、当該死者に関する情報は当該生存する個人にとっても適正に管理されるべき情報といえるのであるから、法の文理解釈からしても、目的解釈からしても、法のいう個人情報の「個人」を、当該情報に氏名等が示された個人に限定する理由はないというべきである。
したがって、被控訴人の主張は採用できない。
③ 前記①のとおり、死者の財産に関する情報は、生存する相続人や受遺者に関する情報でもある。よって、本件印鑑届出書に記載されている情報は、死亡したBの本件預金口座に関する情報であり、控訴人はその受遺者であるから、控訴人に関する情報として、法2条1項の「生存する個人に関する情報」に当たると認められる。
以上のとおり、控訴人の請求は理由があるから認容すべきところ、これと異なり、控訴人の請求を棄却した原判決は失当であり、本件控訴は理由がある。よって、原判決を取り消して、控訴人の請求を認容することとして、主文のとおり判決する。
(3)最高裁判所平成31年3月18日第一小法廷判決―判例時報2422-31
① 法は、個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、個人情報取扱事業者の遵守すべき義務等を定めること等により、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とするものである。法が、保有個人データの開示、訂正及び利用停止等を個人情報取扱事業者に対して請求することができる旨を定めているのも、個人情報取扱事業者による個人情報の適正な取扱いを確保し、上記目的を達成しようとした趣旨と解される。このような法の趣旨目的に照らせば、ある情報が特定の個人に関するものとして法2条1項にいう「個人に関する情報」に当たるか否かは、当該情報の内容と当該個人との関係を個別に検討して判断すべきものである。
したがって、相続財産についての情報が被相続人(死者)に関するものとしてその生前に法2条1項にいう「個人に関する情報」に当たるものであったとしても、そのことから直ちに、当該情報が当該相続財産を取得した相続人(生存者)等に関するものとして上記「個人に関する情報」に当たるということはできない。
② 本件印鑑届書にある銀行印の印影は、亡母が上告人との銀行取引において使用するものとして届け出られたものであって、被上告人が亡母の相続人等として本件預金口座に係 る預金契約上の地位を取得したからといって、上記印影は、被上告人と上告人との銀行取引において使用されることとなるものではない。また、本件印鑑届書にあるその余の記載も、被上告人と上告人との銀行取引に関するものとはいえない。その他、本件印鑑届書の情報の内容が被上告人に関するものであるというべき事情はうかがわれないから、上記情報が被上告人に関するものとして法2条1項にいう「個人に関する情報」に当たるということはできない。
③ 以上と異なる原審(第2審:広島高裁岡山支部)の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、以上に説示したところによれば、被上告人の請求は理由がなく、これを棄却した第1審判決は結論において正当であるから、被上告人の控訴を棄却すべきである。
4.私の見解をまとめてみますね
それでは、以上の判例の見解を参考にして、預金等の財産について相続が発生した場合に、被相続人である死者の個人情報が、相続人から開示請求できるか?という点をまとめてみましょう。
(1)まず、旧個人情報保護法第2条第1項で個人情報を「生存する個人に関する情報」と限定しているので、死者に関する情報は個人情報として遺族を含め誰にも開示請求されないことが想定されています。(例外として、地方公共団体で定められてきている個人情報保護条例では、「死者に関する情報」も個人情報保護の対象にする例もありますが、改正個人情報保護法第167 条第1項で「地方公共団体の長は、この法律の規定に基づき個人情報の保護に関する条例を定めたときは、遅滞なく、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、その旨及びその内容を委員会に届け出なければならない。」と定められており、法律と異なる定めが許されるかという点から、条例の定めが制限される可能性があります。)
(2)次に、法律の立場からの解釈に立った場合、死者の個人情報であっても、相続等によって死者の財産上の権利義務一切を取得した相続人の個人情報でもある場合には、相続人が自己の個人情報として開示請求できると考えます。
個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン(PDF) p2において、行政解釈として、「死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報となる。相続人本人として情報開示できる。」との解釈が示されています。
(3)問題は、死者の個人情報であっても、相続等によって死者の財産上の権利義務一切を取得したことの一事をもって「相続人の個人情報」になるということにはならないという点です。そもそも相続の対象は、相続開始時に被相続人(甲爺さん)に属した一切の権利義務であって(民法第896条)、個人情報あるいは個人情報開示請求権そのものが相続されるわけではないと考えられるからです。死者の個人情報は、生存中においても法定相続人からすれば他人の個人情報であってアクセスできなかった性質のものでから、民法第896条但書で「被相続人の一身に専属したもの」として、相続対象にはならないと解すべきでしょう。
(4)それでは、どのような場合が死者に関する情報が生存する相続人個人の個人情報に当たると考えることになるのでしょうか。
最高裁判例では「当該情報の内容と当該個人との関係を個別に検討して判断すべきものである。」としています。その具体的判断基準として「当該相続人自身の自己情報コントロール権の行使の必要があると認められる場合」あるいは「相続財産に“関する”情報と言える場合」という基準が示されています。(京都大学大学院法学研究科教授 曾我部真裕氏の意見書)
問題の相続財産である「預金債権」について検討すると、預金番号、預金種類、口座番号、預金額、預金の契約上の地位を示す契約書類、取引記録は「相続財産に“関する”情報」と言えると思いますが、それ以外に、銀行において専ら銀行口座を管理し、預金契約に基づく取引を効率的かつ安全確実に行うために作成する印鑑届書や住所変更届書類などのいわゆる口座管理書類は、相続人自身の個人情報になるものではないと思われます。
なぜなら、銀行実務において、印鑑届は、預金払戻請求等が出された場合に、書類に押印されている印影と印鑑届書の届出印の印影を照合し本人確認をするために利用するものであり、本人死亡後には届けられた印章が銀行との関係で使用されることはなく、相続が生じたとしても、相続人の印章の使用がなされるだけで、相続人が相続した預金債権の行使に使用されることは一切なくなります。
従って、被相続人の印鑑届は、専ら生前の本人との関係で使用される典型的な口座管理書類であって、相続人自身の相続した預金債権に“関する”情報とは言えないし、相続人自身の個人情報になるとも言えないと判断されることになります。
以 上
情報公開条例による開示請求と権利濫用不開示(却下)
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
地方自治体においては、その保有する文書等を開示することで情報を公開できるとする情報公開条例を定めています。これらの条例においては、住民等に情報開示請求をする権利を認めているものの、情報開示請求が権利濫用された場合の定めについては、総務省の平成21年調査では、都道府県レベルでは10都道府県で定めがあり、他の府県では定めはないと報告されています。権利濫用審査基準として「行政機関の事務を混乱又は停滞させることを目的とする開示請求」について例示している例が多いようです。
また、権利濫用禁止の条項を定めていなくても、ほとんどの都道府県の条例では、「開示請求者による適正な開示請求」「開示請求者による情報の適正な使用」の規定を定めたり、情報公開条例に関する解釈及び運用の基準において、開示請求権の濫用と認められる場合についての具体例を例示していたりして、適正でない開示請求に対しては、何らかの対応ができるとする趣旨が盛り込まれています。
1.権利濫用の法理
情報公開法においては、開示請求が権利の濫用と認められる場合についての明文化された規定はないので、権利の濫用と認められる場合かどうかについては、一般法理により判断することになります。情報公開条例で権利濫用禁止の条項を定めていない場合でも同様です。
なお、総務省で定める「行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく処分に係る審査基準」(総務省訓令第 126 号)においては、開示請求が権利の濫用に当たる場合には、開示しない旨の決定をすることとされています。
この中で、権利の濫用に当たるか否かの判断は、「開示請求の態様、 開示請求に応じた場合の行政機関の業務への支障及び国民一般の被る不利益等を勘案し、社会通念上妥当と認められる範囲を超えるものであるか否かを個別に判断して行う」こととされ、「行政機関の事務を混乱又は停滞させることを目的とする等開示請求権の本来の目的を著しく逸脱する 開示請求は、権利の濫用に当たる」としています。
他方、地方自治体では情報公開条例を定めており、その中で「何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。」とした上で、更に「何人も、この条例に基づく行政文書の開示を請求する権利を濫用してはならない。」と定めている例もあり、権利の濫用に当たる請求があったときは、当該請求を拒否する(不開示決定又は却下)ことができますし、総務省が定めるように、条例で明確な権利濫用禁止の定めがない場合でも、一般法理として「権利濫用法理」により開示請求を認めない旨の決定(非開示決定又は却下決定)をすることは可能とされています。
そもそも開示請求は、条例に基づき住民の知る権利を尊重し、行政文書の開示を請求する権利を保障するとともに、自治体の説明責任を果たし、住民と協働することにより、公正で開かれた政治の推進を図るためのものです。
一方、開示請求者には、条例の目的に即した請求を行う権利の適正な行使及び得た情報の適正な使用が求められます。
実施機関は、条例に基づく開示請求の趣旨に反するような請求については、権利の濫用として開示請求を拒否することができるとされている場合でも、その適用に当たっては慎重な運用が求められます。
2.権利の濫用の適用について
そもそも現行の情報公開請求制度は、基本的に国民ないし市民が情報公開請求を適切に行う局面を念頭に置いており、情報公開請求権が濫用された場合についての対処はもとより、そもそも情報公開請求権が濫用されること自体を想定していないものと考えざるを得ないでしょう。この点は情報公開制度自体の欠陥であると言え、一般法理から補う必要があります。
一般法理としての権利の濫用の適用に当たっては、開示請求の回数、対象文書の量、請求者の言動、請求の内容・方法など、当該開示請求による実施機関の業務遂行の停滞その他様々な事情を総合的に勘案し、開示請求者の被る不利益等考慮すべき要素等に照らして慎重に判断することが求められます。
判例は、単に大量の文書資料の開示請求であることだけで権利の濫用は認めていませんので、いやがらせを意図とする大量開示請求だとして安易に不開示の決定をするような運用は慎まなくてはいけません。
3.権利の濫用が疑われる場合の事務処理の流れ
情報公開請求制度は、それに関する多くの論稿や論評も含めて、基本的に国民ないし市民が情報公開請求を適切に行う局面を念頭に置いて定めていることから、一般法理から情報開示制度の例外として開示請求が権利の濫用だと疑われる場合には、厳格に対処する必要があり、且つ、例外ゆえに開示請求が権利の濫用だと疑われる場合でも、不開示決定が安易に行われないように適正且つ慎重な判断手続きがなされるべきであることは当然要求されるものであり、以下の手順例で判断されるのが正当であろうと考えられます。
①開示請求を受理し、濫用の疑いがある場合、まずは主管課において不開示指針等に沿って判断する。
②主管課において濫用にあたると判断した場合、総務課と協議する。
③総務課において濫用にあたると判断した場合、その判断に従って主管課が不開示決定書を申請者に送る。
4.権利の濫用の適用に当たって考慮すべき要素
(1)裁判例:東京地裁平成 15 年 10 月 31 日判決―判例秘書 L05834552
情報公開法に基づく自動車検査証の記載事項(検査登録事務所で行われ、車体の形状が『教習車』で登録された時の車両に関する申請書類の一切等)に係る開示請求をしたのに対して、行政庁が、「本件開示請求に対応するためには、仮に職員1名を専従作業員とし、1日8時間全く休憩なしで、同じ作業効率で作業を進めたとしても、9か月以上かかることとなり、業務に著しい支障を来すのみならず、他の情報公開請求に対応する余裕がなくなり、かえって法の立法趣旨が没却されることから、本件開示請求は権利の濫用と認められるべきであり、不開示処分とすることが適当であると主張したのですが、裁判所は次のように判断して、権利濫用による不開示決定は取り消されました。
<裁判所の判断>
1 「情報公開法においては、著しく大量の文書の開示請求であっても、そのことのみを理由として、不開示とする旨の規定を置いておらず、また、開示期限の延長を行うことで、通常業務と並行的に順次開示手続きを進行させていくことが想定されている。
したがって、開示請求文書の開示に相当な時間を要することが明らかである場合であっても、そのことのみを理由として、開示請求権の濫用として、開示請求を拒むことは原則としてできない。 開示請求に係る行政文書が著しく大量である場合又は対象文書の検索に相当な手数を要する場合に、これを権利濫用として不開示とすることができるのは、請求を受けた行政機関が、平素から適正な文書管理に意を用いていて、その分類、保存、管理に問題がないにもかかわらず、その開示に至るまで相当な手数を要し、その処理を行うことにより当該機関の通常業務に著しい支障を生じさせる場合であって、開示請求者が、専らそのような支障を生じさせることを目的として開示請求をするときや、より迅速・合理的な開示請求の方法があるにもかかわらず、そのような請求方法によることを拒否し、あえて迂遠な請求を行うことにより、当該行政機関に著しい負担を生じさせるようなごく例外的なときに限定される。」
2 「本件では本件開示請求を濫用したと認めるに足りる事情は認められない。行政機関においては、開示請求者に対して、差し当たり開示請求文書を半年分や一年度分に限定することや、まずその程度の開示を行ってそれ以外の分はその後に順次開示すること等の了解を得ることも可能であったと解される。」
(2)このように、具体的に権利の濫用にあたるかどうかの判断基準としては、単に大量文書の開示請求であるというだけでは足りず(平成19年8月31日高松高裁判決―判例秘書L066220712、平成19年10月31日さいたま地裁判決―判例秘書L06250518も同旨)、例えば以下のような事情が加わる必要がありますし、以下のような事情がある場合には、大量文書の開示でなくとも権利の濫用とされます。
● 実施機関の業務遂行の停滞を目的としていると認められるとき
(例) 正当な理由がないにもかかわらず、過去に開示請求を行った同一の行政文書について、開示請求を繰り返すとき
●開示請求を行い、決定されたにもかかわらず、正当な理由がなく閲覧等を行わないことを繰り返し、開示を受ける意思がないと認められるとき
(例) 複数回の閲覧期日の通知をしても、閲覧日に来訪しない事を繰り返しているとき
●特定の部、課、係等への集中又は連続した大量の開示請求であって、言動等により実施機関の特定の部署又は特定の職員への威圧、攻撃などを目的としている又は業務遂行を停滞させる害意が認められるとき
(例) 開示請求者において特定の職員を誹謗、中傷又は威圧するなどの言動があるとき
●特定の職員が関与する行政文書についての集中又は連続した開示請求であって、言動等により威圧などの害意が認められるとき又は他に業務遂行を停滞させる害意が認められるとき
●大量請求
(例) 「○○課の全ての文書」など大量の請求であり、開示請求の内容が具体的でなく、補正を求めても応じないとき
なお、開示請求に対して権利濫用を認めた判例として次の判例がありますので、ご紹介しておきます。
・名古屋地裁平成25年3月28日判決―判例秘書 L06851154
(開示請求書提出数は、平成17年度が7件、平成18年度が22件、平成19年度が217件、平成20年度が88件、平成21年度が413件、平成22年度が575件と全体開示請求件数の10%から82%を占める多数及び大量の開示請求を行った上、文書特定の補正拒否と開示前の取り下げ又は開示閲覧しない等の繰り返し、職員に対し写真撮影に応じるよう求めたり、自分を委員に選任せよとの不当要求を繰り返し、応じなければ大量の文書開示請求をするという形態であった。)
以 上
地方自治体作成の「初盆名簿」と個人情報保護(政教分離の検討も含めて)
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
○N町においては、死亡届受付の際に「初盆名簿」登載用に故人・喪主・公民館名・小組名を記載してもらって、毎年8月初旬に「初盆名簿」冊子を町内全体で回覧しているが、個人情報保護の観点から何か問題になるでしょうか?
「初盆名簿」を不要とする町民の意見では、個人情報保護の観点以外に、政教分離の観点から問題があるとする意見も出ているのですが、かかる観点から「初盆名簿」の作成回覧は、違法となるのでしょうか?
1.個人情報の取得について
個人情報を取得する場合には、「取得前」に利用目的を本人に明示する必要があります。個人情報を取得した場合、あらかじめ本人に告げた利用目的の達成に必要な範囲でしか利用できません。
従って、「初盆名簿登載用」と使用目的を明示した取得であれば(提出用紙に「初盆名簿に登載させていただきます。」と使用目的が記載してあれば)、個人情報保護上の問題は生じません。
しかしながら、かかる取得手続きを経ないで、公務員が死亡届出から「初盆名簿登載用」として故人・喪主・公民館名・小組名を名簿用紙に転記する方法の場合には、死亡届出の使用目的(戸籍住民票上の処理目的)を逸脱する取得となるか、目的外使用となるので、個人情報保護条例に違反する取得又は使用になる可能性があります。
2.個人情報の配布(初盆名簿の作成及び配布)について
(1)上記のとおり、個人情報取得時に「初盆名簿登載用と使用目的を明示した取得」であれば、初盆名簿の作成及び配布は、個人情報保護条例違反とはなりません。
(2)取得時にかかる使用目的を明示していない場合には、初盆名簿回覧(配布)は個人情報保護条例違反となる可能性があります。
3.初盆名簿の作成及び配布と政教分離について
(1)「政教分離の原則」とは、国家と宗教は切り離して考えるべきであるとする原則のことをいいます。政治と宗教が結びついた場合、国が特定の宗教に有利となるよう国政を行うことになるため、特定の宗教以外の宗教は、排除されていくおそれがあることから、信教の自由を保障するためにこの原則があります。
国家の行為が政教分離違反であるか否かを判断する際に採用される基準として、目的と効果の2つに着目し政教分離に反するか否かを判断します。これを「目的効果基準」と言い、①その行為の目的が宗教的意義を持ち、かつ、②その行為の効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為であるかどうかで判断することになります。そもそも、宗教的意義を有さない行事は「習俗」とされ「宗教儀式」ではないとされます。
(2)「習俗」といえば、一般に節分、七五三、雛(ひな)祭り、端午(たんご)の節句、各種の村祭り、死者の葬りの際の北枕とか副葬品、そして正月の門松などがそれに該当するでしょう。
日本の「初盆」は、日本国内においては、仏教行事なのでしょうか、神道行事なのでしょうか、儒教行事なのでしょうか、それとも習俗にすぎないのでしょうか?
初盆は、先祖の供養であり、供養の方式が仏教上も神道上も宗教的儀式で執り行われる限りでは、供養儀式自体は「①その行為の目的が宗教的意義を持つ」ということになり、単なる「習俗」とはならないでしょう。しかし、お盆の行事全体そのものが宗教行為かと言えば、その点は「習俗」という面が強く表れているのではないかとも考えられます。そこで、問題は「②その行為の効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為であるかどうか」ですが、初盆や先祖供養は本来の釈迦仏教の考えではなく、日本の古来の先祖霊崇拝の文化土壌に日本仏教や神道や儒教の考えが融合したものと評される面もあり、特定の宗教としての行事ではないことから、日本人一般の社会的通念からすれば、初盆の行事自体が「その行為の効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為」ではないと解釈される余地があります。
そもそも、N町における初盆名簿の作成及び配布は、その効果としては、宗教的行事を促す契機になるという意味で、宗教的行事に間接的に資する側面があるとしても、それ自体は「①宗教的儀式」そのものでもなく、かつ「②一定の宗教を援助、助長をする」効果についても、宗教とは無関係な広報としての行政サービスとしての目的による間接的かつ付随的なものにとどまっており、これが「宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるようなものである」とは到底認められないものであり、政教分離の原則に反するものではないと考えます。
(3)類似事案の判例として、東京地裁令和3年2月18日判決(判例地方自治No483-43)があります。
これは、警察署長が宗教法人のお寺が主催する節分会に参加して護摩祈祷と豆まきをした上、警察署警察官複数が雑踏警備に配置されていたという事案で、市民から、それらの参加行為や警備協力は政教分離の原則に違反する行為であるとして、その時間相当分の警察署長及び配置警察官への給与支出と出張交通費等の支払いが違法な財務会計上の行為であるので不当利得返還をすべきであるとして住民訴訟を提起された事案です。
裁判所の判断は、
「本件の警察署長等の護摩祈祷と豆まき参加行為は、宗教との関わり合いの程度が我が国の社会的文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度根本的目的との関係で相当とされる限度を超えるものとは認められず、憲法上の政教分離原則及びそれに基づく政教分離規定に違反するものでない。雑踏警備の実施について、結果として本件宗教儀式の実施に資する面があったとしても、その効果は、宗教とは無関係な市民の安全という目的の実現に伴う間接的付随的なものにとどまっており、特定の宗教を援助、助長、促進し又は圧迫、干渉等を加えるようなものとは認められないというべきであるから、信教の自由の確保という制度根本的目的との関係で相当とされる限度を超えるものとは認められず、憲法第20条3項の宗教活動にあたるとは言えず、憲法第89条の政教分離原則に違反するものとは言えない。」としています。
(4)このような判例からみても、N町における初盆名簿の作成及び配布は、宗教行為そのものでもありませんので、信教の自由の確保という制度根本的目的との関係で相当とされる限度を超えるものとは認められず、憲法第20条第3項の宗教活動にあたるとは言えず、憲法第89条の政教分離原則に違反するものではないと考えられます。
以 上
民事訴訟におけるDNA情報(DNA鑑定書)の取扱い
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
前回、刑事捜査手続き上の「DNA情報」の取扱いを説明しましたので、それに続き、民事訴訟上での「DNA情報」の取扱いについて基本的な点をお話しておこうと思います。
1.DNAとは?
DNA(デオキシリボ核酸)は、生物の細胞の核内に存在し、A(アデニン)、T(チミン)、G(グアニン)、C(シトシン)の4種類の部品でできていて、終生不変であり、私たちの「体を作る設計図」とも言われています。すべての人は指紋のように個々の特異的なDNA領域を持っているため、その特異的な領域を分析すること(鑑定)で個人の識別が可能になるとされています。
2.民事訴訟とDNA鑑定について
民事訴訟においては、DNA鑑定が問題となる典型的なものとしては、親子関係の存否がほとんどのようですが、不法行為訴訟や保険金請求訴訟などで加害者や被害者を特定するためにDNA鑑定が用いられている例もあるようです。DNA鑑定が民事訴訟の場に用いられる方法としては、多くは当事者が依頼した専門家の鑑定意見書(書証)として提出される場合(民事訴訟法第219条以下)ですが、裁判所において証拠調べとしての鑑定(民事訴訟法第212条以下)手続きで鑑定人が行った鑑定書が作成される場合もあります。前者の場合を私的鑑定(書)、後者の場合を公的鑑定(書)と呼ぶ例もあります。
3.DNA鑑定の留意点
DNA鑑定の検体としては、「毛髪」「口腔内の細胞」が一般的ですが、吸い殻 / 歯ブラシ / ヒゲ剃り / ガム / コップ・ペットボトル・缶 / ストロー / おしゃぶり / 血痕・血液 / 精液・体液・尿 / 毛髪・爪 / 生理用品 / 病理試料 / 血清 / 臓器・骨・歯 / 臍帯・胎盤 などでも可能とされています。私的鑑定、公的鑑定いずれの場合でも、鑑定実施の前提として、鑑定対象物(鑑定資料又は検体と呼ばれています。)が、DNA鑑定の対象となる特定人から適切に採取されたものであることが最も重要になります。
鑑定の結果としては、鑑定対象から採取された検体であることまで保証できるものではありませんので、民事訴訟において、DNA鑑定を証拠として採用して真否の判断に用いる場合には、鑑定結果とは別に、「鑑定された検体が、鑑定の対象となる特定人から適切に採取され、且つ採取時又はその後に汚染されないようにされたものであること」を証拠付ける必要があります。採取時の方法を画像撮影するか、第三者の立ち合いを求めた形で行うかという対応を取っておく必要があります。
4.DNA鑑定の拒否とそれに対する訴訟的対応について
民事訴訟でDNA鑑定が必要と判断されたが、当事者の一方がDNA鑑定の検体提供を拒否した場合は、どのような取扱いになるのでしょうか。
刑事訴訟においては、強制処分としての一定の令状に基づいて強制的に検体を獲得する方法が定められています。具体的には、被疑者からの鑑定資料の採取は、任意処分の場合は、口腔内粘膜等の任意提出(刑事訴訟法第221条)によりますが、強制処分の場合は、鑑定処分許可状と身体検査令状の併用(刑事訴訟法第218条、第225条)により被疑者の身体に対して直接強制力をもって行われています。
しかしながら、民事訴訟においては、そのような直接的な強制処分としての規定はありません。
民事訴訟法上の手続き規定を見てみますと、裁判所において当事者に対し証拠提出を求める方法としては、同法第223条で文書提出命令の定めがあり、第234条では、当事者が文書提出命令に従わないとき(他の証拠での立証が著しく困難となる場合も含む)は、裁判所は、当該文書の記載に関する「相手方の主張を真実と認めることができる」と定められており、検証手続きを定める第232条第1項で「第219条、第223条、第224条、第226条及び第227条の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。」と規定しています。
これらの規定により、裁判所はDNA鑑定のために血液等の採取・提供を命ずることができ、当事者は、検証協力義務としての検証受忍義務(血液採取受忍義務)及び検証物提示義務(血液提供義務)があり、正当な理由のないかぎりこれを拒否できないという一般的な義務があることになります。
それでも、一方当事者が検証協力義務としての検証受忍義務(血液採取受忍義務)及び検証物提示義務(血液提供義務)に従わない場合には、間接的な強制方法として「不利益認定」として、他方当事者の主張する事実を真実と認められてしまうようになっています。例えば、不法行為訴訟で原告から「加害者は被告である」と主張されたのに対し「加害者は自分ではない」と主張して争っている被告が必要な加害者のDNA鑑定手続きとして被告自身のDNA検体を提出を正当な理由なく拒否してDNA鑑定ができなかった場合には、原告の「加害者は被告である」との主張を認めることができる(民事訴訟法第224条第3項)という結果になってしまうわけです。
これは、いわば「証明妨害」として捉えて制裁する方法になりますが、証拠に基づく真実発見よりも、民事訴訟上の信義則としての手続的正義を重視するという立場になります。
5.DNA鑑定の拒否と人事訴訟について(親子関係の存否に関する裁判等の場合)
民事訴訟の特別法として人事訴訟法があります。人事訴訟法の審理対象は「人事訴訟」(=離婚の訴え、嫡出否認等その他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え)になります(第2条)。
この人事訴訟法第19条第1項は、民事訴訟法第224条等の規定(不利益認定規定)や自白規定の適用を明文で除外しています。このことにより、親子関係存否確認等の人事訴訟においては、親子間のDNA鑑定を拒否した場合には、拒否した当事者に必ずしも不利益に判断されるということにはなっていません。これは親子関係という身分に関する事項については、証拠に基づいて客観的に真実かどうかを見極めることを重視し、手続上の信義則違反に基づいて簡単に真実とすることはできないというものになりますので、一般的な民事訴訟としての判断方法は取らないということになります。このことはDNA鑑定の拒否に対しての民事訴訟と人事訴訟との大きな違いであることが認識されておくべきです。
但し、人事訴訟であっても、DNA鑑定を拒否したことに何ら合理性がない場合には、そのことを親子関係の存在を推認させる間接証拠として他の関連証拠と合わせて考慮すれば、親子関係の存在を認めることができるという認定をすることは実務上の事実認定方法としては許されているようです(東京地裁平成29年2月15日判決参照)ので、総合的判断をする裁判所においては、不当な結論になることはないようです。
以 上
警察取り調べでの「被疑者DNA型記録」等の採取の法的根拠を学ぼう!!
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
〇Aは、痴漢行為の迷惑防止条例違反と強制わいせつ嫌疑で現行犯逮捕され、処分保留となったが、逮捕された際の警察の捜査上で、Aの被疑者DNA記録(口内唾液の任意提出、指紋掌紋記録、写真記録(以下「3記録」という。)が作成されていた。
これは、憲法第13条で保障されているプライバシーの権利及び「個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由」又は「個人に関する情報をみだりに整理保管及び内部利用されない自由」を侵害するものだから、Aの人格権及び人格的利益に基づく妨害排除請求としての各記録(国に対して3記録、地方公共団体に対して指紋掌紋記録のみ)の抹消を求めたいが、抹消できるでしょうか。
1.DNAとは?
DNAは、デオキシリボ核酸の通称ですが、ヒトの細胞では核の中の染色体にあり、A(アデニン)、T(チミン)、G(グアニン)、C(シトシン)の4種類の部品でできています。DNAは、はしごをひねったような形をしていて、核の中の染色体の中に折りたたまれて入っており、私たちの「体を作る設計図」とも言われています。すべての人は指紋のように個々の特異的なDNA領域を持っているため、個人の識別が可能になるとされています。裁判上は、家庭裁判所での親子関係の判断や刑事裁判等での犯罪者の特定に利用されています。犯罪の被疑者として逮捕された際には、警察の捜査上で、写真記録や指紋記録以外にも、被疑者として「口内唾液の任意提出」がなされるなどしてDNA記録が作成されています。
2.ところで、法令上は末尾に示す3つの規則で定められていますが、「3記録」の抹消事由は、「本人が死亡したとき」、「記録を保管する必要がなくなったとき」とだけ定めてあり(DNA型記録取扱規則第7条、指掌紋取扱規則第5条、被疑者写真の管理及び運用に関する規則第5条)、相談事例では、Aは、被疑事件が処分保留となったとしても、無罪又は処分なしとはなっていないことから、「記録を保管する必要がなくなったとき」に該当しません。
また、「記録を保管する必要がなくなったとき」とは、「被疑事件捜査・司法手続上の必要性」ではなく、「記録を保管する必要性」であるので、「捜査が終わったから必要がなくなった」ということにはならず、捜査終了後も「将来の捜査」のために記録として保管し続ける必要性がある場合には、「記録を保管する必要性がある」ということになります。
従って、現在の法令や規則からすると、各記録のAの個人情報の抹消請求をしても認められないことになります。
3.現在の検察での被疑者取り調べでは、「3記録」が採取されているようです。警察は、十分な説明もしないまま、「任意捜査」として、「被疑者から承諾を得た」として写真撮影をし、指紋やDNAを採取していますが、「DNA採取月間」というのがあるようで、ノルマ達成のために、軽微な事件においてDNAを採取されている可能性があります。
このような、被疑者証拠の採取の実態と現在の法令や規則からすると、結局、一度警察から嫌疑を受けて「3記録」を採取されると、その証拠は「本人が死亡」するまで警察庁で管理されることになってしまいます。
4.そこで、そもそもそのような「3記録」の警察採取制度は、憲法第13条で保障されているプライバシーの権利及び「個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由」又は「個人に関する情報をみだりに整理保管及び内部利用されない自由」を侵害するものであるから、Aの人格権及び人格的利益に基づく妨害排除請求としての各記録(Aの個人情報)の抹消請求により抹消されるべきであるという考え方が出てくるわけです。
個人を特定する科学的証拠に基づいて個人が罪を犯した場合の犯罪捜査と刑事司法判断を容易にする必要性はあるものの、個人を特定する科学的証拠は、犯罪に関係しない日常生活の場においても国家が国民を監視するという「監視社会」を作り出す危険があります。少なくとも、被疑者特定証拠(3記録)は、「記録を保管する必要性」ではなく、「被疑事件捜査・司法手続上の必要性」が消滅した場合には、個人情報の抹消請求により抹消されるべきであるという規定が定められるべきではないかと考える余地が出てきます。しかし、判例は、次に述べるように現制度の規則規定のままでの運用を肯定しています。
5.この事例に関しては、東京地方裁判所平成31年2月28日判決(判例地方自治464-96頁)で「被疑者DNA型記録については、犯罪捜査に資するためという目的外での収集や利用が制限され、その漏えい、滅失又は毀損を防止するために必要な措置を講じるものとされ、更に濫用的利用等については刑罰が科されることとされており、警察において、被疑者DNA型記録が目的外に使用されたり、第三者に漏えい等されたりするなどといった具体的な危険が生じているとも認めることはできない。」とされており、指紋や顔写真についても同様に制度上濫用や漏えいについては罰則等があり得ること等から、「3記録」の抹消請求を否定しています。
<参照条文>
刑事訴訟法第218条 警察法第5条 第38条 第81条
警察法施行令第13条 警察庁組織令
DNA型記録取扱規則
指掌紋取扱規則
被疑者写真の管理及び運用に関する規則(写真規則)
〇 法的根拠条文
刑事訴訟法
第218条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
2 差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
3 身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、第一項の令状によることを要しない。
警察法
(任務と及び所掌事務)
第5条 国家公安委員会は、国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行うことにより、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とする。
2、3 略
4 国家公安委員会は、第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。
一 警察に関する制度の企画及び立案に関すること。
二から二十五 略
二十六 前各号に掲げるもののほか、他の法律(これに基づく命令を含む。)の規定に基づき警察庁の権限に属させられた事務
5 前項に定めるもののほか、国家公安委員会は、第一項の任務を達成するため、法律(法律に基づく命令を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事務をつかさどる。
6、7 略
(組織及び権限)
第38条
1~3 略
4 第五条第五項の規定は、都道府県公安委員会の事務について準用する。
5 都道府県公安委員会は、その権限に属する事務に関し、法令又は条例の特別の委任に基いて、都道府県公安委員会規則を制定することができる。
6 略
(政令への委任)
第81条 この法律に特別の定がある場合を除く外、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
警察法施行令
(国家公安委員会規則等への委任)
第13条 国家公安委員会が法第五条第四項の規定による管理に係る事務又は同条第五項若しくは第六項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定める。
2 都道府県公安委員会が法第三十八条第三項の規定による管理に係る事務又は同条第四項において準用する法第五条第五項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、都道府県公安委員会規則で定める。
警察庁組織令
(刑事企画課)
第22条 刑事企画課においては、次の事務をつかさどる。
一~四 略
五 刑事資料の調査、収集及び管理に関すること。
六 略
警察法施行規則
(刑事指導室)
第23条 刑事局刑事企画課に、刑事指導室を置く。
2 刑事指導室においては、令第二十二条第二号及び第四号に掲げる事務並びにこれらの事務に関し必要な刑事資料の調査、収集及び管理に関する事務並びに同条第六号に掲げる事務のうち日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十五条の規定による合同委員会との連絡に関する事務をつかさどる。
3、4 略
DNA型記録取扱規則
(作成等)
第3条 警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「犯罪鑑識官」という。)は、警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課(課に準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)から嘱託を受けて被疑者資料のDNA型鑑定を行い、その特定DNA型が判明したときは、当該被疑者資料の特定DNA型その他の警察庁長官が定める事項の記録を作成しなければならない。
2 略
(整理保管)
第6条 犯罪鑑識官は、第三条第一項の規定により被疑者DNA型記録を作成したとき又は同条第二項若しくは第三項(第四条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定による被疑者DNA型記録、遺留DNA型記録若しくは変死者等DNA型記録の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。
2 犯罪鑑識官は、被疑者DNA型記録、遺留DNA型記録及び変死者等DNA型記録の保管に当たっては、これらに記録された情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るため必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(抹消)
第7条 犯罪鑑識官は、その保管する被疑者DNA型記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該被疑者DNA型記録を抹消しなければならない。
一 被疑者DNA型記録に係る者が死亡したとき。
二 前号に掲げるもののほか、被疑者DNA型記録を保管する必要がなくなったとき。
2、3 略
指掌紋規則(指掌紋取扱規則)
(指掌紋記録等の作成)
第3条 警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課(隊その他課に準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、所属の警察官が被疑者を逮捕したとき又は被疑者の引渡しを受けたときは、指紋記録等及び掌紋記録等(以下「指掌紋記録等」という。)を作成しなければならない。
2 警察署長等は、身体の拘束を受けていない被疑者について必要があると認めるときは、その承諾を得て指掌紋記録等を作成するものとする。
(処分結果記録の作成等)
第5条 警察署長等は、第三条の規定により指掌紋記録等を作成した場合において、警察庁長官が定める事由に該当するに至ったときは、速やかに処分結果記録を作成し、これを警察庁犯罪鑑識官及び府県鑑識課長に電磁的方法により送らなければならない。
2 警察庁犯罪鑑識官又は府県鑑識課長は、前項の処分結果記録の送信を受けたときは、当該処分結果記録を整理保管し、又は当該処分結果記録に係る処分結果資料を作成し、これを整理保管しなければならない。
3 警察庁犯罪鑑識官又は府県鑑識課長は、その保管する指掌紋記録等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該指掌紋記録等及び当該指掌紋記録等に係る処分結果記録又は処分結果資料を抹消し、又は廃棄しなければならない。
一 指掌紋記録等に係る者が死亡したとき。
二 前号に掲げるもののほか、指掌紋記録等を保管する必要がなくなったとき。
写真規則(被疑者写真の管理及び運用に関する規則)
(被疑者写真記録の作成)
第2条 警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課(これに準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、所属の警察官が被疑者を逮捕し、又はその引渡しを受けたときは、画像を電磁的方法により記録することにより当該被疑者の写真(以下「被疑者写真」という。)を撮影し、当該被疑者写真及び当該被疑者の氏名、生年月日その他当該被疑者を識別するために必要な事項を電磁的方法により記録したもの(以下「被疑者写真記録」という。)を作成しなければならない。ただし、当該被疑者を他の警察署長等に引き渡す場合には、被疑者写真記録の作成を省略することができる。
2 警察署長等は、身体の拘束を受けていない被疑者について必要があると認めるときは、その承諾を得て被疑者写真を撮影し、被疑者写真記録を作成するものとする。
(被疑者写真記録の抹消)
第5条 警察庁犯罪鑑識官は、その保管する被疑者写真記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該被疑者写真記録を抹消しなければならない。
一 被疑者写真記録に係る者が死亡したとき。
二 前号に掲げるもののほか、被疑者写真記録を保管する必要がなくなったとき。
(被疑者写真の閲覧)
第7条 警察署長等は、被疑者の特定その他犯罪捜査のため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、被害者その他必要と認める者に対して被疑者写真を閲覧させることができる。
以 上
騙された公務員も損害賠償責任があるの?~印鑑登録の変更(廃止と申請)手続きに際して~
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
<質問> ○○市の市民課に勤めている地方公務員Yです。Aという人物が、市民Xさんの運転免許証を偽造(氏名はXさんで写真はAに変造)した免許証を示して、Xと称して、従来のXさんの印鑑登録の廃止届と新たな印鑑登録申請をしてきました。免許証の氏名と住所確認をして写真とAの顔を確認したので、印鑑登録の手続きを進めたのですが、まず、運転免許証を免許証識別装置(EXC-2500ZR2は約3秒で真贋判定を行う事ができる)に挿入したら「不可」の判定が出ました。免許証の裏に色々とシールなどが貼ってあり、厚さが異なっているので「不可」の反応が出たのだろうと考え、Aに対して「免許証に加工などはしていませんよね。」と聞いたところ、Aが「何もしていない。」と答えたので、手続きを進めました。印鑑登録申請書の「住所」の一部が運転免許証に書いてある住所と異なっていましたが、申請書の住所の方が書き間違いだと思って、その部分を私のほうで事実上訂正して手続を完了し、新たなX名義の印鑑登録証明書をXさんだと信じていたAに交付してしまいました。
その結果、悪人Aは、司法書士と通じてXさんの不動産(時価1億円)を売却してその代金をだまし取って逃げたようです。市民Xさんは、弁護士に依頼して、不動産登記の取戻裁判をして不動産を取り戻せたようですが、裁判にかかった弁護士費用500万円と慰謝料200万円を私に請求してきました。
一番悪いのはAであり、Aに騙されただけの安月給の一公務員である私が、このような損害賠償を払う責任があるのでしょうか。
<回答>
1.このような悪い奴が仕組んだ犯罪の場合には、一番悪いA(悪人A)が全部の責任を負わなくてはならないはずです。この場合、「被害者」は市民Xさんであり、土地を買ったのに取り戻された売買相手の方や売買登記に関与した司法書士、そして騙されて印鑑証明書を作らされ交付したYさんでしょう。
しかし、悪人Aが逃げてしまっている場合には、その被害者間で損害賠償請求が起こってしまいます。悪意がなくても誰かに過失があれば、その人が「不法行為責任」を負うという解決の仕方が民法などの法律に規定されているからです。
公務員の場合には、国家賠償法第1条第1項に「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」との定めがありますので、公務員Yさんに過失があれば、薄給のYさんではなく、Yさんが勤めている地方公共団体である○○市が賠償責任を負わされることになります。Yさん個人は原則として賠償責任を負いませんので安心してください。
でも、公務員はミスしても個人で賠償しなくていいなどと安易には考えないでください。同法第1条第2項に「前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」との定めがあります。ひどいミスの時は、この規定により○○市から賠償分を個人で負担せよという取り扱いがなされますので、日頃からの慎重な事務処理を心がけてください。
2.それでは、本件の場合、Yさんの印鑑登録業務の処理について国家賠償法第1条第1項の「故意又は過失によって違法」であったのでしょうか。悪人Aに騙されたことが「過失で違法」なのでしょうか。Yさんが悪かったのでしょうか。それを検討しましょう。
まず、過失責任とは、本来注意しながら仕事をすべき立場にある人が、相手方に不当な損害等の結果が生じることが気を配れば分かったのに、そのような注意や気配りをしなかったから、不当な結果が生じたという場合の法的責任を言いますので、その人に「注意義務」があり、「不当な結果の予見ができたこと又は予見可能性があったこと」が過失責任の要件になります。公務員は本来市民に対して法律に従って適正な処理をする立場にありますので、ご相談の事例の場合には、Yさんにおいて、市民課窓口に来ている悪人Aが市民Xでなく、運転免許証は偽造されているのではないかと気づく機会があったかどうか(不当な結果又は不当な結果の回避について予見又は予見可能性があったかどうか)がYさんの「過失責任」の有無の大前提になります。
(1)この点、運転免許証識別装置で「不可」と出たことは「予見可能性」があったことを意味します。仮に、運転免許証の裏にシールなどを貼った場合等に本物でも「不可」と出る経験をしていたとしても、特に真正なものであることの積極的な理由がないかぎり、「不可」の検査結果を「真正」と判断するのには合理性は無いように思います。
(2)次に、免許証の住所と印鑑登録申請書の住所の一部が違っていた点です。A本人が正確な住所を書けなかったということですから、窓口に来ている人物が市民Xでないかと疑うことが可能になります。
(3)Yさんとしては、以上の点を疑った結果、Aに対して「免許証に加工などはしていませんよね。」と聞いて、Aが「何もしてない。」と答えただけで手続きを進めていますが、運転免許証の確認や本人確認としては、生年月日、干支、家族構成などを尋ねてみることも容易であるし、家族への連絡をしてみるという方法もあり得ますので、確認方法としては不十分だった(すなわち、注意義務を十分に果たしていない)と言われる可能性があります。
(4)このような事例が問題となった、さいたま地裁平成30年9月28日判決(判例時報2410-63)は、次のように判断しています。
(判旨)
「本件についてみると、原告を名乗る申請者Aは、本人確認書類として原告名義の運転免許証(本件免許証)を提示したこと、本件免許証には申請者である原告の住所として「Y市I区L(以下略)」と記載されていたこと、埼玉県公安委員会が発行する運転免許証の住所表示は「Y市L町○丁目○番○号」と記載されること、原告を名乗る申請者Aが作成した申請書には「Y市I区N(以下略)」と記載されていたこと、上記のとおり本件免許証には町名が「L」と記載され、照合による情報においても町名は「L」であったこと、本件識別装置に本件免許証を挿入したところ「不可」と表示されたこと、Y市の担当職員はAを窓口に呼んで運転免許証を加工しているかを尋ねたところ、加工していないと回答したこと、担当職員は運転免許証の厚さによっては「不可」と表示されるため、今回も偽造によるものではないと判断したこと、そして、申請書の「N」を「L」と訂正し、申請者Aが原告本人であると判断して、所定の印鑑登録手続をしたことは上記認定のとおりである。
印鑑登録申請を担当した部署において、埼玉県公安委員会の発行する運転免許証の住所表示が「○丁目○番○号」であり、申請者により提示された運転免許証が上記表示となっているかを審査して運転免許証の偽造の有無を確認することが規定されているのでなければ、担当職員がその知識や経験のみで運転免許証の住所表示から偽造の有無を審査して判断することは容易でないといえる。
しかしながら、これに加えて本件では、申請書に記載された住所と運転免許証に記載された住所、照合した登録票の住所が異なっており、原告の年齢を考慮しても、住所の町名の記載を誤ることは多くないと考えられ、担当職員は申請者Aが原告本人であるかを疑う機会があったというべきである。しかも、運転免許証の偽造を検知する本件識別装置では本件免許証が不可と判定されており、本件免許証が偽造された可能性があることを疑うことができる状況にあった。
ところが担当職員は、申請者が住所の記載を誤ることがあるとの理由で申請書の住所を誤記として訂正してしまった。申請者が住所の記載を誤ることがあるにしても、本人が誤ったと判断する根拠があるのでなければ、申請書に住所を記載させて本人の同一性を確認する意味はなくなってしまうものというほかない。
また、担当職員の質問に対して申請者Aが加工していないと回答し、運転免許証の厚さによっては本件識別装置が不可と表示することがあったとしても、本件免許証が偽造されたものでないと判断できるだけの十分な根拠があったものではない。
そして、申請者Aが原告本人であるか、提示された運転免許証が偽造されたものではないかという疑問が生じたときは、担当職員としてさらに本人であるかどうかの審査をすることができた。例えば、担当職員は、生年月日、干支を質問したり、住民票を確認できるのであれば、家族構成、転居日等を質問したりすることができる。このような質問でも疑義が解消されないときは、申請者の了解を得て、家族に連絡を取るなどの方法もあり得るところである。本件の申請者Aは、申請書の住所の記載を誤っており、申請書の記載事項以外の質問をすることによって申請者Aが原告本人でないことが判明した可能性が高いといえる。
以上のとおり、Y市の担当職員は、印鑑登録の申請者Aが原告本人であるかどうかを確認する職務上の義務を負っていたところ、申請書記載の住所が本件免許証および照合した情報の住所と異なり、運転免許証の偽造の有無を判定する本件識別装置でも不可と表示され、申請者Aが原告本人ではないと疑うに足りる状況にありながら、運転免許証に加工していないかと質問したほかに本人であるかどうかの審査をせず、本人であれば容易に回答することができる質問によっても申請者Aが原告本人でないことが判明した可能性が高いといえるのであるから、Y市の担当職員は職務上の注意義務を尽くしたものとはいえず、本人と判断して所定の印鑑登録をした手続は違法なものと解することが相当である。」
この判例の結果は、公務員Yさんにおいては、「私は騙された被害者なのに、なぜ法的責任を負わされるのか?」という思いになるでしょう。
そこで、被害者の立場になる者同士の損害賠償の問題のときには、最終的な被害者である市民Xさんにも何らかの過失があったのではないかという「過失相殺」(民法第722条第2項)の処理がなされて損害賠償額が減額される場合が多々あります。相談事例では市民Xさんに、免許証を悪人Aに改ざんされるような免許証の保管が不十分であったとか、その他Xさんにおいて悪人Aの行為を予見できた事情等がある場合には、被害者Xさんの過失責任も当然に考慮されることになりますので、被害者相互間においても公平的な解決が図られる制度にはなっています。
以 上
住民基本台帳事務処理とDV被害者の支援措置②~DV加害者の代理人弁護士からの戸籍附票写しの交付申請があった場合の対応~
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
(前号から続く)
1.具体的事案におけるY市長の処理
DV加害者(A男)の代理人弁護士Xが、和解離婚後のDV被害者(B女)の仏壇や衣類・タンス等の引渡し協議のために、B女の戸籍附票(住所が記載されている)の写しの交付申請をしたという前回の具体的事案において、申請を受けたY市長はどのように対応したでしょうか。
Y市長は、既にB女に対するDV被害者支援措置を開始していたこと、申請者弁護士Xからは申出書に記載された「離婚訴訟代理業務」「離婚裁判の後処理のためにB女と連絡を取る必要があるがB女が所在不明となった」という内容以外にはXからの詳細な説明はなく、またXに対して説明を求めることもなく、XがA男の離婚訴訟事件の代理人として本件交付申請を行っていることから、戸籍附票の写しを交付した場合、A男に対してB女の住所を伝えるおそれが大きい者による申請である(加害者からの申請があった場合と同様である)と判断して、住民基本台帳法第20条第4項で規定されている「当該申出を相当と認めるとき」に該当しないとして戸籍附票の写しを交付しないとする処分(交付拒否処分)をしました。
なお、この際、Y市長はXに対して、B女につきDV被害者支援措置が開始されているという事実は説明しないままでの交付拒否処分をしていました。
弁護士Xは、Y市を相手に、本件交付拒否処分は裁量権の逸脱・濫用であり違法であるとして、交付拒否処分の取り消しを求める行政訴訟を提起しました。
2.結論の分かれた判例
さて、Y市長がDV加害者(A男)の代理人弁護士Xの戸籍附票の写しの交付申請を、A男の交付申請と同じであるとして、住民基本台帳事務処理要領の定める取り扱いに基づき交付拒否したことは、違法なのでしょうか。自治体の現場としては、戸籍附票の写しについて権利行使や義務履行のために弁護士が職務上請求をしてきた場合の有用利用の趣旨とDV被害者の安全の保護の趣旨との対立している状況において、その交付の可否についての判断は難しいものがあると思います。
この事案では、裁判所の結論も分かれています。一審地裁判決は、「交付拒否処分は違法であり、交付すべきであった」としていますが、二審高裁判決は、「交付拒否処分は適法であり、交付しない取扱いでよい」としています。あなたは、どちらの見解を支持されますか?
(1) 和歌山地裁平成29年6月30日(判例時報2375・2376号189頁)
一審地裁判決の要旨は次のとおりです。
①(違法判断基準)市町村長は、DV加害者からDV被害者の戸籍附票写し交付申出がされた場合でも、戸籍附票の写しを交付する必要性が高く、かつ被害者の保護の見地を含む諸事情を総合考慮した上で交付することに相当性が認められる場合に、支援措置を講ずることとした者(被害者)に係る戸籍の附票の写しの交付申出に対し、利用目的を適切に審査することなく、加害者による申出(又は依頼者が加害者である申出)であることのみを理由に戸籍の附票の写しの交付を安易に拒絶することは、住民基本台帳法の解釈として許される裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用するものとして違法となる。
②(比較考量事情)A男は、離婚和解条項で定められた仏壇・タンス等の引取りが実現する前に、B女が代理人弁護士との委任関係を終了したことからB女への連絡手段を失っており、代理人弁護士Xが戸籍の附票の写しを取得することによりB女の住所を知る以外にB女と仏壇等の引渡しの協議をし又は提訴する方法はないことから、Xが戸籍の附票の写しを取得する必要性は高い。
他方、B女は、離婚和解において仏壇等の授受についてA男と協議する旨合意しているから、A男又はその代理人と協議できる状況を整える信義則上の義務があるのに、自分の代理人弁護士を解任して以降、A男側と連絡を絶って、協議することを拒絶している。(B女の保護性は弱いと判断している?)
従って、A男は住民基本台帳法第20条第3項第1号の「自己の義務を履行するために戸籍の附票の記載事項を確認する必要がある者」に該当し、その代理人であるXにおいて戸籍の附票の写しの交付を受ける必要性が高く、交付することに相当性が認められる。
③(行政裁量行為での調査不足)Xは弁護士であり、基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とする法律専門職であることからすれば、加害者の親族等などの弁護士以外の代理人からの場合と異なり、Y市長は、Xに対して、B女が支援措置の対象者であることを伝えた上で、B女の戸籍の附票の写しをA男に交付しないという方法やB女の住所をA男に伝えないように誓約してもらう等の方法により、被害者の保護に支障が生じないようにして戸籍の附票の写しの交付申出の目的を達することも可能であったにもかかわらず、Xに有用使用の目的等につき何ら質問や調査もせずに、本件処分(交付拒否)をしているのであるから、その裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用するものとして違法というほかない。
なお、本件では、申出書に「離婚訴訟代理業務」「離婚裁判の後処理のためにB女と連絡を取る必要があるがB女が所在不明となった」と記載されているのであるから、事務処理要領第6の10コ(イ)の「申出に特別の必要が認められる場合」にあたる事情が存する可能性について容易に予測できたのであるから事実確認をする必要性が高かったと言える。
(2) 大阪高裁平成30年1月26日(判例時報2375・2376号182頁)
一審地裁判決に対して、住民基本台帳事務処理要領による取扱いを重視し、DV加害者の代理人弁護士による戸籍附票の写しの交付申請もDV加害者本人による申請に準じて取り扱うという解釈をして、DV被害者としての支援対象者に支援措置の必要性があるので、交付拒否は適法であるとしています。二審高裁判決の要旨は次のとおりです。
①(事務取扱要領の法的拘束性)住民基本台帳法第3条では「市町村長は、常に、住民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」と定められており、住民に関する記録の適正な管理を図り、住民のプライバシー保護に配慮することは、市町村長の基本的な責務であり、市町村長はその責務を果たすため必要な措置を講ずるように努めなければならないのであり、他方、同法第31条第1項で「国は都道府県及び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。」と定められていることから、DV被害者等への支援措置の運用に関しては、国より事務処理要領が定められているのであるから、各市町村長は、その定めが明らかに法令の解釈を誤っているなどの特段の事情がない限り、これにより事務処理を行うことが法律上求められているといえる。
事務処理要領第6の10によれば、市町村長はDV被害者等の保護を目的として、住民基本台帳法第20条第4項等に基づき支援措置を講ずるものとされ、加害者とされている者からの戸籍附票の写しの交付申出については、原則として同条第3項各号に掲げる者に該当しないとして同法に基づきこれを拒むとするものであり(平成16年5月31日総行市第218号質疑応答)、これは、住民のプライバシー保護に配慮する住基法の目的に合致すると共に、DV被害者の適切な保護を図る責務を果たすという配偶者暴力防止法第2条、第9条の観点からも合理性を有するものであるから、事務処理要領第6の10は住基法の解釈を誤ったものということはできない。従って、市町村長はDV被害者等に係る戸籍の附票の写しの交付については、事務処理要領第6の10に従って運用し、裁量権を行使すべきこととなる。
②(裁量判断~比較考量~)加害者から依頼を受けたことが明らかな代理人弁護士からの戸籍の附票の写しの交付申出は、加害者本人からの申出がなされた場合に準じて扱われるべきであり、支援措置としての戸籍附票の写しの交付誓約は、支援対象者(被害者)について支援措置の必要性がある場合に、戸籍の附票の写しの記載が加害者に知られることにより、支援対象者の生命又は身体に危険が及ぶ可能性をできる限り排除しようとするためのものであり、目的達成の手段として不相応な制約ということはできない。
本件申出書に記載された利用目的は、訴訟事件の事後処理のためにB女と連絡を取る必要がある(仏壇等の引取りの協議をするための連絡)というにすぎず、本件申出以後の確認では、B女はA男の代理人弁護士Xから連絡を受けることすら拒否しており、その結果、代理人弁護士に対して戸籍の附票の写しを交付することは相当でないとして、交付拒否した本件処分は、Y市長の裁量権を逸脱し、濫用したものということはできない。
③(結論)原判決は相当でないから、本件控訴に基づき原判決を取消し、A男代理人弁護士Xの請求を棄却する。
3.地方自治体担当者の苦悩と基本的な対応について
地方自治体の業務には、市民の紛争当事者の一方と他方から挟み撃ちの状態になる業務が多くあります。本件のように、事後的に判断できる裁判においてさえ、考え方や結論が異なる事案を、地方自治体の担当者は的確に判断して戸籍付票の写しの交付をするか拒否をするかを決める立場に立ちます。判断に困る場合には、基本的には立ち止まる形での処理(本件では拒否しておく)でいいのではないかと思います。
そのことで、後に裁判で拒否したことが違法であると判断されたとしても、それは担当者個人の責任ではないと考えられます。その判断は法的にも難しい場合には、仮に拒否処分が違法だと判断されたとしても、判例上は、当該公務員には不法行為としての故意又は過失がないという認定がなされ、結局国家賠償法による賠償請求は認められないことが多くあるからです。
以 上
住民基本台帳事務処理とDV被害者の支援措置①~DV加害者の代理人弁護士からの戸籍附票写しの交付申請があった場合の対応~
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
1.住民基本台帳法による戸籍附票交付請求制度
戸籍附票には、戸籍記載者の住所履歴や現在の住所が記載されていますが、誰でも自由に戸籍附票の写しの交付を受けられるわけではありません。住民基本台帳法第20条では、「戸籍の附票に記録されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属」(同条第1項)の他、「戸籍の附票の記載事項を利用する正当な理由がある者」(同条第3項第3号)、「特定事務受任者(弁護士・弁護士法人・司法書士等)から、受任している事件又は事務の依頼者が前項各号に掲げる者に該当することを理由として、戸籍の附票の写しが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該戸籍の附票の写しを交付することができる。」(同条第4項、第12条の3第3項)とあり、弁護士も依頼者から具体的事件の受任している場合で必要性がある場合には、市町村長に対して、第三者の戸籍附票の写しの交付申請をして、第三者の居住先等を知ることができる仕組みになっています。
2.具体的事案
次のような場合には、市町村長は、代理人弁護士による戸籍附票写しの交付請求に応じることができるのでしょうか。それとも交付拒否をすべきでしょうか。
(1)A男とB女は夫婦であり、A男のB女に対する暴力による夫婦不和により、B女の避難別居(居所を明らかにしない)状態での離婚訴訟の末、離婚和解が成立した。
(2)和解条項で「A男は和解成立後、A男宅にあるB女先祖の仏壇や衣類・タンス等をB女が引き取ることを認め、引取り日時・場所等は別途協議して定める」とあったので、B女との協議を試みたが、和解離婚時のB女の代理人弁護士から「訴訟終了によりB女との委任関係はなくなるので、今後はB女と直接連絡して協議して欲しい」と言われていたことから、B女の弁護士を通じて協議ができなくなり、B女の住所を調査する必要があった。
(3)A男は、離婚訴訟の代理人であったX弁護士に、B女の住所調査を依頼し、X弁護士は、請求者をXとする交付請求書(「離婚訴訟代理業務)依頼者A男)によりB女にかかる戸籍附票の写しの交付請求をした。
(4)B女は、離婚訴訟前からY市に対しDV被害者としての支援措置の実施を求める申出をし、Y市長は警察署等の第三者機関から意見を聴取し、B女に対しDV被害者としての支援措置を開始していた。B女は訴訟後も支援措置ないしその延長を受けたい旨を申し出ると共に、A男の代理人弁護士からの連絡を受けることも拒否する旨の連絡をしている。また、B女は裁判所の離婚和解時において、仏壇等の引取り協議はしないままでよいとの意向を示している。
3.DV被害者に対する支援措置とは?
配偶者でなくなった者の戸籍附票の写し交付申請要件の「正当な理由」や職務上の請求要件の「相当と認めるとき」の解釈に影響を与えるものとして、平成16年5月31日「住民基本台帳事務処理要領の一部改正について(通知)」(法務省民一第1581号)による「ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者を保護するための支援措置」制度があります(いわゆる「DV被害者等支援措置」)。
これは、配偶者等から暴力等を受けて、警察等の第三者機関により警告や保護命令等が実施されている被害者に支援措置申出があった場合に、市町村長が住民票や戸籍附票写し等の本人以外からの交付申請に対して、市町村長が、その使用目的等の厳格な審査を行って交付するか否かを検討し交付拒否する場合があるという制度です。その結果、DV等の被害防止のために、DV加害者等に対しては交付申請要件の「正当な理由」や職務上の請求要件の「相当と認めるとき」に該当しないとして、戸籍附票の写しの交付を拒否し、被害者の現在の住所・居所等を知らせないという運用がなされることになります。
4.問題点
このような「支援措置」を行っているB女に対して、DV加害者であるA男の代理人弁護士(Ⅹ)から、B女がどこに住んでいるかの判明する戸籍附票の写しの交付申請があった場合、市町村の担当者は、どう対応すべきなのでしょう。
住民基本台帳事務処理要領の第六の10にその支援措置に関する以下のような規定があります。
支援措置
(ア) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出に係る支援措置
A 市町村長は、支援対象者に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧について、以下のように取り扱う。
(A) 加害者が判明しており、加害者から申出がなされる場合(閲覧者、閲覧事項取扱者の中に、加害者が含まれている場合を含む。)
法第11条の2第1項各号に掲げる活動に該当しないとして申出を拒否する。
(B) 支援対象者本人から申出がなされた場合
支援対象者本人からの閲覧の申出については、対象となる住民が氏名等により特定されているものであるため、閲覧制度ではなく、住民票の写しの交付制度により対応することが適当である。
(C) その他の第三者から申出がなされた場合
加害者が第三者になりすまして行う申出に対し閲覧させることがないよう、十分留意して厳格に本人確認を行うことが適当である。
また、加害者の依頼を受けた第三者からの閲覧に対し閲覧させることがないよう、利用の目的等について十分留意して厳格な審査を行うことが適当である。
なお、加害者が国又は地方公共団体の機関の職員になりすまして閲覧を請求することも考えられるため、法第11条に基づく請求であっても、閲覧者については、十分留意して厳格に本人確認を行うことが適当である。
B 市町村長は、その判断により、閲覧申出において特別の申出がない場合には、支援対象者を除く申出であるとみなし、支援対象者に係る部分を除外又は抹消した住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供することとして差し支えない。なお、この場合、市町村長は、閲覧申出用紙に明記する等により、あらかじめその旨を申出者に明らかにする。
ただし、このような取扱いをする場合にでも、国又は地方公共団体の機関による請求の場合及びその他の者による支援対象者に係る閲覧を求める特別の申出の場合には、Aの例により取り扱う。
(イ) 住民票の写し等及び戸籍の附票の写しの交付又は申出に係る支援措置
市町村長は、支援対象者に係る住民票(世帯を単位とする住民票を作成している場合にあっては、支援対象者に係る部分。また、消除された住民票及び改製前の住民票を含む)の写し等及び戸籍の附票(支援対象者に係る部分。また、消除された戸籍の附票及び改製前の戸籍の附票を含む )の写しの交付について、以下のように取り扱う。
(A) 加害者が判明しており、加害者から請求又は申出がなされた場合
不当な目的があるものとして請求を拒否し、又は法第12条の3第1項各号に掲げる者に該当しないとして申出を拒否する。
ただし、(ア)-A-(C)に準じて請求事由又は利用目的をより厳格に審査した結果、請求又は申出に特別の必要があると認められる場合には、交付する必要がある機関等から交付請求を受ける、加害者の了解を得て交付する必要がある機関等に市町村長が交付する、又は支援対象者から交付請求を受けるなどの方法により、加害者に交付せず目的を達成することが望ましい。
(B) 支援対象者本人から請求がなされた場合
加害者が支援対象者本人になりすまして行う請求に対する交付を防ぐため、代理人若しくは使者又は郵便等による請求を認めないこととする。ただし、特別の必要がある場合には、あらかじめ代理人又は使者を支援対象者と取り決める、支援対象者に確認をとるなどの措置を講じた上で、請求を認めることとする。
また、第2-4-(1)-①-ア-(イ)に準じて本人確認をより厳格に行う。
ただし、市町村長が当該措置を不要と認める者については、この限りでない。
(C) その他の第三者から申出がなされた場合
加害者が第三者になりすまして行う請求に対する交付を防ぐため、第2-4-(1)-①-ア-(イ)に準じて本人確認をより厳格に行う。また、加害者の依頼を受けた第三者からの請求に対する交付を防ぐため 、(ア)―A―(C)に準じて利用目的についてもより厳格な審査を行う。
ただし、市町村長がこれらの措置を不要と認める者については、この限りでない。
5.この事務処理要領によれば、本件具体的事案の場合には、A男や弁護士Xにおいては提出先のある事案ではないので、(イ)-(A)のただし書きの「請求事由をより厳格に審査した結果、請求に特別の必要があると認められる場合でも、加害者に交付せず目的を達成することが望ましい。」との原則からすれば、加害者代理人弁護士(X)にも交付しないか、または、代理人弁護士(X)のみの範囲で使用し、加害者A男には知らせないという制限付きで交付するということを検討することになるでしょう。
次回、実際の裁判ではどういう結論になったかを論じていきます(次号に続く)
以 上
公務災害補償における通勤災害の「逸脱・中断」の例外とは?
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
<事例>
Aさんは、普通自動二輪車での通勤途上、通勤道路沿線にあるコンビニエンスストアに立ち寄り当日の昼食を購入し、同店舗の駐車場から通勤道路に入ろうとした際に、駐車場内で自動車と衝突し、普通自動二輪車ごと転倒し左膝関節骨折等の怪我を負った。通勤災害として治療費・休業損害の補償を受けられるか。
1.お正月も終わり、御用始め・仕事始めと共に通勤生活が始まりましたが、朝方の通勤時には多くの通勤者がコーヒーや軽食を求めてコンビニエンスストアに立ち寄る姿を見かけます。
今回は、公務員の公務災害補償制度における通勤災害について学んでおきましょう。
(1)地方公務員災害補償法で、次のような定めがあります。
第1条「地方公務員等の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)の迅速かつ公正な実施を確保する」(一部省略)
第2条第2項「この法律で「通勤」とは、職員が、勤務のため、次に掲げる移動(代表的なものとして「一 住居と勤務場所との間の往復」が挙げられている)を、合理的な経路及び方法により行うことをいう」(一部省略)
同条第3項「職員が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合には、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて総務省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。」
(2)これを分かりやすくまとめると、次のようになります。
① 通勤災害と認められるためには、公務員が勤務の為、住居と勤務場所との間を合理的な経路及び方法により往復することにより当該災害(事故等)が発生したものでなければなりません。
② 合理的な往復の経路であっても、「逸脱」又は「中断」した場合には、逸脱又は中断した間はもちろん、その後通常の往復経路に戻った場合でも通勤災害にはなりません。
③ しかし、経路からの「逸脱又は中断」が「日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための必要最小限度のものである場合(地方公務員災害補償法施行規則第1条の5「日用品の購入その他これに準ずる行為」等)には、当該逸脱又は中断の間を除いて、通勤災害と認められます。
(3)さらに解釈を細かく検討してみましょう。
① 「逸脱」とは、通勤とは関係のない目的で合理的な経路から逸れることをいい、「中断」とは、合理的な経路上において、通勤目的から離れた行為を行うことをいいます。したがって、通勤の途中で劇場に寄って映画を見たり、酒屋で一杯飲みをしたりする場合は、逸脱又は中断に該当し、当該逸脱又は中断後は通勤とはみなされません。
② 地方公務員災害補償法施行規則の「日用品の購入その他これに準ずる行為」とは、飲食料品、衣料品、家庭用燃料品など、職員又はその家族が日常生活の用に充てるものであって、日常しばしば購入するものを購入する行為、又は家庭生活上必要な行為であり、かつ、日常行われ、所要時間も短時間であるなど、前記日用品の購入と同程度に評価できる行為をいいます。したがって、日用品の購入のほか、独身職員が通勤途中で食事をする場合、理髪店、美容院へ行く場合などがこれに該当するとされる余地もあります。
2.本件事案の検討
(1)本件事案では、Aさんは、当日の昼食を購入するためにコンビニエンスストアに立ち寄っていますので、通勤とは関係のない目的で合理的な経路から逸れており、「逸脱」「中断」に該当しますので、本来は通勤災害にはなりません。
(2)次に、例外の「日常生活上必要な行為であって総務省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合」「日用品の購入その他これに準ずる行為」に該当しないでしょうか。
公務災害補償基金本部裁決例では、「例えば、通勤途上で尿意をもよおしたためにトイレを借用する目的でコンビニエンスストアに立ち寄ったり、喉の渇きを癒すために水分を補給する目的で立ち寄ったりした場合には、人の生理的な理由があり、必要最小限度の「ささいな行為」と言えるものであり「通勤に伴う合理的必要行為」と認められるが、本件の場合には、早朝の通勤途上で当日の昼食を購入する目的でコンビニエンスストアに立ち寄ったものであり、生理的な理由とは異なり、「通勤に伴う合理的必要行為」でもなく「ささいな行為」でもない。」と判断しているものがあります(災害補償2021年10月No.570―33頁)
しかし、Aさんの当日の昼食の購入は、上記の例で示したように、地方公務員災害補償法施行規則で示される「日用品の購入その他これに準ずる行為」に該当している点で、通勤災害の適用はあると解釈すべきでしょう。しかしながら、次の点を更に検討しなければなりませんので、まだ通勤災害の適用があるとは断定できません。
(3)通勤災害として適用されるために検討しなければならないのが、災害を受けた場所です。「逸脱」「中断」の場合、通勤災害として適用されるのは、その後通常の経路に戻り、その経路上で災害を受けた場合に限定されています(法第2条第3項は「当該逸脱又は中断の間を除き」としています。)。本件の場合、災害を受けた場所は駐車場内であり、通常の経路に戻っていないため、まだ「当該逸脱又は中断の間」の災害ということになります。そのため、本件事例の場合には、災害時と災害場所の関係で、通勤災害にはならないことになります。
(4)結論:Aさんは、通勤災害としての補償を受けることはできません。
以 上
<お正月と法律>年賀状を見て思ったこと~文書の訂正 印影の訂正~
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
(相談)
あけましておめでとうございます。年賀状もパソコン等でにぎやかに作成されたものが多くなり、毛筆やペン字での手書きのものはすっかり少なくなりました。手書きのため文字を訂正した年賀状も昔は何通かもらったものです。今年の年賀状を見て思ったのですが、パソコン利用で文章の書き直しは何度でも自由にできるので、訂正のある書面は一般的な書面としても全く見かけないようになりましたね。
ところで、パソコン利用の文書でも、書き直しせずに訂正して契約書などとして官公庁に提出したり、法律的な文書で手書きが求められている書面で訂正したりする場合もあるやに聞いています。契約書の記名の訂正、押印の訂正について、正しい訂正方法があれば、教示されたい。
(回答)
「文書の訂正」ということで、最初に法律上のことで申し上げておきたいことは、年賀状はパソコンを利用して作成してもいいのですが、遺言状は「自筆(手書き)」でないといけないということです。自筆遺言状(正式には「自筆証書遺言」といいます)をパソコンで書き、無効な遺言状となった例(判例:東京高裁平成13年11月28日判決―判例時報1780号104頁)もあります。
自筆遺言状の字句の訂正方法については、民法第968条第3項に「自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」とありますが、この規定の他に文書や印影の過誤訂正方法を定めた法律や通達等はないようです。
そもそも、押印制度は、中国・日本などの一部の慣行として維持されてきているもので、印鑑登録制度以外に法的に定められたものはないようです。
従って、一般的な文書や契約書等の押印の訂正方法について法的に正しい方法というものはないと言わざるを得ません。
但し、社会慣例として、公文書においても私文書においても、文書の過誤はそれぞれの分野での慣例に従った方法で行われていますので、慣例上求められる方式はあります。
一般的には、上記の遺言状の過誤訂正(加除)の方法に準じて、「二重線で消したその上部に正しい文字や数字を書き加える。訂正部分の近くの欄外あるいはページの上段の欄外に訂正した行、削除した字数と書き加えた字数を「○行目、○字削除、○字加筆」のようにして記載する。その後に記載した削除、加筆の字数の横または下に契約当事者双方が署名、押印で使用した印鑑と同じもので訂正印を押印する。」というのが最も厳格な方法であろうと思われます。記名部分の訂正はこの方法となるでしょう。
契約者双方が作成したものとなる契約書では、双方が同じ契約書を所持するので、抹消した人の印鑑だけで訂正してもいいのですが、後の争いが無いようにするには、契約者双方の押印をしておくべきでしょう。
「印影」の訂正方法としても、上記の文書の訂正方法に準じて、訂正したい「印影」の上に二重線を引き、余白に「印影を削除した」と記載して、契約者の正しい印影(契約書の場合には契約者双方の印影)を押印する、という方法になるでしょう。
そうなると、昨今のコロナ禍のリモートワークの影響で打ち出された「官公署届出等での押印廃止」(令和2年7月7日付総務省自治行政局長通知「地方公共団体における書面規制、押印、対面規制の見直しについて」等)が問題になります。文書に印鑑・印影が不要であれば、文書の訂正として「印影」が押印できないし、押印しても全く意味がなくなるからです。
しかし、私は、この点は特に影響しないのではないかと思います。文書の訂正方法としては、契約書の場合には、契約者同士が「訂正していること」を承知していれば良いのであって、双方が合意した訂正方法(例えば、訂正したい印影に×印を付けるとか、×印を付けた印影は削除したものであるとの付記をするだけ)であれば、問題はありませんし、敢えて印鑑や印影を必要とするものではないからです。
もっとも、文書による契約書において将来の争いが全く生じないようにしたい場合には、「文書や印影の訂正」ではなく、「新たに別個の文書を作成し直す」ということが求められます。
公文書の場合も、基本的には、文書決裁後の訂正は認めない(修正のための決裁文書を起案する)との内閣府大臣官房公文書管理課長通達(平成30年8月 10 日 府公第172号)がありますので、文書は「訂正」ではなく、「作成し直す」ことを基本にすればいいわけです。
お正月は、「年を改める」こと。新しい1年を作っていくのですから、「旧年を訂正」する方法(=コロナ禍の収束)ではなく、「新年を作成」する方法(=コロナ禍の終息)で良い年が迎えられるといいですね。
以 上
遺産となる預金を勝手に使った者が得をする?
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
<事例>
被相続人甲には、長男Aと長女Bの2人の子供がいました。Aは結婚して被相続人の隣に住んでおり、Bは嫁いだので、親である甲の元気な姿を見るために時々甲宅を訪問し話し相手になっていました。甲が死亡した際に、BはAから「甲の遺産として預金通帳にも何も残されておらず、分けるものがない。」と言われましたが、通帳取引経歴を調べてみると、甲が死亡する1年前に400万円がAの銀行口座に振り込まれており、その後半年間で、更に合計500万円が引き出されていました。1年前の400万円は子供の大学進学費用として甲がAに贈与したものであり、その後の合計500万円について、Aは「自分は引き出していないし使っていない。」と主張していましたが、裁判の結果、1年前の贈与400万円は有効と認められ、その後の使途不明金500万円についてはAが勝手に取得したものとして、その500万円分のうちBの法定相続分はAの不当利得になるとして、250万円をBに支払うこととなり、Bが勝訴しました。
しかし、本来なら使途不明金500万円の預金が残っていたことになり、遺産分割協議を行えば、Aには1年前の400万円贈与という「特別受益」があるので、Bの取り分が250万円より多くなるのですが、250万円より多くもらうことができるでしょうか?
<解 説>
1.検討課題の説明
今回は、お金の計算のクイズみたいな事例です。
甲には、死亡1年前の時点で900万円の預金があったわけですが、そのうち、Aに400万円贈与し、更にAが500万円を勝手に引き出して使い、甲の死亡時点では、何の遺産も残っていなかったという事例になります。
本来は、甲の遺産としては900万円あったので、それが死亡時まで残されていれば、Aが450万円、Bが450万円の遺産を取得することになるものです。(なお、遺留分としても各自225万円の権利を有しています。)
しかしながら、死亡前にAへの生前贈与400万円、Aの使途不明不当利得500万円があったことから、Bの相続の権利(相続分450万円、遺留分225万円)は変わらずに確保されるものなのかを検討していきたいと思います。
2.400万円の贈与による不平等の修正
相続人(子の相続)の均等相続の原則(民法第900条第4号)から、他方の子供に生前贈与がなされている場合に、死亡時に実際の遺産が残っていれば、遺産分割協議がなされ、その分割計算方法として、「特別受益」が問題になります。特別受益とは、相続人が被相続人から生前に贈与を受けていたり、相続開始後に遺贈を受けていたり、被相続人から特別に利益を受けていることを言います。特別受益を受けたものが共同相続人の中にいる場合に法定相続分通りに相続分を計算すると、不公平な相続になってしまいます。このような不公平な状態を是正するため民法第903条で特別受益がある場合の相続分の計算が規定されています。Aへの400万円贈与は「特別受益」になります。民法第903条によって、特別受益分400万円は遺産に算入され、本件の場合には、400万円が遺産分割対象となり、Bは法定相続分1/2の200万円を取得し、使途不明金返還分250万円と合わせれば本来の相続分450万円が取得できることになります。
しかしながら、この点については、相続時に「現実の遺産」が残っていなかった場合に、そもそも遺産分割手続きができるか?という大前提の問題があります。遺産分割手続きは死亡時に存在する相続人の相続「共有」状態の遺産を分割する手続きだからです。
3.使途不明金に関する遺産性
Bの立場から、「現実の遺産」としては使途不明金分の金銭が残っていたはずであるという主張が考えられますが、使途不明金の問題は、そもそも遺産としてはどういう性格のものになるのでしょうか?
この点については、現実の預金として残っていない以上は、「預金」としての遺産とは言えません。「預金」としての遺産分割手続きはできません。
使途不明金の問題は、そもそもAが甲の生存中に、甲に無断で甲の預金からお金を引き出し使ったという横領又は窃盗等の犯罪行為に類するものであり、甲はに対して、民法上の不法行為としての損害賠償請求権(民法第709条)又は不当利得返還請求権(民法第703条)という「債権」を有している状態であり、「甲のAに対する金銭債権」という「債権」の遺産ということになります。
そうであれば、「債権」としての遺産分割手続きができるのではないかということになりますが、これについては、最高裁昭和29年4月8日判決-判例タイムズ40-20等で「相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権があるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する。」とされ、「損害賠償請求等の金銭債権は可分債権であり、各相続人の分割単独債権となり共有関係には立つものではない。」とされており(なお、この分割債権性は、預金の共有関係を認めた最高裁平成28年12月19日大法廷決定―判例時報2333-68においても変更されていない)、その結果、使途不明金の不法行為損害賠償請求権又は不当利得返還請求権の可分債権は、相続と同時にすでに分割済みであり、遺産分割の対象にはならないということが確定しています。ただし、相続人全員の同意があれば、遺産分割手続きの対象とすることができるという裁判所の運用例があります。(最高裁昭和54年2月22日判決等)
従って、Bとしては、使途不明金に関する遺産分割は、Aの同意がない以上は遺産分割手続きをすることができませんので、Aの特別受益を考慮した平等な分配を求めることができないという状態になります。
4.遺留分減殺の方法からの検討
Bは、遺産分割すべき遺産が無いという状態なのであれば、相続すべき遺産がなく、自分の遺留分が侵害されたのではないかということから、遺留分侵害分の返還(又は損害賠償)をAに求めることを検討することになります(民法第1046条)。
遺留分とは、「相続人が一定の割合の受け取りを法律上で保証されている相続財産の取り分」のことですが、民法第1042条により、Bは生前贈与及び使途不明金等を相続財産とした900万円全体について法定相続分(1/2)の更に1/2の遺留分権を有しています。それを金額に換算すれば、900万円×1/2×1/2=225万円になります。
問題は、Bにおいて遺留分額225万円が侵害されているかどうかですが、Bは使途不明金の裁判で250万円勝訴していますので、遺留分225万円以上の相続財産を取得できていることとなり、遺留分は侵害されていないことになりますので、残念ながら、遺留分を加えて、250万円以上を請求できる根拠にはなりません。
5.結論
以上の検討の結果、本来の900万円の遺産が残っていれば、Aが450万円、Bも450万円の平等分割できたものが、Aへの生前贈与と、使途不明引き出しというAの行為により、最終的には、Aが400+250=650万円、B使途不明金返還分250万円のみという不平等な結果が生じてしまうことになります。
それで、表題を「遺産となる預金を勝手に使った者が得をする?」としたのですが、この不平等な結果の原因は、相続人全員が使途不明金を遺産分割の対象とすることに合意しないと、原則として遺産分割事件において解決をすることができないという手続き上の制約に基づくものであり、これをやむを得ないと考えるのか、遺産分割手続きの対象範囲を広げる法改正を図るべきと考えるか、あなたはどちらでしょうか?
(なお、民法改正により民法第906条の2により「遺産分割前の遺産処分」に関する「みなし遺産」規定が設けられていますが、これは「遺産相続後の遺産分割前の遺産処分」の意味に限定され、遺産相続前の遺産処分の場合には適用がないと解釈されていますので、この問題はまだ解決されていません。)
以上の経過からして、遺産となる預金を勝手に使ったAのほうが得をするということになりそうですが、Aは、「500万円を勝手に引き出している」ということになると、遺産分割上は有利になっても、刑事上の問題としては、「勝手に引き出して取得したもの」として、窃盗罪又は横領罪の刑事犯罪になり、懲役等の刑事上の処罰を受けて、その結果、損害を受けた者(甲又はB)に対する損害賠償義務を負いますので、結局は、刑事上の処罰を受ける分、非常に「損をする」という結論になります。
以 上
田舎の土地の登記手続を放置していてもよいか?
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
(相談内容)
私は宮崎県内の片田舎のN町で農家の長男として生まれ育ちましたが、公務員となって家庭も持ち東京で生活しています。N町に住んでいた両親が亡くなり、私が成人したとき(昭和60年)に生前贈与を受けて私の所有名義に移転登記した家・屋敷(不動産所在地はN町、所有者である私の登記上の住所は、学生時代のF市ののまま)の不動産と、父が平成30年に死亡した際の相続財産である農地と駐車場になっている雑種地(不動産所在地N町)がありますが、兄弟姉妹が多いのですが、誰も「田舎(N町)
の土地は要らない」と言っていて、父や母からの相続登記をしていないままです。不動産登記はこのまま放置していても構わないでしょうか?
(ご回答)
1 わが国においては、すでに少子高齢社会が始まっていますが、全体的な人口減少により、田舎では誰も住んでいない「限界集落」地域が発生していくと言われています。誰も住まないのであれば田舎の土地は無用の長物となり、かつては相続財産としてプラス財産の中でも最も価値のあった不動産ですが、これからは、固定資産税や賦課金等の負担や管理費用だけが生じるマイナス財産(負債)になっていくのではないかと思われる状況が発生しています。ご相談者のように、相続財産として誰も田舎の土地は要らないと言っている状況は、そのことを示しています。
2 不動産の登記制度は、本来は価値ある不動産の所有者を明記することにより第三者に対する公示力及び対抗力(民法第177条等)によって権利者を保護することを目的とする制度であります。また、建物の新築時に行う『建物表題登記』、建物を取り壊した際に行う『滅失登記』及び土地の地目が変わった場合の『地目変更登記』などのいわゆる「表示に関する登記(表示登記)」に関しては過料制裁による登記義務が定められていますが(不動産登記法第164条)、所有権移転登記(相続登記も含む)、住所変更登記、所有権保存登記などの「権利に関する登記(権利登記)」については、不動産権利者(所有者等)の権利であり不動産権利者(所有者等)の義務ではありませんので登記しなくても過料制裁はありません。
今般、民法や不動産登記法等の改正法律が成立(令和3年4月21日)しました。改正前の不動産登記法上は、相続登記も住所変更登記も「権利登記」ですから、そのまま放置していても構わなかったのですが、今後は「権利の登記」の放置は過料制裁の問題になります。
3 この不動産登記法の改正により、「相続登記」と「登記名義人の住所変更登記」は義務化されましたので、登記手続きを放置していると、「相続登記」の場合には10万円以下の過料制裁、「住所変更登記」の場合には、5万円以下の過料制裁を受けることになりますので、放置したままではいけないことになります。
なぜ、これらの登記手続きだけを義務化したのかと言いますと、昨今、不動産登記簿を見ただけでは所有者が直ちに判明できないような土地や、所有者が判明しても住所地に所有者が所在せず所在不明で連絡できないような土地(これを「所有者不明土地」と言います。)が、全国土の22%にまで及んでいて(平成29年国交省調査)、公共事業用地買収等の手続きが円滑に進まない状況や、土地管理が全くなされず荒れ地となって近隣や地域に悪影響を与えるなどの社会問題が生じていることから、登記に関する法制度を整備する必要があったからです。
そこで、過料制裁を加えるという形で、「不動産を取得した者は、取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする」(改正不動産登記法第76条の2)、「氏名や住所等に変更があったときは、登記名義人は変更した日から2年以内に変更登記の申請をする」(同法第76条の5)という定めに改正されました。
相続登記義務化は令和6年4月までに施行され、住所等変更登記義務化は令和8年4月までに施行される予定ですので、まだ3年程先の話ですが、対応の準備をしておく必要があります。
ご相談への回答としては、「田舎の土地や建物の登記手続は放置しないで確実に手続きをしましょう。」ということになります。
4 相続土地国庫帰属制度の導入について
最後に、相続した土地について誰も不要だとして所有者が決まらない場合の対処方法として「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(相続土地国庫帰属法)が制定されたことをお話しておきます。
ご相談者の場合のように、相続登記がなされず放置されている土地が増加している原因の一つとして、相続人各自が相続した土地の利用を希望しないケースが増えています。現在の法制度としては不動産の所有権放棄は原則として認められていないことから、結果として土地の所有権等の権利が残りながら権利者が不在のままで登記も管理も放置されていくわけです。
そこで、相続又は遺贈により取得した土地の所有権を持ちたくない場合には、国庫(国の所有)に帰属させるという制度を創設しました。しかし、これには次の要件が必要で、どんな土地であっても国が引き取ってあげるという制度ではありません。
①土地所有権の管理を阻害するような要素や争いのある土地や管理に過分の費用や労力を要しない土地であること
②10年分の土地管理相当額の負担金を納めること
この要件は、国はまっさらの土地で、かつ買い取ってくれるのではなく、国庫納入負担金10年分を払ってもらえば土地を国が引き取ってあげます、という制度ですから、冒頭に申し上げた、相続する田舎の無用な土地は、相続土地国庫帰属制度を利用したとしても負担だけ負うマイナス財産になるわけです。なお、相続土地国庫帰属制度は令和5年までには施行される予定です。
以 上
法定外公共物の管理に関する考え方(ある法律相談から)
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
(相談)
法定外公共物である水路(その形状が消失している)を挟んだ両側の土地(不動産登記法第14条第1項の地図上の水路の西側土地がA氏所有地、水路の東側土地がB氏所有地)の各所有者A氏とB氏とが境界争いをしており、境界の基準となる水路の位置を現地で確定するように〇〇市に強く要求している。〇〇市としては、水路を示す資料がないことから、A氏、B氏それぞれに境界確定訴訟を提起してもらって解決するしかないと訴え提起を指導しているが、どちらも自分に費用がかかる手続きはしたくないと訴え提起をせずに、〇〇市が測量等をして相手方に水路を明確に示して解決しろと要求を続けている。〇〇市としてはどういう対応をすればよいか。
(説明と回答)
1 法定外公共物とは
道路や身の回りにある用排水路、湖沼、池沼などの公共物のうち、道路法、下水道法などの特別法によって管理の方法等が決められているものを法定公共物といいます。これに対して、道路法や河川法などが適用されないものを法定外公共物といいます。代表的なものに、里道(赤道)、水路(青道)があります。
2 法定外公共物の管理について
法定外公共物は、すべて慣習法に基づいて管理が行われ、今日に至っていると言われています。法定外公共物でも、国が公共の用に供するものとして「国民に使用を許可しているもの」であり、国民は「使用料支払義務」の代替として「公共物を保全管理する義務」を有するとされています。公共物を保全管理するとは、公共物内に私権を設定せずに、形状や位置の変更を加えずに利用又は使用することであり、その使用の範囲を管理する(すなわち、官民境界を明示する)義務を有しているとされています。
「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(平成11年7月16日法律第87号。以下「地方分権一括法」という。)により、法定外公共物を市町村へ譲与することになりましたが、そもそも、国有財産法第18条第1項・第6項の規定によれば、公共物は受益者(国民)が、道路は道路として、水路は水路としての使用目的を果たすことを条件として法制上無償使用が許可されているものであり、その反対給付として受益者に保全管理する義務が生じると解釈されてきたのです。
地方分権一括法は、法制上、公共物の使用許可者が国から市町村に変更されたにすぎず、受益者の保全管理義務は変更ないので、市町村は、受益者に保全管理義務があることを指導する立場にあり、決して管理義務を負うものではないことに特徴があります。
使用許可を受けたり使用を認められている受益者は、その使用している公共物と自己の所有地との法定境界(地租改正処分確定境界)を不動産登記法第14条第1項に基づく地図及び旧土地台帳付属地図(公図)に基づいて明示する義務を有しているとされてきたことから、決して、公共物管理権限(使用許諾権限)を有する市町村側で、「境界を示す義務」があるわけではありません。
3 本件の回答における基本的考え方(法定外公共物に関する通達等について)
以上の見解を明示する通達や法令はないようですが、従来からそのように解釈されてきていることから、本件では、A氏及びB氏に対して、水路位置の現地での明示を〇○市がしなければならい義務はないと言えます。受益者兼隣接地所有者であるA氏とB氏が境界確定訴訟等で私権行使をすれば足りる話だと考えられます。
4 境界確定訴訟について
なお、境界確定訴訟は、形式的形成訴訟という性質の裁判になるのですが、形式的形成訴訟は、当事者の提出する証拠に基づいて当事者の主張で求められた範囲内で裁判する通常の民事裁判(給付裁判、実質的形成裁判)とは異なり、当事者の主張や証拠を検討し参考にはしますが、それらに何ら拘束されることなく、最終的には、裁判官の合理的判断で境界線を定めることができますので、境界の基準となる水路(法定外公共物)に関する資料や証拠もなく何ら証言できないとしても、裁判所は判決で境界線を定めることはできます。
「水路を示す資料がないことから、A氏、B氏それぞれに境界確定訴訟を提起してもらって解決するしかないと訴え提起を指導している」というご対応でよろしいかと思います。
出典 塚田利和「法定外公共物の成立と境界確定の実務」新日本法規(2000年)
以 上
「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」って、誰のことをいうのか?(その③)
(付録)配偶者の生計維持要件について
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
1.問題点
今までの2回は、「配偶者」の範囲について説明してきましたが、我が国の社会福祉生活の救済又は向上を図るための給付行政関連法令では、次の条文に示すように、「配偶者」等の給付を受けられる身分的地位以外に、「生計を維持した者」といういわゆる生計維持要件を求める規定があります。
そこで、最後に付録として、その生計維持要件について説明いたします。
○厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)
(未支給の保険給付)
第37条 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時
その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。」
(遺族)
第59条 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持したものとする。
4 第1項の規定の適用上、
被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
○同施行令
(遺族厚生年金の生計維持の認定)
第3条の10 法第59条第1項に規定する被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた配偶者、子、父母、孫又は祖父母は、当該被保険者又は被保険者であつた者の
死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣の定める者とする。
2.生計維持要件とは?
厚年法の「生計を維持していたこと」(生計維持要件)は、施行令により「被保険者であつた者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた」という生計同一要件とされており、更に、その生計同一要件については、厚生労働省年金局長通知(平成23年3月23日「生計維持関係認定基準等取扱通知」)により次のように定められています。
(1) 次のいずれかに該当する場合
①「住民票上同一世帯に属しているとき」
②「住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき」(内縁関係を想定)
③「住所が住民票上異なっているが、現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき」
(2) 上記の①、②、③に該当しない場合においても、
単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、
A「生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること」
B「定期的に音信、訪問が行われていること」
➡「その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められること」
(3) 上記(1)(2)の基準で生計維持関係の認定を行うことが
実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなる場合には、上記(1)、(2)の基準によらずに認定することができる。
3.事案の検討と判例の見解
生計維持要件・生計同一要件について具体的な例で考えてみましょう。
○具体例
夫婦間で、妻が夫の暴力(DV行為)から逃れるために、約30年の夫婦生活の後、約13年間別居し、住民票上の妻の住所も移転していた場合に、遺族厚生年金を受給できる「配偶者で、かつ、死亡の当時その者と生計を同じくしていた者」に該当するでしょうか。
このような事案について、上記の生計同一要件を認定基準に従って詳細に検討した判例があります。以下、東京地方裁判所の令和元年12月19日判決を紹介します。
この判例は、認定基準の上記2の(2)「単身赴任、就学又は病気療養等のやむを得ない事情により別居している」が、「その事情が消滅したときには、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められること」を該当性の一つとして判断しているようにも思えますが、認定基準2の(3)の「上記(1)、(2)の基準で生計維持関係の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ社会通念上妥当性を欠くこととなる場合には、上記(1)、(2)の基準によらずに認定することができる。」場合の一つの例として判断したものだと解することができます。
○判例(東京地裁令和元年12月19日判決-判例秘書)
(事案の概要)
①原告は、昭和44年10月13日、Aと婚姻し、その後、平成15年5月15日に別居するまでの約33年間にわたり、同人と同居していた。
②昭和45年11月10日、双子である長男及び長女が出生したが、Aは、その頃から、原告に対してたびたび暴力を振るうようになった。
③Aは、平成2年頃から、原告や長女に対して頻繁に暴力を振るうようになった。(長女の右耳の鼓膜に傷害を負わせるなどしたため、長女は同年9月より家を出て一人暮らし)
④原告は、Aによる暴力をその後も繰り返し受け、平成11年1月21日には、Aにより顔面を殴打され、全治1か月を要する鼻骨骨折の傷害を負った。Aの暴力により身の危険を感じたとき、原告は、一時的な避難のために家を出て、長女や親戚の家に身を寄せるなどし、このような家出は複数回に上った。(家出の際、自己が管理していたAの銀行等口座から預貯金を引き出し、当面の生活費として使用したほか、いざというときのために現金で貯蓄していた)
⑤原告は、平成15年5月14日、Aから激しい暴力を受けた上、「明日はバットを持ってきてたたき殺すから、がん首洗って待っておけ。」と言われ、生命の危険を感じ、翌15日にAが外出している隙に長女に迎えに来てもらい、Aとの別居生活を開始した。(別居を開始する際、Aが自宅の金庫内で保管していた現金200万円(長女の婚姻時の結納金100万円、Aの母の遺産分配金100万円)を持ち出したほか、平成15年5月16日、Aの銀行口座から合計170万円を引き出したりしたが、Aは、「お金がなくなれば戻ってくれば良い」などと言うのみで、原告に対して返金を求めたことはなかった。)
⑥Aは、別居開始以降、原告の居場所を探して、原告の実家や熊本市内の親戚の家を訪ね、「これからも叩く。俺の言うことをきかないなら叩く。」などと言い、原告に対する暴力を反省する態度は全く見せなかった。
⑦原告は、Aが退職後国民健康保険にも入らず、原告も加入できていないことから、健康保険への加入の必要性を強く感じたことから、同年4月4日、自らの住民票上の住所を東京都足立区の長男の住所へ移し、さらに、長男が平成24年7月24日に千葉県鎌ケ谷市に転居した際にも、住民票上の住所を長男の転居後の住所へ移した。
⑧Aは、第三者への暴行・傷害2件で約3年間の懲役刑で服役し、大分刑務所を出所後、平成28年8月21日頃から同月31日頃までの間に自宅で死亡した。(Aの死亡は同年9月6日に発見され、死亡の届出は原告が行った)
⑨平成28年11月30日「被保険者の死亡の当時、その者によって生計を維持したもの」には該当しないという理由で、原告に対して遺族厚生年金を支給しない旨の決定がなされた。
(争点)
本件の争点は、本件不支給処分の適法性であり、具体的には、原告が厚年法第59条第1項にいう「被保険者の死亡の当時、その者によって生計を維持したもの」(生計維持要件)に該当するかであり、さらにいえば、厚年法施行令第3条の10にいう「被保険者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた者」(生計同一要件)に該当するかどうかですが、遺族年金不支給という結果が、最終的には「その認定が、実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ社会通念上妥当性を欠くこととなる場合」にならないかという観点からの判断も必要になります。
裁判所の判断(判例の内容)は次のとおりです。
(判決の骨子)
1. 厚年法59条1項が、遺族厚生年金を受けることができる遺族について、被保険者等の死亡当時、その者によって生計を維持したものであることを要する(生計維持要件)としているのは、被保険者等の死亡によって生計の途を失う者は生活保障の必要性が高いため、これを遺族厚生年金の支給対象として保護しようとするものと解される。
2. 認定基準では、「単身赴任、就学又は病気療養等のやむを得ない事情により別居しているが、生活費、療養費等の経済的な援助が行われていることや、定期的に音信、訪問が行われていることといった事実が認められ、その事情が消滅したときには、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき」であれば生計同一要件を満たすものと認定し得ることとしているが、これは、当該配偶者が被保険者等と別居し、住民票上の世帯及び住所も別にしているが生計同一要件を満たすと評価できる典型的な場合について定めたものというべきであり、夫婦の在り方にも様々なものがあり得ることに照らせば、生計同一要件を満たすと評価される場合を認定基準に定める場合に限定するのは相当ではない。
この点、認定基準総論ただし書において、認定基準の定めに従うことにより生計維持関係の認定を行うことが実態と著しく懸け離れたものとなり社会通念上妥当性を欠くこととなる場合には、認定基準の定めによらずに認定すべきものとしているのは、以上に説示したところと同旨をいうものとして正当というべきである。
3. 本件において、原告は、被保険者であるAの死亡当時、同人と住民票上の世帯又は住所を同一にしておらず、起居を共にしていたとも認められないため、それでもなお生計同一要件を満たすと評価できる事情があるといえるか否か(が問題である。)
4. 長男及び長女が出生した昭和45年頃から始まったAによる暴力が、次第にその頻度及び程度を増し、一時的な避難のための家出を繰り返しても事態は改善しないどころか、生命の危険を感じる事態となったことから、原告は、平成15年5月にAとの別居を開始するに至ったものであり、別居はやむを得ない事情によるものということができる。
また、(経済面でも)別居中の原告の生計を維持するには、原告の年金収入及び長男や長女等による経済的援助だけでは足りず、同居中の夫婦財産である金銭を生活費に充てるために原告が別居時に持ち出すなどしたことについては、Aも黙認していたり、また、長期間に及ぶ別居にもかかわらず、原告又はAのいずれからも離婚に向けた働きかけがされたことはなく、原告とAとの婚姻が形骸化し、婚姻が解消されたのと同様の状態にあったとは評価することができない(状況であった)。
5. 被告は、本件が、認定基準の「生活費、療養費等の経済的な援助が行われている」場合や「定期的に音信、訪問が行われている」場合に当たらない旨を主張するが、当該認定基準は、当該配偶者が被保険者等と別居し、住民票上の世帯及び住所も別にしているが生計同一要件を満たすと評価できる典型的な場合について定めたものであり、
生計同一要件を満たすと評価される場合をこれに限定するのが相当でないことを示しており、また、原告がAと長期間にわたり別居したのはAの暴力から逃れるためであるから、Aの原告に対する積極的な経済的援助や定期的な音信、訪問等が期待し得る状況になかったことは明らかであり、
本件の事情の下において、これらの経済的援助や音信等がないからといって生計同一要件を認めないとすることは、厚年法施行令3条の10の解釈適用を誤るものといわざるを得ない。本件は、認定基準総論ただし書により、認定基準の定めに従うことにより生計維持関係の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり社会通念上妥当性を欠くこととなる場合には、認定基準の定めによらずに認定すべきものとしている(場合に相当するものとして、)原告については、厚年法施行令3条の10に定める生計同一要件及び収入要件のいずれも満たすものと認められ、したがって、
厚年法59条1項にいう生計維持要件を満たすものと認められるから、同項に定める遺族厚生年金を受けることができる遺族に該当する。
そうすると、原告がこれに該当しないことを理由として遺族厚生年金を支給しないものとした本件不支給処分は違法であり、取り消されるべきである。
以 上
「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」って、誰のことをいうのか?(その②)
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
前回(1)(2)(3)に続き、今回は、我が国の給付行政関連法令での給付を受けられる地位としての「配偶者」には「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も含む」とされているが、その範囲に同性間の婚姻(同性婚)をしている場合も含まれるのかという問題を検討していきたいと思います。
(4)同性間の婚姻(同性婚)の場合、婚姻届書が提出できなくても当該地方自治体からのパートナーシップ証明書の交付を受ける場合がありますが、この場合には、諸給付を受けられる「配偶者」ということになるのでしょうか。
地方自治体からのパートナーシップ証明書の交付を受けている場合、同性婚夫婦の相互の権利が法的保護の対象になるかという点については、女性同士の同性婚をして地方自治体からパートナーシップ証明書の交付を受け、円満な共同生活を続けていたX子とA子に対して、男性BがA子と男女関係を結び、X子とA子との同性婚共同生活が破綻したという事案において、X子から男性Bに対して(不貞行為)慰謝料請求を認めた判例(東京高裁令和2年3月4日判決(原審:宇都宮地裁真岡支部令和元年9月18日判決)があり、同性婚も一定の法的保護を受けられるという傾向にあります。
しかしながら、公的給付制度における「配偶者」性による受給権まで保障されるかどうかについては、次に示すように肯定説、否定説の両説がありますが、最高裁の判例はなく、現時点では名古屋地裁判例に示されるように、「我が国において同性間の共同生活関係を婚姻関係と同視し得るとの社会通念が形成されていたということはできない。」ことを理由に、「同性の犯罪被害者と共同生活関係にあった者が、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「犯給法」という。)第5第条1項第1号にいう『事実上婚姻関係と同様の事情にあった者』に該当するとまではいえない。」として、同性者の内縁関係又は同性婚の関係にある者については、公的給付を受けられる「配偶者」性は否定されています。
【1】 論説(参考)
*肯定説
内縁法理は、単に経済的弱者を保護するための制度と捉えられるべきものではなく、広く、種々の理由から法律上の要件を満たさないために婚姻の届出をすることができない者に対して及ぼし得るものとされている。すなわち、〈ア〉婚姻適齢に達していない場合、〈イ〉再婚禁止期間中である場合といった、時の経過によって婚姻障害事由が消滅する場面において、内縁法理による保護が及ぶのはもとより、〈ウ〉重婚の禁止や〈エ〉近親婚の禁止にそれぞれ抵触する場合など、公序良俗との抵触や倫理性の点に疑義がある場合においてすら、少なくとも一定の事例では内縁法理による保護が及ぶことは判例上確立した法解釈である。このように、公序良俗との抵触や倫理性の点に疑義がある場合についてすら、内縁関係としての保護が及ぼされている状況に照らせば、同性間の共同生活関係についても、公序良俗との抵触や倫理性の点に疑義がない以上、内縁関係として保護されるべきであることは当然である。
なお、内縁関係の定義において「夫婦」という用語が用いられることがあるが、これは、同性婚〔同性間の婚姻〕が想定されていなかった時代の名残であり、また、これまで同性間の共同生活関係が内縁関係に該当するか否かが争われた事例がなかったからにすぎず、同性間の共同生活関係を除外する趣旨ではないとみるべきである。
*否定説
「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」とは、いわゆる内縁関係にあった者をいい、具体的には、当事者間に社会通念上夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があり、かつ、当事者間に社会通念上夫婦の共同生活と認められるような事実関係が存在する必要がある。
① 民法においては、婚姻により配偶者の関係にあるものは「夫婦」とされており、同法第739条、第750条等によれば、「夫婦」とは、夫と妻という両性の関係を前提とする概念であると理解されるのであって、現に同法第731条においても「男」、「女」という表現が用いられている。
② 戸籍法第74条に基づく婚姻の届出の様式(戸籍法施行規則第59条、附録第12号様式)においても「夫になる人」、「妻になる人」の記載が必要とされている。
③ これらのことからすると、現行法上、婚姻は異性間で行われることが前提となっているものと解され、犯給法にこれと異なる趣旨の規定は存しない。そうすると、「事実上婚姻関係と同様の事情」として位置付けられる内縁関係も、当然に異性間の関係であることが前提となるから、同性間の関係がこれに包含されることはあり得ず、これに反する立論は、いかに国民の意識等を背景としているとしても、立法政策論の域を出ないというべきである。現在、種々の形で同性パートナーが異性の場合と同様に保護されている旨を指摘するが、原告が指摘する制度は、同性間の共同生活関係を婚姻関係と同様に扱うというものではなく、事実上の配慮として同性間の共同生活関係について一定の利益を付与するものにすぎないから、同性間の共同生活関係において婚姻の意思や婚姻としての実態が認められるという社会通念が形成されているとはいえない。
【2】判例
〇名古屋地裁令和2年6月4日判決―判例時報2466-13(控訴中)
(事案の概要)
(1)原告(男性)と本件被害者(男性)は、平成6年頃に知り合って交際するようになり、その頃から約20年間同居して生活していた。
(2)(本件殺害行為)原告と交際していた本件加害者は、平成26年▲月▲日、原告と本件被害者との関係が継続しているために原告を独り占めすることができないなどと考えて、本件被害者に対して殺意を抱き、原告及び本件被害者の居宅において、本件被害者の左胸部を持っていた洋出刃包丁で1回突き刺すなどし、本件被害者を出血性ショックにより死亡させた。
(3)原告は、平成28年12月12日、愛知県公安委員会に対し、「犯罪被害者の配偶者」(犯給法第5条第1項第1号)に当たるとして、犯給法第4条第1号所定の遺族給付金の支給の裁定を申請したが、愛知県公安委員会は、平成29年12月22日付けで、本件申請につき、遺族給付金を支給しない旨の裁定をした。
(判決骨子)
(1)同性の犯罪被害者と共同生活関係にあった者が犯給法5条1項1号の「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当し得るか否かについて
ア 犯給法は、犯罪行為により死亡した者の遺族又は重傷病を負い若しくは障害が残った者(遺族等)の犯罪被害等を早期に軽減するとともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるようにするため、犯罪被害等を受けた者に犯罪被害者等給付金を支給するものであり(1条、3条)、重大な経済的又は精神的な被害を受けた遺族等が発生した場合には当該遺族等を救済すべきとする社会一般の意識が生じ、他方で実際上不法行為制度の下での損害賠償等により救済を受けられない場合が多い中で、その状況を放置した場合には法秩序に対する国民の不信感が生ずることから、社会連帯共助の精神に基づき、租税を財源として遺族等に一定の給付金を支給し、遺族等の経済的又は精神的な被害を緩和するとともに、国の法制度全般に対する国民の信頼を確保することを目的とするものと解される。
イ(ア) 犯給法5条1項は、遺族に支給される遺族給付金の支給範囲を、犯罪被害者の配偶者とした上、その配偶者に「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」を含むものとしている。このような犯給法5条1項の規定内容からすると、
犯給法は、民法上は法律婚主義が採用されていることから(739条1項)、一次的には死亡した犯罪被害者と法律上の婚姻関係にあった配偶者が遺族給付金の受給権者とされるべきであるものの、前記のような犯給法の目的に鑑み、死亡した犯罪被害者との間において法律上の婚姻関係と同視し得る関係を有しながら婚姻の届出がない者をも保護しようとするものであると解される。そして、①前記のとおり、犯給法の目的が、社会連帯共助の精神に基づいて、租税を財源として遺族等に一定の給付金を支給し、国の法制度全般に対する国民の信頼を確保することにあることに鑑みると、
犯給法による保護の範囲は社会通念により決するのが合理的であること、②犯給法5条1項2号、3号に掲げられた
親子、祖父母、孫や兄弟姉妹といった親族は、社会通念上、犯罪被害者と親密なつながりを有するものとして犯罪被害者の死亡によって重大な経済的又は精神的な被害を受けることが想定される者であり、これらと並んで同項1号に掲げられている「配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)」に該当する者についても、同様の者が想定されていると考えられることからすると、同性の犯罪被害者と共同生活関係にあった者が犯給法5条1項1号の「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当するためには、同性間の共同生活関係が婚姻関係と同視し得るものであるとの社会通念が形成されていることを要するというべきである。
(イ) この点につき、原告は、重婚的内縁や近親婚的内縁といった、法律上婚姻が認められていない類型における内縁関係にあった者についても「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当し得ることは解釈として確立していることを指摘し、そうである以上、特に法律上禁止されていない同性間の共同生活関係は、当然に内縁関係として保護されるべきであり、同性同士で共同生活関係にあった者は「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当し得るという趣旨を主張する。
確かに、①重婚的内縁の場合、戸籍上届出のある配偶者との婚姻が事実上の離婚状態にあるとき、②近親婚的内縁の場合、近親者間における婚姻を禁止すべき公益的要請よりも犯給法の目的を優先させるべき特段の事情が認められるときには、そのような関係にあった者は、それぞれ「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当する余地があるものと解される(①につき、最高裁昭和54年(行ツ)第109号同58年4月14日第一小法廷判決・民集37巻3号270頁参照、②につき、最高裁平成17年(行ヒ)第354号同19年3月8日第一小法廷判決・民集61巻2号518頁参照)。しかしながら、
重婚や近親婚は、婚姻に該当することを前提とした上で、これを認める弊害に鑑み、政策的に法律婚としては一律に禁じられているものである。それゆえ、個別具体的な事情の下で婚姻を禁ずる理由となっている弊害が顕在化することがないと認められる場合には、法律婚に準ずる内縁関係としての要保護性まで否定する理由はないとの判断が働き、そのような場合の内縁関係は法律婚に準ずるものとして保護されるものと解される。これに対し、同性間の共同生活関係については、政策的に婚姻が禁じられているというのではなく、そもそも民法における婚姻の定義上、婚姻に該当する余地がないのであるから(なお、この解釈自体については、原告も争うところではない。)、重婚や近親婚の場合とは自ずから局面を異にしているといわざるを得ない。
したがって、重婚的内縁や近親婚的内縁が一定の場合に内縁関係として保護されるからといって、同性間の共同生活関係が内縁関係に含まれる理由となるとは解されない。
ウ 同性間の共同生活関係に関する理解が社会一般に相当程度浸透し、差別や偏見の解消に向けた動きが進んでいるとは評価できるものの、同性間の共同生活関係を我が国における婚姻の在り方との関係でどのように位置付けるかについては、
同性パートナーシップに関する公的認証制度を設ける地方公共団体は多数に上るものの、その契機となった渋谷区条例が制定されてから本件処分当時までは約2年が経過していたにとどまり、現在においても依然として、相当数の地方公共団体においては同性パートナーシップに関する公的認証制度は設けられておらず、また、地方公共団体や民間企業における人事関連制度や民間企業における各種サービスの下で同性間の共同生活関係を異性間のものと同様に扱う取組も依然として地方公共団体や民間企業に広く浸透しているとはいい難く、いまだ社会的な議論の途上にあり、本件処分当時の我が国において同性間の共同生活関係を婚姻関係と同視し得るとの社会通念が形成されていたということはできない。
エ 結論
本件処分当時の我が国において、同性の犯罪被害者と共同生活関係にあった者が、犯給法5条1項1号にいう「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当するとまではいえない。
(5)最後に
このように名古屋地裁判決では、「本件処分当時の我が国において同性間の共同生活関係を婚姻関係と同視し得るとの社会通念が形成されていたということはできない。」として、同性者の内縁関係又は同性婚の関係にある者については、公的給付を受けられる「配偶者」性は否定しているのですが、控訴中であり、上級審がどのように判断されるか注目されるところです。我が国の社会通念が、同性間での夫婦としての関係を認める方向へ進んでいく中においては、男女夫婦、女性間夫婦、男性間夫婦であろうが、一律に公的給付を受けられる「配偶者」性が認められる時代になるであろうと想定されます。
以 上
「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」って、誰のことをいうのか?(その①)
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
1.問題点
我が国の社会福祉生活の救済又は向上を図るための給付行政関連法令では、次の条文に示すように、行政分野の給付を受けられる地位としての「配偶者」には「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も含む」との法律の規定がなされており、この「配偶者」「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」の意義及び範囲をめぐって、同性婚の許容の問題を含めて、それに該当するか否かの判断が難しい例が多くあるようです。これらの問題に関して判例の見解が示されてきています。今回は、その点を3回に分けて検討してみたいと思います。
・第1回(①)「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」には、いわゆる重婚的内縁も含まれるのか。
・第2回(②)「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」には、同性婚の内縁関係も含まれるのか。
・第3回(③)「(付録)配偶者の生計維持要件について」
まず、法律の規定例を冒頭に示しておきます。
○厚生年金保険法第3条第2項
この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
○同法第37条第1項(未支給の保険給付)
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
〇犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(犯給法)第5条(遺族の範囲及び順位)
遺族給付金の支給を受けることができる遺族は、犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
二 犯罪被害者の収入によつて生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
三 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2.配偶者の定義と範囲
配偶者の意義ですが、わが国は法律婚主義を取っています(民法第739条・戸籍上の届出)ので、「法律上の婚姻関係(戸籍上の婚姻関係)にある者」を言います。
婚姻は、「夫婦生活の実態があること」と「法律上の届出(婚姻意思)があること」の二つの要件が必要とされていますので、その二つの要件が備わっていない次の場合には、有効な婚姻関係とは認められない場合があります。
その一つは、民法第742条第1号の場合です。婚姻届出があっても、当事者間に婚姻する意思が無い場合には婚姻は無効となり、婚姻している配偶者とは認められないことになります。
二つ目は、民法第742条第2号の婚姻届出自体がない場合です。夫婦生活の実態がない場合には、婚姻は無効であり婚姻している配偶者とは認められません。但し、夫婦生活の実態がある場合には、「内縁関係」として、「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」として保護される場合があります。
三つ目は、有効に婚姻したが、夫婦の実態が解消され離婚も合意しているが離婚届出をしていないので戸籍上は婚姻関係が残っている場合には「外縁関係」(「内縁関係」の反対の状態なので「外縁関係」と呼ばれる)として、婚姻している配偶者になるのかどうかが問題となる場合があります。
最後に、「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に、同性婚又は同性の内縁関係も含まれるのか否かが昨今問題になっています。
3.判例による具体的判断
それでは、裁判で争われた例で、それぞれの問題点を考えていきましょう。
(1)一旦婚姻する意思で婚姻したが、当事者双方離婚する意思で夫婦生活を解消したものの離婚届出だけを提出していない場合、これを「外縁関係」という場合がありますが、この場合には、諸給付を受けられる「配偶者」ということになるでしょうか。
次の判例は、事実上離婚状態にあるいわゆる外縁関係になる場合には、「婚姻している配偶者」には該当しないとした判例です。
但し、この判例では、他方の「内縁の妻」の「配偶者」性を認める旨の判示はしていません。この点は、後記の(3)の最高裁平成17年4月21日判決―判例時報1895-50で、重婚関係の内縁の妻を「配偶者」として認めることができるかという観点で争いになっています。
〇最高裁判例昭和58年4月14日判決―判例時報1124-181
(事案の概要)
法律上の配偶者Bが、被保険者(夫A)死亡後の遺族年金支給を求めた事案である。当該の被保険者には、その当時、10年以上同居していた内縁の妻Xがいた。
(判決骨子)
「(遺族年金給付資格のある)配偶者の概念は、必ずしも民法上の配偶者概念と同一のものとみなさなければならないものではなく、…遺族給付は,組合員…が死亡した場合に家族の生活を保障する目的で給付されるものであって…戸籍上届出のある配偶者(B)であっても、その婚姻関係が実体を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消される見込みのないとき、すなわち事実上の離婚状態にある場合には、もはや右遺族給付を受けるべき配偶者には該当しないというべきである。」
(2)民法第734条第1項により婚姻が禁止された近親者同士の内縁関係あった者については、諸給付を受けられる「配偶者」又は「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」ということができるでしょうか。
当初、最高裁判例(昭和60年2月14日訟月31巻9号2204頁)では、姻族一親等にあたる事実婚配偶者(近親婚違反の夫婦)の遺族年金支給裁定が問題となった事件で、判決では、「(近親婚禁止の規定により)将来においても法律上有効な婚姻関係に入りうる余地のない内縁関係を反倫理的でないと解することはできず、公的給付を受けるにはそれにふさわしい者を給付対象とすべきものと解され、将来において法律上有効な婚姻関係に入りうるかなどの点について、重婚的内縁の場合とは事情を異にしており、反倫理的関係に立つ者に受給資格を認めることはできない」としていました。
しかし、次に示す最高裁判例では、近親婚の程度が姻族一親等夫婦事案ではなく、三親等の傍系血族間夫婦事案であったことから、反倫理性は弱いこと等を理由に、遺族厚生年金の支給を受けることができる「配偶者(内縁関係の配偶者)」として認めています。
〇最高裁平成19年3月8日判決―判例時報1967-86
(事案の概要)
厚生年金保険の被保険者であったA(Xの父の弟)との間で内縁関係にあったXが、Aの死亡後、厚生年金保険法第3条第2項にいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」として同法第59条第1項本文所定の被保険者であった者の配偶者に当たり、Aの死亡当時、同人によって生計を維持していたと主張して、Y(社会保険庁長官)に対し、Aの配偶者としての遺族厚生年金の支給裁定を請求したところ、Yから、上記内縁関係は、民法第734条第1項により婚姻が禁止される近親者との間の内縁関係に当たり、Xは厚生年金保険法第59条第1項本文所定の配偶者とは認められず、遺族ではないとして、遺族年金を支給しない旨の裁定を受けたことから、その取消しを求めた事件である。
第一審は、Xの請求を認めたが、控訴審は反対に Xの請求を退けた。
(判決骨子)
「厚生年金保険制度が政府の管掌する公的年金保険制度であり…婚姻法秩序に反するような内縁関係にある者まで、一般的に遺族厚生年金の支給を受けることができる配偶者にあたると解することはできない。…(本件の)三親等の傍系血族間の内縁関係も、このような反倫理性、反公益性という観点からみれば、基本的にはこれと変わりがない…。」
「(本件)内縁関係については、それが形成されるに至った経緯、周囲や地域社会の受け止め方、共同生活期間の長短、子の有無、夫婦生活の安定性等に照らし、反倫理性、反公益性が婚姻法秩序維持等の観点から問題とする必要がない程度に著しく低いと認められる場合には、…禁止すべき公益的要請よりも遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するという法の目的を優先させるべき特段の事情があるというべきで…(本件)内縁関係については、上記の特段の事情が認められ、Xは、厚生年金保険法第3条第2項にいう『事実上婚姻関係と同様の事情にある者』に該当し、同法第59条第1項本文により遺族厚生年金の支給を受けることができる配偶者に当たるものというべきである。」
(3)法律上の配偶者と事実上の配偶者とが並存していた場合において、いずれが遺族年金受給資格者たる「配偶者」又は「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」になるのでしょうか。
重複結婚は禁止されていますので、重複婚状態になる内縁関係の法律上の保護は受けないのではないかという問題があり、前述の最高裁判例昭和58年4月14日判決―判例時報1124-181では、「法律上の妻(B)」の外縁関係での「配偶者」性は否定していましたが、「事実上の配偶者(X)」の内縁関係による「配偶者」性は判断していませんでした。
しかし、次の最高裁判例では、「法律上の妻(B)」の外縁関係での「配偶者」性は否定していましたが、「事実上の配偶者(X)」の内縁関係による「配偶者」性を認めています。
〇最高裁平成17年4月21日判決―判例時報1895-50
(事案の概要)
①A夫とB(戸籍上の妻・法律上の配偶者)は、法律上、正当な婚姻手続を経た夫婦である。両者はAが勤務していた国立大学の宿舎で同居していたが、昭和53年ないし55年ころからAが宿舎を出て別居して生活するようになり、Aが死亡した平成13年1月12日まで20年以上の長期にわたり別居を続けた。
その間、両者の間に交渉はなく、Aが宿舎料を負担していたほかはBの生活費を負担することもなかった。AとBは、両者の婚姻関係を修復しようとする努力はせず、昭和57年以降は会うこともなかった。
②X(内縁の妻・事実上の配偶者)は、A夫がBとの別居後に親密な関係になり、昭和59年ころからAと同居して夫婦同然の生活をするようになり、その生計はAの収入によって維持されていた。Aが死亡した際も、Xが最期まで看護をした。
③Aの死亡後、X(事実上の配偶者)がY(保険者たる日本私立学校振興・共済事業団)に対して、遺族年金の給付請求をしたところ、YはBが存在することを理由にXへの支給をしない旨の裁定をしたため、Xが、上記裁定の取消を求めて訴えを提起した事案である。
④私立学校教職員共済法第25条は国家公務員共済組合法を準用し、同法第2条には「(遺族とは)組合員または組合員であった者の配偶者…で、組合員…の死亡の当時(失踪の宣言を…同じ。)その者によって生計を維持していたものをいう」旨の規定があり(同条第1項第3号)、さらに配偶者については「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。」と、厚生年金保険法と同様の規定がある(同条第4項)。
(判決骨子)
「AとB(戸籍上の配偶者)は、「20年以上もの長い期間にわたって別居しており、AとBは、別居を開始する以前に離婚の話し合いを行っており、…Bがこれを拒絶し、ついには2人の間で話し合い自体ができない状態になったまま、別居に至ったということができる」、「AとBは、…夫婦としての感情の交流を窺わせるような手紙のやり取りはない」、「また、Aは…Bに対して相応の生活費を送金して…いないこと、他方において、BもAに対して長い間生活費の負担を求めることはなく…BとAとの経済的な依存関係についてもこれを認めることはできない」。
このような事実関係の下では、AB 間の「婚姻関係は実体を失って形骸化している上、そのような状態が固定化していて、その関係が近い将来に修復される見込みはなかった」というべきであり、他方、X(事実上の配偶者)は、Aとの間で事実上の婚姻関係にある者というべきであるから、B(戸籍上の配偶者)は私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第2条第1項第3号所定の遺族として遺族共済年金の支給を受けるべき「配偶者」に当たらず、X(事実上の配偶者)がこれ(「届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」)に当たる。
最後の、「同性婚又は同性の内縁関係も含まれるのか」という昨今の問題については、次回詳細に検討してみたいと思います。(次回に続く)
以 上
宮崎県下の全市町村へのお願い~犯罪被害者等支援条例の制定を!!~
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
1.犯罪被害者の実情と法律
私たちは、社会の中で多くの人と共に生きており、自ら安全・安心な生活をしていても、いつ、どこで他者から理不尽な犯罪による被害を受けるかもしれません。そして、ひとたび犯罪被害に遭い身体的にも精神的にも大きなダメージを受けようとも、これからも今まで住んできた「地域(市町村)」で生きて行かねばなりません。我が国でも、多くの方々が思いもよらず、犯罪被害者やその家族・遺族となり、犯罪による直接的な被害を受けるだけでなく、それに伴い生じる精神的なショックや再度の被害への不安、周囲の無理解や心無い言動など、二次被害にも苦しみ、社会から孤立する状況も見られるところです。
このような状況に置かれた犯罪被害者やその家族・遺族(以下「犯罪被害者等」といいます。)には、犯罪者としての嫌疑を受けている刑事被疑者・被告人の憲法上の権利以前に、私たちの社会に生きる一人一人としての個人の尊厳にふさわしい処遇がなされることが憲法上の人権として保障されている(憲法第11条「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。」・憲法第13条「すべて国民は、個人として尊重される。」)ものであり、犯罪被害者あるいはその遺族として地域社会から孤立することのないよう、国や地方公共団体・地域の人々が犯罪被害者等に対して、早期に被害から回復し平穏な日常生活を取り戻すことができるよう、手を差し伸べ、寄り添い、支え合っていける社会であって欲しいという願いは、法的制度としても実現されなければなりません。
このような問題意識を受けて、国は、平成16年12月1日、犯罪被害者等基本法(以下「基本法」といいます。)を制定しました。この基本法は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的として、そのための施策に関する基本理念を定め、国および地方公共団体の責務を明らかにしています。犯罪被害者等は被害を受けた後にも従来の「地域」で生活していかなければならないことから、「地域住民」の生活に関する権限と責務を有する地方公共団体においては、犯罪被害者等に対する支援の責務を負う(基本法第5条)とされているのです。
2.犯罪被害者等支援活動について
犯罪被害者支援の基本は、警察や弁護士などが刑事裁判業務の中だけで行うものではなく、「地域」の中での生活再生の支援なのです。
例えば、宮崎県内で平成15年に設立(平成16年4月法人化)された「公益社団法人みやざき被害者支援センター」のボランティア支援員が地域の被害者の方への支援に入ろうとしても、被害者自身は、見知らぬ支援員には不安感や遠慮を感じるでしょう。信頼できる親戚や近所の知人に頼ります。また、どこかに相談する場合、一番身近な役場や市役所や地域の民生委員に相談するでしょう。福祉の手続きをするための相談になるでしょう。そのような犯罪被害者の「地域性」からして、地方公共団体がいち早く取り上げて寄り添ってあげるということが必要なのです。
被害者が希望する行政による具体的な施策例としては、
1 犯罪被害者給付金支給法では支給外となる事例への給付金制度による経済援助
2 地域での生活環境に関する援助としてボランティア支援員の派遣及びボランティア支援員や支援団体の育成
3 犯罪被害者支援に関する総合的な相談窓口の創設
4 地域警察や公益社団法人みやざき被害者支援センターとの連携と地域支援ネットワークの構築
等が挙げられます。
(1)宮崎県内の被害者支援活動の先駆性
これらの施策を、「犯罪被害者支援条例」として制定することは、国の施策や指示を待たなくても可能です。実は、これらの実践面では、宮崎県及び県内市町村は全国の先端を行っていました。犯罪被害者等基本法ができたのは、平成16年12月ですが、それ以前の平成15年11月に社団法人 宮崎犯罪被害者支援センターが設立され、平成16年4月から活動を始めています。そして、同時期から宮崎県は犯罪被害者支援事業も開始しており、支援事業委託に伴い、当時の社団法人 宮崎犯罪被害者支援センターの財政基盤になるものとして、宮崎県と全市町村から委託費と負担金(一人当たり3円)を拠出していただいているのです。
宮崎県内の犯罪被害者支援活動は、法律ができる前から、県下全市町村の行政が、全国に先んじて、関係機関の連携と具体的体制の下で、実践的な段階を進んできているのであり、そのことは行政を担当されている皆さんが大いに自負できることだと思います。
(2)宮崎県下での犯罪被害者等支援条例の制定の動き
ただ、宮崎県で遅れている点もあります。宮崎日日新聞(令和2年5月18日付)や読売新聞(令和2年5月25日付)にも書かれていましたが、令和2年5月時点では、県内の地方公共団体の中で「犯罪被害者支援条例」を制定している市町村が一つもなく、県も条例をもっていなかったという点です。(但し、その時点においても、宮崎県と木城町が条例制定に向けて準備をしておりました。)
全国的な被害者支援条例の制定状況を見てみますと、都道府県レベルでは、宮城県が平成15年12月に「宮城県犯罪被害者支援条例」を全国で初めて公布・制定しています。
市町村レベルでは、宮城県条例よりも先に、埼玉県嵐山町が平成11年に条例を制定したのを皮切りに、滋賀県守山市や東京都日野市などが条例を定めています。令和に入ってからは、各都道府県で「犯罪被害者支援条例」が制定され(但し、令和3年4月時点で長野、広島、鹿児島、宮崎が未制定)、大分県では、県をはじめ県内全市町村で犯罪被害者支援条例が制定されるなど、地方行政が積極的に犯罪被害者支援のできる体制作りをしてきています。
宮崎県では、令和2年12月から令和3年1月にかけて、「宮崎県犯罪被害者等支援条例(仮称)骨子案」を公表して意見募集(パブリックコメント)手続きを進めてきており、令和3年6月の宮崎県議会において「宮崎県犯罪被害者等支援条例」を審議し、公布されれば令和3年7月から施行する予定であります。
「宮崎県犯罪被害者支援条例」が施行されるとなれば、宮崎県が、充実した安全・安心な地域を目指す宮崎県政の政策のひとつが実現されるものと大いに評価するものです。さらには、この県の条例が道標となり、地域として最も犯罪被害者等に寄り添うべき市町村において「犯罪被害者等に対する支援条例」が定められることによって、県と連携した手厚く具体的な犯罪被害者支援策を実現することが可能となります。
また、条例の制定は、市町村職員はもとより地域住民である私たちにとっても、犯罪被害者等に対する支援の具体的な行動の道標にもなります。
県内の市町村では、木城町において令和3年4月に「木城町犯罪被害者等支援条例」が公布・施行されました。その他の市町村においても条例制定へ向けた動きが見られます。犯罪被害者等支援条例を定めている国内の市町村においては、専門的な職員を配置した総合支援窓口の設置、既存の住民サービスの犯罪被害者等支援への活用、犯罪被害者等を対象とした新たなサービスの整備、簡易かつ迅速な手続による見舞金や生活費の支給等の支援が設けられています。
このような犯罪被害者支援が、住んでいる地域の被害者等支援条例の有無によって受けられたり受けられなかったりすることは、望ましいことではありません。そのようなことがないように、宮崎県内の全ての市町村で犯罪被害者等を支援するための条例が制定されなければなりません。
私は、宮崎県弁護士会の犯罪被害者支援委員会委員、公益社団法人みやざき被害者支援センター役員、宮崎県町村会顧問をしている立場ではありますが、犯罪被害者支援活動を担う宮崎県民の一人として、宮崎県及び県内の全市町村で犯罪被害者等支援条例の制定がなされることを期待し願っている次第です。
以 上
20歳・19歳・18歳の同時成人式?~令和4年4月1日施行の民法の改正~
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
(相談)相談日:令和3年4月1日
私には、平成14年3月15日生まれの長男(19歳)と平成16年1月30日生まれの次男(17歳)がいますが、民法改正法(成人年齢改正)が令和4年4月1日に施行され、長男は20歳のままの成人なのですが、次男も18歳で成人になりますので、令和5年1月の成人式は長男20歳、次男18歳で合同の成人祝いの宴会を親戚家族で企画したいと思います。何か注意する点があるでしょうか?
(解説)
1 民法改正と18歳成人
2018 年(平成30年) 6月13日、成人(成年)年齢の引き下げを主な内容とする「民法の一部を改正する法律(以下、改正法)」が成立しています。この法律の施行日は、2022年(令和4年)4月1日となっており、この日まで18歳になっている国民は、令和4年4月1日から成人扱いになります。法律制定から法律施行まで4年間の猶予期間をもうけたのは、消費者被害への対策や他の年齢基準の法律の改正検討をすることと、18歳成人の法制度を国民に周知させる必要があったからとされています。
2 令和4年4月1日施行日に想定される状況について
今回の改正法の施行により、成人となる時点が20歳から18歳に前倒しになります。この成人年齢の引き下げは、1876 年太政官布告以来継続してきた成人の定義である「成人=20歳以上」が約150年を経て変わるという画期的な意義があるのですが、今回の改正法は、成人年齢の引き下げに際した経過措置も規定しており、施行日時点の年齢ごとの成人年齢の区別は図表のとおりになります。
| 施行日:2022 年(令和4年)4月1日時点の年齢 |
成人年齢 |
| ① 18歳未満 |
18歳に達したときに成人する |
| ② 18歳以上20歳未満 |
施行日に成人したことにする |
| ③ 20歳以上 |
20歳に達したときに成人したことにする |
この結果、令和4年4月1日には、ご相談のように18歳、19歳、20歳の年齢の異なる子供たちが「同時に成人になる」という状況が発生することになります。そこで、各市町村においては「成人式」をどのような方法で行うのかを検討しているようです(新聞報道によれば、従来どおり20歳のみの成人式・二十歳祝賀式を行う方針の市町村が多いようです)が、それぞれの家族・親族間でも「兄弟合同成人祝い」があることも想像できます。
しかしながら、次にご説明しますが、20歳成人の長男と18歳成人の次男とは、法律上、異なった取り扱いを要求されている場合がありますので、その点を注意する必要があります。
3 その他の改正内容
(1) 民法自体の改正の内容を整理すると、改正内容は,上記の①「成人年齢の18歳への引き下げ」以外に、②「婚姻適齢の 18歳への統一」、③「養親年齢の20歳維持」の3つがあります。
「婚姻適齢の18歳統一」については、婚姻が可能になる年齢が、旧法では「男性 18 歳・女性16歳」でしたが、改正法では
「男女ともに18 歳」に定められました。また、旧法の「未成年者が結婚した場合には成人とみなす」という成年擬制は廃止されました。成人年齢と婚姻可能年齢が「18歳」として一緒になり、「未成年が結婚する」という場面がなくなるからです。
「養親年齢の20歳維持」は、旧法では、養親となるための要件を「成年に達した」と規定していましたが、これをそのまま定めておくと、18歳で養子をもらって親になることができるということになってしまうのですが、他の法律がまだ「20 歳に達した者」にしか権利や能力を与えていない場合も多くあることから、養子をもらって親になれる年齢は、従来どおり「20歳以上」としておくほうがよいとの考えで、改正法は、養親となるための要件を「成年に達した」との表現から「20歳に達した」と改正しています。
(2) 民法の成人年齢改正に関連して、他の法律の年齢基準についても改正されたものが多くあり、改正により年齢要件の基準を新たに18 歳と改正したものと、従来どおり20 歳の要件を維持したものがありますので、それぞれの法律を確認する必要があります。
選挙権が18歳から認められるとした、公職選挙法改正は皆さんご存じでしょうが、国籍法や旅券法などの戸籍に関連する法律も18歳へ改正となっています。
しかし、健康面や健全育成面で未成年者を保護しようという目的の法律は、ほぼ「20歳」のままの規定を維持しています。例えば、未成年者に射幸性の影響を与えないように、競馬法、自転車競技法、小型自動車競走法、モーターボート競走法などは、20歳未満の者に対する公営ギャンブルの禁止規定を維持していますし、未成年者喫煙禁止法、未成年者飲酒禁止法も、20歳未満の者に対する喫煙、飲酒の禁止を継続しています。(但し、未成年者飲酒禁止法は「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」に改名され、対象も第1条第2項と第3条第2項を除き全て「満二十年ニ至ラサル者」から「二十歳未満ノ者」に改正されるだけで、未成年者の親権者や監督義務者が科料に罰せられる法第1条2項や第3条2項は改正されていませんので、親が18歳や19歳に親が飲ませたとしても、成人者に対しては親権者としての監督義務はありませんから、科料に処せられることはないという解釈になるものと思われます。)
4 ご注意点
そういうことですので、20歳成人の長男と18歳成人の次男の合同成人お祝い会を催されるのは良いとして、お祝い会で18歳の次男が飲酒することは厳禁ですので、その点は十分に留意していただく必要があります。
以 上
親族間の交通事故損害と保険金請求
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
(事例1)
A男とB女は夫婦であり、A男運転の自動車にB女が同乗して出かけたところ、A男のよそ見運転で自損事故を起こし、B女が重傷を負って長期間の入院治療をした場合、A男の搭乗者保険によってB女は損害賠償保険金を受け取ることができるか。
搭乗者保険特約がない場合に、A男の対人賠償保険によってB女は損害賠償保険金を受け取ることができるか。
(事例2)
A男とB女は夫婦であり、長男甲と長女乙の子供がいる。長男甲の運転の自動車に長女乙が同乗して出かけたところ、長男甲がよそ見運転をし、高速道路で自損事故を起こし、長男甲も長女乙も死亡した。長男甲の自動車保険は搭乗者保険特約がなく一般的な対人賠償保険のみであった。子供たちの相続人は、A男B女夫婦だけである。
長男甲から支払われるべき長女乙の死亡損害金を自動車保険(対人賠償保険)から受け取ることができるか。
解説
1 まず、車の同乗者が自動車事故で負傷又は死亡した場合の損害賠償に関しては、搭乗者保険による保険金支給が考えられます。搭乗者傷害保険とは、車に乗っている人(運転手を含む)が交通事故で怪我又は死亡してしまったときの損害を補償する保険です。例えば、A男が保険会社と契約する自動車保険のひとつで、A男の車での交通事故で運転手や自分の車の同乗者が怪我をしてしまった場合に、怪我による治療や入院などの損害費用を補償してもらえる保険になります。搭乗者とは、補償の対象となる車に搭乗している「運転者以外の人」のことを指します。同乗者には、配偶者、子どもといった家族のほかに、知人・友人といった他人も含まれます。また、搭乗者傷害保険は、搭乗中の者が死傷した場合に定額を補償する傷害保険であり、賠償責任保険ではないことから、相続関係者の相続による賠償債権・債務の混同の問題は、搭乗者保険からの保険金支払いには影響は与えませんので、搭乗者保険による保険金は受け取ることができます。
なお、搭乗者保険で死亡保険金の受領者は約款上「法定相続人」と定められている場合が多いと思われますが、死亡保険金が相続財産になるのか、相続財産ではなく法定相続人となるべき者の固有取得財産なのかの争いがありますが、判例(大阪地裁平成16年12月9日判決)は、相続財産ではなく法定相続人となるべき者の固有取得財産としています。受取相続人は死亡同乗者の相続を放棄しても、搭乗者保険からの死亡保険金を受け取ることができることになります。
2 次に、搭乗者保険特約がない場合、自動車保険の対人賠償保険からの賠償保険金は支払われることになるでしょうか。
対人賠償保険は、例えば、A男が自分の車を運転中に交通事故を起こし、運転者以外の第三者(相手車の運転手や搭乗者、歩行者)が怪我又は死亡してしまったときの人的損害について、A男の保険でその損害分を支払うという賠償責任保険です。保険金の支払いの前提として、当事者間での「損害賠償債権債務関係の存在」と「損害賠償金の支払」が必要になります。そこで、親族間で損害賠償を請求したり、損害賠償を払ったりする関係が実際にあり得るのか、加害者と被害者の両方が死亡した場合に、その相続人は相互に損害賠償請求をするのかという請求権行使の現実性の有無と保険金支払いによる利得性が問題になります。
この点を、事例に即して説明していきましょう。
(1)事例1の場合
夫の過失で妻が負傷した場合、法的には、妻は夫の不法行為に基づき損害を受けたのですから、夫に対して入院費用や休業損害等を請求できることになるのですが、現実的には夫婦は経済的一体性がありますので、夫婦生活の費用負担面からしても相互に損害賠償請求はしないというのが実態だと思います。
搭乗者保険が無い場合に、妻が被害者として夫が契約している対人賠償保険(自賠責保険)から被害者として損害賠償請求して賠償保険金をもらうことはできるのでしょうか。
そもそも、対人賠償保険(自賠責保険)の基礎になる妻から夫への損害賠償請求については、円満な家庭生活を営んでいる夫婦間においては、損害賠償請求権が行使されない場合が多く、通常は、愛情に基づき自発的に、あるいは、協力扶助義務の履行として損害の填補がなされ、もしくは、被害をうけた配偶者が宥恕の意思を表示することがあることから、一般的に、夫婦間における不法行為に基づく損害賠償義務が自然債務に属する(裁判による強制請求はできない)とか、損害賠償請求権の行使が夫婦間の情誼・倫理等に反して許されない、と考える余地があります。
それにもかかわらず、保険金がもらえるという仕組みがあることを利用して、賠償保険金をもらうということは、法的にも許されるのでしょうか。
この点を問題とした裁判例があり、最高裁昭和47年5月30日判決(判例時報667号3頁)は、次のように述べて、妻からの保険金支払請求(被害者請求)を認めました。
「損害賠償請求権の行使が夫婦の生活共同体を破壊するような場合等には権利の濫用としてその行使が許されないことがあるにすぎない」、「自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)一六条一項による被害者の直接請求権に基づき、保険者に対し、損害賠償額の支払を請求する場合には、加害者たる配偶者の損害賠償責任は、右の直接請求権の前提にすぎず、この直接請求権が行使されることで夫婦の生活共同体が破壊されるおそれはなく、他方、被害者たる配偶者に損害の生じているかぎり、自賠責保険によってこの損害の填補を認めることは、加害者たる配偶者、あるいは、その夫婦を不当に利得せしめるものとはいえない。」としています。
(2)事例2の場合
交通事故により加害者も被害者も死亡した場合、それぞれの相続人が被害者死亡という損害発生につき、その損害賠償債権と損害賠償債務を相続により各自の相続人が承継することになります。(民法第896条は「相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定めています。)
事例2の場合、加害者長男甲の損害賠償債務は、相続人である父親A男と母親B女に相続される可能性があります。被害者長女乙の損害賠償債権(長男甲に対する賠償請求権)も、相続人である父親A男と母親B女に相続される可能性があります。なお、相続に関しては、民法第915条で相続開始を知ったときから3箇月以内に相続放棄することで権利義務を承継しないこともできます。民法第921条第2号で、相続放棄しなかった場合には相続を単純承認したこととなり、確定的に債権債務を承継取得したことになります。
① それでは、相続人であるA男B女夫婦が、長男甲の相続も長女乙の相続も単純相続した場合には、長女乙の死亡損害金を自動車保険から受け取ることができるでしょうか。
この点は、最高裁平成元年4月20日判決・判例時報1314号54頁により、相続により賠償義務者と賠償債権者が相続により同一人に帰属したことにより賠償債権債務関係が混同で消滅する(民法第520条)ので、乙の相続人による保険金請求権は消滅し、長女乙の死亡損害金を自動車保険から受け取ることができないとされています。
判例要旨は以下のとおりです。
「自賠法三条の損害賠償債権についても民法五二〇条本文が適用されるから、右債権及び債務が同一人に帰したときには、混同により右債権は消滅することとなるが、一方、自動車損害賠償責任保険は、保有者が被害者に対して損害賠償責任を負担することによつて被る損害を填補することを目的とする責任保険であるところ、被害者及び保有者双方の利便のための補助的手段として、自賠法一六条一項に基づき、被害者は保険会社に対して直接損害賠償額の支払を請求し得るものとしているのであつて、その趣旨にかんがみると、この直接請求権の成立には、自賠法三条による被害者の保有者に対する損害賠償債権が成立していることが要件となっており、また、右損害賠償債権が消滅すれば、右直接請求権も消滅するものと解するのが相当である」
② 相続人であるA男B女夫婦が、賠償義務のある長男甲の相続は放棄し、賠償請求権のある長女乙の相続だけを単純相続した場合には、長女乙の死亡損害金を自動車保険から受け取ることができるでしょうか。
これは、賠償義務者も賠償債権者も双方相続すると権利が消滅するので、賠償義務の相続は放棄し、賠償債権者のみを相続しようという方法です。
結論としては、賠償債権者(被害者としての賠償請求)は承継されているわけですから、乙の相続人による保険金請求権は消滅していないので、長女乙の死亡損害金を自動車保険から受け取ることができるという解釈をする立場と、反対に、本来権利義務のいずれも承継できるのを権利のみ承継して利得することは信義則上許されないとして、長女乙の死亡損害金を自動車保険から受け取ることができないという解釈をする立場の2つがあるように思います。
この点、判例(大阪地裁平成3年9月20日判決)は、後者の立場から、「被害者及び加害者の債権債務関係は、本来、交通事故という1つの不法行為から発生した1つの権利義務関係として同一人格に帰属しており、表裏一体かつ密接不可分の関係にあると考えられるから、加害者の被害者に対する債務が相続放棄された後も、被害者の加害者に対する債権のみが債務と別個独立に分離して存続するものとするのは権利義務関係の一体性から妥当ではない。」として、長女乙の死亡損害金を自動車保険から受け取ることはできないとしました。
③ 相続人であるA男B女夫婦が、父親A男は長男甲の相続をし、長女乙の相続は放棄し、母親B女は長男甲の相続を放棄し、長女乙の相続をした場合(賠償義務者は甲の相続人父親A男、賠償権利者は乙の相続人母親B女となった場合)には、母親B女は長女乙の死亡損害金を自動車保険から受け取ることができるでしょうか。
この方法は、更に、賠償債務の相続と賠償債権の相続を工夫して、相続後も賠償債務承継者と賠償債権承継者が別々に存在する形を作り出すという方法です。法律上の技巧的な方法ですが、「経済的一体性をもつ一つの夫婦において、結果的に、本件交通事故によって発生した権利義務のうち、保険金請求という権利のみを確保し、同交通事故による実質的義務を免れる」という方法として保険制度の悪用・乱用と見る見解もあるのでしょうが、判例(福岡高裁平成14年3月28日判決)は、次のように判示して、母親B女は長女乙の死亡損害金を自動車保険から受け取ることができるとしています。
「夫婦共同体として経済的に一体のものであるということに着目すれば、当該夫婦は、結果的に、本件交通事故によって発生した権利義務のうち、保険金請求という権利のみを確保し、同交通事故による実質的義務を免れることになるが、夫婦においては、本件保険契約の存在が前提になっているからこそ妻は夫に対する損害賠償債権を確定する必要を生じたのであり、そのことから妻の請求権の行使を仮装ということはできないし、保険会社としても、本来は加害者の損害賠償義務を負うべき契約上の地位にあったのだから、単に混同の利益を受けられなかったにすぎないのであり、このことをもって、妻の請求権行使を権利濫用又は信義則違反とすることは認められない。」
(3)最後に
上記(2)③のような保険金取得のための知識や方法は、弁護士の知恵によるものです。何か複雑になりそうな法律問題が起きた場合には、早期に弁護士に相談されることで良い解決方法が見つかる場合もあります。弁護士による相談をお勧めします。
以 上
印鑑と指印、花押
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
前回に引き続き「押印」シリーズとして、判例で問題となった押印に関する法的問題「印鑑の代わりに指印を押した自筆遺言書、花押を使用した自筆遺言書の有効性」についてお話したいと思います。
1 自筆遺言書と「押印」
民法第968条は、第1項で「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」第3項で「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」と定めており、遺言者が自らの手で各自筆遺言書を書くには、「印を押さなければならない。」としています。
遺言書に、自筆署名以外に「押印」を求める趣旨は、「遺言の全文等の自書とあいまつて遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによつて文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにある」とされています(最高裁平成元年2月16日判決)。
ここでいう「印を押す」というのは、日本で慣行として行われている「印章」「印顆(いんか)」を朱肉又は墨・インク等を付けて印影を残すことを意味することになります。
「印章」とは、木、竹、石、角、象牙、金属、合成樹脂などを素材として、その一面に文字やシンボルを彫刻し、個人・官職・団体のしるしとして、公私の文書に押して特有の痕跡(印影・印痕)を残すことにより、その責任や権威を証明するものを言いますが、「印顆」も同意義の言葉であり、世間一般では、正式には印章と呼ばれるもののことを、ハンコ、印鑑(いんかん)と呼んでいます。「印影」は、その印章で押された痕跡のことを言います。
2 印章(印鑑)の種類について
印章(印鑑)について、現代日本で生活・実用品として用いられる印章は、市町村に登録した「実印」、金融機関に登録された「銀行印」、届け出を必要としない「認印」の3種類に大別されますが、押印の種類についても、署名印以外に、契約印、契印、割印、訂正印、捨印、止印、消印、封印と呼ばれる使い方があります。
3 印鑑に関する日本の法律の定めについて
自筆遺言書の作成の場合の「押印」(印を押す)の印鑑(印章)は、本来「その責任や権威を示す」ものであるとされているわけですが、どのような文字が刻まれているとか、どのような形の印章かという点は、実は法律では全く定めていません。本人が本人のものとして使う意思があり、又は使っていた行為があれば、「名字だけの印章」でも「名前だけの印章」でも、更に言えば、「名字名前と合わない文字の印章」であっても構わないことになります。
4 「指印」「拇印」は「押印」として有効か。
印鑑(印章)の定義がないのであれば、木、竹、石、角、象牙、金属、合成樹脂などを素材として使っている「印章」ではなく、「押印」として直接本人の「指印」「拇印」を押した場合、遺言書は有効なのでしょうか?
この点については、最高裁平成元年2月16日判決は、次のような理由を述べて、有効と判断しています。
「(民法第968条の自筆遺言書の)押印としては、遺言者が印章に代えて拇指その他の指頭に墨、朱肉等をつけて押捺すること(以下「指印」という。)をもつて足りるものと解するのが相当である。けだし、同条項が自筆証書遺言の方式として自書のほか押印を要するとした趣旨は、遺言の全文等の自書とあいまつて遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによつて文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解されるところ、右押印について指印をもつて足りると解したとしても、遺言者が遺言の全文、日附、氏名を自書する自筆証書遺言において遺言者の真意の確保に欠けるとはいえないし、いわゆる実印による押印が要件とされていない文書については、通常、文書作成者の指印があれば印章による押印があるのと同等の意義を認めている我が国の慣行ないし法意識に照らすと、文書の完成を担保する機能においても欠けるところがないばかりでなく、必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは、かえつて遺言者の真意の実現を阻害するおそれがあるものというべきだからである。」
5 「花押(かおう)」は「押印」として有効か。
それでは、次に、自筆遺言書を、印鑑や「指印」の代わりに「花押」でした場合には、その遺言書は有効なのでしょうか?
(1)「花押」について
「花押」って何でしょう? 日本には古来より、署名の代わりに名前の下に個人独自の一筆書きを記す「花押」というものが公家社会と武家社会にはありました。「花押(華押)」は、署名の代わりに使用される記号・符号をいうのですが、元々は、文書へ自らの名を普通に自署していたものが、署名者本人と他者とを明確に区別するため、次第に自署が図案化・文様化していき、特殊な形状を持つ花押が生まれたようです。
「花押」が利用された武家社会では、家督を継いだ子が、父の花押を引き継ぐ例も多くあり、花押が自署という役割だけでなく、特定の地位を象徴する役割も担い始めていたと考えられていますが、江戸期にはさらに「花押型(花押を判にしたもの)」が普及し花押が印章と同じように用いられ始め、花押の印章化という現象が生じました。
ところが、明治維新により、明治6年に、実印のない証書は裁判上の証拠にならない旨の太政官布告が発せられたことから、花押が禁止されたわけではないのですが、花押はほぼ姿を消し、印鑑が取って代わることとなっていきました。
日本国政府の閣議における閣僚署名は、明治以降現在も花押で行うことが慣習となっているようです。多くの閣僚は閣議における署名以外では花押を使うことが少ないため、閣僚就任とともに花押を用意するケースが多いようです。下記の写真例は、ウキペディア等を参照して引用したものです。個人的に思うのですが、「花押」は、個性を持った「サインの古風版」とも言えるのではないでしょうか。
(豊臣秀吉の花押) (徳川家康の花押) (伊藤博文の花押)
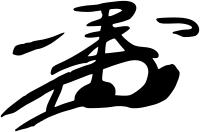
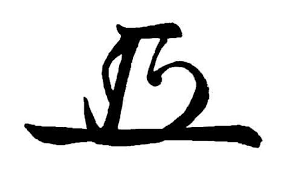

(2)裁判例
問題は、民法第968条の自筆遺言書の押印として、遺言者が印章に代えて、この「花押」を使用した場合の遺言書は有効となるのかという点です。
最高裁判所(最高裁平成28年6月3日判決)は、次の理由で「花押による自筆遺言書は無効である」としました。
「花押を書くことは、印章による押印とは異なるから、民法968条1項の押印の要件を満たすものであると直ちにいうことはできない。そして、民法968条1項が、自筆証書遺言の方式として、遺言の全文、日付及び氏名の自書のほかに、押印をも要するとした趣旨は、遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解されるところ(最高裁昭和62年(オ)第1137号平成元年2月16日第一小法廷判決・民集43巻2号45頁参照)、我が国において、印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難い。 以上によれば、花押を書くことは、印章による押印と同視することはできず、民法968条1項の押印の要件を満たさないというべきである。」としています。
(なお,この判例の前審である福岡高等裁判所那覇支部(平成26年10月23日判決―判例秘書登載)は、「花押でも自筆遺言書は有効である」としていたようです。)
6 結論
判例の結論は、「指印」「拇印」による自筆遺言書は有効であるが、「花押」による自筆遺言書は無効となるという結論になります。「指印」「拇印」は社会内で「押印」と同等に扱う慣例がありますが、「花押」はそのような慣例がないので認められないという理由で,結論の違いが出たようです。
そうであれば、今後、仮に、多くの人が自分の「花押」を作り出して使うことが頻繁になれば、「花押」も「押印」又は「個性的なサイン」として認められるようになるのかも知れませんね。例えば、「押印」廃止の流れの中で、印鑑が不要になった手続の書面に、個性的なサインとして「花押」を付け加えたりしたら、書類を受け取った側はどう反応されるでしょうかね。
以 上
法律からみた押印制度改革
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
1 2020年(令和2年)のコロナ禍での自宅勤務・リモートワークの問題として指摘された決裁制度での「押印」制度について、最近の報道によると、国や官庁では「ハンコの廃止」「押印要否の見直し」を進めるようです。
具体的には、令和2年(2020年)7月17日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2020」では、「書面・押印・対面主義からの脱却等として、実際に仕事場や役所に足を運ばなくても手続きができる「リモート社会」の実現に向けて、全ての行政手続きについて、原則として書面・押印・対面を不要としてデジタルで完結できるように見直しを行うこと、更に、民民間の商慣行についても官民一体となって改革を推進することが示されています。
それ以前に、民民間の商慣行に関しても、国と経済団体による共同宣言(令和2年7月8日付け「書面・押印・対面」を原則とした制度・慣行・意識の抜本的見直しに向けた共同宣言)において、書面・押印・対面が商慣行や社内手続きとして定着しているものであっても、取引先等との協調又は、経営者のリーダーシップに基づき、押印廃止や書面の電子化を推進するものとされています。
*リモートワーク・リモート社会とは、リモート(remote)の意味が「離れた、遠隔の、隔たりのある、かけ離れた、間接的な」などの意味を持つ英単語ですので、ITの分野では、離れた場所にある二者(人や機器など)が通信回線やネットワークなどを通じて結ばれていることを表すことになりますので「通信回線やネットワークなどを通じて働くこと、そのような働き方をする社会」という意味になります。
2 押印制度と印鑑登録制度
(1) 日本の法律には、以上の印章(印鑑)の定義や使用義務を定めた法律はありませんが、他方、印鑑による押印の法的効果を規定する法律の定めがあります。
① まず、民法第968条が「遺言」に関して、第1項で「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」第3項で「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」と定めてあり、民事訴訟法(以下「民訴法」という。)第228条第4項では「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」との定めもあります。
これらは、遺言の真正又は有効性を認める要件であり、それ以外の一般文書においても、「押印」があれば文書の名義の真正(その文書が作成名義人によって実際に作成された)という「成立の真正」を推定することを意味し、私文書にある印影が本人または代理人の印章によって押された場合には、反証なき限り、その印影は本人または代理人の意思に基づいて押されたと推定され、その結果、同項の要件が満たされるため、文書全体が真正に成立した(遺言書の場合は有効に成立した遺言書であること)と推定されます。
民事裁判においても、契約書に署名又は押印のある契約は成立が推定され、契約書の内容どおりに約束されたことが認められることが多くなります。なお、当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、民訴法第230条で「裁判所は、決定で10万円以下の過料に処する。」と定めています。
② 次に、刑法第167条では、「行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、3年以下の懲役に処する。」規定があり、印章等の社会的信用を保護する定めがなされています。
(2) 日本では、法律には義務制度としては明記されていませんが、印鑑登録の制度があります。
① まず、個人の印鑑登録については、個人が自己の居住地の市町村に印鑑を登録しその旨の照明をしてもらう制度ですが、あえて法律上の根拠を求めれば、個人の印鑑登録は「市町村の自治事務」であり、地方自治法第2条第2項、第8項の「地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のもの」を根拠とする制度と言えます。自治事務は、地域において住民福祉の向上を目的として処理する事務を広く含むものであり、その取り扱いは各自治体の印鑑登録条例によることになります。
また、個人の印鑑登録に関しては、“印鑑登録証明事務処理要領通知 (昭和49年2月1日自治省通知、―平成16年3月2日総務省通知)があり、各市町村は、この通知に倣って取り扱っています。
次に、会社の設立等に当たって登記を申請する際の法人印鑑登録については、商業登記法第20条「登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない。」との規定が法的根拠となります。
② この印鑑登録制度の信用性を基に、不動産登記手続きや商慣行上の重要な取引契約をする場合には、自らが書面を作成したことなどの証明のために、登録印鑑による押印と登録証明書を提出することを求める取り扱いが日本では定着しているということになります。
(3) 行政手続き上の「押印」
行政手続き上の書面に関しては、個々の行政法令が「押印」の定めをしていることが多くあります(例えば、行政不服審査法施行令第4条第2項「審査請求書には、審査請求人(審査請求人が法人その他の社団又は財団である場合・・・以下省略)が押印しなければならない。」と定めています。民間から行政への手続きの中で押印を求めている行政手続きが添付書類を含めておよそ1万5000種類あるといわれています。)。
これについて、菅内閣の河野太郎行政改革担当相は令和2年11月13日の閣議後の記者会見で、行政手続きで印鑑証明が必要なもの、あるいは登記、登録、銀行への届け印を除き、本人確認、本人認証にならない認印は全て廃止すると発表し、内閣府は全府省に行政手続きで求める押印の原則廃止を要請したという報道がされていました。
3 今後の方向性について
行政手続きでの「押印」制度は、本人確認という程度の「認印」による簡易な押印制度ですので、廃止方向で実現していくだろうと思われますが、各市町村の自治事務として確立運用されてきて、不動産取引及びその登記手続や銀行取引等の重要な取引契約で実用化されてきた印鑑登録制度は、その社会的意義は大きいものがあり、法令改正をするだけで解消できるわけでもないことから、実印(登録印鑑)による押印制度が直ちに廃止される方向にはならないだろうと考えられます。
最後に、押印制度の背景にある印鑑製造や刻印の技術は、単に生活実用品製造としての職業面がある以外に芸術文化の面も有しており、その技術や文化が衰退することはあってはならないという思いも残ります。明治時代には、欧米にならってハンコをやめて署名に統一すべきだとの意見も出たようですが、日本のハンコ文化は現在まで生き残ってきています。
(次回は、「押印」シリーズ(その2)として、「印鑑と花押について」掲載する予定です。)
以 上
お正月と法律 ~届かないおせち料理~
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
1 おせち料理の事前予約販売
おせち料理は、五節句の料理の1つで、平安時代に宮中で行われた「お節供」の行事に由来します。江戸時代後期に江戸の庶民がこの行事を生活に取り入れ、全国におせち料理が広まり、節句の中でも一番目の正月にふるまうご馳走だけが「おせち料理」と呼ばれるようになったようです。おせち料理は、従来は、年末に食材を買い込んで女性方が自宅で作り上げるという縁起物料理でしたが、昨今は、有名デパートや有名料理店からの宅配予約が人気になっているようです。ふるさと納税のお礼品にもおせち料理がある時代になっています。
2 おせち料理の配達
おせち料理は元旦の縁起物料理ですから、事前予約販売のほとんどが、「おせち料理の事前予約販売」は、元旦前日までに届けられるか、引き取りを求められるものです。ある有名デパートの場合には、おせち料理のお届け期日について、例えば、「冷凍のものは2020年12月30日、冷蔵のものは2020年12月31日にお届けします。時間指定はできません。」などとしております。
3 届かないおせち料理
ところで、おせち料理を12月31日までの必着で予約したにもかかわらず、翌日元旦になっても届かない場合はどういう法律問題になるかを考えてみましょう。
例えば、テレビ番組の「行列のできる法律相談所」の相談テーマで、次のようなドラマシーンがありました。それを台本風に再現してみます。
(年末大晦日の会話)
母「おかしいわね。今日の午前中に到着するはずだったのに…。」
・・・夜になっても「おせち」は一向に届く気配がない・・・
そこで、業者に問い合わせてみると・・・
業者「申し訳ございません…。何かの手違いでお届け出来なくなりました。」
母 「はぁ? 何ですって!?」
業者「もちろん、代金は全額お返し致しますので。」
・・・業者はミスを認め、おせちの代金3万円は全額返金するという。
・・・しかし!
怒った母「こんな田舎で今さら代わりの物なんて用意できるわけがないじゃない!」
・・・近所のお店はすでに正月休み。今からおせちを用意するのは不可能。
怒った母「あなた方の無責任さのせいで、めでたいお正月が台無しよ!
慰謝料払ってもらいますから! 」
果たしておせちが予定通り届かなかった場合慰謝料は取れるのか?
4 おせち料理が元旦までに届かない場合の損害賠償請求の有無について
(1)改正民法第415条では、債務不履行の場合には損害賠償ができる旨の定めがあります。問題はどのような「損害」がおせち料理の注文者に生じているか?です。
改正民法第415条第2項の「履行に代わる損害賠償」とは、代金相当額の損害でしょうから、契約解除により代金を返還してもらえれば、損害はないことになります。返金分に代金支払日から実際の返金日までの遅延損害金(年3分の割合)を要求することが具体的な損害賠償請求ということになるでしょう。
(2)もうひとつの損害は、「行列のできる法律相談所」の相談テーマのように「精神的慰謝料」というものの請求が認められるかという点です。
「慰謝料」は、民法条文上は不法行為規定である民法第710条に規定する「財産以外の損害」ということになるのですが、契約関係の債務不履行責任の条文規定では使われていない文言です。
ⅰ>その規定の違いから債務不履行責任(契約責任)の損害については「財産以外の損害」としての精神的慰謝料は発生しないという見解もあります。—この見解に従えば、テレビ番組の例では、お母さんは「めでたいお正月が台無しにしたおせち料理の未到着」についても「慰謝料」は請求できないことになります。
ⅱ>他方、一般的にも「損害」の中には、財産的損害だけでなく精神的損害(慰謝料)も含まれるのが通例であり、条文の規定の差異は、民法710条は不法行為責任に関して注意的に規定しているだけであるとして、債務不履行責任の損害賠償の中には「財産以外の損害」としての精神的慰謝料も含まれるとする見解があります。—この見解に従えば、テレビ番組の例では、お母さんは「めでたいお正月が台無しにしたおせち料理の未到着」について「慰謝料」を請求することができることになります。3万円程度のおせち料理を注文してそれが駄目だった場合の精神的損害としては、正月気分を害されたとしても、代金以上の精神的損害ということは通常考えられないので、代金の1割~2割程度の慰謝料が認められるのではないかと思われます。
この点を考慮してか、おせち料理販売業者の広告には、「天候・交通などの事情により、商品入荷の遅延・不能の場合もございます。あらかじめご了承ください。やむを得ず商品をお届けできない場合には、ご返金にてご容赦くださいますよう、お願い申し上げます。」と配送上の留意点を告知している例もあります。
5 最後に
今年のお正月は皆さん、いかがお過ごしでしたでしょうか。
コロナ禍のお正月であっても、我が家や親しい親戚の家で、温かいお酒と共におせち料理を堪能されたのであればよろしいかと思います。奥さん方をはじめ「おせち料理」を準備していただいた方や配送をしていただいた方など全ての方々に、感謝しましょう。
以 上
育児休業取得後の解雇は許されるか?
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
○A子は、Y会社の従業員であったが、感情が不安定で強迫観念が強く、よく上司に反抗的で攻撃的な言動を行うことが何度もあったことから、「上司の命令・指導に従わない」「職場での協調性がない」との人事評価を受けていた。
A子は入社5年後に産休・育休を取って復職し、その4年後(入社9年後)に二度目の産休・育休を取って、その育休後に復職の申し入れをしたが、Y会社は、A子の休業中職場の雰囲気が良い感じになり、問題行動の多いA子の復職で職場の雰囲気がまた悪くなることを危惧して、この機会にA子に対して退職勧奨を行ったが、拒否されたので、勤務態度が悪く職場秩序を乱すことを理由に解雇した。
この解雇は許されるでしょうか。
(解説)
12月は、クリスマス気分や年末のあわただしい雰囲気の中で、子供たちや女性が笑顔で楽しく過ごしている時季です。日本の社会で女性が生き生きと働くためには子育ての環境が整う必要がありますが、法律制度として産前産後休暇制度や育児休業制度が定められても、実社会での運用が充実していかないと女性の働きやすい環境が整っていることにはなりません。そこで、今回は、女性の働き方と会社の対応が問題になった上記の例を検討してみましょう。
1 解雇に関する法律の規定について
まず、本件に関する解雇の有効性判断に必要な法律の規定としては、次の3つの法律があります。
① 労働契約法 第16条 (解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
② 男女雇用機会均等法(以下「均等法」という。) 第9条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)
1 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
4 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
③ 育児・介護休業法(以下「育休法」という。) 第10条(不利益取扱いの禁止)
事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
このように、均等法第9条第3項は妊娠・出産・産休を「理由として」解雇してはならないと定めており、育休法第10条も育児休業をしたことを「理由として」解雇してはならないと定めていますから、本件解雇理由が「勤務態度が悪く職場秩序を乱すこと」を理由としている普通解雇であることから、形式的には均等法第9条第3項や育休法第10条に直接違反しているということにはならないだろうと思われます。しかし、実際はそのこと(育児休暇を取得したこと)を契機にA子を解雇したのではないか、という疑いは拭えません。
2 本件解雇の有効性の判断について
(1)本件解雇が形式的に「勤務態度が悪く職場秩序を乱すこと」を理由に解雇している以上は、まずは、労働契約法第16条の「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」であるか否かを検討することになるでしょう。
解雇の合理的理由としては、それぞれの就業規則には「業務能力の欠如又は劣悪」とか「適格性がない」、「上司の業務命令に従わない」、「遅刻欠勤が多い」、「勤務態度が悪く協調性がない」などが列挙されていますが、判例上で解雇が認められるのは、「労働者側に改善の余地がないほどの責任がある場合」などのごく限られた場合に限定されています。
(2)本件のA子の場合には、上司などへの攻撃的態度などの問題行動については、その都度注意指導をして段階的に軽い懲戒処分等で対応し、それでも懲戒処分が重なるだけでA子の問題行動が改まらない場合に、初めて「改善の余地のないほどの問題行動が続いている」として解雇するという手順を踏むべきだろうと思われます。
従って、復職希望者を、即座に解雇をすることには、「合理的な理由」もなく「社会通念上相当である」と認められるものではなく、本件解雇は無効と判断されます。
3 判例の見解(東京地裁平成29年7月3日判決―労経判69-4:シュプリンガージャパン事件)
判例は、同様の事案について、次のとおり、均等法第9条第3項や育休法第10条に違反する無効な解雇となるとしています。
(1)「事業主が解雇をするに際し、形式上、妊娠等以外の理由を示しさえすれば、均等法及び育休法の保護がおよばないとしたのでは、当該規定の実質的な意義は大きくそがれることになる。もちろん、均等法及び育休法違反とされずとも、労働契約法第16条違反と判断されれば解雇の効力は否定され、結果として労働者の救済は図られるにせよ、均等法及び育休法の各規定をもってしても、妊娠等を実質的な、あるいは、隠れた理由とする解雇に対して何らの歯止めにもならないとすれば、労働者はそうした解雇を争わざるを得ないことなどにより大きな負担を強いられることは避けられないからである。
このようにみてくると、事業主において、外形上、妊娠等以外の解雇事由を主張しているが、それが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないことを認識しており、あるいは、これを当然に認識すべき場合において、妊娠等と近接して解雇が行われたときは、均等法第9条第3項及び育休法第10条と実質的に同一の規範に違反したものとみることができるから、このような解雇は、これらの各規定に反しており、少なくともその趣旨に反した違法なものと解するのが相当である。」
(2)「本件解雇は妊娠等に近接して行われており(被告が復職の申出に応じず、退職の合意が不成立となった挙句、解雇したという経緯からすれば、育休終了後8か月が経過していても時間的に近接しているとの評価を妨げない。)、かつ、客観的に合理的な理由を欠いており、社会通念上相当であるとは認められないことを、少なくとも当然に認識するべきであったとみることができるから、前記(1)で判断したところによれば、均等法第9条第3項及び育休法第10条に違反し、少なくともその趣旨に反したものであって、この意味からも本件解雇は無効というべきである。」
4 まとめ
実際の裁判では、「上司への反抗的な態度、攻撃的な言動」が具体的にはどのような内容であり、どの程度のものであるかが、いつ、どこで、誰と、どういう内容で、どういう理由で、どうなったかという詳細な事実関係が調べられることになります。職場での「客観的に理由のある部下の主張」が、上司からみれば「攻撃的な言動、反抗的な態度」と受け取られてしまっている場合もありますので、その差異を区別認識するためにも、具体的な事実関係の証拠調べを行うことになります。
仮に、上司からだけでなく一般社員からみても「上司への反抗的な態度、攻撃的な言動」と評価される場合であったとしても、更に、そのような出来事が「継続して複数回生じていて」、「改善の余地のないほどの問題行動が続いている」と評価できるものであるかどうかで、解雇理由があるかどうかが判断されますので、日本の労働関係においては単発的な反抗態度のみで労働者を解雇処分にすることは難しいと考えておく必要があるでしょう。
以 上
企業(実業団)スポーツ選手と法律~企業の一般社員の労働(雇用)契約とは異なるのか?~
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
1 企業スポーツ選手の定義
(1) 企業スポーツ選手とは、企業に所属するアマチュアの社会人スポーツのことを言います。企業は、その選手の所属するスポーツ競技活動を援助し、広告宣伝効果又は社員の士気高揚などのメリットを得ます。令和元年のラグビーワールドカップ日本大会の宣伝番組となったTBS日曜劇場番組「ノーサイド・ゲーム」の「ときわ自動車のアストロズ」の選手などがそうです。宮崎県内で言えば、旭化成のスポーツ選手など2020東京オリンピック(開催が2021年へ延期)への出場に全精力を傾けている日本のスポーツ選手のほとんどが、この企業スポーツ選手だろうと思います。
(2) 日本の企業スポーツ選手の活動の変遷は、企業の一般社員と同じく勤務した後、退社後の夕方夜に練習するという実態から始まり、サッカーやバレーボール競技の人気上昇等の環境変化から各競技スポーツの日本リーグが発足した。競技技術の世界レベル化・ハイレベル化が要求されると、従来の連取形態では追いつけずに、徐々に企業スポーツ選手も社員でありながらスポーツ練習と試合活動を本業とするという方向に発展し、現段階では、企業と個人がプロ契約(期間を限定し、選手活動のみを行って報酬を得る契約)をする選手も出てきている状況に至っています。
また、バスケットボールなど競技の人気を高める手段としてプロ契約していくということもあるようです。
(3) 純粋なプロ契約ではなく、一応社員の身分を有しながらスポーツ競技活動を委嘱又は要求される契約をしている場合の選手を、仮に「企業スポーツ選手」と呼ぶこととします。その選手の企業での身分関係や法律関係は、入社契約や雇用契約という契約で細かな内容が定めてあるわけではないので、企業内での活動実態に即して判断されることになります。
企業スポーツ選手の型としては「準社員型」と「準プロ型」分けられます。例えば、午前中だけでも会社の職場での仕事をして午後から練習や試合活動を行う場合は「準社員型」(職場での業務従事性が強い)、会社の職場にはほとんど出社せずに机すらなく練習や試合活動を行う場合は「準プロ型」(職場での業務従事性が弱い)という区分になるでしょう。
また、いずれも雇用契約を基本としていると思われますので、入社契約において期間の定めがない場合又は雇用期間が1年間以内で更新が予定されている場合には、「準社員型」になります。労働契約としての労働期間は3年又は5年を超えることを禁止していますので(労働基準法第13条・第14条)、3年又は5年以上の期間を契約する場合は、「準プロ型」選手の場合が多いようです。また、「準プロ選手型」の場合には、給料面においても一般社員と異なる給与査定基準が定められ、試合での成績により高額なボーナスが支給されるシステムになっている場合が多いようです。
2 「準プロ型」選手としての入社契約の場合の法律上の身分関係
「準プロ型」の入社契約については、その契約の本質が「雇用契約(民法第623条)」なのか、「請負又は委任契約(民法第632条、第644条)」なのかを考える必要があります。前者は、企業による職務への従属性が求められ、後者では企業による職務への従属性はなく受諾者(選手)の独立性による職務遂行が求められるものであり、その区別がなされているからです。
「準プロ型」の入社契約は、プロ契約と同様に「請負又は委任契約」と位置付けられることが多いと思います。請負契約又は委任契約であれば、企業は選手との契約をいつでも解除できることになります(民法第641条、第651条第1項)。企業がチームの解散を決めるなどした場合には「準プロ型」契約選手は契約が解約され、他の企業への転籍又は引退を考えることになります。そういう意味では、法律上の身分関係は保証されないことになります。但し、企業も無条件に選手を解除できるわけではなく、期間を定めていた場合などはその期間分の報酬等を損害として支払う必要があります(民法第642条、第651条第2項)。
3 「準社員型」選手としての入社契約の場合の法律上の身分関係
(1)「準社員型」入社契約についても、その契約の本質が「雇用契約(民法第623条)」なのか、「請負又は委任契約(民法第632条、第644条)」なのかを考える必要がありますが、統計調査によると、正規社員として一般業務に従事しておりその従事時間も、シーズン中は1日約3時間30分、オフでは1日約5時間20分で、それ以外の時間は練習時間に当てられているという調査結果があるようです。給与も一般従業員と全く同様かスポーツ手当が付加される程度ということのようです。
この場合には、企業による職場での業務従事性があり企業への従属が強いので、「雇用契約」になるものと思われます。
(2)また、「準社員型」選手に対して労働法の適用があるかどうかについては、労働基準法の「労働者」、労働契約法の「労働者」に該当するかどうかを検討する必要があります。労働基準法第9条では、労働者は「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」とされ、労働契約法第2条第1項では、労働者は「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」と定義されており、いずれも「使用される者」として使用者に指揮命令の下で労働すること(使用従属関係があること)が本質になっていますので、その点を判例の判断基準にしたがって詳細に検討してみましょう。
① 業務従事の指示に対する諾否の自由が無いこと
準社員型選手は、一般業務に関しては指示された職場で指示された業務を遂行しており、スポーツに関しても、指示された時間に練習し、指示された競技会への出場も従うことになりますので、諾否の自由は認められていません。
② 業務遂行上の指揮監督があること
スポーツの練習においても練習メニュー等が監督から指示され、競技会での戦略の具体的指示がなされるシステムで行われており、指揮監督がなされているでしょう。
③ 勤務場所・時間指定等の拘束性があること
スポーツ業務の練習場所や活動場所・練習時間等が管理され、選手はそれに拘束されています。
④ 代替性があること
スポーツ業務について選手の代わりに一般業務の誰々さんが出場することは考えられないので代替性はないが、一般業務については、競技期間中、代わりの職員が行う形であり代替性はあることになります。
⑤ 報酬の労働対価性
一般従業員と異なり「スポーツ手当」が付加されると、それはスポーツ業務に関する対価性を有するものであり、給与全体につき一般業務とスポーツ業務を行っていることに対する対価性は認められるでしょう。
従って、「準社員型」選手は、個別的労働法上の「労働者」に該当し、労働基準法や労働契約法の適用がある「雇用契約(労働契約)」を締結しているものと解釈できます。
(3)「準社員型」選手の労働法上の身分と権利
① 一般業務に関する教育訓練・研修
企業においては良質な労働力を得るために社員への教育訓練・指導助言・研修等を行うことになりますが、企業スポーツ選手の場合には、一般従業員と異なり、研修などの教育訓練の場に常時出席することは困難になります。スポーツ業務の練習や競技会出場などをしながら一般業務に関するスキル向上を求めるのには、一定の配慮が必要になり、仮に、十分な教育訓練の機会を与えないまま、実際の人事評価において一般業務のみの低い能力評価をして給与査定や昇進査定を行うことは人事権の濫用(労働契約法第3条第5項)になるでしょう。
② パワハラ・セクハラからの保護
一時期、スポーツ団体内でのパワハラ・セクハラ問題がテレビで放映されていましたが、企業内でのパワハラ・セクハラ問題も労働法制下での大きな問題になります。パワハラ問題については明確な法律上の定めはありませんでしたが、労働施策総合推進法第30条の2に定められました(セクハラについては、従来から男女雇用機会均等法第11条第1項に定めがあります)。
一般業務に関してのパワハラ・セクハラだけでなく、スポーツ業務に関しての練習等でのパワハラ・セクハラも当然に対象になります。ただし、「スポーツの練習時の監督の厳しい指導がパワハラに該当するのか?」という根本的な問題は、個々の事情を総合的に勘案して判断するしか方法がないと思われます。監督と選手の間に信頼関係が持てない場合には、選手からパワハラ問題として提起される可能性が出てくるでしょう。
③ 企業チームの解散・廃部と選手の解雇
企業チームが解散又は廃部になった場合には、「準プロ型」選手は、契約解除(解雇)されることになるとしても、「準社員型」選手については、労働法の適用がある以上は、労働法上の解雇制限規定及び解雇制限法理があり(労働契約法第16条、第19条)企業者は自由に解雇できるというものではありません。解雇をするには「客観的合理的な理由」があり「社会通念上相当である」との要件を満たす必要があります。この点で、スポーツ業務がなくなったとしても、一般業務は残っているわけで、また他の部署に配転して一般業務を行うことができるような場合には、解雇の合理性や相当性はないとされています。
また、そういう観点から、「準社員型」選手の入社契約においては、選手活動終了時には一般社員に復帰できる又は他の職種に変更するなどの取り決めをしている例もあるようです。
このような観点からして、「準社員型」選手については、一般の従業員と同様に、解雇制限法理より、一般業務に対する労働能力を発揮できる可能性がある限り、従業員としての地位・身分は保証されるということになります。
以 上
高齢者死亡に関する親族の不協力への対応(その2)~死後事務委任契約の法的問題点~
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
(ご相談)
過疎化している○○町の町立病院では高齢者の方々の入院が多く、入院者のAさんは、遠方に住む息子さんBさんとも疎遠になっており、近所で付き合いの深かったお坊さんCさんに「自分が死んだら葬式から何から何まで全部処理して欲しい。そのお礼として300万円の報酬を事前に払う。」という約束をして、地元の司法書士さんに死後事務委任契約書を作ってもらいました。
その契約書には「寺院墓地にお墓を建立するので、葬儀及び供養をして欲しい。預金の中から病院費用や葬儀代も支払って欲しい。」と、自分の写真と300万円をCさんに渡していた。Aさんの死後、相続人の息子Bさんから、「死後事務を委任する契約は、A死亡時に終了するので無効であり、300万円を返還して欲しい。」と言ってきた。
お坊さんCは、どうすればいいのでしょうか。
1 民法第873条の2創設(平成28年改正)
平成28年の民法一部改正において創設された民法873条の2は以下のとおり定めています。
第873条の2 (成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)
「成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)
この規定は、成年後見人は、後見する被後見人(認知症等の判断不充分者)が死亡した場合には、成年後見は当然に終了し、成年後見人は原則として法定代理権等の権限を喪失しますので(民法第111条第1項第1号、第653条第1号)、死後の病院代の未払分の支払いや葬儀等の支払いも成年後見人としてはできませんので、支払いを止めたままで相続人に管理して貯金・現金等の財産を引き渡して未払債務の説明をして引き継ぐという必要がありました。死後早々に必要な火葬手続きや葬儀などの依頼も本来は行う権限はなく、後見終了時の応急処分(民法第874条、第654条等)として許される場合があるというのが従来の法的取り扱いでした。
しかし、成年後見人は、相続人への引継ぎに一定の時間と事務量が必要であることから、相続人が早々に対応しない場合には、成年被後見人死亡後には、死後事務を行う必要があり、また社会通念上これを拒むことは困難でした。そこで、成年後見人制度の範囲で成年後見人の終了事務が迅速かつ適法に行えるために、第873条の2が創設されたわけです。
2 一般的な知人・友人による死後事務の場合
(1)それでは、法定後見人や任意後見人でもない一般的な知人に、自分の死後の葬儀や供養の手続き等の死後事務を頼むことは無理なのでしょうか?
民法第653条第1号(委任の終了事由)によれば、委任契約は、委任者又は受任者のどちらかが死亡すれば終了する定めになっています。 そこで、Aさんの相続人の息子Bさんから、「死後事務を委任する契約は委任者であるA死亡時に契約も終了するので、無効である。」という主張も一理あることになります。
法律上の解釈論争として「委任者の死亡を委任契約の終了事由とする民法第653条第1号の規定は強行法規か否か」という争いがありました。
しかし、この点は最高裁平成4年9月22日判決により、「自己の死後の事務を含めた法律行為等の委任契約が成立している場合、死亡によっても右契約を終了させない旨の合意を包含する趣旨であり、民法第653条の法意がかかる合意の効力を否定する趣旨ではない。」として強行法規ではなく、任意規定だとしています。この最高裁の判例以降は、実務上、死後事務委任契約は有効なものとして締結されています(東京高裁平成11年12月21日判決、東京地裁平成28年7月29日判決等)。
(2)次に、死後事務委託契約は、委任者死亡後に、相続人が気に入らない委任契約として、相続人からすぐに解除されてしまうのではないでしょうか?
民法第651条第1項は「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」と定めていますので、委任契約が委任者Aさんの死後にも有効であったとしても、契約の地位の承継をした相続人(委任者)からいつでも解除されてしまい、AさんとCさんの委任契約は無かったことにすることは、法律上は可能です。
このような事態を回避するために、Aさんは生前の委任契約の際に、「死後事務委任に関しては委任者からの解除権は放棄する。」という条項を定め、民法第651条第1項の適用を排除しておく必要があります。但し、このような民法の規定の排除を定めた契約条項が有効かどうか、争われた事案があります。
東京高裁平成11年12月21日判決では「委任者の死後における事務処理を依頼する旨の契約においては、委任者は、自己の死亡後に契約に従って事務が履行されることを想定して契約を締結しているのであるから、その契約内容が、不明確又は実現困難であったり、委任者の地位を承継した者にとって履行負担が加重であることなど契約を履行させることが不合理と認められる特段の事情がない限り、委任者の地位の承継者が委任契約を解除して終了させることを許さない合意をも包含する趣旨と解することが相当である。」と判示して、無理由解除権放棄の特約が有効となることを認めました。
3 ご相談の結論
以上により、お坊さんのCさんは、相続人Bさんに対して、死後事務委任契約の有効性を主張して300万円を返還しなくても構いませんが、相続人の相続財産が全くない場合、300万円はAさんの唯一の財産だったということになるので、遺留分(相続財産の1/2)を相続人が有することを勘案して、法的争いを防ぐ意味で、半額150万円程度を返還するという和解的な解決をすることも良いかも知れません。
以 上
高齢者死亡に関する親族の不協力への対応
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
(ご相談)
ある自治体からのご相談です。
「ある過疎の町立病院で高齢者の方々の入院が多く、入院中、意思疎通ができなくなる患者さんもいらっしゃいます。そのような患者Aさんの場合に、遠方に住む息子B男さんが、入院契約・身元引受人誓約書も提出しています(入院費用は介護施設入院中のAさんの妻(痴呆症状態)の預金口座から自動引き落としで未払いはない)が、B男さんは病院の治療同意や協力要請には何ら対応しないままでした。Aさんが死亡された際にも、B男さんは病院の電話やFAX連絡に何ら返事もしてこず、遺体の引き取りをしてくれません。他に協力できる親族も見当たらない場合、Aさんのご遺体について、どのように手続きをすればよいでしょうか。」
(回答)
1 コロナ禍の中の日本のお盆の時期も終わりましたが、お盆時期になると人の生死の話を考えてしまいますね。
今の日本は、少子超高齢化社会へ突入しており、多くの方が子供たちに看取られることもなく、介護施設、福祉施設又は病院で死亡されることが多くなっているようです。そして、その相続人である子供たちは、費用のかかる葬儀などは省略することはいいとしても、遺体の引き取りや遺骨の引き取りを堂々と拒否する人が多くなっているようです。特に、勝手に出奔して家庭を捨て長く音信不通となったままでその親が亡くなったというのであれば、実の子であっても、遠路を厭わず死亡地に赴き遺体の引取り葬儀を行う気持ちになれない場合もあるでしょうが、そういう事情もないにも関わらず、費用の工面や手続きの面倒さだけから、遺体の引き取り拒否をするというご相談の事例も、今は突拍子もない話ではないようです。
2 日本人の精神風土としては、家族の一員が死亡すれば、遺体を引取り、葬儀をした上で、火葬をし、ご先祖の祭られているお墓に納骨するというのが一般的な慣習です。
では、法律上はどのようになっているのでしょうか。問題は、遺体の引き取り、火葬に付す義務のある者は誰か、という点ですが、実はこれを定める法律は見当たりません。「墓地、埋葬等に関する法律」では、「死体の埋葬又は火葬(以下2者一括して「埋葬」と言う。)を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)がこれを行わなければならいない。」とし、市町村長の最終的な埋葬義務を定めているのですが、誰が本来の埋葬義務者なのかについては全く触れていません。この点は「慣習」に委ねているのだろうと思いますが、慣習違反には何ら法律上の罰則等はありません。慣習違反に何か制裁があるとすれば、親族や近しい人たちから「義理も人情もない」、「親不孝者」、「無責任者」と陰口をたたかれるというだけのことでしょう。
3 もうひとつの法律である戸籍法を見てみますと、戸籍法第87条は、人が死亡した場合、「同居の親族」、「その他の同居者」、「家主等」の順序で、死亡届出をする義務を課しています。これを手掛かりに、誰が遺体の引取り義務があるかということを考えてみますと、死亡届義務がある以上は、少なくとも、同居者が同居場所等において遺体を受取る立場になるということで、同居の親族には遺体の引取り義務と埋葬する義務があると解釈することも可能だと思われますが、その場合でも、引取義務違反に対しては、引取りを強制する方法がありません(強制不能)ので、埋葬法の本則に立ち返り、結局「埋葬を行う者がいないとき」として市町村長が行うこととなります。
そういう法律の定め方からしますと、この息子B男さんは、まず「同居の親族」には該当しませんので、法律上、父親の遺体の引取り義務も埋葬をする義務もないことになります。
もし、この場合に、誰も引き取らず(身元判明者であれ身元不明者であれ)葬儀など埋葬・火葬執行者がいない場合は、厚労省管轄の福祉政策の一環として「行旅病人」及び「行旅死亡人」として市町村の長がこれを行うと定めていますので、死亡地の市町村長が火葬にして、一定期間、遺骨を保管し、その期間内に親族から遺骨の引取り申出でがあればその人に渡します(条例で定める保管料の支払を求められます)が、期間内に申出がなければ提携の寺院又は公共埋葬施設に埋葬されることになります。
その場合、市町村(病院)としては具体的にどのような手配をすればいいのでしょうか。
正解があるわけではないのですが、市町村の手続でも病院に長い間ご遺体を置いたままにはできないでしょうから、取扱例のひとつとしては、病院では患者が亡くなった場合に遺体の搬送をよくお願いしている葬儀業者があるはずなので、そういった業者を聞いて、まずはその葬儀業者に搬送を依頼し、近くの斎場等の安置所にしばらく安置されている状態にして、市町村で火葬手続きを進めていくという取扱例があるとのことです。
これが、ご相談に対する回答ということになります。
4 それでは、親族でもない友人が、遺体を引取って火葬・埋葬することができるのでしょうか。
ご遺体を引き取り埋葬、火葬するためには、「墓地、埋葬等に関する法律」第5条1項の規定により、まず市町村長の許可を受けなければならないと定めています。
市町村長の許可を受けるために、同法「施行規則」第1条には①死亡者の本籍、住所、氏名 ②死亡者の性別 ③死亡者の出生年月日 ④死因 ⑤死亡年月日 ⑥死亡場所 ⑦埋葬又は火葬場所 ⑧申請者の住所、氏名及び死亡者との続柄を記載した申請書を、死亡地の市町村に提出しなければならないと定めています。そこでは、申請者と死亡者の「続柄」の記載を求めていますが、親族でないといけないと定めてはいません。従って、遺族親族でなければご遺体の引き取りができないということはありません。友人の方でも、市町村に備え付けの申請用紙に必要事項を記入し提出、市町村長が許可すれば、引き取り葬儀・火葬が可能です。
5 参考までに
孤独で亡くなり引き取り手のいない人に対する無縁仏としての手続は、年間3万2000体以上になるようですが、そのほとんどが、身元が判明して家族がいるのに引き取られない場合で、引き取り拒否が近年急増しているとのデーターもあるようです。「関わりたくない」とか、「縁は切れている」、「もうしばらく会っていない」といったことが引き取り拒否の主な理由なのだそうですが、市町村としては、このように、引取拒否された遺骨を市町村の無縁墓地や受け入れお寺に埋葬する手続きが市町村の業務として急増することは覚悟しておいたほうがよいでしょう。
以 上
殿ちゃま・近ちゃま九州国珍道中記(法律解説編)その12
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
第14章 殿ちゃま、男になる!(理事長実績編“弁護士の灯火論”)
九弁連結成50周年を終え、殿ちゃまは、九弁連51年目の理事長に就任し、理事長方針としては、「九弁連100周年に向けた新たな1年目のスタートの年」として、“九弁連はひとつ”“九州は一体”との九弁連活動をどのようにして具体化していくのかという視点から運営方針を提示された。
その運営方針は、筑紫の国福岡県弁護士会の理事に賛同されて、九弁連各県の理事たちの協力のもと、“50年後から100年に向けての着実な第一歩”としての実績を理事長として残されたと評価されている。吉野正九弁連副理事長(福岡県弁護士会会長)の言によれば、「殿所理事長は男になった!」ということである。
その業績は、簡単に挙げても形になったものが多くある。
①ブロック・サミットの提唱・開催―日弁連、各県弁護士会の制度以外に、各地域弁護士会連合会(ブロック)が独自の運動・活動を活発化させるための全国レベルの協議連絡機構となろうとする構想の確立
②法律相談センターの全国3番目(五島)、4番目(石垣)の設置開設―弁護士過疎地域の法的サービス組織のスタート
③九弁連組織の充実―各理事の委員会担当制度の実施、予算基準の明確化、事務局長の相談員機構(旧事務局長の支援)の発足
④司法修習短縮改変に伴う弁護士会事前研修の確立・実施
これらは、殿所哲理事長時代の形成財産として、九弁連活動の貴重な活動組織として、九弁連に半永久的に残るものだろうと思われる。
平成11年3月、 殿ちゃまは、九弁連理事長としての退任挨拶を次のように締め括っている。
「この年度の、各弁護士会を代表される理事の方々で構成される九弁連は、意見の違いや立場を乗り越えて、他の人々の話しを聞き取ることへの高い能力を持ちあわせた集団でありました。理事集団の意見の収斂の仕方等、心技とも極めて高度でこのうえなく怜質であり、私の最も尊敬できる集団でありました。九弁連結成51年目を迎えた年であり、50年前の九弁連の姿から見れば、今日の九弁連の発展充実は夢のように写ったかも知れません。第3回国連総会(1948年、昭和23年)で、世界人権宣言が採択されてから、今年は丁度50周年…その間の人権の容貌も多様な価値観に突き押されながら、大きく変革せざるを得ませんでした。歴史の重たい流れの中での1コマの今日、私たちが、今後の50年先を、その時代の九弁連の姿を、形のある映像として思い描くことは困難でありましょう。しかし、私どもは、時の流れと共に、より良きものを求めて、毎日毎日1枚1枚紙をめくるようにして連続した日常的行動の中から、時宜に適した展望を見出して行かなければなりません。九弁連が今日まで50年を要して達成した現在の姿でも、時代の変革について行けない不足部分はありますように、いつの時代でも完成と未完成とが同居するのが常であります。今後の50年先の時代でも変革と日常性的安定の葛藤は普遍的な事象だろうと考えます。それを承知の上で、今年のなにほどかの前進と残された不足部分を次期の理事長・理事各位に引き継ぎたいと思います。今年のなにほどかの前進が、今後の時代の流れに沿って、原型を失って変革されようと私たちは一向に構いません。しかし、私たちが、弁護士としての信義・正義と真実追求という心の灯火(ともしび)そのものは燃やし続けなければならないと思います。」
この挨拶は、殿所哲弁護士の“弁護士の灯火(ともしび)論”として後世に残る挨拶となりました。まこち、いい挨拶じゃったねぇ~。パチパチパチ(拍手)。
(法律解説)
このシリーズの第1章の法律解説で、九州弁護士会連合会の説明をしており、宮崎県弁護士会から初めてその九州弁護士会連合会の理事長に就任されたのが、殿所哲弁護士(殿ちゃま)であることを紹介しております。私と共に宮崎県町村会の顧問弁護士であることから、このコーナーにこのシリーズ「殿ちゃま・近ちゃま九州国珍道中記(法律解説編)」を載せていただいております。
殿所弁護士の理事長退任のご挨拶は、「弁護士の灯火(ともしび)論」と呼ばれているものでした。
弁護士の使命は弁護士法第1条に高らかに謳われております。私を含め、すべての弁護士が、法的紛争に巻き込まれ悩む人々、法的被害を受けている人々、安心した暮らしができない人々の明日を、かすかにでも明るくする「灯火(ともしび)」であるように努めてもらいたいと思っております。
1 弁護士の使命
「社会正義の実現」と「人権擁護」、これは私たち弁護士が生業の中で常に意識しなければならない弁護士の使命です。
弁護士法第1条は、弁護士の使命として次のように定めています。
「1 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。」
弁護士は、同じ法曹の裁判官や検察官のように国からの給与等は無く、自分で事務所経営を行い依頼者からいただく報酬で生活していますので、その使命は「依頼者の権利及び利益の擁護」とみられてしまう面もあるのですが、本質的な使命は、「基本的人権の擁護」と「社会正義の実現」です。その使命を達成するために、弁護士には職務の自由と独立が要請され、高度の自治が保障されています。私たち弁護士は、その使命を自覚し、自らの行動を規律する社会的責任を負っているのです。また、依頼者に良質なリーガルサービスを提供するため、常に教養を深め、法令及び法律事務に精通するべく日々研鑽に努めていかなければなりません。
私も、弁護士会会長(平成23年)や弁護士会常議員会議長(令和元年)として弁護士会で新年の挨拶や企画活動の挨拶等をする際には、「会員弁護士の皆様が、社会正義の実現と人権擁護の弁護士の使命の下で、益々ご活躍されるよう期待しております。」などと、弁護士の使命については常に触れるようにしていました。
2 社会正義とは?
それでは「社会正義」とは何をいうのでしょうか?
社会正義は、「社会的公正」「配分的正義」とも呼ばれ、欧州の騎士道、日本の武士道にも通じるものがあると言う人もいます。勧善懲悪の思想や天道思想も同じ考えでしょうか。簡単に言えば「社会生活を行う上で必要な正しい道理」ということでしょう。現代思想としては、具体的には、人権や平等主義(公平)、累進課税などを通した収入や財産の富の再分配などが社会正義の要素として挙げられます。
民主主義は、理性のある国民一人一人の自由な判断に基づく国家の意思決定方式であり最も「正しい」方法だとされていますが、理性に基づかない多数決方式は衆愚政治を導いてしまいますし、国民一人一人の「理性」こそ、社会正義の基本です。私たちの「理性」は、自分の立場で考える理性をいうのではなく、相手や他者の立場に立って考える「理性」であることを忘れてはなりません。私は「社会正義」とは、「他者の立場に立って考えたことを基本に判断をしていくことで実現できる社会実相のこと」をいうのではないかと考えています。
そこには、個々人が個々の自分の能力を身に付けることも含まれますし(能力主義)、勉学や労働の機会均等も含まれますし、社会的弱者への時の配分(格差是正)や社会保障思想も含まれてきます。それは、抽象的な私たち国民というよりも、人間一人一人が、時代の発展・変容という時間の流れのなかで、その都度その都度、学び続け志向されて行かなければならないものです。
小学校の恩師山下フミ先生から小学校卒業時に戴いた言葉は「学ぶべし、怠るべからず、人の一生は勉強の連続である」という言葉でした。
また、大学時代の恩師である九州大学名誉教授三島淑臣先生(法哲学・法思想史)から教えていた導歌に「辿りゆく麓の道は多けれど、同じ高嶺の月を見るかな」というのがあります。誰しもが、そういう社会正義の月を見られるように常に勉強し学びながら麓から高嶺へと登りゆくわけです。
そして、殿所哲先生が“弁護士の灯火論”の挨拶で言及されているように、「私どもは、時の流れと共に、より良きものを求めて、毎日毎日1枚1枚紙をめくるようにして連続した日常的行動の中から、時宜に適した展望を見出して行かなければなりません。」ということが、まさに弁護士の「社会正義の実現」という歩みなのだろうと思います。
これでこのシリーズ「殿ちゃま・近ちゃま九州国珍道中記(法律解説編)」は終了となります。お読みいただき、ありがとうございました。
( なお、「最終章 そして、桜の咲く頃に~女房に感謝を込めて~」は、殿ちゃま・近ちゃまから妻たちへの個人的な感謝の言葉を書き綴った文章にすぎず法律解説ができませんので、“割愛”させていただきます。 m(__)m )
以 上
殿ちゃま・近ちゃま九州国珍道中記(法律解説編)その11
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
第13章 あと一年、ご苦労さん! あれ~?双子?
平成11年3月末。
お正月もとっくに過ぎ去り、いよいよ、九州弁護士会連合会の会務も最後の理事会を迎え、最終理事会の前に、平成11年度の次期理事候補を集め、九弁連次期理事予定者会議を実施することになっている。
話は変わるが、九弁連会務は筑紫の国の福岡県弁護士会が理事6名を擁し、そこに活動の中心メンバーが揃う。近ちゃまの九州大学法学部同期のT辺M彦・T辺N克の兄弟(いずれも福岡県弁護士会の弁護士だからすごいよねぇ。)の兄T辺M彦氏も理事として活躍していた。理事は任期1年であるから、次期予定者会議には、平成10年度の現理事が参加することはない。
平成11年度次期予定者会議には、予定者以外に、平成10年度役員中、現理事長殿ちゃま・事務局長古賀ちゃま・事務局次長近ちゃまが参加するのみである。
予定者会議直前、各県から次期理事予定者が次々と弁護士会館の会議室に入ってくる。
福岡弁護士会の理事も全員新顔である。しかし、T辺理事の顔も見える。
殿 「やあ、T辺先生、継続でもう一年ですか、ご苦労さん!来年度も頑張ってください!」
と、殿ちゃまが、T辺理事の肩を叩いて、親しそうに挨拶!
T辺N克 「え?はい?あの~」
T辺N克 「あの~、私は、こういうもので(名刺を出す)、殿所理事長とは初めてお会いするんですが…。」
殿 「え?あれ?ん?」
T辺N克 「兄が平成10年度の現理事で、私は、双子の弟のほうになるんですが。」
あ~あ、殿ちゃま、またまた、ちょんぼ!
廊下で次期理事予定者の方々の受付をしながら全員が揃うのを待っていた近ちゃまのところまで、殿ちゃまが、トコトコやって来て、
殿 「おい! ! また、失敗、失敗。福岡のT辺弁護士は、双子か!現理事のT辺M彦先生とばかり思って、“また、もう1年頑張ってください。”と言って肩をポンと叩いたら、“私は弟です!”と言われてしまったよ!」
近 「あ!そうでした。彼らは、私と九州大学の同級で双子なんですよ~。」
殿 「何で、それを先に教えんのか!」
近 「・・・・・・」
・・・どうして、近ちゃまがお叱りを受けるのだろう?
(法律解説)
この章では、「人間違い」の場合の法律関係を説明するしかないかと思います。
1 刑事裁判での人間違いについて
(1)誤認逮捕
誤認逮捕(ごにんたいほ)とは、警察などの捜査機関がある人物を被疑者として逮捕したものの実際にはその人物は無実であったことが判明した場合の逮捕行為を言います。そもそも法律上許される逮捕は、ある人物に対して犯罪の嫌疑を持った場合に必要性があればなしうるものであり、刑事訴訟法第199条において「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。」と定めています。捜査機関は逮捕を行うことで犯人の逃亡や証拠隠滅を防止し、起訴をして有罪判決を得られるだけの証拠を集めるための捜査を行います。この「嫌疑」はその時点の証拠関係から判明した相当程度のものでよいとされるので、逮捕後に十分な捜査をした結果、逮捕した者が実は罪を犯していなかったと判明すること(「嫌疑が晴れる」ということ)は、制度上起こり得ることです。
しかし、誤認逮捕されたほうは、たまったものではありません。逮捕されると日本のマスコミは犯罪者であるという前提での報道をしますので、社会的名誉や仕事を失うことが必ずあります。そのような場合、国家は逮捕された人に補償をしなければならないということになります。
日本国憲法では「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる」(憲法第40条)と規定しています。刑事補償法第4条第1項で、抑留又は拘禁による補償については、1日あたり1000円以上12500円以下の割合による補償金の交付を受けられる旨を規定しています。
しかし、刑事補償法の対象となるのは、起訴されて無罪判決を得た人が、逮捕・勾留されていた場合だけで、起訴される前に容疑が晴れ釈放された場合については、刑事補償法の対象にはなりません。逮捕後、起訴される前に容疑が晴れ釈放された場合の手当は「被疑者補償規程」に拠ります。第2条は「検察官は、被疑者として抑留又は拘禁を受けた者につき、公訴を提起しない処分があった場合において、その者が罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由があるときは、抑留又は拘禁による補償をするものとする。」と定めていますが、被疑者補償規程は、法務省訓令という行政機関の内部規程に過ぎず、誤認逮捕された者に補償を請求する権利を与えたものではないので、補償されるか否かは、全て検察官の裁量次第とされていますので、補償されない場合には、誤認逮捕が違法であるとして、国家賠償請求をする方法が残っていますが、今の法律解釈では、誤認逮捕されたことが必ずしも国家賠償法にいう「違法」とはされないという問題が残っています。
(2)殺人行為での人間違いについて
① ある犯人が、Aを殺そうとしてAに向かってピストルを撃ったが、Aには当たらず、隣のBに当って、Bが死亡しました。犯人には誰に対する何罪が成立するでしょうか?
② 同じく暗闇での人影がAだと思ってピストルで撃ってその人に当ったが、人影はBであり、Bが死亡し、Aはその場にはいなかった場合、犯人には誰に対する何罪が成立するのでしょうか。
〇このような問題が刑法の試験で出されます。刑法における「事実の錯誤」という論点の理解を求める問題です。
「事実の錯誤」とは、犯罪構成要件事実に対して錯誤があった場合のことを言います。上記の例では同じ「人違い」であるのですが、①の場合は「方法の錯誤」、②の場合には「客体の錯誤」と呼ばれています。この区別は、犯人の目の前に現実に認識したAがいるかいないかで区別されていますが、(毒薬入りジュースを送り付けた場合のように目の前にAがいないことを前提としてA宛に郵送した場合のような離隔犯の場合には、この区別は難しくなります。
この問題を解決する刑法学説には色々な見解がありますが、基本的な考え方によれば、どちらの場合でも、実際に亡くなったBへの殺人既遂罪を認め、①の場合にはAへの殺人未遂が加わりますが、②の場合にはAへの危険性すら生じていないのでAへの殺人未遂罪は成立しないと解釈されています。
2 民事裁判での人間違いについて
(1)契約する相手を間違えた場合
契約は、契約する人と契約する対象物と契約する内容の意思表示で成立するとされています。その契約の三要素の一つを間違った場合には、契約という意思表示を間違ってしたことになりますので、意思表示の錯誤が生じていることになります。民法第95条には「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」と定めてありますので、契約相手の人違いについては、「法律行為の要素」に関する錯誤と言えますので、その契約は無効にすることができるとなりそうですが、一般には契約の対象物が重視される契約において、人違いは錯誤とならない(大判大8.12.16)とする判例もありますが、契約相手の個性に着目する無償契約では、要素の錯誤が認められ無効となると解釈されています。
「結婚も」二人の合意による身分契約とされています。この場合の人間違いは相手の個性に着目する場合ですから、相手と違い人との婚姻届けが出されている場合には、婚姻意思がなかったものとして婚姻は無効になります(民法第742条に「婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。」と定めてあります。)
なお、格言に「結婚は男と女が互いに錯誤することで成立する。」という種類のものがありますが、これは法律的なことを言っているのではなく、男と女とはお互いに理解し難い間柄であり、間違った認識をしたから初めて結婚することになるのだ。」というエスプリであります。(エスプリとはフランス風ジョークとでも言えましょうかね。)
(2)裁判で訴える人を間違えた場合
民事裁判で、原告がAさんを訴えようとしたのに、訴状の被告名としてBさんと書いた場合に、裁判の被告として裁判に出てこないといけない人は誰でしょうか、という問題があります。
① 訴状が被告Bさんに送られる前に、原告が間違いに気づいた場合には、訴状の訂正をしてAさんへ送ってもらえばそれで解決します。
② 訴状の被告Bと書かれたまま、Bさんに訴状が送られた場合にはどうでしょうか。この場合には、訴状はBさんに届きますので、Bさんが被告となって訴訟の当事者とならざるを得ません。但し、その後に、原告がBさんではなくAさんを訴えたのだとして「表示の訂正」としてAさんを当事者とする方法を取ってきた場合に、「表示の訂正」によって、再度、Aさんに訴状送付をして裁判を続けられるかは問題です。Bさんが全く無駄をふまされただけで終わるからです。Bさんが同意しなければ「表示の訂正」はできないでしょう。原告はBさんへの訴えを取り下げて、新たにAさんを訴え直す必要があります。
③ Bさんを表示した訴状がBさんに送られたのに、Aさんがその裁判の相手は自分のことだろうと考えて、第1回口頭弁論の裁判からAさんがBさんとして出頭して訴訟を行ってきていたが、判決を行う段階で、Bさんの名前でAさんが訴訟をしていて、原告も訴訟行為をしているAさんを訴える意思で訴訟行為をしてきた場合も「人違い」というより、その訴訟の当事者被告として誰を確定するべきかという問題になります。この場合、行動説、意思説、表示説の立場があるようですが、実際に訴訟行為をした者(Aさん)が判決を受けるべきであり、表示がBさんであっても、判決はAさんの表示に変更訂正してAさんに対して行うべきであるという見解が妥当です。
以 上
殿ちゃま・近ちゃま九州国珍道中記(法律解説編)その10
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
第12章 日本の南端の島で~「あれ?これ、どこから覗くんですか?」~
(後編:竹富島-西表島-由布島の三島巡り)
早朝の沖縄石垣の空は、快晴!!!
石垣法律相談センター開設の九弁連会務も昨夜の地元懇親会で終わり、今日は、殿ちゃまと観光予定の一日である。
近ちゃまは、早く起きて石垣の空を見上げて快晴を確認すると、ホテルの電話で殿ちゃまを無理やり起こす。
近「もしもし、先生、起きられました? 天気は晴れです。今日予定していた石垣島一周案はやめます。今日は、もうひとつの案の、竹富島-西表島-由布島の三島巡りにします。船に乗りますので、早くでかけましょ。石垣に来て西表島に行かなかったら、後でみんなから馬鹿にされるそうですよ。」
と、殿ちゃまを説得。
早速、二人でホテルのレストランの朝食を取りながら、
殿「夕べは、石垣の弁護士の件はおどろいたなぁ。病気の弁護士が来ているとは誰も思わんわなぁ。」
近「沖縄弁護士会の会長も、理事長のお話をしたら、ええっ~!って、びっくりしていましたから。それより、早く食べて出かけますよ。」
ゆっくりと朝食を取りたがる殿ちゃまを急かしてあたふたと朝食を済ませ、石垣港から船旅の写真撮影旅行へ、しゅっぱ~つ!
近ちゃまは、買ったばかりの「写し絵覗箱」(一眼レフカメラのこと)を担いで、殿ちゃまもでっかい一眼レフカメラを担いでの旅である。
殿「どらどら、いいカメラを買ったねぇ。初心者用だが機能がいっぱい付いていていいよ。しかしねぇ、その機能を君は使えるかなぁ?その機能を使えんようじゃなぁ~。」
近「いいんです。自動になっていますので、シャッターだけ押せれば写るんです。先生がカメラを買え!って僕に言われたんですよ。」(第6章参照)
殿「う、うん。そうか・・・。」
竹富島は、琉球王朝時代の琉球瓦屋根と珊瑚積みの塀の街並みがそのまま残った生活様式が見られ、星の砂の砂浜「コンドイ浜」もある。竹富島には交通信号機はない。竹富島から出る海中観光船から見る珊瑚礁と魚の群れはほんとに綺麗である。その美しさと静けさに、南の国ののんびりとした生活感を感じ取ることができる島である。
西表島は、熱帯・亜熱帯系植物の原生林の島で、天然記念物のイリオモテヤマネコ、カンムリワシが生息する。川の両側に広がるマングローブの景色は、原始時代を想像させるような異景である。西表島には交通信号機が小学生の勉強用に一ヶ所だけある。若い運転手が奇妙な敬語を使って案内するバスで西表島回りの観光案内をしてくれた。南の国のジャングルという雰囲気の島である。
由布島は、水牛の島である。遠浅の海を西表島から、の~んびりと水牛車に揺られて渡る。南の国の離れ小島という感じの島である。島全体が観光園となっている感じであった。
昼食は、八重山「長命定食(長寿定食)」という名の、地元八重山の食べ物ばかりの定食である。食べる人の長寿を願って地元の長寿者の食事を定食化したもののようである。
殿ちゃまが長命定食を強く希望されて、近ちゃまも仕方なく同じ注文をした。
殿「おい。これ、おいしいねぇ。何だろうか?」
近「それが、ミ・ミ・ガー・で・す。」
殿「ありゃあ~。ブタの耳か!」
(ゲテモノ嫌いで、沖縄の牧志公設市場でも買おうとしやらんかったミミガーを何と、殿ちゃまは、おいしそうに食べやったげな。)
殿ちゃまは、でっかい一眼レフカメラの他に、デジタルカメラを持って来ていて観光用スナップ写真を撮っている。
殿「おい。これでちょっと俺を写してくれ。」
と、デジタルカメラを差し出す。
近ちゃまは、デジタルカメラを受け取り、ポーズを取り始めている殿ちゃまから少しずつ離れて行きながら、
近「はい!いいですよ。写しますよ~。」
近「あれ?これ、どこから覗くんですかぁ~???」
殿「え?お前、どこから覗く?!…」
と言ったきり、・・・・殿ちゃまは、腹を抱え、顔を真っ赤にして、クックックと笑いを押さえるのに必死で、しばらく声も出ない。
ひとしきり笑った後、
殿「どこから覗くったって、デジタルカメラは、液晶に画面が出るから覗くところは無いがね。覗く必要はないがね。・・・。このことは誰にも話さんでおいてやるわな。ふっふっふ。」
近「・・・(心の中で・・・きっと誰かに話すに決まっている・・・)」
西表島のマングローブ原生林の川を観光用ボートで上がっていく。ジャングル探検の雰囲気である。
このオプション選択は、殿ちゃまも気に入ってくれた。昨日まで「オプションのパックツアーは自分の時間がゆっくりないから嫌だ。」と不平を言っていた殿ちゃまの顔つきが、いつのまにかにこにこ顔に変わっていた。
・・・そりゃそうだろう。近ちゃまはホテルのツアーデスクで「の~んびり三島巡り」といって“の~んびり”がわざわざ付いているオプションツアーを選んであげたんだから・・・・・。
殿「おい!カンムリワシがいるぞ。」
とカメラを覗いて激写体勢。カシャカシャカシャと高額カメラのシャッター音がマングローブの森に聞こえている。カンムリワシは逃げないで悠々と木々に止まってマングローブの森を見渡している。
「カンムリワシ」は、国の天然記念物であり、プロボクサー世界チャンピオンの具志堅用高のリングネームやガウン背中の刺繍で有名である。そのカンムリワシも間近に観られたし、その雄姿を写真に写せたし、何より広い青空を見上げられる、南の島の天気は快晴であった。
近ちゃまは、“近ちゃんの企画はすばらしい!”と殿ちゃまから誉めてもらいたかったそうじゃ。
宿泊は、高級リゾートホテル日航八重山である。近ちゃまも高級ホテルには泊まり慣れてしまい、な~んの失敗もない。
しかし、殿ちゃまは聞く、
殿「おい。このホテルの部屋の電灯の消し方は分かったか~?(にかッ)」
と、ホテル事件(第3章)を思い出して殿ちゃまが一人笑っている。
2日目の夜は、次期九弁連事務局長と合流して「居酒屋“栄”」で盛り上がる!地元取れの名前の分からない名前の魚を食べたり、チャンプルーを食べたり…。
殿ちゃまは珍しく泡盛をクイクイッと飲んで上機嫌である。殿ちゃが担当された昔の面白い事件の話が延々と続く。暴力団から人質の女性を助け出した事件(「ダンスしながら耳元で」事件)、強姦事件で「いや」と「いや~ん」の違いを争った事件、不倫石積み暗号事件などなど・・・・。
男三人での事件話が延々と続きながら、南の島の夜が更けていった。
翌日3日目、殿ちゃまも近ちゃまも、少々二日酔いであったものの満足できた心持ちになりながら、JTAのジェット機の窓から、カンムリワシになった気分で八重山諸島の島々、珊瑚礁を下に見ている。「日本の南端への旅」からの帰路に着いた。
沖縄のお土産に、殿ちゃまは、なぜか、精力増進・元気回復のハブ酒を買っていた。2万円!
沖縄のお土産に、近ちゃまは、なぜか、豚の耳(ミミガー)と豚の顔(ツラガー)を買っていた。2,000円。
殿ちゃまと近ちゃまの珍道中は、とうとう、日本の南端まで及んだのであり、二人はそれぞれのお小遣いの経済格差(約10倍)を維持しながら、九州を北から東・西へと、そして南まで行ってしまったわけじゃなぁ。
(法律解説)
1 イリオモテヤマネコ・カンムリワシ訴訟
(1)沖縄県・西表島でユニマット不動産(本社東京)が進めているリゾートホテル建設計画に反対し、全国環境保護連盟(東京)などのメンバー10人が29日、国の特別天然記念物イリオモテヤマネコやカンムリワシなど22種の動物を原告として開発の中止を求める訴えを東京地方裁判所に起こしたという裁判事例(平成14年10月,東京地方裁判所平成14年(ワ)第23454号リゾート開発差止請求事件)があります。
その訴訟では、原告らは「開発予定地は絶滅の恐れがある生き物が多く生息しており、コンクリート護岸化などにより生存権が侵害される」と主張していましたが、平成15年2月26日判決で「原告適格がない」として却下されています。同様に動物を原告にした訴訟は鹿児島県・奄美大島のアマミノクロウサギ訴訟などがありますが、その訴訟においても、「原告適格がない」として却下されています(鹿児島地裁平成13年1月22日判決)。
(2)東京地裁平成15年2月26日判決(上記事件)の内容は次のとおりでした。
① 本件訴えは、沖縄県八重山郡a町付近に生息するなどする前記22種の動物(イリオモテヤマネコ等)を原告として提起されたものである。
② しかしながら、当事者能力については、民事訴訟法第28条が、当事者能力は、同法に特別の定めがある場合を除き、民法その他の法令に従う旨規定するところ、民事訴訟法及び民法その他の法令上、自然物たる動物に当事者能力を肯定することのできる根拠を見いだすことはできず、したがって、自然物たる動物である原告らに当事者能力を認めることはできないといわざるを得ない。
③ よって、本件訴えは、当事者能力を有しない者を原告とする不適法なものであり、その不備を補正することができないから、民事訴訟法第140条に基づき、口頭弁論を経ないで本件訴えをいずれも却下することとし、訴訟費用の負担につき同法第61条、第65条第1項本文を適用して、主文のとおり(原告の訴えを却下する)判決する。
2 野生生物の保護と法律
動物を原告とした訴訟は、自然の権利訴訟と言われ、野生生物や自然界と人間が共存する権利、野生生物の権利というものの保護を意図したものです。
そこで、そもそも、日本の法令では野生生物は保護されているか、を見てみましょう 。
法令としては、①鳥獣保護法(1918年制定)、②種の保存法(1992年制定)、③文化財保護法(1950年制定)、 ④外来生物法(2004年制定)、⑤カルタヘナ法(2003年制定)や⑥各地方公共団体の条例等を挙げることができます(長岡大学吉盛一郎論文「自然の権利訴訟」参照)。
① 鳥獣保護法(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律)では、鳥獣を保護し増やすために鳥獣保護区が設けられ、鳥獣保護区では狩猟が規制されます。
② 種の保存法(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)では、野生動植物が生態系の重要な構成要素であり、自然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのでき ないものである(第1条)として「希少野生動植物種」を保護するとしています。
③ 文化財保護法(旧史蹟名勝天然記念物保存法を引き継いでいる)は、天然記念物に指定されるものは、わが国にとって学術上価値が高い動物、植物および地質鉱物であるが、動物が天然記念物に指定されると捕獲が禁止されます。イリオモテヤマネコやアマミノクロウサギなどが指定されています。
④ 外来生物法(特定外来生物被害防止法)は、外来生物を廃除・駆除することによって従来種の生態系への被害を防止するとしています。
⑤ カルタヘナ法(遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律)は、コロンビアの都市カルタヘナでの国際会議で採択された遺伝子に関する議定書の趣旨に沿ったものであるが、遺伝子組換え生物等による生態系や健康への影響を防止するため輸入や使用などを規制するものです。
このような生物保護関連法律や条例に、『自然享有権』や、市民や環境NGOに『自然の権利』を代弁する原告適格規定を設けられていないことから、野生生物が消滅する具体的な危険性が発生した場合の個々の保護、救済手段となる訴訟活動が封じられている状況になっています。
3 デジタルカメラとアナログカメラ
デジタルカメラとアナログカメラの違いはほとんどなく、唯一の違いはフィルムを使用しているかCCD(画素)を使用しているかの違いですが、技術的にアナログカメラで撮影したものをデジタル化することが出来るようですから、更に違いはなくなってきています。
写真を得意な趣味とされている方は、アナログカメラ(フィルムカメラ)にこだわりがある方が多く、フィルムカメラの方が、細かい線もしっかり撮影することができ、絵を撮影した場合には色の変化がくっきりと写ると説明されています。特に、引き伸ばし拡大してもきれいに見ることができるために、大きな写真画像を作る際には、フィルムカメラの方がよいとされています。
4 新型コロナ・ウイルス感染拡大と観光事業
沖縄も宮崎も南国風土を生かした観光事業が行われている地域ですが、中国武漢市から始まったとされる令和2年3月頃からの新型コロナ・ウイルス感染のパンデミック(世界的大流行)は、日本政府の「緊急事態宣言」により人と人との接触をしないことを防止策としたために多くの事業閉鎖となり、観光・飲食店事業においても、外国からの航空便の減便、クルーズ船の寄港の減少等による観光客の減少、さらには、国による小中高校等に対する休校要請や修学旅行等の予定していたイベントの中止・延期要請等により、人々の行き来が無くなり全く事業として成り立たない時期を過ごしてきています。
沖縄県は、コロナ・ウイルス感染防止対策として、観光での来訪を自粛してもらう呼びかけをしています。その内容は次のとおりでした。
「今、首里城や美ら海水族館等、主要な観光施設は軒並み閉鎖しており、沖縄観光を楽しむことはできません。そして、多くの県民が活動自粛している中、沖縄最大の魅力である人の温かさに触れることもできません。また、島しょ県である沖縄県は、医療体制が脆弱です。新型コロナ以外も含めて、病院に入院する必要が生じた場合、病院での受け入れが難しくなることが危惧されます。
県外在住の沖縄ファンの皆さま、愛する沖縄を守るため、そしてご自身を守るため、どうか今は来沖や県内離島への渡航を我慢してください。終息後には「うとぅいむち(おもてなし)」の心で皆様を歓迎いたしますので、今は一番安全な場所である皆さまの「家」でお過ごしください。」
観光事業が成り立たなくなった損失に関する法律問題として、事業者の損失を誰の責任とするのか、事業が成り立たなくなったための従業員の休業状態に対する給与は支払義務があるのかどうか、事業が遂行できないことを理由に従業員を整理解雇できるのか、などの様々な問題が発生します。
基本的には事業閉鎖について日本の制度としては「強制」ではなく「協力要請」をしているにすぎない建前ですから、国への補償請求が当然に認められるわけではなく、又、事業者が国の協力要請で事業閉鎖している以上は、従業員への休業や解雇は「会社の都合による休業又は事業閉鎖」としての面がありますので、従業員は給与の支払いを受け、解雇事由はないとされる可能性があります。
このような事業者にとっての不合理な結果に対しては、現在、国や地方自治体が行おうとしているように特別補助金・支援金として事業損失を補償する制度を創設していく必要があるように思います。
本珍道中記は、そのような感染症パンデミックの無かった「平成の時代」の「のん気な雰囲気での旅行」が楽しめた時代の話であることをお許し願いたく思います。
以上
以 上
殿ちゃま・近ちゃま九州国珍道中記(法律解説編)その10
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
第12章 日本の南端の島で~「あれ?これ、どこから覗くんですか?」~
(前編:「私は元気であります~。」
平成の御世(平成10年)の殿ちゃまと近ちゃまの九州国珍道中の旅も、11月、12月となると、九州弁護士会連合会の殿ちゃま理事長の任期終了が近づき、九弁連会務の仕上げの時期となり、激務の程度も少しずつ軽くなっていく感じじゃった。
これまで数々の珍事件に遭遇した殿ちゃまは、この頃には近ちゃまの少々のミスは慣れっこになったようで、大目にみてくれるようになり、理事長職としての業務の仕上げにと総括準備に入っておりゃったげな。
1) 平成11年3月。
殿ちゃまと近ちゃまは、沖縄・石垣島に旅をしやった。日本弁護士連合会と九州弁護士会連合会が共同して、那覇地裁石垣支部管内に「石垣法律相談センター」を設立し、その開所式と開設記念レセプションに出席するためじゃったげな。
九弁連会務で殿ちゃま理事長が最も力を入れたのが、弁護士0-1(ゼロワン)地域の弁護士会法律相談センター構想の実現である。簡単に言えば、裁判所はあるのに弁護士がいないといういわゆる「弁護士過疎地域」に弁護士による法律相談組織を作っていこうとするものである。
殿ちゃまの九弁連理事長時代の1年間に、なんと!殿ちゃまは、全国3番目に長崎・五島に「五島法律相談センター」を設立し、全国4番目に、南端の島、沖縄・石垣島に「石垣法律相談センター」を開設しゃったわけじゃ。
九州国は離島が多い地域じゃから、全国に先駆けてわずか1年間に2つも「法律相談センター」を開設させたことは、誰が見てん、すごい業績じゃということになるげななあ。
この石垣島への旅は、宮崎-沖縄那覇市(県知事訪問)-石垣市(市長訪問・開設式)-ホテル日航八重山に宿泊という流れで、宮崎―那覇-石垣-那覇-宮崎を2泊3日で観光する余裕のある旅であった。
宮崎空港から那覇空港へ向かう飛行機の中で、
近「先生、今回は今年最後の旅ですから、お互い失敗無しということで慎重に行きましょう。」
殿「君こそ、また、何か失敗するんじゃなかろうなあ?」
近「ところで、石垣は2人の弁護士登録があるのに、何故、弁護士0-1(ゼロワン)地域なんですか?」
殿「沖縄弁護士会の会長の話だと、1人の弁護士は高齢で、病気で倒れていて実働はないということだったなあ。」
近「そうですか、それで、九弁連理事長として働きかけられて、日弁連の0-1地域法律相談センター構想の対象になったわけですね。」
殿「ま、そういうこっちゃ。ところで、那覇空港に着いたら、那覇から石垣町への飛行機は、今度はプロペラ機かな?」
近「えー? 違いますよ。ちゃんとしたジェット機ですよ。40分くらいかかるらしいですから、宮崎-福岡間と同じくらいの距離があるんですよ。しかも、もう間違ってますよ。石垣は町ではなく、石垣市ですよ。」
殿「そうか。田舎じゃろうと思たけどなあ。」
石垣市の人が聞いたら怒りそうな、殿ちゃまのつぶやきである。
那覇市で沖縄県の与那嶺知事(かりゆしのシャツを着ておられました)への挨拶訪問を済ませて、すぐ石垣島へJTA(日本トランスオーシャン航空)の「ジェット機」で移動する。天気は生憎の雨模様・・・・飛行機に搭乗後すぐに、機内アナウンスが「石垣に着陸できない場合は引き返すこともございます。」と告げていた。着陸予定時間が過ぎても、飛行機はなかなか着陸しない・・・石垣上空を40分ほど飛行機は旋回している。
殿ちゃまは、かつての韓国旅行帰路の飛行機引き返し事件を思い出し(*第10章を参照)、“着陸できなかったら、相談センター開設記念式典はどうすればいいか”と心配でたまらんがったげな。しかし、その殿ちゃまの横で、隣座席に座っている近ちゃまは、いびきをグーグーかきながらあんのんと眠っていたげなよ。
ドスンと飛行機が着陸。すぐ急逆噴射。ゴーッと逆噴射音。
体がぐーっと前に引き出される感じになり、飛行機のシートベルトが役立つことが始めて体験できる。
近「あ!やっと着きましたねえ。あーあ、ずいぶん遅れちゃいましたねえ。長く旋回していましたねえ。」
と、冷静に時計を見るふりをして、近ちゃまが一言。
殿「おお、そうじゃったねえ。少し疲れたわ。君は大丈夫か。」
近「はい。寝ないで心配してました。」
しかし、殿ちゃまは、近ちゃまが、着陸の逆噴射のショックで初めて目を覚ましただけで、それまでの40分間の旋回を全く知らず、開設式典に遅れる心配どころか、グーグー寝ていたことは先刻承知の介であった。
石垣空港は滑走路が短く大型機が利用できないために、空港新設計画(白保海上案)があるが、きれいな珊瑚礁を死滅させるとの反対運動が起こり、長い滑走路を想定した空港新設計画は実現していない。そのため、ジェット機のパイロットは、今の短い滑走路に着陸と同時に急逆噴射措置を取らねばならないという極めて技術の要する空港の1つになっているらしい。
2) 石垣島では、医者の資格を持つ石垣市長に挨拶訪問をした後、江戸からきた日弁連会長と日向の国からきた殿ちゃま九弁連理事長が記者会見。近ちゃまも、殿ちゃまの後ろに座って、チャッカリ、瓦版の写し絵(新聞用写真のこと・八重山日報)に写っちょりゃったげな。
開設記念式典レセプションでの殿ちゃまの挨拶は非常に簡明で上手であった。なぜ石垣島が弁護士0-1地域なのかの説明(1人の弁護士が病気で実働していないことまで詳しく解説)まで言及されたものだった。
理事長挨拶と乾杯を終えた殿ちゃまは、その場に石垣から1人だけ出席していた弁護士のテーブルまで挨拶に行き、
殿「やあ、ご苦労さまです。大変でしょうが、法律相談センターもできましたので、今後とも頑張ってください。」
弁「はい。どうも。」
殿「ところで、先生はおいくつになられますか?」
弁「78歳ですわ。」
殿「お元気ですなあ。もう1人の方は、御病気で寝ておられるんでしたねえ。」
弁「いや、いや。もう1人は私より若くてバリバリやっていますよ。」
殿「あ?」 「いやあ?」 「は?」
(ありゃ?こりゃ、まずい!病気の方のほうが開設式典に出てきているようだと、殿ちゃまはすぐ感づいた!!)
殿ちゃまは、ソソクサとその席を離れ、末端テーブルで、普段食べなれない豪華食事をムシャムシャ食べては、沖縄オリオンビールをガブガブ呑んでいた近ちゃまに近づき、
殿「おい。石垣の弁護士は1人病気で倒れているという話じゃったがね。」
近「はい。そうですよ。(ムシャムシャ)」
殿「ところが、今日はその病気の弁護士のほうが開設式典に参加していて、今その人に、“1人は病気で倒れていて実働されていないんですよねえ”、と言ってしまったぞ。」
近「働いていないほうの弁護士が出席されているんですか?」
殿「沖縄弁護士会の会長の話と違うぞ。さっき挨拶で、1人は働いていないから0-1地域になると説明したばっかりじゃ。本人は怒っちょりゃせんじゃろうかなあ。本人は、面と向かって“あんたは働いとらんじゃろ”と言われたようなもんじゃわなあ。」
近「そうなりますねえ。ま。いいじゃないですか。飲みましょ。後で沖縄の会長に話しておきます。」
殿ちゃまの冷や汗もんのお話じゃった。
このお話には、おまけがある。
なんと!石垣のその弁護士先生は、最後に歓迎のスピーチをして、
「先ほどの挨拶の中にも、石垣の1人の弁護士は病気で倒れているとの説明があったが、あれは、多分私のことだろうと思うが、確かに、もう民事の仕事はしてない!しかし、私は、元気であります!………。」と、のたもうた。
殿「ありゃ~。やっぱり、怒っちょった~。」
近「そうみたい・で・す・ね。」
(法律解説)
1、日弁連の「0-1(ゼロワン)地域の弁護士会法律相談センター構想
日本弁護士連合会は、平成時代に入って、「市民にとって利用しやすい、開かれた司法」、「いつでも、どこでも、だれでも良質な司法サービスを受けられる社会」の実現を目指し、司法サービスの全国地域への展開に取り組んできており、特に弁護士過疎・偏在の解消に関しては、1999年(平成11年)の「日弁連ひまわり基金」の設置と全会員からの特別会費の徴収によって、全国に数多くの法律相談センターとひまわり基金法律事務所が開設・運営されるようになりました。国の費用ではなく、弁護士全員が個々人の費用負担で過疎地域への弁護士相談派遣費用や法律相談センターの設置費用を賄うという弁護士たちだけの活動でした。その対象地域は「地方裁判所各支部管内(後に簡易裁判所管内にも適用拡大)の行政区内に弁護士が不在か弁護士1名しかいない場合という0-1(ゼロワン)地域」でした。当時、全国で74か所が対象地域になりました。宮崎では、日南・串間市、日向市、西都市、小林・えびの市が対象とされました。
宮崎県内の0-1(ゼロワン)地域解消事業としては、2002年(平成14年)8月に日南ひまわり基金法律事務所開設、2006年(平成18年)8月に日向入郷地区ひまわり法律事務所開設、2008年(平成20年)10月に小林ひまわり基金法律事務所開設、2010年(平成22年)6月に西都ひまわり基金法律事務所開設を終え、全国的には、2011年(平成23年)12月には全国の地方裁判所支部管内における弁護士ゼロワン地域が一旦解消されるところとなり、当連合会管内においては、現在も弁護士ゼロワン地域の解消状態が維持できています。
ちなみに、殿所弁護士が理事長に就任された九州弁護士会連合会としては、2000年(平成12年)4月のひまわり基金・九弁連対馬弁護士センターの開設に始まり、九州各県の弁護士過疎地域に、ひまわり基金法律事務所の設置を積極的に進め、29か所の公設事務所を設置してきたという実績がありますが、それ以前の1998年(平成10年)の長崎五島福江法律相談センター(全国3番目)と沖縄石垣法律相談センター(全国4番目)の設置は、日弁連費用での設置を九州弁護士会連合会が働きかけたというものです。
2、新石垣空港の開港
石垣空港の新空港建設計画は、その後計画場所の変更(カラ岳陸上案)がなされ、2006年(平成18年)10月20日には起工式が行われ建設工事が始まり、2013年(平成25年)3月7日に新石垣空港が開港し、滑走路が旧石垣空港より500 m長い2,000 mとなったことで、ボーイング777-200・767-300・787-8クラスの中型ジェット旅客機も離着陸可能となり首都圏への直行便も運航可能になったということです。新石垣空港の愛称は「南ぬ島 石垣空港」(ぱいぬしま いしがきくうこう)であり、航空定期便が発着する空港では日本最南端に位置するとのことです。(ウィキペディア(Wikipedia)参照)
以 上
殿ちゃま・近ちゃま九州国珍道中記(法律解説編)その9
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
第11章 殿ちゃまを一人にできない!
殿ちゃまと近ちゃまの九州国珍道中はいつも二人一緒というわけでもない。九弁連理事長という要職にある殿ちゃまだけが一人で旅をする場合もある。殿ちゃまの孤独な旅である。
殿「この前、ブロックサミットに一人で行ったけど、宮崎空港で搭乗手続きを済ませた後、12時50分出発と思ってゆっくり昼食をとって、のんびりとロビーまで行ったら、40分出発だったらしく、
ロビー案内嬢が“殿ちゃま様、殿ちゃま様はいらっしゃいませんか!”“殿ちゃま様はいらっしゃいませんか!”“殿ちゃま様、出発のお時間がきております!”と大声でロビー内を走り回って捜していたんだよ。飛行機の出発を遅らせてしまったよ。やぁ、近ちゃまのことは(第4章を参照)、笑えんなぁ。」
近「な、な、な~んと。飛行機の出発を遅らせたなんて!私は、そこまではしていませんよ。」
殿「君に話したら、それ見よとばかりに笑うだろうなぁ、とその時思ったよ。」
近「そりゃそうですよ。」
殿「やはり、君がおらんといかん。」
やはり、殿ちゃまを一人にしてはおけない、と近ちゃまは思った。
しかし、本来は慎重である殿ちゃまが、そそっかしい近ちゃまの性格に馴染んでしまい、近ちゃま的性格が伝染してしまったのだろうというのが、大方の見方であった。
殿ちゃま68歳、近ちゃま44歳の、もういい年の中年男子であった。
(法律解説)
1,おひとりさまを取り巻く「法的トラブル」
「おひとりさま」という言葉には、独身者の気楽な生活イメージがある反面、身の回りのすべてのことを自分一人でやらなくてはならないシングル生活、又は独居高齢者のイメージもありますが、「法律、制度、お金の三つの知識を強い味方にすれば、たったひとりでも老後は安心!」というスタンスで、「おひとりさまの法律とお金」という本を出している弁護士もおられます。
その本では、夫婦の一方が死亡、又は離婚したりして「おひとりさま」になった場合の法的トラブル、おひとりさまの労働契約の解雇や住宅退去のトラブル、おひとりさま高齢者の振り込め詐欺トラブルなど、多くの孤独な戦いをしなくてはならないための法律知識が助言、解説してあるようです。
(1)おひとりさまになる場合のトラブル
① 配偶者の死亡によって一人になる場合
この場合、法的には「相続(財産の分け方の問題)」や「祭祀承継(さいししょうけい)」(お墓やお骨の管理の問題)のトラブルが生じます。相続で多くトラブルが生じる場合が、第2順位相続の場合と第3順位相続の場合です。
この場合の法定相続人は、配偶者である自分と死亡した配偶者側の血族(父母・兄弟姉妹)であり、残されたひとりぼっち配偶者が他の血族相続人とうまく協議してもらえない状況に追い込まれ相続トラブルになります。
多勢に無勢の場合には、弁護士への早期相談又は家庭裁判所での遺産分割調停などの法的な手続きに則り正当な解決を図る勇気が必要になります。
② 配偶者との離婚によって一人になる場合
この場合、夫婦間において離婚協議がスムーズに行えれば問題は少ないのですが、その場合でも慰謝料の他に財産分与などのお金の問題でなかなか合意できないことが多いようです。離婚は結婚のときよりも何倍ものエネルギーが必要だと言われています。
夫婦で住宅ローンを利用してマンションを購入している場合に、「マンションは自分がもらい、ローンは浮気して離婚の原因となった相手方に払ってもらう」という希望が多く出ますが、浮気の慰謝料と財産分与としてのローン負担は全く別個の法律問題ですので、なかなかうまく協議になりませんし、
他方、「マンションは自分がもらうから、ローンも相手方名義であるが自分の方で払っていく」という場合でも、ローンの債務者名義を簡単に変えることができません(一度ローン残額全額を借り換えれば別ですが)ので、ローン名義だけが残る相手方がなかなか承諾してくれないという問題が生じます。
結局、ローンを返済するためにマンションを売却する方法しか残らず、離婚すれば、従来住んでいたマンションに一人で住むということはあきらめざるを得なくなります。
(2)高齢者社会と高齢者独居生活のトラブル
① わが国の高齢化率は、2019年9月時点で28.4%、4人に1人以上が65歳以上の高齢者となっており、また、少子化等も影響して日本の人口は今後も減少傾向にあることから、高齢者だけの世帯や高齢者の独居暮らしが多くなっています。
ある統計では、高齢者独居の世帯は、平成27年には240万1千世帯、全世帯数の5%程度に上ります。65歳以上の人口に占める割合をみると、男性の13.3%、女性の21.1%が一人暮らしをしているとのデータがあります。
② 独居高齢者の消費者被害による国民消費生活センターへの相談件数は年々増加しており(平成27年度には18万3千件の相談)、そのトラブルの内容については、高齢者宅に直接電話してサービス勧誘する「電話勧誘販売」、訪問してサービス販売する「訪問販売」、
インターネットサービスによる「インターネット通販」が多く、その極めつけが、電話での「オレオレ詐欺」や「振り込め詐欺」による被害であり、全国で総額何兆円もの被害が出ています。
③ 認知症高齢者の場合には、徘徊による近所間トラブル、財産管理懈怠又は財産紛失トラブルなどが介護者や介護施設又は近隣者、親族間で起きたりしています。
この点は、介護保険制度と同時に平成12年4月から開始された成年後見制度の利用を積極的に行ってもらう必要がありますが、同制度を利用せずに、親族又は知人の一人が事実上の介護や財産管理をしていることからトラブルになっています。
2,弁護士同士の関係について
(1)法曹界とは
裁判官、検察官、弁護士、法律学者、法務局・刑務所等の法務関係者の法務・司法など法律関係の仕事に携わる職業の業界関係を「法曹界」と言っています。特に、裁判官、検察官、弁護士を指すことがあり、「法曹三者」とも言われています。
平成28年度で裁判官2,755名、検察官1,930名、弁護士3万7,680名という4万人を超える業界になります。「法曹」という言葉は、もともとは「下級の監獄官吏」の意味で、それが転じて「法を司る官僚」という意味になり、裁判官と検察官を指す言葉として用いられたようです。
(2)弁護士の呼び方について
① 法曹三者で最も多いのが弁護士ですが、弁護士は、他の二者とは異なり公務員ではなく自営業者になります。そこで、弁護士は自分で法律事務所を経営するか、大きな法律事務所に雇用されるか、大きな会社の法務担当者として雇用されるか、国や地方公共団体の職員(期限付き)として採用されるか、という方法で弁護士業務を行うということになります。
もっとも、弁護士資格(法曹資格)を持ちながら、弁護士登録をせずに会社や地方自治体に一般職員として採用される方法もありますが、その場合には弁護士業務を行うことはできないし、行った場合は弁護士法違反となります。
② 法曹界内部の呼び方になりますが、弁護士業務の仕方のうち、最初から法律事務所を経営する場合を「即独弁護士」、雇用される場合を「居候弁護士(イソ弁)」、雇用されないが先輩事務所の一部屋に間借りして仕事をもらう場合を「軒下弁護士(ノキ弁)、企業等に雇用される場合を「組織内弁護士(インハウスローヤーの略で「インハウス」)などと呼んでいます。
一旦検察官となった後に弁護士になった場合を「辞め検弁護士(ヤメケン)」と呼んだりしていますが、他の業界では通用しない呼び方ですし、好意的な呼び方とも言えませんので、品位をモットーとする法曹界にあっては、徐々に呼び名としては消えていくのではないかと思います。
③ なお、殿ちゃまも即独弁護士であり、近ちゃまも最初から即独弁護士です。近ちゃまは、殿ちゃまの事務所の「イソ弁」だったという噂がありますが間違いです。
ただ、殿ちゃまは、近ちゃまが即独弁護士一年目から法律相談客や事件紹介をいただき、大きな案件での共同受任もさせていただきながら弁護士業務を基本から指導していただいた大恩人であります。
今、この文章を書いている令和の時代で、殿ちゃまは90歳の「卒寿」を迎えられ、近ちゃまも66歳の「緑々寿」を迎え、高齢者の部類に元気に突入しております(笑)。
以 上
殿ちゃま・近ちゃま九州国珍道中記(法律解説編)その8
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
第10章 こんなに疲れる韓国旅行って、な~んだコリア(Korea)?
(お詫び:第8章「シーガイアであたふた、あたふた。(九弁連宮崎大会)」及び第9章 「僕は浮気防止役?(摩女梨花での夜)」は、私の勝手な都合により割愛させていただきます。)
1,平成の御代の10年目の6月は雨の多い梅雨であった。
九弁連では年1回の大きなイベントとして、海外視察交流旅行がある。その九弁連海外視察で、「今年は、ハワイか!」という近ちゃまの大きな期待に反し(?)、韓国のプサンとソウルの各弁護士会との交流及び研修を行うことが九弁連国際委員会で決定されちゃったのであり、事務次長の近ちゃまの権限なんて何一つもないみたい・・・・。
近ちゃまは、梅雨の雨空を見上げ、韓国も雨なのかなぁ、ハワイは晴れているだろうなぁ・・・と諦めが悪い。
韓国の英名は「Korea(コリア)」である。韓国は、日本と共通する箸と米食の文化を持ち、長い歴史的交流のある隣国であり、同じ民主主義国家としての経済面、政治面でも相互友好関係の国である。人々の交流が盛んとなり、裁判や弁護士の世界でもその法律家の交流が重要さが増しちょったから、いい研修旅行になるじゃろうと企画されたげな。
研修旅行先が決まり、九弁連理事長の殿ちゃまは旅行団団長、近ちゃまはその随行秘書役となった。
日向の国の宮崎県弁護士会においては、「宮崎の弁護士が誰も参加せず、殿ちゃま先生の団長一人だけで韓国に行かせるわけにはいかない!」という近ちゃまの悲痛な呼びかけに、松ちゃん(松岡茂行弁護士)、谷ちゃん(谷口悟弁護士)たちも交流旅行に参加してくれたげな。近ちゃまのこの言葉に、何かイメージしませんか?
そう、近ちゃまのこのときの言葉は、数年後にイギリスのロンドンで開かれた五大陸優秀選手運動大会(「ロンドンオリンピック」とも言う。)の際に、日向の国出身の水泳メダリストの松田丈志選手が、同競技の北島康介選手が個人種目メダル無しに終わると、「康介さんを手ぶらで帰すわけにはいかない!」と話して結束し、メドレーリレーで銀メダルを獲得したという歴史的な言葉の原点となったんじゃろなぁ。
実際に、韓国視察の準備を始めると、殿ちゃまは、団長としての会議等における挨拶が待っており、韓国との歴史的背景をもとに国際交流上の配慮事項を調査したり、近ちゃまは、団長挨拶にシーガイア九弁連宮崎大会へのご招待や韓国交流実績のある南郷村(現美郷町)「百済の里」の紹介の文言を入れるということで、それらの資料と挨拶文起案にバタバタ、あたふた。
そして、近ちゃまは、こんにちは=アンニョンハシムニカ、ありがとう=カムサムニダなど挨拶に使える韓国語は~何がいいかと考えながら、ハングル語の本を買って来ては、付け焼刃のハングル語の挨拶に挑戦してみたりし、とにかく自分の旅行準備よりも韓国での会議準備の方が大変だったのじゃ。
殿ちゃまは、韓国視察の出発直前にも、筑紫国福岡で日本法律家協会の会合に出席したり、福岡高等裁判所長官や福岡高等検察庁検事長が参加する九州法曹会議に九弁連理事長として参加したりと、筑紫国福岡に滞在し、日向の国宮崎には帰れぬまま韓国に出発するという強行スケジュールである。
2,いよいよ、韓国に到着する。
韓国は、銀行倒産等の大不況(IMF支援)の時期で、経済的にも街並みの雰囲気も活気が無い。空港に降り立つ前に飛行機の窓から見えた韓国は、赤茶けた山が印象的で、ほこりっぽい感じがする。気分的にはキムチの匂いがするような異国の雰囲気があり、旅行のワクワク感が十分に感じられたようじゃ。
ところで、韓国の赤茶けた山の風景は、韓国の日本軍占領下で日本軍が大量の樹木を伐採したからであるという説もあるが、韓国焼き物とオンドル暖房という伝統的文化のため大量の樹木が伐採され続けた結果だという説明のほうが正しいようである。
殿ちゃまは、韓国でもプサン-慶州-ソウルと移動する旅程の中で、団長としてそれぞれの都市に行くたびに大忙し・・・・近ちゃまの起案したハングル混じりの読みにくい原稿で挨拶をしたり、通訳を通じて言葉をかけながら韓国側のそれぞれの弁護士に握手をしたりと外交官並みの立ち振る舞いをしなくてはならない。
韓国側の弁護士は、韓国語で話をされるのだが、実は英語以外に日本語も話せる人が多い。日本側の弁護士は、韓国語がほとんど分からない。語学教育の差だろうか?
近ちゃまは、九州各県弁護士の皆さんに頼られたかどうかは別にして、旅行代理店の随行者みたいな役回りとなり、各訪問先の入場料や食事代の支払いなどの会計担当である。
参加者からの預り金の入ったリュックをいつもスーツの上に背負ったままアタフタと動きまわっていたげな。松ちゃんも谷ちゃんも、換金の計算に戸惑っている近ちゃまをテキパキと手伝ってあげてたげな。カムサムニダ~。
観光客のようにのんびりと飲み食いして楽しめる企画や予定もなく、ガイド付きの真面目な史跡観光の他は、韓国プサン弁護士会、韓国ソウル弁護士会での交流会、弁護士会館見学、国会見学、憲法裁判所見学、地方裁判所見学と、研修見学行事や意見交換会議ばかりで、観光旅行気分で参加していた松ちゃんと谷ちゃんは、だんだんと不機嫌(!)になり始める。
しかし、二人は、各自の自由時間も殿ちゃまと近ちゃまに合わせて一緒に行動してくりゃって、近ちゃまはありがたかったげな。カムサムニダ~。
近ちゃまの「殿ちゃまを一人にするわけにはいかん!」という松田丈志的な一言の下で、松ちゃんも谷ちゃんも自由行動を控えてくれたのである。
しかし、最後のソウルの最後の夜は、ちゃっかり殿ちゃまをホテルの部屋に置いたまま、三人でそ~っと抜け出してソウルの夜の街へ・・・(実際は、ソウルの飲み屋街の屋台で通りを歩いている韓国美人を眺めながら、大いに飲み食いしただけで終わってしまったが)。
韓国ならではの経験といえば、殿ちゃまと近ちゃまたち三人は、公式行事を終えた夕方の自由時間に「カジノ」に行ったことじゃねぇ。ホテルの中に外国人専用の「カジノ」が入っているのである。
殿ちゃまの「みんな、1万円ずつで終わっちょけよ。」という厳しいお達しに従い、1万円限定のカジノ遊び(ルーレットゲーム)じゃったげな。肝心な殿ちゃまは、すぐに1万円負けてさっさとホテルの部屋に戻ってしまった! 松ちゃんは、1万円で3時間も粘っていた。
流れをつかんだ人の懸けたところに自分も懸けるというせこい勝負方法ではあったが、流れをつかんだ人が誰かを見極められるというのはすごい才能であると感心した次第である。
近ちゃまも1万円を限度にカジノゲームをしたが、殿ちゃまの次に早く負け、松ちゃんのカジノの風を読む風情を3時間も眺めておりゃったらしい。谷ちゃんは、最後のスロットルで「中当たり」程度のコインをジャラジャラと出していて損はしなかったようであった。強運の谷ちゃんである。
3,九弁連韓国視察の帰路は、ソウループサンー福岡-宮崎へと一日をかけての飛行移動である。
問題が発生したのは、入国後の最後の旅程の福岡空港でのことである。福岡発-宮崎行の飛行便の案内でがっくり。福岡に着き、更には結構長い入国手続きでも疲れ果てていたのであるが、「宮崎は天候不良!」との情報が飛び込む。詳細に情報を確認すると、午後4時発の福岡-宮崎便は飛ぶ、次の午後5時発の便は飛ぶか飛ばないか検討中とのこと。
殿ちゃまは、松ちゃん、谷ちゃんや他の参加者と一緒の4時の便、近ちゃま一人だけが5時の便である。何の手違いだったんじゃろかい?
殿ちゃまは「じゃ、先に帰るからね。」と冷たいお言葉を残し、他の参加者と一緒に4時の便に搭乗して行きゃった。・・・ 残された近ちゃまは、天候回復を祈りながら、人の少なくなった福岡空港で一人疲れ果てて待つのであった。
ところが、空港場内案内で「宮崎行き4時発の便は天候不良のため、折り返しになりました。5時発の便も欠航となります。」とアナウンス。近ちゃまは自分の便の欠航の残念さよりも、前の便が戻ってくるということに大喜び!
「みんなも帰って来る!」
と元気な気持ちになっていた。
近ちゃまは、福岡空港の到着ロビーで殿ちゃまたちが重い荷物を抱えて出てくるのをニコニコ顔で「お帰りなさい。」と出迎えてあげた。
心の中で、「万歳、万歳」と近ちゃまは叫んでいたが、みんな宮崎上空で40分も旋回飛行に揺られていたらしく、憮然として、かつ、疲労困ぱいの表情・・・今回の韓国視察は、最後まで疲れに疲れる旅行であったという結末を象徴するトラブルであった。
谷ちゃんは、「もう頭にきた!今日は博多に泊まる!」と言ってぷりぷり怒って福岡空港から出て行き、博多の街へ消えて行きゃった。
他には、ゴルフバッグを抱えて次の便で無理に飛んで行って鹿児島空港に向かわされ(着陸地変更)、鹿児島から更に高速バスで帰らされたという参加者もおりゃった。
殿ちゃまと近ちゃまは、最後に、夕食も取る暇もないまま、天神バスセンターへ急遽移動し、高速バス・フェニックス号の指定席を手に入れることができ、二人で宮崎までの帰路に着く。殿ちゃまは高速バスの席に深く沈むよう疲れて眠っておりゃった。暗い高速バスのガラス窓に映る殿ちゃまのその横顔には疲れが出ており、68歳の老いが覗いていた。
近ちゃまは、小さくつぶやいたげな。「殿ちゃま、本当にお疲れ様でした。」
宮崎到着は夜10時半、ソウルを出発して17時間の長旅の一日であった。
参加した日向の国の宮崎県弁護士会の全員がとてもとても疲れた、「なんだコリア?!」とダジャレでも通じないくらい疲れた初めての韓国旅行じゃったげな。ひんだれたねえ~。
ところで、韓国は、観光目的でゆっくりのんびり食べて飲んで楽しめる外国です。ご飯やみそ汁、魚料理を箸で食べるという日本式で通用する部分もあり、それに加えてチヂミ、トッポギ、おでん、なべ料理など韓国独特の料理も存分に味わえるようですし、気楽で楽しい外国旅行が経験できる良い国ですよ。
皆さん、韓国旅行は、最初から観光旅行を企画した方が絶対に楽しいと思います。「コリア(こりゃ)また、行こう!」ということになりますよ~。
(法律解説)
1,九弁連海外視察
九弁連には、20の連絡協議会(委員会)が設置されており、その中の国際委員会により毎年、韓国・台湾・ハワイ・シンガポール・オーストラリア等の海外弁護士会との交流を兼ねて海外視察旅行が企画されます。参加者は自費ですが事務所経費として認められるところにメリットがあります。
これは、現代の法律・裁判関係において国際的な枠組みでの対応(外国人との離婚、外国との契約トラブル等)が必要となったことに関して、外国弁護士会と交流を持ち、手続き対応、資料提供、相互研究をしていく必要が生じていることから、各単位会だけでなく、九弁連全体で活動しようという意図で行われてきているものです。
九弁連理事長が旅行団の団長となり訪問先の多くの弁護士たちの前で挨拶をします。当然、通訳が付いた会議になるのですが、渉外事務所で働く弁護士ならともかく、外国人と馴染みのない国内生活を送っている多くの弁護士にとっては、語学下手が多く、国際交流は、言葉が通じない点でとても重荷に感じます。
2,アジア通貨危機
(1)平成9年7月よりタイを中心に、インドネシア・韓国と広がったアジア各国の急激な通貨下落(減価)現象を「アジア通貨危機」と呼んでいます。
韓国では、起亜自動車の倒産を皮切りに、経済状態が悪化。国際通貨基金(IMF)の援助を要請する事態となり、現代グループなどに対して財閥解体が行われたりして「IMF危機」と呼ばれていました。
(2)その不況の冷めやらない平成10年に九弁連韓国視察を行ったのですが、韓国の街にも活気がなく、宴会も自粛ムードで静かな雰囲気で過ごしたという印象でした。
(3)この韓国IMF危機について、後日、金大中政権が開催した「IMF危機事態の責任」を問う国会聴聞会で、前政権担当者が、「日本系の金融機関が、日本国内の予想外の金融事情から短期債権の満期延長を拒否し、1997年11月~12月に急に70億ドルを回収していったのが金融危機をもたらした原因だ。」
との発言に対して、金大中政権は、「欧米系金融機関が資金を引き揚げたのに対し、日本系金融機関は、最後まで韓国金融機関への協調融資に応じていた。」と事実関係を明らかにし、日本の非難に終始した前政権を激しく非難して、日本を擁護したということがあるようです(「Wikipedia」による)。
(4)日本の通貨「円」と韓国の通貨「ウォン」は、1:10の価値比率となるようなので(1円が10ウォン)、韓国で買い物をする際に「10,000」という値札を見ると、一瞬“高いなあ”と思いますが、すぐに換算すると“あ!千円かあ。安いんだぁ。”と思い直しながら、買い物をしました。
その後、日本国内の何かの行事で賞金を渡すときに、「2万・・・・」という段階で一旦息を止めると、みんなが「うぉ~」とびっくりして、その後おもむろに「ウォン、を贈呈します。」と続けると、みんなが「な~んだ、2万ウォンかあ。2千円じゃが(笑)」となっていくウケ狙いで使わせてもらったことがあります。
3,カジノについて
我が国でも、2016年(平成28年)12月15日の衆議院本会議で「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」(IR推進法)が成立し、カジノの法制度化への道が開かれることになりました。
しかし、2020年(令和2年)1月6日、カジノを含む統合型リゾート(IR)事業をめぐり、現職の国会議員が収賄容疑で逮捕された汚職事件で、贈賄側とされる中国企業が国会議員5人に現金を配ったと供述するなど、政治的な利権も絡む問題が露見しています。
カジノ導入により、外国観光客の大量来日、カジノ税収入の増大とそれによる国家や自治体の財政健全化というメリットが挙げられますが、国民のギャンブル依存性の問題や治安の悪化、犯罪組織の関与等の大きな弊害も指摘されています。
そもそも、「カジノ」は、イタリアでの音楽、ダンスの集会所に起源をもち、19世紀後半からゲーム、賭博の場となったもので、賭け事を主とする遊興施設を意味しており、モナコ、マカオ、ラスベガスなどが有名ですが、イギリス、フランス、ドイツ、ボルトガル、ギリシャのヨーロッパ各国にもあるようです。
韓国では昭和50年頃にカジノが解禁され、現在では15箇所以上もあり、韓国の夜を盛り上げています。韓国のカジノは、外国籍で19歳以上の方であれば入場が認められており、韓国籍の方はカジノで遊べないことになっていましたが、平成12年以降は韓国人も利用できるカジノが認められています。
入場料は無料ですが、入場にはパスポートが必要となります。18歳未満の未成年者・幼児は付き添いの成人が同伴しても入場できないようです。
4,再度の韓国旅行(済州島での国際会議)
近ちゃまコト私は、この韓国視察後の十数年後にあたる平成23年9月23日~25日に再度、韓国を訪問しています。日韓の弁護士トップ層が合同会議を行う「日韓バーリーダース定期会議」へ日弁連理事としての参加でした。
場所は、韓国のハワイと称される「済州島(チェジュ島)でした。高級海浜リゾート地、テレビドラマの撮影地として美しい景色が人気の場所です。
会議後のパーティーの御馳走や「城山日出峰(ソンサンイルチュルボン、2007年にユネスコ世界自然遺産に登録された火山)」の朝焼けの風景、日の出撮影、強い風の中のミニ観光など、僅か3日間でしたが韓国の観光を満足しました。「コリア(こりゃ)また、行こう!」という気持ちになりました。
済州島の特徴を言い表すのに、「三麗」と「三多」、および「三無」という言葉があるそうです。
三麗とは、「美しい心」「素晴らしい自然」「美味しい果物」といった島民の心や景観の美しさ、特産物を意味します。
三多とは、「石と風と女の3つが多い」という意味。火山島であるため、火山の噴火により流出した火山岩が多く、台風が度々通過する上、季節風の吹く地域であるということです。
三無とは、「泥棒がいない」「乞食がいない」「外部からの(泥棒と乞食の)侵入を防ぐ門が無い(必要無い)」という意味だそうです。
かつての済州島は、厳しい自然環境を克服するため協同精神が発達しており、そのこともこの3つが無かった(あるいは必要とされなかった)とされてきた所以であると言われています。アジアの良い精神風土が育っているようでいいですよね。
以 上
恋愛か?わいせつか?(中学校の教師と生徒)
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
1,青少年育成保護条例(通称「淫行禁止条例」は、都道府県ごとに規定されており、その条例のほとんどが、基本的には「18才未満の者と淫らな性行為をすることを禁ずる」と定めています。
民法等の改正により成人年齢を20歳から18歳に下げても、この基準は変わらないだろうと言われていますが、そもそも、女性が16才で婚姻できる(民法第731条)にも関わらず、18歳以下の女性と性交渉を持ってはいけないという矛盾点は、なかなか説明しづらいものがあります。
矛盾点の解消としては、「淫行」の定義及び解釈で行なわれています。
「淫行」とは、簡単に言えば「性欲を満たすために青少年とセックスおよびそれに類した性行為を行うこと」とされ、恋愛感情を伴う婚姻目的の真剣交際は「淫行」にあたらないとの解釈です(昭和60年10月23日最高裁大法廷判決―福岡県青少年育成保護条例事件)。
ここで言う「真剣交際」とは、誘惑、威嚇など相手を困惑させる手段を伴わず、性欲を満たすためだけの性行為ではない場合を指すようです。
2,事例で考えてみましょう。
大学卒業後にアルバイトの塾講師を辞め、中学教師となる予定だったA男(以下「A男」という。)と15歳の女子中学生B子(以下「B子」という。)」の交際についての判例があります。
2人の交際は、A男が大学生時代に塾講師のアルバイト先の教室で、同塾に通っていた当時中学3年生のB子と平成27年2月頃に携帯電話のラインの交換を始めたことが契機となり、B子がA男に交際を申し出たことから始まっています。
これに対して、A男は2度交際を断りましたが、3度目(平成27年3月末)にはB子の想いが真剣なものであることを理解し交際を始めたようです。この時点において、A男は学習塾の「講師が生徒と連絡先を交換することは禁止する」との契約に違反していますが、大学卒業と同時に塾講師を辞める時期でもあったことから契約違反の認識は薄かったようです。
問題は、交際開始直後の平成27年4月からA男が公立中学校(B子の通った中学校とは別の中学校)の教員として採用されたことから、B子との交際をB子の保護者(両親)に報告したいと相談したところ、B子が「親は許してくれないし、理解を得ることはできない。」と拒否したこと、そして、B子から「休日の部活動(顧問)に行っている間にA男のアパートに赴いて昼食を作って一緒に食べたい。」と申し出られ、A男が合鍵を渡したこと、交際が発覚するまでの5か月間に10回程度アパートに出入りがあったということです。
アパートや外出先でのデート内容は後述のとおりです。
この交際が発覚(B子の母親が娘の携帯電話の着信履歴を確認し、A男との交際を知る)後、教育委員会が地方公務員法第29条第1項第1号(地公法第33条信用失墜行為、服務規定違反)及び第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合)の規定により「懲戒免職」とする処分を行ったが、A男は「懲戒免職処分になるほどの悪いことではないのではないか。」として、処分取消の訴訟を起こし、一審のさいたま地方裁判所(平成29年11月24日判決)は、A男の言い分(真剣な交際だった)を取り入れ処分を取消したのですが、二審の東京高等裁判所(平成30年9月20日判決確定)では、「本件交際は非違行為であり正当化することはできない。」として懲戒免職処分を有効としました。
| 交際内容 |
一審裁判所の評価 |
二審裁判所の評価 |
| 交際開始後の平成27年5月上旬に東京スカイツリーでデートし、キスをした。キス姿のプリクラも撮影した。 |
交際は女子中学生B子が積極的に望んだもので、将来を見据えて真剣に交際していたもの。
A男の性的欲求を満たすために行った非違行為とは認めらない。
青少年健全育成条例違反に問われていない。 |
B子は当時15歳の高校生で未成熟であり十分な判断能力があったとは言えず、また適齢期にも達していないことからB子の同意があっても正当化されるものではない。
キスや抱擁は、性的行為であり性的羞恥心の対象となるものでありわいせつ行為である。
|
| 7月 江の島・お台場でデートし、B子がA男の背後から抱きつき夜景を見たりし、その日はA男アパートに宿泊、一緒のベッドで就寝した(性行為やこれに準ずる行為はしていない)。 |
アパートに宿泊することを許した点は、B子の保護者の監護権等を侵害し公務員としての信頼を得る立場の意識や責任感に欠ける。
アパートの宿泊は一度だけであり、キスや抱擁以上の性的行為には及んでいない。 |
B子は当時15歳の高校生で未成熟であり十分な判断能力があったとは言えず、また適齢期にも達していないことからB子の同意があっても正当化されるものではない。
外形的に見ると15歳の未熟なB子と性的関係を持ったものと受け取られかねないものであり、その程度としても深刻且つ重大であるというべきである。
|
| アパートの合鍵を渡し、交際期間中にアパートで抱きしめキスをする行為(お互いに立ったままでのキス)を合計10回程度した。(午後6時にはB子を帰宅させていた) |
鍵を与えアパートへの自由な出入りを許したことは公務員としての信頼を得る立場の意識や責任感に欠ける。
キスの程度や体勢から、わいせつ性の程度は低い。 |
B子は当時15歳の高校生で未成熟であり十分な判断能力があったとは言えず、また適齢期にも達していないことからB子の同意があっても、正当化されるものではない。
キスや抱擁は、性的行為であり、性的羞恥心の対象となりわいせつ行為にあたる。
外形的に見ると15歳の未熟なB子と性的関係を持ったものと受け取られかねないものであり、その程度としても深刻且つ重大であるというべきである。
|
| 7月頃には相互に一生一緒に居たい旨伝え合った。交際発覚後もB子の保護者にはA男もB子も「互いに一生一緒にいるつもりで交際していたと述べた」。 |
(そのまま認定) |
B子は当時15歳の高校生で未成熟であり十分な判断能力があったとは言えず、また適齢期にも達していない状況において、A男はB子の保護者に一切話をしないまま非違行為に至っており、「将来を見据えて真剣に交際していた」と軽々しく評価できない。
|
| B子の両親に発覚する8月末まで、B子の保護者への交際報告や許可を得ることをしなかった。 |
B子の保護者の監護権等を侵害したことは公務員としての信頼を得る立場の意識や責任感に欠ける。
B子が保護者への報告を拒否したのでありA男の責任性は減弱される。また発覚後A男はB子の保護者に謝罪している。
B子の保護者の意向に応じてB子とは一切会っていない。
|
B子は当時15歳の高校生で未成熟であり十分な判断能力があったとは言えず、また適齢期にも達していないことから、交際中の非違行為を正当化することはできない。
謝罪したとしてもB子の保護者からの宥恕は受けていない。
|
| 交際全般への評価 |
自身の勤務先の生徒とほとんど年齢の変わらない婚姻適齢期にも達していない女子生徒を恋愛対象としたことが、保護者において「我が子の未成熟さに乗じて性的行為したと不信感を抱いてもやむを得ないものであり(教育の現場から退かせることをB子の保護者は希望している)、中学校の教職、公教育全体への信頼を損なう行為で、「職の信用を傷つけ、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」として懲戒事由に該当する。
ただし、結果としてB子の健全な育成が妨げられるような心身の傷を受けたものではなく、学校やB男への非難苦情も1件のみで他の生徒や学校・社会に与えた影響が重大であったとまでは言えず、処分選択につき、職を失う免職処分は重すぎるため違法である。 |
勤務先以外の中学校の生徒との交際でも自校の生徒と交際するのと同視すべきである。
B子は不祥事として両親や世間に知られ、A男が懲戒処分を受け責任を感じておりその心身に少なからず悪影響を与えている。中学校の生徒・学校や社会にも疑念や不安・不信を呼び起こしたことが想像できる。
本件処分において停職より重い処分である免職が選択されたことが不合理であるとは到底言えず、処分権者の裁量の範囲内の処分量定であり、適法である。
|
3,そもそも、恋愛による交際は何歳くらいから認められるのでしょうか。また、学校の先生は自分の生徒との恋愛や交際はなぜ許されないと考えられているのでしょうか。
有村架純主演のTBSのドラマ「中学聖日記」においても(この場合は、判例の事案と異なり女性が高校教師で男子生徒からの恋心を受けるかどうかに悩み尽くすというドラまであった)「愛は時に暴走する。人は時に間違う。だけど、決して勘違いしてはいけない。自分たち以外の誰かを傷つけてまで許される恋などないのだと。世の中には踏み越えてはならない法的なルールと心の掟があるのだ。」という良心的な結末(スキャンダラスな性的関係に発展しないままで新しく歩みだすという結末)で終わりました。
教育の関係は、先生が生徒を保護し育成していくものであり、生徒から何かを得たり生徒の未成熟さによる判断や想いに乗じたりすることは当然許されるものではありません。
生徒と恋愛するというのは、生徒の未成熟さによる判断や想いを利用することになり、教育者としてあるまじき行為です。周りの生徒やその保護者だけでなく同じ教員仲間たちからも非難の目を向けられることになります。
また、先生と生徒の恋愛がダメな一番の理由は、それが法に触れることだからです。
児童福祉法第34条第1項第6号「児童に淫行をさせる行為をしてはならない」に違反し、各都道府県で定める青少年健全育成条例の18歳未満の未成年者との淫行・性交類似行為禁止規定にも違反することになります。大人は18歳未満の子どもと恋愛関係になってはいけないことになっています。
普通の恋愛をすると、親しくなるうちにスキンシップや性的行為をするようになります。しかし、恋人同士の仲睦まじいキスやハグであっても、それが先生と生徒という関係である以上、「淫行」「性交類似行為」へと解釈され問題になってしまうのです。
児童福祉法は子どもを守るための法律なので、たとえ生徒から迫ったことだったとしても、処罰対象は先生のみです。先生は生徒との交際が判明した時点で法律違反を犯したとされるのです。そして懲戒免職という厳しい処分で仕事も失うことになります。
今回のA男とB子の恋愛の結末は、A男が教師職を失い、B子と会わないことを承諾して、二人それぞれの生活が始まっていますが、一審どおりにA男が失職しなかったとしてもその後もA男は学校の教師を続けていけたでしょうか。
ただ、教師を続け、B子が成人する時期に結婚まで至ったのであれば、元教え子と卒業後に結婚する例は多い(社会的に許されている)ようですから、教師生活を続けていけたのではないかと思ったりします。皆さんは、A男さんの人生を考えた場合、一審判決を支持しますか、二審判決を支持しますか?
以 上
お正月と法律(その⑥)~~お年玉~~
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
1,お年玉の由来
お年玉とは、お正月に子供たちに渡す小遣い銭・金員を言いますが、由来としては、子供たちに与えていた「餅」だったようです。そもそも一連のお正月行事というのは、新年の神様である「年神様」を家に迎え、もてなし・見送るための行事として伝えられてきています。
年神様は、新しい年の幸福や恵みとともに、私たちに魂を分けてくださるものと考えられてきました。鏡餅は、年神様の依り代であり、餅玉には年神様の「御魂」(みたま)が宿ります。この年神様の御魂が宿った餅玉が、その年の魂となる「年魂」です。
そして、年魂をあらわす餅玉を、家長が家族に「御年魂」「御年玉」として分け与えました。これがお年玉の由来のようです。この餅玉を食べるための料理が「お雑煮」で、餅を食べることで体に魂を取り込みます。お年玉の「玉」には「魂」という意味があるわけです。
江戸時代には、お餅だけではなく品物やお金を渡すこともあり、こうした年始の贈り物を「お年玉」と称するようになり、お年玉の風習は明治、大正、昭和と受け継がれ、昭和30年代後半の高度経済成長期ごろから都市部を中心にお金が主流となり、今やお年玉袋にお金を入れて子供たちに渡すのが「お年玉」という風習になっています。
2,お年玉は、法律的には、「金銭の贈与契約」
お正月に「お年玉」としてお金を子供たち渡すという行為は、法律的には「金銭の贈与契約」ということになります。贈与の場合、贈与税がかかるかどうかの問題があります。
(1)どのような贈与に贈与税がかかるのか?
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までに贈与された財産の価額を合計し、その合計金額から基礎控除額110万円を差し引いた課税価格に対して、税率を乗じて計算します。
(相続税法第21条の5 贈与税の基礎控除として、「贈与税については、課税価格から60万円を控除する。」との定めになっていますが、租税特別措置法第70条の2の4 贈与税の基礎控除の特例として「平成13年1月1日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税については、相続税法第21条の5の規定にかかわらず、課税価格から110万円を控除する。」と定められています。)
この場合の税率は、累進税率といって、基礎控除を行った後の課税価格に応じて定められており、金額が高くなるほど、税率が高くなる仕組みになっています。
贈与税の申告と納税は、贈与があった翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。
さて、一般的には、子供たちはいくらくらいのお年玉をもらうのでしょうね。合計110万円ももらう子供はいないでしょうね。合計何万円単位が常識の線でしょう。そのため、「お年玉には税金はかからない。」「申告する必要もない。」と覚えていていいのでしょうね。
(2)誰が払うの?
それでも、大金持ちの人たちは、成人した子供たちにも、お正月に、お年玉として110万円以上のお金を「高額福袋を買ったりして自由に使いなさい。」とあげる家庭もあるかも知れません(うらやましい限りですが・・)。そのような場合の贈与税は誰が払うのでしょうか?
相続税法第1条の4(贈与税の納税義務者)第1項により「 贈与により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの」すなわち、貰う側が納税義務を負うとされており、更に、相続税法第34条(連帯納付の義務)第4項により渡す側にも連帯納付義務を課しています。もらった子供かあげた親のどちらかが贈与税を払うことになります。
(3)複数の人から贈与を受けた場合と基礎控除110万円との関係は?
相続税法第21条の2で「贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その年中において贈与により取得した財産の価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。」と定めていますので、贈与税は、その人が一年間に贈与された財産の総額に対してかかるという点です。
贈った回数、贈った人ごとに基礎控除の枠が別々に設けられるわけではありません。従って、例えば、父から控除額限度内として100万円を贈与されたが、更に同一年内に祖父からも100万円の贈与を受けた場合には、取得した側としては、合計200万円の贈与を受けた結果になりますので、110万円を超える贈与となり、贈与税がかかります。
3,お年玉と贈与税
(1)お正月に複数の人からお年玉をもらい、合計で120万円となった場合
例えば、田舎に親戚が多く、何十人という親族から数千円ずつもらったお年玉が110万円を超えた場合にはどうなるでしょうか?
「お年玉」は「個人から受ける香典、年末年始の贈答・祝物などのための金品で社会通念上相当と認められるもの(相続税法第21条の3-9 昭50直資2-257改正、平15課資2-1改正)」になるのであれば、結果として110万円を超えても「非課税」となると思われます。
(2)少数の人から高額お年玉をもらった場合
例えば、お年玉として父から100万円、祖父から100万円をもらった場合はどうでしょうか?
相続税法第21条の3第1項第2号において「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうちの通常必要と認められるもの」は、非課税となると規定してありますが、お年玉の額としては100万円ずつというのはそれぞれ高額であり、社会通念上相当と認めにくい額をもらっていることになりますので、贈与税課税のリスクが生じます。
しかし、世の中には経済的格差というものもあり、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められるか否かが判断されますので、高額所得者層の「お年玉」としては相当と認められる場合もあるのかも知れませんが、高額所得者層をそこまで優遇する必要はないでしょうねぇ。
以 上
殿ちゃま・近ちゃま九州国珍道中記(法律解説編)その7
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
第7章 沖縄のステーキは大きいなあ(おっきなわ)!
昔、「北海道はでっかいどう!」というテレビコマーシャルがあった。それと反対の南にある沖縄でも「沖縄は大きいなあ(おっきなわあ)!」という体験をした。
殿ちゃまと近ちゃまは、琉球国沖縄にも2回ほど旅に出ている。琉球国沖縄は、日向の国宮崎に比べ観光客がたくさん訪れており活気のある雰囲気に満ちていた。空も抜けるような青さ、海もきれいなマリンブルーが遠くまで広がり、そこに住む人々の情も温かい。
平成の時代になってようやく復元し終えた朱の漆で彩られた“首里城”・・・琉球王国の歴史的遺産であるが、殿ちゃまと近ちゃまは、その首里城観光も行ってきている。
令和の時代に一夜にして火災で焼失するという出来事が待っているということなど知らない、修学旅行生やハネムーンの新婚さん等でにぎわっていた時代のことである。
殿ちゃまと近ちゃまは、沖縄弁護士会での弁護士会会務を終えて、那覇空港から日向の国まで帰る夕方の飛行機まで時間がある。観光客であふれる国際通りをぶらぶら歩いており、殿ちゃまの提案で昼食を国際通りのど真ん中にある「牧志公設市場」でしようということになった。牧志公設市場へ行くと、一階の市場フロアには、肉・海鮮類が豊富に並ぶ。
近ちゃまは殿ちゃまにブタの顔の皮丸ごと(チラガー・面の皮の意味)、ブタの耳(ミミガー)、豚足(アシテビチ)を、「これ珍しいですよね。これいいですね」などと声をかけて、殿ちゃまに買わせようとするが、殿ちゃまは買おうとしない。
“殿ちゃま先生は「ゲテモノ」(安くて美味しい食べ物)はお嫌いか…?!”
貝類も多いが、人の顔より大きな夜光貝には驚きしかない。魚はアオブダイというマリンブルー色の魚が中心で、他にも熱帯魚みたいな赤、青、黄色の色とりどりのものが並んでいる。
さすがの近ちゃまも故郷である南郷(目井津)のカツオやマグロを食べて育ったので、正当派魚通(さかなつう)としては、なかなか食べようという気になれない。
殿ちゃまが言う、
殿「一階で牛ステーキ肉を買って、二階で調理してもらってステーキを食おう!」
近「そんなことができるんですか?」
殿「できる!そうしよう!わしに任せとけって。」
殿ちゃまは、誠実そうな若夫婦のやっている肉屋を選んで、
「一番高い肉をステーキ二枚分切ってちょうだい。」
と頼んで、厚さも「もっと厚く厚く。」「そこの脂肪は切り落として」と細かい指示をしている。
とてつもなく大きなステーキ肉となってしまった。
それを若夫婦が二階の食堂に持ち込んでくれて、一枚500円の料理手間賃で豪華なステーキ料理にしてくれた。野菜もポテトもつけてくれた。焼いても、やはりとてつもなくでっかいステーキである。
運ばれてきたときに、「沖縄のステーキは大きなわあ!」と近ちゃまがダジャレを言ったのだが、殿ちゃはスルーした。
殿ちゃま、近ちゃまは、ほふほふ、ムシャムシャと食べ始めるがなかなか食べ終わらない。
殿「おい。帰りの飛行機の時間がないぞ。」
近「まだ、一切れ分。もう入りませんね。食べ残して行くしかないですねえ。」
殿「ちょっと、大きすぎたか。あっはっは。」
近「私、こんな・・(モグモグ)でっかいステーキ・・・(ムシャムシャ)・・・初めてですよ。沖縄のステーキは大きなわあ!」
殿「・・・・。行くぞ。」
帰りは、タクシーの運ちゃんが裏道ばかりを走ってくれて、沖縄ラッシュにかからずに飛行機の時間に滑り込みセーフで間に合わせてくれた。
近ちゃまは、飛行機に乗った途端、“あ~ぁ!”とため息をついた。食べ残したステーキの一切れに未練が残っていた。
そのとき、殿ちゃま曰く、
殿「おい。残したステーキ肉に未練を残すなよ。」
近ちゃまは、思った。・・・・・・“なんでわかるんだろ?”と。
(法律解説)
1,世界遺産と“首里城”
(1)近ちゃまは、沖縄には、九弁連会務以外に個人的に沖縄返還直後の大学生時代に父親の戦友探し(沖縄本部町や伊江島等を訪問)や、裁判所書記官時代の出張、弁護士になってからの事務所旅行、家族旅行、長男央国・彩夫婦の結婚式などで訪問しています。
首里城にも復元されている時期に数回訪れています。2000年(平成12年)12月、「琉球王国のグスク及び関連遺産群」として世界遺産に登録された。(登録は「首里城跡(石垣など)」であり、復元された建物や城壁は世界遺産に含まれていない)。
守礼の門を絵柄にした「2000円札」も発行され、私も1枚大切に所持しています。
2019年(令和元年)10月31日未明に火災が発生、正殿と北殿、南殿が全焼したことは、テレビニュースの火災映像が日本全国民の目に焼き付いて記憶されていくことだろうと思います。首里城歴史での5度目の焼失らしいのですが、何度でも復元への道を歩み始めていくしかありませんね。
(2)世界遺産の登録手続きについて(Wikipediaを参照)
国際連合教育科学文化機関(United Nations Educational,Scientific and Cultural Organization:ユネスコ)の世界遺産の登録決定は次の手順で行われます。
1.各国政府は暫定リストの中から条件の整った物件をユネスコ世界遺産センターに推薦(自薦)
推薦は2019年推薦分から1国あたり1年につき1件まで
2.推薦物件につき、ユネスコの諮問機関が現地調査
3.文化遺産については ICOMOS(国際記念物遺跡会議)、自然遺産についてはIUCN (国際自然保護連合)に依頼
4.諮問機関は現地調査に基づき評価結果を勧告する(勧告は「記載」「情報照会」「記載延期」「不記載」の4段階)
5.ユネスコ世界遺産委員会(年1回開催)で、諮問機関の勧告を基に審議し、記載(登録)の可否を決定
また、世界遺産登録の前提条件として、
①国が世界遺産条約を締結していること。
②登録をめざす物件は「土地や土地と一体になった物件(不動産)」であること。
③登録をめざす物件は国の法律で確実に保護されていること。
例えば日本の場合には、文化遺産は文化財保護法によって国宝、重要文化財、史跡、名勝、重要文化的景観などに指定されていること。自然遺産は自然環境保全法によって国立公園や都道府県が指定する自然環境保全地区などに含まれていることが必要になります。
2,食材持ち込みの食堂での飲食と契約の種類
沖縄の公設市場である牧志市場二階の食堂街で行なっている「食材持ち込みの食事」(料理代金500円)の契約は何の契約と言えばいいのでしょうか。普通の食堂の場合には、メニュー食品提供契約であるが、食材持ち込みの場合には店の品物を提供するわけでもなく、調理という労力を手持ちの調味料を負担して提供しているだけであるので、調理という業務委託契約か調理請負契約とでもいうべきものでしょうか。
普通の食堂では料理品という物を有償で提供するので「物の売買契約」に近い契約ですが、食材持ち込みの場合には、「物」はこちらの所有物なので、物の売買契約という側面はなく、物を加工する労力を提供してくれている「雇用契約又は請負契約」に近い契約ということになります。そうすると、食材持ち込みの場合の調理代金500円は、料理人の手間賃ということになり、物を売った代金ではないため、仮にそもそも持ち込んだ食材が傷んでいてお腹を壊したという場合には、お店は傷んだものを売ったわけではないので、その責任を取る必要はないことになります。
ただし、料理器具等にばい菌が付着していてそれが調理の過程で食材に感染した結果の食中毒であれば、調理方法に問題があったことになりますので、その場合にはお店に責任を取る義務が生じます。
(なお、通常の食堂での料理提供契約の場合には、食材の傷みであろうが調理過程でのばい菌感染であろうが、食中毒の責任を全面的に負うことになります。)
3,沖縄の公設市場(牧志市場)について
沖縄の公設市場(牧志市場)は、令和元年6月から建替え工事が始まり、令和4年4月からの新市場開場予定で、その間は、仮設市場での営業になるようです。
【市場閉場、移転・仮施設準備期間】
2019年6月17日(月)~2019年6月30日(日)
【仮設市場開業期間】
2019年7月1日(月)~2022年3月31日(木)
沖縄那覇市の中心街である国際通りに隣接する公設市場(牧志市場)は、戦後のヤミ市から続いており、市場内は新鮮で色鮮やかな魚や、豚の足(テビチ)、バラ肉(三枚肉)、豚の顔の皮(チラガー)まで売られています。
その他ゴーヤーや島らっきょ、ヘチマなど沖縄の食文化に欠かせない食材がずらりと売られています。二階には数店舗の食堂があり、市場で買った食材を有料で調理してくれますし、新鮮な食材で作った沖縄料理を食べることもできますので、殿ちゃまと近ちゃまは、この方法で「でっかい沖縄ステーキ」を食べさせていただいたわけです。
以 上
殿ちゃま・近ちゃま九州国珍道中記(法律解説編)その6
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
第6章 菊池“温泉”じゃなかったの?
肥後熊本の旅(熊本県弁護士会訪問の旅)は、殿ちゃまの超高級車トヨタクラウン・マジェスタで行くことになった。カーナビ付きである(平成4年にトヨタ車にカーナビが搭載され始めたばかりである)。
運転は当然近ちゃまの役目と思いきや「お前は運転が下手みたいだ。高速道路以外の難しい通常の道は自分で運転する。」と殿ちゃまが一言。
出発一週間前、殿ちゃまいわく、
「今度の熊本は車で行くから、会務が終わったら菊池へ回ってゆっくりしようかねえ。」
近ちゃまは、“菊池”“ゆっくりする”この二言で「やったーぁ!菊池温泉だ。」と、ニンマリして「いいですねえ!」と返事をした。
出発当日、殿ちゃまの超高級車に乗ったとき、近ちゃまは、ふと、車の後部座席に“帽子”と“ウォーキングシューズ”が載せてあるのが目に留まったが、「休みの日にどこかの運動公園まで行かれて、ウォーキングコースでも歩かれたのかなぁ。」と思った程度で、別段気に留めることもなかった。
肥後熊本での会務を終え、高級ホテルにて食事を終えて就寝する際、
殿ちゃまいわく、
殿「明日は朝4時起床で、菊池渓谷に写真撮りに行くぞ!」
近「え?菊池渓谷?菊池・温・泉・じゃ・な・か・っ・た・ん・ですね。」
殿「早朝の菊池渓谷はいいぞ~!朝陽が木々の間からパァーッと差し込んでねぇ~。」
近「はい~?!」
翌朝、早い目覚めの移ろいの中で、薄暗い山道を殿ちゃまの運転で超高級車が進んでいく。
菊池渓谷入り口に到着するや否や、殿ちゃまは、撮影用チョッキを着て、ウォーキングシューズに履き替えて、帽子を被って、完全なイデタチ。
近ちゃまは、背広スーツの上着だけを脱いで白のビジネスワイシャツにビジネス革靴のままである。
殿ちゃまの超高級車の後ろのトランクを開けてみると、そこにはカメラ機材がびっしり!
近ちゃまは、殿ちゃまのカメラ三脚を運ぶ役である。渓谷の山道をとぼとぼと運ぶには運んでいたが、運び慣れていないのと生来貧乏だがおぼっちゃま育ちのためすぐ肩が痛くなり、それを見るに見かねた殿ちゃまが、カメラ三脚と弁当の入った袋とを交換してくれる。
「殿ちゃまって、やさしい!」と思いながら、弁当の入った袋だけを大事に持って菊池渓谷を歩く近ちゃまでありました。
菊池渓谷の奥に入って、清々しい朝の光を浴びたせせらぎの中で、写真の光の取り方、自然の色・陰影の見方を近ちゃまは初めて教わり、殿ちゃんのカメラでシャッターも切らせてもらった。半日をかけての写真の勉強であった。
持参したお弁当は、大自然の中で食べるわけだから、美味しかったなあ。
しかし!近ちゃまは、最後まで思っていた!
~~「“菊池でゆっくり”というのは、なんで菊池温泉じゃないんだあー!」と。
(法律解説)
1,旅行契約と行先の間違い(意思表示の錯誤)
実際にはあまりないのでしょうが、旅行会社と個別的に「菊池温泉宿泊1泊旅行」契約をしたところ、実際に企画された旅行先が「菊池渓谷日帰り旅行」だった場合に、そもそも「菊池渓谷日帰り旅行」に行かなければならないことになるのでしょうか?
(1)この殿ちゃまと近ちゃまとの「菊池」への旅行の約束においても、「菊池」という言葉に対して、殿ちゃまは「菊池渓谷写真撮影の旅」の意味で言われている一方で、近ちゃまは「菊池温泉一泊ごちそうの旅」の意味で理解しており、二人の解釈の食い違いが生じています。
このように、表現した言葉と思っていた言葉の意味が違う場合を、法律上は「錯誤」(さくご)と言います。
(2)契約などの法律行為を有効とするか無効とするかを定める民法では、人が契約しようとする意思(真意)に基づいて法律の効果を認めようとしています。
これを「意思主義」と言います。逆に、契約しようとして言った言葉に基づいて法律の効果を認めようとすることを「表示主義」と言います。
意思主義の下では、例えば、殿ちゃま側で言いますと、“菊池渓谷に行って写真を撮ろう。近ちゃまに菊池渓谷に行こうと言おう”という内部意思(真意)があり、その真意どおりに言葉にしようという表示意思もあって「菊池へ回ってゆっくりしようか」と表示されて、菊池渓谷へ行くことになったので、殿ちゃま側には、何の錯誤も生じていません。
それに対して、近ちゃま側は、まず、内心の意思を決める動機としては、“菊池温泉でゆっくりできて豪華料理を食べられるのだなあ。”という内容になります。
そして内心の意思としては、その動機に基づき“行きたいなあ。”と思って、“行きたい”と言おうという表示意思もあって、「いいですねえ。」と同意しています。
その結果、実際には、“菊池温泉で豪華食事だ”という動機とは異なり、“菊池渓谷に行く”という別な結果になっていますので、本当の意思とは違う結果になっており「錯誤」が生じています。しかもその錯誤は「動機」と「表示した結果」との間で生じています。これを「動機の錯誤」と言います。
(3)現民法第95条では「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」と定めていて、錯誤の意思表示は無効となるとしています。
改正民法(2020年施行)第95条では
1 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
と定めています。
ところで、意思主義の下でも、なぜそのような意思表示をしたのか?という部分の「動機」は、契約上は取り上げられません。例えば、リンゴを売ってくださいと果物屋さんに申し出た人に、果物屋さんは「なぜ買うのですか?」という動機は問いません。
動機には「そのリンゴが美味しそうだから」とか「子供に食べさせたいから」とか「スケッチの題材にしたいから」とか人様々な動機があり、それをいちいち確認しないと売れないというと、すごく取引が煩雑になってしまうからです。
ですから、「美味しいだろう」と思って買ったら「美味しくなかった」という錯誤を理由にリンゴの売買契約を無効にすることはできません。現民法の規定では「動機の錯誤」の取り扱いは明記されていませんでしたが、改正民法では、上述のとおり改正民法第95条第1項第二号により動機の錯誤が明記され「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」取り消され無効となることが認められています。
なお、現民法下でも解釈上「動機の錯誤は、その動機が表示された限りで意思表示の要素の錯誤となり無効とすることができる」とされていましたので、全く動機の錯誤を取り上げないというわけではありませんでした。
(4)そこで、近ちゃまは、殿ちゃまが「菊池に回ろうか」と言われたときに、近ちゃまが心の中で思ったまま、言葉に出して「菊池温泉ですね。豪華料理を食べるんですね。」と言っておけば、動機の錯誤を主張して、無効だから「菊池渓谷には行かない。」と言えたのですが、菊池温泉と豪華料理の話は一言も言葉に表示していませんので、近ちゃまの同意は、法律上の錯誤とはならず有効なものとなり、菊池渓谷へお供しないといけないことになる次第です。
2,弁当に関する契約は?
菊池渓谷で食べた美味しいお弁当は、殿ちゃまに買っていただきました。弁当の「贈与契約」が有効に成立した次第です。でも、「勤労の対価」としての弁当であったのであれば、無償の贈与契約ではなく、雇用契約や委任契約が有効に成立したということにもなります。
以 上
犯罪被害者の実名報道について(実名報道反対の立場から)
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
(冒頭)今月は、シリーズ連載を中断して、喫緊の時事問題を取り上げさせていただきます。
皆さんもまた地方自治体の公務員の方々も考えてもらえないでしょうか。
京都市伏見区のアニメ制作会社「京都アニメーション」放火殺人事件(令和元年7月18日発生)で社員など35名が亡くなった被害者遺族に関する京都府警の記者発表とマスコミ報道について、法的な観点から問題点を検討してみたいと思います。
1,京都府警は、事件後40日を過ぎる令和元年8月27日に、身元が公表されていなかった死亡被害者のうちの25名の実名を公表し、新聞テレビのマスコミは一斉にその被害者または遺族についての「実名報道」をしているようです。
宮崎の地方紙でも過去の取材写真を使用して死亡した被害者の写真を載せて「被害者の実名報道」をしていました。
京都府警によると、今回公表された25名のうち20人のご遺族が実名公表に難色を示したり、拒否したにも関わらず「事件の重大性に加え、社会的関心が非常に高く、公益性があるため公表した方がいいと判断した」との理由で公表しています。
宮崎の地方紙は、被害者実名報道に関する「おことわり」として「事件・事故の被害者については、その現実を的確に伝え社会全体の教訓とするため原則実名で報じており・・・事件を風化させないためにも多くのファンを持つ作品に関与した一人一人を実名で報じる必要があると判断しました。
社会的影響が大きい重大事件であることも考慮しました。」と併記してありました。
2,平成28年4月1日から「犯罪被害者等基本法」が施行されています。この法律の立法趣旨として「犯罪等を抑止し、安全で安心して暮らせる社会の実現を図る責務を有する我々もまた、犯罪被害者等の声に耳を傾けなければならない。
国民の誰もが犯罪被害者等となる可能性が高まっている今こそ、犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ、その権利利益の保護が図られる社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出さなければならない。」と冒頭附則で定められています。
同法第5条では「(地方公共団体の責務)地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。」と定め、
同法第6条では「(国民の責務)国民は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、国及び地方公共団体が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならない。」と定められており、
各地方自治体には被害者支援施策の実施義務があり、マスコミ各社は国民の一人として「犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないように行動する義務」があるとされています。
犯罪被害者が、法律制度の中で一人間として人権保障されるようになり始めたのは、ここ十数年のことです。それまでの犯罪被害者やご遺族は、日本の社会の中で何ら声も出せないまま、その機会も手段も与えられないゆえ、刑事裁判では証拠として扱われ、報道の世界からは、社会への警鐘のために勝手に報道される対象に過ぎませんでした。
そのことは、同法の冒頭附則の「近年、様々な犯罪等が跡を絶たず、それらに巻き込まれた犯罪被害者等の多くは、これまでその権利が尊重されてきたとは言い難いばかりか、十分な支援を受けられず、社会において孤立することを余儀なくされてきた。さらに、犯罪等による直接的な被害にとどまらず、その後も副次的な被害に苦しめられることも少なくなかった。」と表現されています。
3,私は、このコーナーで「犯罪被害者と犯罪報道①②③」を寄稿していますが、その中で、『犯罪被害者の人権保護は、国家がその人権保障・手続保障・制度保障をしていないという意味で、昨今、新しく問題とされた人権問題であり、犯罪被害者に関しては、マスコミも放置し、あるいは逆に報道被害を与え続けてきた分野であります。
(ちなみに、犯罪被害者によるアンケート結果では、犯罪被害者の実名報道の禁止についての意見としては、まず、マスコミでの犯罪被害者の実名報道に何らかの問題があると考えている人は68.8%の多数である。)
また、犯罪被害者の人権を考える場合、犯罪被害者は犯罪被害後も、その「地域」で生きていくという事実の直視が重要であります。マスコミ報道による「地域での影響」「地域からの被害者への目」「地域での被害者の立場・環境」を考えれば、「被害者実名報道」はほとんど意味を持たないだろうと思われます。
なぜなら、現在のマスコミの犯罪被害者実名報道の意義は、地域において被害者だと知らなかった人に「この人が被害者だ」と教えるだけの「被害者実名報道」なのであり、地域での弊害を増やすだけのことしかできておらず、そこに、報道としての高貴な配慮・真実を伝えるという高貴な職業性は全くないことになっています。
市民側に立った「個々の市民の権利」を保障できる社会的存在としてのマスコミ・報道機関の役割からすれば、犯罪被害者の報道に関しては、「匿名」報道の原則が導き出されるだろうと考えます。犯罪被害者が「被害者実名報道」を望んでいない場合に、「犯罪被害者の実名報道」をする必要性と価値がどこにあるのか?・・・・考えてみてください。
「犯罪被害者の実名報道」の問題は、新しい人権問題として、犯罪被害者救済・犯罪被害者支援という新しい視点をもって、マスコミ報道各社全体で考えて改変していくことが必要な問題なのです。』『被害者報道は、警察の実名発表、報道機関は匿名報道であるべきである。』と指摘させていただきました。
また、神奈川県弁護士会は、平成29年11月17日に『(神奈川県座間市9名殺人事件に関して)警察が報道機関に被害者氏名等を発表する際、ご遺族が顔写真の公表や実名報道をやめてほしいと申し入れていても、未だにそのような報道は行われている状況です。報道する側にも理由があるのでしょう。
犠牲者の痛みを共有するためとか、社会全体で事件について考えるために、実名であることが必要だと言う方もいます。私たちとしても、「報道の自由」や「取材の自由」の重要性を否定しているわけではありません。
しかし、そこには、犯罪被害者、遺族のプライバシーがなぜ暴力的に奪われるのか、なぜ本人や遺族の同意なしに生活状況を書き立てられ、勝手に写真を使われるのか、なぜ自宅を報道陣に囲まれて帰宅できないような生活を強いられるのかについての答えはありません。プライバシーの権利とは、自分についての情報を適切にコントロールする権利と理解されています。
「知られたくないことは知られない権利」「放っておかれる権利」ともいえます。犯罪被害者には、遺族には、プライバシーはないのですか。報道の正義のために、社会全体の理解のために、犯罪被害者、遺族のプライバシーが損なわれることが許されるのでしょうか。』という弁護士会会長談話を出しています。
4,今回の京都アニメーション放火殺人事件の被害者実名報道の理由も「社会的影響が大きい重大事件であるから」「事件を風化させてはいけないから」という理由ですが、そのことで、なぜ「報道されたくない」という被害者やご遺族のプライバシーの権利や心理的負担という犠牲が強いられてよいのか、それについての法的根拠は何ら示されていません。
このように、犯罪被害者やそのご遺族に関する実名報道と取材行為が全国的に旧態依然に行なわれている報道の視点は犯罪被害者支援・被害者の人権保障という新しい視点は学び取れていないように思います。
犯罪被害者等基本法の根本理念は「犯罪被害者等の権利利益の保護が図られる社会の実現」(冒頭附則)」なのです。この基本理念からすると、犯罪被害者等から「実名報道されてもよい」という同意を得られない以上は、マスコミは匿名報道をすべきなのです。
マスコミは警察機関のように権力機関ではありません。国民側に寄り添う「国民」の一人です。国民の一人としてマスコミ機関が「犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、国及び地方公共団体が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならない。」(基本法第6条)と定められてことを厳守されるように要望する次第です。
以 上
殿ちゃま・近ちゃま九州国珍道中記(法律解説編)その5
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
第5章 汽車の旅でのコーヒー事件
1,グリーン指定席事件
陸の孤島日向の国から豊後の国大分に行くには、飛行路線はない。電気で走る列車で行くことになる。まだまだ映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』(Back to the Future)のタイムマシン列車や銀河鉄道のように宇宙を走る列車999(スリーナイン)のように、列車が空を飛ぶ時代でもなかった。
更に昔は石炭で走る蒸気機関車(汽車)というものや重油で走るディーゼル機関車で陸上の鉄の線路を走る形式で豊後の国に行っていた。
日本国有鉄道と呼ばれていた時代(平成の御代の前の昭和時代)もあったが、この頃は、分割民営化により「JR九州」と呼ばれる株式会社の列車になっていた。
特急列車の座席には、自由席、指定席、グリーン指定席の種類があり、グリーン指定席は金額も高く、えらいお金持ちの社長さんか芸能人などのハイクラスの人たちしか乗らない。
日向の国と豊後の国を通る日豊本線では、にちりん特急シーガイア号も走っていて、それにはツバメレディというきれいな「おなごし」が乗務していたげな。
なぜ「ツバメレディ」というのかというと、JR九州の主要本線は、筑紫の国から薩摩までの鹿児島本線である「特急ツバメ号」が走っており、その特急ツバメ号の女性乗務員を「ツバメレディ」というのだが、日豊本線(日向国と豊後国間)を走るにちりん特急シーガイア号は、その特急ツバメ号の車種を転用していたからじゃげな。
① 近「大分弁護士会訪問は何で行きましょうか?JR列車だとしたら、殿ちゃまはグリーン車でしょうか。」
と、近ちゃまが、殿ちゃまの事務所秘書(光ちゃま)に聞いていた。秘書光ちゃまは、お客様の伝言をそのままを一字一句間違わずに殿ちゃまに伝えられる几帳面かつ有能な秘書(ただし年齢不詳、しかし若い)である。
それをそのまま聞いた殿ちゃまは、
殿「また、近ちゃまが変なことをわざわざ聞いてきたねえ。何を考えているんだろ?JR列車のときはグリーン車で行かんで、何で行くつもりやろか?」
と不思議がっていた。
そう。弁護士は弁護士報酬規定で、旅費は最高額(グリーン料金を含む。)を請求できるという規定があるので、列車出張の際はグリーン車を利用するハイクラス階級なのである。しかし、薄給公務員を長く経験した近ちゃまは貧乏根性が染み付いていて、まだ一度も特急グリーン車を利用したことがなかったのである。
いよいよ、近ちゃまにとってグリーン車初搭乗の日。
殿ちゃまと隣同士の席である。ゆったりした大きめの席。スリッパまである。しかも、グリーン車料金なんて高くはないのだ!普通特急料金より1,000円高いだけである。近ちゃまは、「な~んだ。」と頭の中でつぶやきながら、今までえれ~高いはずだと思ってグリーン車を利用しなかったことを後悔する。
ツバメレディがいる!うん、美人の部類である。
その美人ツバメレディーが「コーヒー、お茶はいかかですか?」とやってくる。
近「いくらですか?」と聞く。
隣に座っていた殿ちゃまが、その途端にあわてて、近ちゃまの横腹をつついて
殿「こら、こら、グリーン車は、コーヒー、お茶は無料なんだよ。」
と小さな声でささやく。
近ちゃまは、大きな声で
近「えー!タダー?!ほんとですか!」
近ちゃまは、早速ツバメレディに
近「コーヒーもお茶も、どちらもください!」
殿「どっちか、ひとつだけやがね~。」
近「え?そうなんですか。」
美人ツバメレディ「うふふふ。」
② 殿ちゃまと近ちゃまは、長崎(幕府天領)-佐賀(肥前国)、佐賀(肥前国)-福岡(筑紫国)と西九州を横断する旅に出た。この旅もJR列車利用である。グリーン車の味をしめた近ちゃまは、佐賀-福岡もグリーン車利用と思い込み、肥前の国佐賀駅で「緑の窓口」(JA列車の切符を買うところ)へサッサと歩く。
殿「おいおい。どこへ行く?」
近「え。グリーン車の切符を買いに。」
殿「福岡まで30分もかからんのだぞ。」
近「え?グリーン車じゃないんですか?」
殿「…………」
殿ちゃまは、近ちゃまが、わざと緑の窓口に行くふりをしたように思ったのだが、近ちゃまは本気でグリーン車に乗りたかったんだそうな。
③ 殿ちゃま、近ちゃまは、大分(豊後国)には二回旅に出た。大分から宮崎への帰りは、グリーン車が満席で予約ができなかった。殿ちゃまも仕方なく空席が多かったので一般自由席に座って帰ることになった。
席を並べて、車窓を眺めながら、訴訟の話、特に訴訟で問題となった男女関係、日本の古の男女関係の話、三行半とは?妾(めかけ)とは?などの話であるが、二人で話が盛り上がる。
そこに、車内販売が「お茶、コーヒーはいかがですか、ジュース、週刊誌はいかがですか」とやってきた。
殿ちゃまは、近ちゃまに話しを続けながら
殿「コーヒー頂戴」
と注文する。コーヒーが殿ちゃまの席のテーブルに置かれ、殿ちゃまがゆっくりとコーヒーを飲む。
しばし、話も休止。
車内販売の女の子は、黙って、そこに立ったままでいる………?。
そう。殿ちゃまが代金を払おうとしないのである。
長い、なが~い、殿ちゃまと販売員の子だけの、停止画像状態であった。
それに気づいた近ちゃまが言う
近「先生、ここはグリーン車じゃないんですよ。お支払は?」
殿「あ!あ!そうか。グリーンじゃなかったんだ。コーヒーいくら?」
女の子「(ほっとした顔で)300円でございます。」
(法律解説)
1,国鉄分割民営化と裁判
国鉄分割民営化とは、自民党中曽根康弘内閣が実施した昭和末期の行政改革を言います。日本国有鉄道改革法(昭和61年12月4日法律第87号)に基づいて民営化方策が取られました。
日本国有鉄道(国鉄)を「JR(ジェーアール):Japan Railwaysの略。」として、6つの地域別の「旅客鉄道会社」と1つの「貨物鉄道会社」などに分割し、民営化するものである。北海道旅客鉄道(JR北海道)、東日本旅客鉄道(JR東日本)、東海旅客鉄道(JR東海)、西日本旅客鉄道(JR西日本)、四国旅客鉄道(JR四国)、九州旅客鉄道(JR九州)の各旅客鉄道会社6社と、日本貨物鉄道(JR貨物)1社の計7社が、1987年(昭和62年)4月1日に発足しました。
(1)国鉄分割民営化は、国鉄時代の巨額赤字負債を解消する方策であり、国鉄分割民営化の時点で、累積赤字は37兆1,000億円に達していた。このうち、25兆5,000億円を日本国有鉄道清算事業団が返済し、残る11兆6,000億円を、JR東日本、JR東海、JR西日本、JR貨物、新幹線鉄道保有機構(1991年解散)が返済することになりました。
経営難の予想されたJR北海道、JR四国、JR九州は、返済を免除されましたが、ローカル線の多い各社は、民営化後もローカル線廃止が必要になるなどの赤字運営対策が余儀なくされている面があります。(ウィキペディアより抜粋引用)
(2)他方、この法律に基づき実行された昭和62年(1987年)4月1日の国鉄分割民営化により、約27万7,000人の国鉄職員のうち、JR各社に再就職できたのは約20万人で、結果として約7万7,000人の再就職未定者が発生し、最終的に1,047人がJR以外の再就職を拒否し解雇された結果となりました。
この解雇者は、国鉄当時の労働組合員が多く、「JRが社員採用時に所属組合による差別という不当労働行為を行った。」として、昭和62年(1987年)に相次いで全国の地方労働委員会に救済を申し立てました。各地方労働委員会や中央労働委員会(中労委)は、対象者全員を分割民営化当日にさかのぼって採用する旨の救済命令を出したのですが、JR各社はこれを不服として東京地方裁判所に中労委命令の取消を求めて行政訴訟を起こし、東京地方裁判所、東京高等裁判所、最高裁判所はすべてJR各社勝訴の判決(不当労働行為に関する使用者責任は、JR各社が承継しているのではなく、国鉄清算事業団が承継しているので、JR各社には責任がないとの趣旨の判決)を出し、平成16年(2004年)11月11日、国労が最後に残った事件の上告を取り下げ、JR各社の完全勝訴が確定したという裁判での争いが生じました。(ウィキペディアより抜粋引用)
(その後、元原告ら(解雇された労働者)は、上記最高裁の判決に基づき、国鉄清算事業団の業務を引き継いだ独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を相手取って解雇無効と慰謝料を求めた裁判を起こし、平成17年(2005年)9月15日に、東京地方裁判所は慰謝料請求について原告側勝訴の判決を出しました。)
2,JR各社と企業イメージカラー
JR各社について、分割民営発足時にイメージカラーが発表されています。
(1)北海道旅客鉄道 - ライトグリーン(萌黄色)。真白な雪の大地から一斉に芽生え、やがて野山を彩る柔らかな色。新会社のさわやかで伸びやかなイメージを表現した。
(2)東日本旅客鉄道 - グリーン(緑色)。東北・信越・関東の豊かな緑色で、力強く発展していく新会社の未来を象徴させる。また、東北・上越新幹線のカラーでもある。
(3)東海旅客鉄道 - オレンジ(橙色)。限りなく広がる東海の海と空の彼方を染める夜明けの色。新鮮ではつらつとしたオレンジのように、フレッシュな新会社を表す。また、この地域を走る湘南色の電車にあやかっている。
(4)西日本旅客鉄道 - ブルー(青色)。日本の文化と歴史に彩られた地域にふさわしい色とされ、地域に密着した会社を表している。また、山陽新幹線のカラーでもあり、豊かな海と湖を象徴するカラーでもある。
(5)四国旅客鉄道 - ライトブルー(水色)。太平洋の青さより、さらに鮮やかなブルーであり、「青い国・四国」で知られる澄みきった空のブルーとして、新会社のフレッシュさを表現している。
(6)九州旅客鉄道 - レッド(赤色)。南の明るい太陽の国には、燃える熱意の色「赤」がふさわしいとされた。全力で明るくスタートダッシュを切る新会社の意欲的な姿勢を表現している。
(7)日本貨物鉄道 - コンテナブルー(青22号色)。新会社のフレッシュさと信頼感を演出するカラー。国鉄末期にコンテナ色として使用されてきていた。
それぞれのJR列車に乗ったときに、車掌さんの帽子や制服のポイントにどんな色が使われているか見てみると楽しくなるかも知れませんよ。
3,食堂車と社内販売
(1)食堂車
日本の鉄道における食堂車は1899(明治32)年、山陽鉄道(現在のJR山陽本線)を走る列車に「食堂付1等車」が連結されたのが始まりとされています。その後、第二次世界大戦をはさみ、鉄道の発展とともに食堂車を連結する列車も増えていきました。昭和の高度成長期における鉄道の豪華発展時代が、食堂車が最も盛んに利用された時期でしょう。駅弁好きの私も一度だけ食堂車を利用したことがあります。
やはり贅沢な感じがして気後れしたことを覚えています。その後、新幹線が超高速化し乗車時間が短くなれば、到着先で食事を取ることができることから利用者が少なくなり、平成12年頃に新幹線等の一般車両からも食堂車は廃止されました。
しかし、近年において「食堂車」は一般的な列車のものではなく、JR九州の「ななつ星in九州」といった豪華クルーズトレインなど観光列車に食堂車が連結される形になってきました。
(2)車内販売
列車等の車内において、ワゴン車やカゴに物品(飲食品や雑誌など)を並べて、車内を巡回して販売するサービスのことです。日本では1934年(昭和9年)、食堂車が連結されていない列車で弁当類販売の要望があったため、鉄道省が試験的に販売したところ好評であったことから、 1935年(昭和10年)11月より列車内乗込販売手続を制定して開始されたようです。
現代では、駅構内の売店や「駅ナカ」と呼ばれる商業施設、駅周辺のコンビニエンスストア・ファーストフード店など、駅内外の飲食店や小売店が充実してきていることからあらかじめ乗車前に購入する客が増えてきており、車内販売は縮小ないし廃止傾向にあります。
社内販売を担当するものは、JR社員の専門部門が行っていた時代もあるようですが、車内販売のある列車を運行するJR各社は車内販売専門の子会社を持っていたり、他の販売会社に業務委託したりするので、子会社や委託会社の従業員が担当しているのが通常であり、また、正規従業員ではなく派遣・契約やアルバイトといった非正規雇用で採用しているケースも少なくないようです。
(ご注意!)なお、後日の私の体験からすると、グリーン車両のお客様にコーヒー等の無料サービスをしていたのはJR九州だけのようで、JR九州もそのサービスを平成22年3月に取り止めており、現在はグリーン車での車内販売でも有料となりますのでご注意ください。
次号に続く
殿ちゃま・近ちゃま九州国珍道中記(法律解説編)その4
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
第4章 安価で飛行機の旅を楽しむ方法?(ヒコーキドタバタ搭乗珍事件)
昔、日向の国宮崎は、“陸の孤島”と呼ばれていて交通の便は不便じゃった。筑紫の国、博多の九弁連会務に旅するのも、九州国を巡回する旅も「ヒコーキ」という「空飛ぶ鉄の固まりの乗り物」で移動しなければならなかった。
殿ちゃま、近ちゃまも「ヒコーキ」を利用することが多くなり、JASの会員になり、平成10年当時の航空路線過当競争時代にあった数々の割引制度や格安制度を研究しながら「ヒコーキ」を利用しちょりゃったげな。格安航空券を利用する際の条件として、「ヒコーキ」便の変更はできないか、または変更すると元の料金との差額負担(追加料金)が求められるというものもあったげな。
殿ちゃまは「ぶげんしゃ」じゃったから、あんまり割引航空券や格安航空券は気にしやらんがったけど、近ちゃまは貧乏弁護士じゃったし、近ちゃまのえれ~きれいなカミサンの秀(ひで)ちゃまが、節約が好きな人じゃったかい、格安航空券を見つけてきて出張時に近ちゃまにその航空券を渡すときに「ヒコーキ便の変更すると高くなりますからね。予定どおり行動してくださいね。」と厳しく(?)近ちゃまに言いつけちょりゃったげな。
① 筑紫の国での九弁連会務が早く終わった日の筑紫国空港行き地下鉄電車の中で~~
殿「会務が早く終わったから、飛行機を一便早くして午後2時の便で宮崎に帰ろうかねえ。」
近「え?あの~、私の航空券は変更できないやつで、午後5時の便なんですが…」
殿「変更できない?君は、どんな航空券を買っているんじゃ?」
近「早割航空券ですよ。カミサンが買ってくれたんです。」
殿「あんたんところの奥さんは偉いねえ~。」
近「先生だけ先にお帰りください。」
殿「4時間も空港で何をしとくの?試しに変更したら何円くらい追加料金が必要なのか、聞いてみたら?」
近「そうですねえ。ひょっとしたら追加料金なしにしてくれるかも知れませんし。」
殿「それは無いよ。しかし、弁護士たるものが追加料金の額を聞いて“じゃ、変更しません”というのも恥ずかしいな。」
近「そうですねえ。」
殿「しかし、知識としての勉強にはなるわな。やってみたら?」
近「はい。そうですねえ。」
近ちゃまは、地下鉄空港駅に着いて、福岡空港のJAS搭乗受付カウンターにおもむろに近づき受付嬢に
近「この券、次の便に変更できますぅ?」
嬢「これは早割券でございますので、追加金が必要になりますが…」
近ちゃまは、「やっぱりそうか。」「どうしようか。」と思案し、後ろにいてくれたものと思っていた殿ちゃまを見たが、後ろには誰もいない!
…殿ちゃんを捜すと、ずーっと端のカウンターで、一人離れて搭乗手続きをしてござる。俺は知らんよという様子で。
近ちゃまは、寂しそうに
近「じゃ、5時のままで結構ですから、5時の便の搭乗手続きとJASマイルカードの手続きをお願いします。」
と、JASカードを受付嬢に差し出すと、
嬢「カードをお持ちですか、ちょっとお待ちください。」
と言って、受付嬢が部屋に下がって、そして出てきていわく、
嬢「2時の便は空席が多ございますので、搭乗していただいても結構ですが。」 と!
そのころ、ようやく殿ちゃまがおもむろに私に近づいてきて、
殿「どうやったか。」
近「ただで、いいそうです。」
殿「えー!そうか!よく変更してくれたね。」
近「私がハンサムだからでしょう。しかし、先生は何であんな遠いところで搭乗手続きをしていたんですか?すぐ隣のカウンターも空いていたですよ。」
殿「いやいや、アハハ。アハハ。タダで良かったがね。」
殿「ところでさ、君は航空券の回数券は知らんのかね。僕は回数券にしているんだが、変更も利くからいいよ。何でそれにしないの?」
近「そんなのもあるんですか、カミさんと相談して、これからはそうします。」
② 近ちゃまは、その後、カミサン秀ちゃまにその話をして、次の出張からは、航空券回数券を購入してもらい、これで殿ちゃまと対等に飛行機に乗れるぞ~と自信満々で筑紫の国の九弁連会務のため殿ちゃまに同行した。
その帰りの福岡空港での話である。
近「先生、私も今回は回数券ですからどれに変更してもいいですよ。」
殿「そうか、奥さんが買ってくれたか。しかし、今回は変更なしじゃ。予定どおり午後5時の便で帰ろう。」
殿ちゃまと近ちゃまが空港の搭乗受付カウンターで搭乗手続きをすると、受付嬢が、近ちゃまにやさしくのたまう。
嬢「お客様、回数券のホルダーもお願いします。」
近「え?ホルダー?なに?それ?」
嬢「回数券の一番上の部分になりますが…。」
近「なーんだ。それなら、宮崎の僕の自宅に置いてあるよ。」
嬢「はい?は??・・・回数券の場合はホルダーをご持参いただかないと困りますが・・・」
近ちゃまは意味が分からない。
殿ちゃまが、「また何かしたのか?」と、心配顔で後ろから顔を出す。
近「いいえ。回数券のホルダーが無いと言われちょるだけです。」
殿「何処に忘れたんだ?」
近「忘れたんじゃありません。自宅にちゃんと置いてあるんです。」
殿「馬鹿なこつ!回数券はホルダーと一緒に持ってこんこつ。」
近「しかし、宮崎空港ではホルダーがないまま乗れたじゃないですか。」
殿「回数券はホルダーと一緒に提示してくださいと書いてあったどが。ホルダーが無いとヒコーキに乗れんがね。」
近「え?そうなんですか?」
このやりとりを笑えみながら聞いていたカウンター嬢が、近ちゃまにやさしく、
嬢「お客様、この次からは、ホルダーをご持参ください。今回は、どうぞご搭乗ください。」とおっしゃる。
近「いや~。あんたはいい人じゃね~。」と、近ちゃまは、満面の笑み。
近ちゃまは、無謀にもまた易々とヒコーキに乗れることになった。
後で、殿ちゃまいわく、
殿「今の受付嬢は、“この二人はきっと田舎もんで、何も知らんようだから、説明してもわからんであろう。”と思って、半ばあきれ果てて乗せてくれることにしたんだろうなあ。宮崎弁で二人ともしゃべっとったからわからんじゃったろな。」と。
③ 殿ちゃまと近ちゃまは、九弁連の沖縄弁護士会訪問で琉球(沖縄)に行くことになった。日向(宮崎)~琉球(沖縄)間のヒコーキ機便は1日一往復便しかなく遅れることはできない。しかも、日向~琉球便は、観光ルートで旅行会社がツアーで航空券を買い占めているのでなかなか予約ができなかったが、近ちゃまの秘書の努力で「指定席指定済みの航空券」を手に入れることができた。その券は、既に座席指定が書き込まれているので、空港カウンターでの搭乗手続きは終わっているようなイメージになるので、空港でよく「〇〇様、お手持ちの航空券は受付け手続きが必要ですので、受付けまでお起こしください。」と呼び出される間が抜けた感じの人もチラホラ見ていた経験があった。
“今日は、沖縄まで行かなくちゃならない。遅れると後の便はない。”と、近ちゃまは、日向の国・宮崎の飛行場近くの南バイパス道路を、高級車でない中級クラスの中古トヨタ・クレスタで走りながら、気が急いでいた。
飛行機の出発15分前には空港に着けるだろうか?
今朝は飛行機の出発時間を20分後と勘違いしていてのんびり朝食を済ませていたが、カミサンの秀ちゃまが航空券を最終確認していたら、時間が違うということになり、サザエさんのドラ猫がお魚食わえて走るように、沢庵をパリパリ食べながら、あわてて自宅を飛び出し、カミサンの運転で車を走らせて来たのである。
一方、殿ちゃまは、出発30分前に宮崎空港に着いて、近ちゃまが来るのを待っていたが、なかなか顔を現さない。
出発15分前から、空港ビル内放送で「近ちゃま様、お手持ちの搭乗券は搭乗受付が必要です。搭乗受付カウンターまでお越しください。」と名指しで呼び出しを始めた。殿ちゃまは、「また、何かシデカシタな。」と気が気ではない。
近ちゃまは、出発10分前に受付カウンターに、ぜいぜい言いながら息を切らして到着。
その時、空港ビル内放送で「近ちゃま様、お手持ちの搭乗券は受付手続きが必要です…………」と放送中。
それを聞いた近ちゃまは、受付嬢に
近「ちゃんとここに来ているでしょ。まるで私が搭乗手続きを知らない人間みたいな放送になっているじゃないの。ちゃんと訂正放送してよ。」と訳の分からない抗議をしていた。要は、急げ!なのである。近ちゃまが殿ちゃまを見つけて近寄ると、
殿「また、何をしたんだ。さっきから君の名前が呼び出されていたぞ!」
近「座席指定搭乗券なので、私が搭乗手続きをしないでいいと思っているのではないかと搭乗受付嬢が誤解して呼び出しをしていたようで、けしからんです。私はちゃんと座席指定券でも搭乗手続きが必要なことは知っていたんですから。」
殿「それで、時間もないのに文句言っていたのか?」
近「はい。ちゃんと受付嬢に搭乗手続きをしなくちゃならないことは知っていたと説明しておきました。」
殿「遅れてきて、また無駄な時間を費やして~。呼び出しは、ただ、時間内に搭乗手続きをしなかったからだろ? …しかし、あれだけ呼び出されれば、これで君の名前も少しは有名になったかなあ。アハハ・・・。」
(法律解説)
1、「ぶげんしゃ」の意味と「分限」制度
(1) 文中にある「ぶげんしゃ」は、鹿児島及び宮崎西南部地区の方言(又は古い言葉の残り)で、「金持ち物持ちの人、経済力のある人、裕福な身分の人」を指す言葉です。単なる方言ではないということについては、江戸時代において金持ちを表す言葉には、「長者」と「分限者」があったそうで、江戸語辞典(東京堂出版;新装普及版)によれば、「長者」は「金持ち」と載っており、「分限者」は「ものもち、富豪」となっていて、「ぶげんしゃ」の漢字表記は、この「分限者(ぶげんしゃ、ぶんげんしゃ)」であるとされています。そして「分限」は、元は「身分」という意味であって、ここから「富んだ身分」「経済力」を表すようになっただろうされています。
また、日本大百科全書でも「物事の程度や分量、物事を行う能力や限度、あるいは身分の程度や分際をいう。「ぶげん」とも読み、分限者などと使う。また、その置かれた立場の様子や経済状態もいい、とくに江戸時代には、財産・資産の程度をいい、その財産や資産を多く有している人、すなわち富豪や資産家をさしていうことばとして用いられる。さらにこの上をゆく富豪を長者と称してこれを区別している。」されています。
(2) 法律の中で「分限」という言葉を探すと、「公務員の分限制度、分限手続き」が思い浮かびます。法律上で分限とは、「公務員の地位」を指します。
① 分限処分については国家公務員法または地方公務員法に定められていますが(国家公務員法第74条、78条、79条等、地方公務員法第27条、28条等)、公務員の地位に不利益な影響を与える行為を「分限処分(ぶんげんしょぶん)」といい、非行などを理由に公務員の道義的責任を追及する「懲戒処分」を除いたものを総称する身分に関する処分ということになります。
② 分限処分をなし得る事由は、分限処分の目的が広くは公務能率の維持および適正な運営を目的とするものですから、「勤務実績がよくない場合」、「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合」、「その他官職に必要な適格性を欠く場合」という職員側の事由(国家公務員法第78条、地方公務員法第28条)が抽象的に定められている他、いわゆる人員整理も認められていますが、具体的には様々な事案が考えられます。分限処分の種類には免職、降任、休職、降給の4種があります。
③ 公務員の身分保障と分限処分の濫用の禁止分限処制度の前提として、公務員には身分保障があります。公務員の身分保障は、公務員職員は、法律又は人事院規則に定める場合(勤務実績不良、心身故障による職務遂行困難等)でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはないという定めを置いて(国家公務員法第75条1項、地方公務員法第27条)、公務員職員が恣意的にその職を奪われることのないように身分を保障しているものです。法はこのことにより、公務の中立性・公正性を確保しようとしているわけです。従って、公務員職員の分限処分においては、恣意的な濫用は許されないのは当然です。最高裁判例(昭和48年9月14日判決)は「分限処分については、任命権者にある程度の裁量権は認められるけれども、もとよりその純然たる自由裁量に委ねられているものではなく、分限制度の…目的と関係のない目的や動機に基づいて分限処分をすることが許されないのはもちろん、処分事由の有無の判断についても恣意にわたることを許されず、考慮すべき事項を考慮せず、考慮すべきでない事項を考慮して判断するとか、また、その判断が合理性をもつ判断として許容される限度を超えた不当なものであるときは、裁量権の行使を誤った違法のものであることを免れないというべきである。」として分限処分の濫用は許されないとしています。
2、格安航空券の解約手数料(違約金)は高すぎる?
(1)ある裁判で、片道4万3,800円の航空券を割引運賃1万3,290円という約70%割引格安航空券を購入したのであるが、搭乗62日前にキャンセル事情が発生したのでキャンセルしたところ、8,190円の取り消し手数料がかかったという例があり、購入者が「少なくとも60日も前であれば代わりの乗客を確保することができ、航空会社に損害は生じないし、「そもそも購入代金1万3,290円の約61%もの手数料率は絶対的に高すぎる。消費者契約法に違反している」と主張している例があります。
(2)消費者契約法第9条第1項第1号において以下のとおり定められています。
次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
1 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分」
つまり、キャンセルをしたときの違約金・手数料は、キャンセルの理由や、時期などに応じ、キャンセルに伴う事業者に生ずべき平均的な損害の額以下でなくてはならず、それを超えるキャンセルをしたときの違約金・手数料は無効となるという規定です。
(3)格安航空券のキャンセルで航空会社にどれだけの損失が発生するか、その判断は難しいところがありますが、割引運賃ではなく普通運賃(4万3,800円)と比較すれば、8,190円は20%程度の金額にすぎず、キャンセル料としては高額とはいえないという反論や旅割系のチケットを購入する際には、取消手数料が高額であることがきちんと表示されており、利用者はそれを認識したうえで購入しているのだから、航空会社の定める違約金や解約手数料に不当性はないという反論もあり得るでしょう。
みなさんは、どう考えられますか?
次号に続く
殿ちゃま・近ちゃま九州国珍道中記(法律解説編)その3
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
第3章 え?こんなに高いお宿に泊まるの?
今は令和。昔々の平成の御代の頃は、お宿は、カプセルホテル、ビジネスホテル、シティホテル等の大衆ホテル(料金1万円以下)以外に、高級有名ホテルがあり、トランプ米国大統領が宿泊したプラザホテル、帝国ホテル、ホテルオークラ、ホテルニューオータニが最高級ホテル(料金2万円以上)と言われていた時代じゃった。
最高級ホテルは、江戸時代の大名が泊まる「大本陣」というようなものじゃろう。
殿ちゃま、近ちゃまの場合、旅に出て行く先々でのお宿の手配は原則として秘書役(カバン持ち)の近ちゃまの仕事ということになっちょった。
宿泊出張が盛んになる4月下旬の頃、
近「先生、出張のお宿はいかがいたしやしょう?」
殿「福岡は、ホテルニューオータニにしよう。僕は会員だから、君もニューオータニ会員になれ。あそこの朝食はビュフェ形式でおいしくていいよ~。卵料理も選べるし、野菜サラダもあるしね。」
近「え!そんな高いとこ、あっしゃ~、一度も泊まったことないザンス!」
殿「いいじゃないか。泊り方教えてやるから。」
近「泊まり方?…」
近ちゃまも、殿ちゃまが会員入会の保証人となってくれたので、めでたくニューオータニ会員となって、初めてゴールド色の会員カードを所持することを自慢するかのように、最高級ホテルに宿泊することになった。
福岡での九弁連会務を終えて、食事を済ませてホテルニューオータニ福岡へ。近ちゃまは、広いロビーの高い天井をキョロキョロと見上げながら、殿ちゃまの後を付いていく。部屋はそれぞれ別個に取ってある。
すごい部屋である。とてつもなく広~いツインの部屋を一人で使う。今では当たり前かも知れないが、歯ブラシ・石鹸・シャンプー以外にヘアーブラシもミニ化粧品まで備え付けてあり、室内の白いスリッパは持ち帰ってもいいという具合である。
そういう部屋で、近ちゃまは、殿ちゃまと同じような「殿様」になった気分でゆったり過ごして、さぁ寝る時間である。ツインベッドのどちらに寝たらいいのか迷ったが、朝の陽射しで目覚めるように入り口から遠い窓際のほうを選んだ。そして、ベッド上部にあるベッド灯を消そうとしたが、
ON/OFFのスイッチが見当たらない。花の飾りはついているけど…。
近「あれ?」
OFFにするつまみスイッチか紐かがあるはずだが…ない。フロントに聞くのも恥ずかしいし…。
近「よし!入り口のルームキーボックスのキーを抜けば消える。しかし、部屋全体が消えて真っ暗になるだろうし、部屋が広いからキーボックスのところからベッドまで遠いな。真っ暗になるとベッドまで行けない。あらかじめベッドの位置の見当をつけて、キーを抜くなりベッドに飛び込めばいい。よし!」
と、近ちゃまはキーを抜くなり入り口から遠いベッドに走り飛び込む。
成功!
近「あれ?電気が消えないじゃないか。」
と、ベッドの上で近ちゃまがつぶやいていると・・・
徐々に明りが暗くなっていく。
近「あ!ちゃんとベッドに行けるようにしばらくは点いているんだ。すごい!
明日の朝、殿ちゃまにも教えてあげよう!」
と、大感激の夜であった・・・・zzzzzzzzzzz。
翌朝、朝食ビュッフェで、殿ちゃまと朝の挨拶をして、野菜サラダを取りながら
近「先生!すごい発見したんですよ!あのですね、ベッドの灯りの消し方が分からなかったのですが・・」
殿「は?ちゃんと灯りの所に飾りボタンのつまみがあるだろうが。」
近「あれ~、あの飾りがスイッチですかあ。」
殿「じゃ、夕べはどうやって寝たんだ?電気をつけっぱなしで寝たのか?」
近「いいえ。つけっぱなしじゃ僕は眠れない気質(タチ)なので、入り口のキーボックスからキーを引き抜いて寝ました。」
殿「え?え!え!え?それじゃ、夜トイレに行くときは真っ暗じゃがね。」
近「はい。でも、キーを抜いてもすぐ消えずにジワーッと消えるんですよ!知ってました?? キーを抜くなりベッドに飛び込んだのですが、ゆっくりベッドまで行けるようになっているんですよ!」
殿「そうじゃなくて、ベッドの灯りのつまみを回せばいいだけじゃがね。」
近「あぁ、あの飾りは、単なる飾りじゃなかったんですねぇ~。」
殿「田舎もんは、電灯を消すには紐があるはずじゃと思っちょるわなあ。」
*徐々に消えていくライトを「フェードアウトライト(FOライト)」と言うようです。
ところで、大分にはニューオータニはない。次の大分出張では近ちゃまにホテルの選択とその予約一切を殿ちゃまが任せてくれた。近ちゃまの慣れ親しんだ大分市内の某ビジネスホテルに宿泊(料金6000円で安い!)。
ツインのシングルユースだともったいないから殿ちゃまもシングルームを予約してあげた。(後で「なんで、ツインのシングルユースにしなかったんだぁ?」と殿ちゃまに不満を言われたが・・・。)
受付フロントで、フロント係が「歯ブラシ、髭剃りはお入用ですか?」と聞いてきた。殿ちゃまは「え?」と言って理解できないようである。このホテルは、資源節約のため、歯ブラシ・髭剃りは持参していないお客だけにフロント係がそれを渡す方式で、部屋には備え付けていないのである。
殿「なんで、部屋に置かないのかな?」と不思議な経験をされたようである。 部屋に着くと、殿ちゃまは「狭いなあ」「ベッド灯は紐じゃね。(笑)」「ベッドから足が出やせんか。」と少しだけうるさい。最後には「部屋じゃ狭くてゆっくりできんから、明日は起きたらすぐ出発しよう。」とわがままなことをおっしゃる。
しかし近ちゃまは、その夜は紐を引いて消灯もできゆっくり眠れたげな。
話は、またホテルニューオータニに戻るが、ニューオータニ会員には宿泊料金が会員料金になる以外に、宿泊の度に10パーセントの割引券が交付されるようであるが、航空機JASマイルカードのマイル獲得ホテルでもある。
既に2~3回の宿泊を経験して、ホテルニューオータニの宿泊通になったつもりの近ちゃまは、事前にニューオータニでJASマイルカードが使えることを調査し、殿ちゃまに先んじて殿ちゃまに善いことを教えてあげたいと思って、ニューオータニ福岡のフロントで、10パーセント割引券とJASカードを出して格好良くチェックイン手続きをしていた。
それを見ていた殿ちゃまが、
殿「そのJASカードは何だ?」
近「先生、知らなかったんですか、このホテルではJASマイルがもらえるんですよ。」
殿「へえ~、そうかい。」
近「先生もJASカードを出されたらいいですよ。エヘン。」
ところが、見目麗しいフロントのお嬢さんいわく、
女「お客さま、大変申し訳ございません。割引券ご使用の場合には、マイルは付かないことになっております。」
近「え?、あ?」と、近ちゃまの面目はつぶれ、立ち往生?!?。
殿ちゃまは、その場に腹を抱えて、クックックと笑いを必死で押さえていたのでありました。
(法律解説)
1、JASマイルカードによるマイル取得と公務員の公務出張に関する問題点
(1)「JAS」とは、株式会社日本エアシステム( JAPAN AIR SYSTEM CO. LTD)の英語略語である。1971年(昭和46年)から2004年(平成16年)まで存在した日本の航空会社です。それ以前は、東亜国内航空(TDA)であった。
福岡と宮崎間の飛行機は、この航空会社の便が多く運行されていました。
マイルカードとは、マイレージカードであり、マイレージ(マイル)とは、各航空会社が提供するポイントサービスのこと。主に飛行機への搭乗で貯まるもので、貯まったマイルは各航会社の無料航空券に交換することができるサービスとなっています。
(2)ところで、官庁や会社等の公的出張で航空マイルを個人が取得することについて、法的な問題が生じています。
そもそも、航空マイルは、法人向けカードがなく、会社がマイルを取得して法人として使用することを想定しておらず、マイルは飛行機搭乗者個人がマイル取得登録をした上で、飛行機に登録者個人が搭乗しなければ付与されないため、航空券の購入のみでは発生しません。したがって、マイルは実際に飛行機に搭乗した搭乗者個人を対象として付与されているとする立場があります。それに対して、会社経費や公費で搭乗券を購入して搭乗しているのだから、マイルの経済的価値は会社経費や公費から発生したものであり、会社や官公庁のものになるという立場があるわけです。
中央官庁におけるマイルの取り扱い例がありますが、各省庁は、当初は、公費により購入した航空券での搭乗によって得られたマイルは、個人のマイレージカードに登録しないように求めていました。
ただし、中央官庁の現時点での取り扱いは分かりませんが、地方自治体や民間団体等では、そのままではマイルが誰のものにもならず無駄になってしまうことから、定期的に出張をする必要がある職員などには、公用マイレージカードの作成を促している取り扱いも認めているようです。その場合には、マイレージクラブの仕組み上、カード自体は個人名義のままですが、プライベート用のカードとは使い分けをして、公用マイレージカードに出張の分のマイルが蓄積され、官公庁の出張時の航空券をそのマイレージで無料で取得できるという取り扱い例になっているようです。
(3)個人的見解
私は、個人的には、マイレージ取得に関するルールを会社や団体が決めていない場合には、会社等はそのマイレージの権利を放棄している又は取得意思はないものとして、また、マイレージクラブの仕組み上、カード自体は個人名義のままで個人の搭乗者の搭乗を根拠に付与されているもの以上は、公費・私費の区別はマイレージ制度には何ら関係の無い問題であり、公費出張による搭乗であっても、マイレージの権利は個人のものになると考えます。
2、「朝の陽射しで目覚める」ことの意味
体内時計を御存じでしょうか?「生物の体内にあるとされる、時間を計る仕組み」を言うのですが、生物の活動性が光や温度などの外界条件に影響されると同時に、その外界条件が変化しない環境においても、その活動性が日周期性を示す(例えば、意識しなくても日昼はカラダと心が活動状態に、夜間は休息状態に切り替わる)ということから、生物の中には独自の活動周期性(時計的なリズム)があるとされています。
ヒトの体内時計は、隔離環境では約25時間の周期で刻まれており、1日24時間周期の昼夜のリズムとはズレが生じるため、起床後、太陽の光を浴びることにより毎日このズレを修正しています。ヒトの体内時計は、脳の一部である視床下部の視交叉上核にあり、網膜からの光信号を受けて松果体からの「メラトニン」というホルモンの分泌をコントロールしています。
「メラトニン」は睡眠を誘うホルモンですが、人間の体は、朝に光を浴びると脳にある体内時計の針が進み、体内時計がリセットされて活動状態に導かれ、その体内時計からの信号でメラトニンの分泌が止まるため体が目覚めて活動的になれるのです。
朝の目覚めは、太陽の陽射しを受けることで、正確な一日の始まりとなるのです。
日本の法律(民法)では、民法第139条で「時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。」民法第140条で「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。」と定めて、私たちが時間や期間に正確に従って生活するという前提での規定を設けています。この時間や期間に合わせる私たち人間の社会生活の基本は、人間の体の周期的な目覚めや睡眠を前提にしていることを改めて自覚する次第です。
次号に続く
殿ちゃま・近ちゃま九州国珍道中記(法律解説編)その2
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
第2章 記者会見するの?しないの?~(日向の国の瓦版)
4月初め、筑紫の国での役員就任の挨拶回り、記者会見を終えて筑紫の国から日向の国に戻ると、日向の国の地方瓦版の記者会見もしなくちゃならないということになる。
日向の国にも3つの電子台局(テレビ局のこと)と5社の瓦版屋(新聞社のこと)があり、殿ちゃまが日向の国から初めて九弁連理事長に就任したことはビッグニュースであるから、当然、日向の国でも記者会見しなければならないはずである。
近「先生、地元でも、理事長就任記者会見をしていただいたほうがよろしいかと思いますが、会見設定、会見内容、理事長プロフィール等は私の方で準備しますし、記者の質問に2~3答えてもらえればいいのですが。いかがしましょうか。」
と、近ちゃまが提案する。
殿ちゃまは、
殿「地元での記者会見はもういいんじゃないか。僕はあんまりマスコミには 出たくないんだ。」と拒否される。
近「前年の佐賀の葉隠れの理事長は、地元佐賀でも記者会見して、電子台(テレビ)でも放送されたようでござんす。」と、近ちゃまは粘る。
殿「佐賀は佐賀。私は私だ。あんまりマスコミには出たくない。」
近「ああ。そうですか。じゃ、記者会見は無しとします。」
と、近ちゃまはあっさりと断念したようであったが、内心は、殿ちゃまの記者会見があったら自分も脇役としてチョッとは電子台に映る可能性があったので、残念でならなかった。
1週間後、日向の国の野崎弁護士が、殿ちゃま理事長の地元記者会見はないのか、と問い合わせてきた。
近「殿ちゃまがマスコミは嫌いだと言われるのでしません。」
と回答したところ、
野崎弁護士から話があるということで、事務所まで赴くと、なぜかお叱りを受ける。
野「殿ちゃまは絶対に地元での記者会見はしないと言われましたか?」
近「マスコミは嫌いだ。あまりマスコミには出たくない。と言われました。」
野「でしょう。“あまり“だったでしょ。それは記者会見するように、もう少し押さないといけないということなんです。3回断られるまで諦めない。偉い人は、自分が目立つようなことを一度頼まれただけではでハイと言う訳ないんです。」
近「え?そうなんですか。記者会見するか、しないかというだけですよ。一度で決断できるでしょ。」
野「近ちゃまは、殿ちゃまの性格をまだ押さえていませんねえ。」
近「いえ、確かに記者会見はもういいんじゃないか、と断られましたよ。」(憮然)
野「“もういい”ではなく、“もういいんじゃないか”でしょ。断定しておられないでしょ。」
近「確かに…。三顧の礼ってことで、3回頼んでみましょうかね。」
それから、近ちゃまは毎週一回、殿ちゃまにお会いする度に「地元での記者会見をしましょうか。」と尋ねてみた。なんと!2週間後、殿ちゃまが地元記者会見に同意!!!?
近ちゃまがバタバタと記者会見を設定し、めでたく記者会見終了。電子台のニュースで放送され、それを契機に殿ちゃまには祝電が次々に送られてきて、殿ちゃま事務所は就任お祝いのお花で満杯状態。事務員はお祝いの電話の対応にてんてこ舞いになったということである。
瓦版の記事は間違っているわけではないが正確に記載されていない場合が多い。殿ちゃまの記者会見での理事長見解についても記事になってみると間違った表現をしている瓦版があり、殿ちゃま曰く、
殿「近ちゃまの押しに負けて地元記者会見をしたが、やはり不正確に伝わることが多いだろ?だから嫌じゃと言うたんじゃ。」
……人の上に立つ人の心持ち、謙譲、謙遜、遠慮、支えてくれる者の動きや行動した場合の結果の見通し、結果に対する評価や影響等いろいろと、偉い人の世界には難しい心の動きや強い影響があるもんじゃ……。
しかし、近ちゃまも電子台のニュース画面にチョコット映って嬉しかったげな。
(法律解説)
1,公的機関の記者会見について
公的機関が報道機関に向けて行う記者会見は、法律に定めたものではなく、公的機関側は「行政等の説明義務、周知義務」として行うものであり、報道機関側は「憲法第21条の表現の自由・報道の自由・国民の知る権利」を支えるものとして行うというものであり、その方式は慣例として認められてきたものです。記者会見の主催が公的機関か報道機関かの争いはありますが、日本の記者会見において公的機関が報道機関向けに行う発表は、通常、記者クラブが主催しており、日本新聞協会は、その理由を、「情報開示に消極的な公的機関に対して、記者クラブという形で結集して公開を迫ってきた」と歴史的な経緯があること、逆に公的機関が主催する会見は一方的な運営がなされるとの疑念を抱いていることを説明しています。
その場合、各記者クラブが主催する記者会見には、その記者クラブのメンバー以外は原則として参加できないという不都合が生じる場合もありますが、ただし、幹事社の事前承認があればメンバー以外の報道機関も参加できるという取り扱いもされています。
2,三顧の礼とは
三顧の礼とは、「地位のある者や権力者が格下の者に何度も出向いて物事を頼むこと」であり、三国志の英雄である劉備が諸葛亮を臣下に加える際に彼の庵を三度訪れて礼を尽くしたということが由来となっています。近ちゃまの場合は、格上の殿ちゃまに三回頼みに行くという場面ですから、逆の関係になるので、厳密には「三顧の礼で迎える」という例ではありませんので、その点ご留意願います。
3,報道内容が事実と異なる場合の法的問題
マスメディア等の報道により、事実と異なる報道がされ名誉権等の人格権を侵害された個人は、その報道内容に関し、「反論する権利ないし法的保護に値する利益」を持っているのではないか(いわゆる反論権、反論文掲載請求権の有無)が論じられてきています。
しかし、最高裁判例昭和62年4月24日(サンケイ新聞事件)は、以下の通り述べて、不法行為として成立しない場合には反論権は認められないとしています。
(1)「この制度(反論権又は反論掲載請求権)が認められるときは、新聞を発行・販売する者にとつては、原記事が正しく、反論文は誤りであると確信している場合でも、あるいは反論文の内容がその編集方針によれば掲載すべきでないものであつても、その掲載を強制されることになり、また、そのために本来ならば他に利用できたはずの紙面を割かなければならなくなる等の負担を強いられるのであつて、これらの負担が、批判的記事、ことに公的事項に関する批判的記事の掲載をちゆうちよさせ、憲法の保障する表現の自由を間接的に侵す危険につながるおそれも多分に存するのである。このように、反論権の制度は、民主主義社会において極めて重要な意味をもつ新聞等の表現の自由に対し重大な影響を及ぼすものであつて、たとえ被上告人の発行するサンケイ新聞などの日刊全国紙による情報の提供が一般国民に対し強い影響力をもち、その記事が特定の者の名誉ないしプライバシーに重大な影響を及ぼすことがあるとしても、不法行為が成立する場合にその者の保護を図ることは別論として、反論権の制度について具体的な成文法がないのに、反論権を認めるに等しい上告人主張のような反論文掲載請求権をたやすく認めることはできないものといわなければならない。」
(2)その結果現行法の下において、反論権が承認されるための条件について
「人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを請求することができる場合による。」ことは、当裁判所の判例(北方ジャーナル事件判決参照)に基づくところであるが、「右の名誉回復処分又は差止の請求権も、単に表現行為が名誉侵害を来しているというだけでは足りず、人格権としての名誉の毀損による不法行為の成立を前提としてはじめて認められるものであつて、この前提なくして条理又は人格権に基づき所論のような反論文掲載請求権を認めることは到底できないものというべきである。」
以 上
殿ちゃま・近ちゃま九州国珍道中記(法律解説編)
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
(巻頭言)
平成22年4月から「何でも法律塾」コーナーを9年間担当させていただいておりますが、平成の時代をも終わり、今年5月から「令和」時代に入ります。
そこで、平成時代を振り返りつつ、面白い話を交えながら分かり易い法律の話をしてみたいと思っています。
この「珍道中記」の登場者「殿ちゃま」「近ちゃま」は、宮崎県町村会の顧問弁護士であり、この二人の実話を面白く脚色させていただきました。
このコーナーでは、時事の法律問題も時折入れることもあると思いますが、可能な範囲でこの「珍道中記(法律解説編)」を続けて掲載させていただきたいと思います。
1、珍道中期間・・平成10年4月1日~平成11年4月5日
2、主題・・九州弁護士会連合会の会務活動に関する理事長・事務局次長同道の旅での出来事、笑い話等を綴る傑作コメディー
とその関連法律制度の解説。
3、登場人物
①殿ちゃま・・宮崎県弁護士会所属弁護士、弁護士会会長経験2回、宮崎県弁護士会の大御所的存在、訴訟以外に公的委員
・宮崎県等の地方自治体や大企業顧問などを兼任し社会的地位も確立している。平成10年度に宮崎県内初選出として九州弁
護士会連合会理事長に就任し、九州の弁護士のトップの地位に立つ。後進の育成に熱心な人物で、経済的には無駄はしない
が一流の物には金銭を出すのはいとわない性格、宿泊は一流ホテルのツインないしダブルの一人使用を好み、趣味はカメラ
写真(写真展入選多数)。昭和5年3月3日生まれ(理事長就任当時68歳、現89歳)、小林市出身。妻・殿所F子様
②近ちゃま・・宮崎県弁護士会所属弁護士、平成5年登録の初心者弁護士、裁判所書記官(公務員)として14年間の公務員生
活を送りながらの司法試験受験生活を経ての弁護士生活であり、殿ちゃまより弁護士生活に関する基本的指導を受ける。殿
ちゃまが九州弁護士会連合会理事長就任と同時に殿ちゃまから九州弁護士会連合会事務局次長兼理事長秘書を委嘱される。
受験生活が長かった割には、悪癖もなく、冗談好き。小さな事務所を独立経営し、財布の中身も公務員時代の貧乏生活感覚
を維持している。宿泊は安いビジネスホテルのシングルを好み、趣味は特になし。昭和28年11月1日生まれ(次長就任当時44
歳、現65歳)、南郷町出身。妻・近藤H子様
4、目次
第1章 昔々、桜の咲く頃、(筑紫の国の舞鶴城址で)
第2章 記者会見するの?しないの?(日向の国の瓦版)
第3章 え?こんなに高いお宿に泊まるの?
第4章 飛行機の旅を安くでする方法を知っています!なに、それ?
第5章 汽車の旅で、コーヒーがタダ!
第6章 菊池“温泉”じゃなかったの?
第7章 沖縄(琉球国)のステーキはでっかいぞ!
第8章 シーガイアであたふた、あたふた。(九弁連大会宮崎大会)
第9章 僕は浮気防止役?(摩女梨花での夜)
第10章 こんなに疲れる韓国旅行ってな~んだ?
第11章 殿ちゃまを一人にできない。(殿ちゃまの失敗編)
第12章 日本の最南端の島で~あれ?これ、どこから覗くんですか?~
第13章 もう一年、ご苦労さん! あれ~?双子?
第14章 殿ちゃま、男になる!(理事長実績編)
終 章 そして、桜の咲く頃に(女房に感謝を込めて)
第1章 昔々、桜の咲く頃、~(筑紫の国の舞鶴城址で)
(はじめに)
今は令和元年。今になっては、もう昔々の平成時代の話になるんじゃが、優しそうな顔立ちの平成天皇と見目麗しい美人で才女と誉れ高い美智子皇后がおられた平成の御代、それも戦争もない平和な時代の話じゃった。
日の本(現在の日本国)の南にある九州国の日向の国の話じゃ。日向の国は太平洋という大海原に面していて、漁業と農業を中心に産業が興されている田舎で、蒸気機関車よりも速く走るという新幹線もまだ通っておらず、交通は不便なところじゃった。
しかし、日向の国の気候は、日照時間も日本一で、「日本のひなた」と呼ばれるように温暖で穏やかだったので、土地の人々は、「男はいもがらぼくと、女は日向かぼちゃの良か嫁女」ということで人柄も、の~んびりしていて、争いごともあんまりなかったそうじゃ。
そんな日向の国の争いごとを一手に引き受けて解決してきた「殿ちゃま」という偉~い弁護士さんがいて、平成10年4月に九州国の一番偉~い「九州弁護士会連合会理事長」になりゃったげな。
理事長として、九州国全部を巡回して争いごとの解決の仕組みを広めるという大変な役目を担わなくてはならなくなったげな。
一人じゃ大変じゃということで、殿ちゃまは、自分の役目の手伝いをさせるために、もっと昔々の水戸黄門様のお話の格さん助さんみたいに細かいことをきちんとやれそうで、気の良さそうな若い弁護士「近ちゃま」を自分の秘書役(カバン持ち)にして、九州国を二人で巡る旅をしやったげな。
その旅の話をまあ聞いてみるとほんと面白いっちゃから、まあ、聞いちみてくだっさい。
(これから以下は、準・標準語に修正しています。)
(桜の咲く頃)
九州弁護士会連合会の理事長・殿ちゃまと事務局次長・近ちゃまは、日向の国から筑紫国(福岡県福岡市)まで、月に最低2回程度出張せんといかんかった。
九州弁護士会連合会(以下、「九弁連」と略称する。)の事務局が筑紫国にあり、九弁連の会務の統括業務をしなければならないからである。
九弁連事務局は舞鶴城址の筑紫国高等裁判所と同敷地内にある。敷地周囲は隣接している舞鶴城址公園と同様に「そめい吉野桜」で蔽われており、春には、咲く桜・散る桜でその風景全体が淡い桜色に染まる・・・。
その桜の咲く頃に、近ちゃまが日向の国からの飛行機から慌てて筑紫国に降り立って、そのまま地下を走る電気式移動車(地下鉄)に飛び乗って、あわてふためきながら、桜咲く舞鶴城址に着くと、殿ちゃまが会務資料の入った大きなカバンを抱えながら、一人お堀の端にたたずんで城址のお堀一面に広がる桜の景色を見入っていた。
近「先生、遅れました。すみませ~ん。」
と、その直前まで法曹関係者への理事長就任挨拶回りを殿ちゃま一人に任せてハワイ旅行に行っていた近ちゃまは、まだハワイでの南国的気楽さを残したまま、軽快なフットワークで、殿ちゃまに駆け寄る。
殿「おお、ようやく君の事務所の5周年記念事務所旅行のハワイから帰って来たか。昨日の理事長就任の挨拶回りは僕一人だけだったから大変だったよ。」
近「そうですかあ。お疲れ様でしたあ。」と気楽な答え。
殿「それにしても、この桜、見てごらん。光も向こうから来ている時間帯だから、いい写真が撮れる景色だよ。」
と殿ちゃまが言う。
殿ちゃまは、趣味の写真もしばらくあきらめて九弁連理事長会務に没頭しなければならないこれから一年のことを真剣に考えていた。
“もう自分も若くはないが、九弁連理事長としての激務でも無理をしなければ大丈夫だ。
この桜を、理事長を退任する一年後の春には、きっと清々しい気持ちで見れるはずだ。”
・・・殿ちゃまは、そんな自分の決意を今の桜景色に一年間預かってもらっておくのだという気持ちで桜を眺めていたのであった。
そんなことも知らない呑気で気楽な近ちゃまは、
近「ほんとですね~。ここの桜景色を見ると、私が弁護士になる前の平成3年4月1日にこの筑紫国裁判所を退職したとき、花束を抱えて裁判所職員同僚・部下に玄関から見送られて、それも黒塗り高級公用車に乗せられて見送られたことが想い出されます。
その時も今の様に桜が満開でした。そのときは、すぐに100メートル先で公用車を降りて、バタバタと裁判所書記官室に舞い戻って、書き残していた裁判調書を書いたんだったなあ。
退職後も2、3日登庁して裁判記録の引継ぎ整理をしたんだったなあ。
あのときは、司法試験に合格した喜びと司法研修所への入所準備での期待感の反面、残務整理の時間が足りなくて寝る暇もなく、大変だったなあ~。」
と、勝手に自分だけの回顧にふけっていた。
……実は、殿ちゃまの覚悟していたとおり、九弁連会務の「激務」がこれからスタートしようとしていた。
(法律解説)
1、そもそも「九州弁護士会連合会」とはどういう法的根拠で結成された連合会なのでしょう?
弁護士の資格と弁護士の組織については、弁護士法という法律が定めています。
弁護士法では、第8条(弁護士の登録)「弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない。」、
第9条(登録の請求)「弁護士となるには、入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録の請求をしなければならない。」、
第32条(弁護士会設立の基準となる区域)「弁護士会は、地方裁判所の管轄区域ごとに設立しなければならない。」、
第89条(同じ区域内の弁護士会の特例)「この法律施行の際現に同じ地方裁判所の管轄区域内に在る二箇以上の弁護士会は、第三十二条の規定にかかわらず、この法律施行後もなお存続させることができる。」
という定めに従い、単位弁護士会は、地方裁判所の管轄区域ごとに設立するのが原則で、45の府県庁所在地と札幌・函館・旭川・釧路の各地方裁判所に対応して設けられている。
東京だけ例外として、歴史的経緯から3つの弁護士会(東京弁護士会、第一東京弁護士会、および第二東京弁護士会)が存在する(法第89条第1項)ことから、日本全国では52の弁護士会が存在します。
しかし、いわゆる高等裁判所を基本とした地区(九州・四国・近畿・関東など)に応じた弁護士会(例えば、九州弁護士会)の定めは弁護士法にもありません。
九州弁護士会連合会は、九州管内の各県単位会弁護士会の任意団体として結成されたものであり、法律に基づく正式な団体ではないのです。
名称も「弁護士連合会」ではなく、「弁護士会連合会」になっています。
任意団体とは言え、九州弁護士会連合会の理事長は九州内の当時は4,000名の弁護士のトップに立つことであり、1年に1回開催される九弁連大会(福岡高裁長官、福岡高検検事長、知事、市長等の来賓をお迎えした大会・参加弁護士数500人規模)を宮崎の地で計画実行するという大きな役目があります。
宮崎県弁護士会から初めてその九弁連理事長に就任されたのが、殿所哲弁護士(殿ちゃま)なのであります。
2、裁判所書記官とは、どういう立場の人でしょうか。
近ちゃまは、弁護士になるまでは、裁判所で裁判所書記官として働いていました。
裁判所に勤務する人には、裁判官、裁判所書記官、裁判所速記官、裁判所事務官、家庭裁判所調査官、裁判所技官、執行官、廷吏という職種があり、すべて国家公務員になります。
裁判所書記官は、裁判所法第60条で「1 各裁判所に裁判所書記官を置く。
2 裁判所書記官は、裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管その他他の法律において定める事務を掌る。
3 裁判所書記官は、前項の事務を掌る外、裁判所の事件に関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行なう法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助する。
4 裁判所書記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。
5 裁判所書記官は、口述の書取その他書類の作成又は変更に関して裁判官の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。」
と定められている公務員です。
官職としては、書記官、主任書記官、次席書記官、首席書記官があり、最高位は、最高裁判所大法廷首席書記官になります。
3、司法試験制度について
司法試験とは、裁判官、検察官または弁護士になるための国家資格、すなわち法曹資格を付与するための国家試験ですが、1923年(大正12年)以前は、判検弁統一の法曹資格試験は存在せず、裁判官と検察官の候補生である司法官試補(現行法における司法修習生に相当)の採用試験である判事検事登用試験と弁護士試験が別個に行われていたようです。
その後、高等文官試験司法科試験となり、戦後の昭和24年から司法試験法が制定され、裁判官、検察官又は弁護士になろうとする者に対して、それに必要な学識及び応用能力を問うことを目的とした国家試験(司法試験法第1条)となっていますが、直接的には、裁判所法第66条2項で定める司法修習生になるための採用試験であり、司法研修所を卒業する際の「司法修習生考試試験」(いわゆる二回試験)に合格して始めて裁判官、検察官又は弁護士になる資格を得ることになります(裁判所法第67条1項)。
ただし、旧司法試験制度は、2002年(平成14年)の司法試験法改正により2011年(平成23年)の試験を最終として、新司法試験へ移行しました。
両試験の大きな違いとしては、(1)受験資格の点において、旧司法試験は受験資格制限がなく、中卒・高卒でも受験することができました(ただし、大学で一定の単位を取得していない人は教養試験に合格しなければなりません)。
が、新司法試験は法科大学院修了者のみを対象とした試験ですので、大学を卒業し法科大学院に入学、卒業した人しか受験することはできません(ただし予備試験に合格することで法科大学院を修了していない人も受験資格を獲得することができます。)。
(2)受験科目数や方式の改正により、新司法試験では、民事訴訟法・刑事訴訟法が両方試験対象科目に入っており、旧司法試験で行なわれた口述試験は廃止されています。
(3)合格者数については、旧司法試験が約400名から500名程度でありましたが、新司法試験では1,500人(多い時で3,000人)程度の合格者が発表されています。
(第2章へ続きます)
以 上
「無実の人の『無知の暴露』」と「真犯人の『作出した虚構』」のどっち?(将来の裁判員になる方々へ)
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
1、日本の刑事司法手続きにおいて、平成21年5月21日に一般市民が裁判員として重大刑罰の刑事裁判に関与する「裁判員裁判
制度」が始まって、10年を経過しようとしています。私は当初、この制度導入については消極的な立場でしたが、10年近く実施さ
れてきて裁判員に選任された方は大変な苦労をされながら裁判員裁判制度の意義を理解されているだろうと考えますと、この制
度を充実させていく方策を検討するということも法律家の役目なのだろうと思います。
2、判例時報2389号に立命館大学の浜田寿美男教授の刑事裁判上の「虚偽自白」についての論考「虚偽自白がどのようなものか
を知らずに虚偽自白を見抜くことができるのか」(以下、「論考」という。)があり、それを読んで非常に感銘を受け、このような判断
手法もあるということを裁判員の方々にも身に付けてもらいたいと思ったので、判例について私なりに理解した点をお話したいと
思います。
ここで、あらかじめ申し上げますと、「虚偽自白」という言葉ですが、普通「自白」は「相手方の主張する自己に不利な事実、又は
検察官の主張する犯罪事実を認めること」を言いますので、自白は自ら不利を認める真実のものだと考えられるため、通常は自
白で虚偽のことを言うことは想定されません。
しかし、自白の中に「自白した犯人が有利になるような虚偽の事実が入り込む」可能性はあります。例えば、他に共犯者はいな
いのに共犯者がいるという引き込み供述やもっと重い罪を隠すための、虚偽の事実の軽い罪についての自白などがそれです。
これを「真犯人の『作出した虚構』」と言います。
さらに最も大きな問題になっているのが、「犯人でもないのに犯人であると犯罪事実を作り出して供述する」という「無実の
人の虚偽自白」というものがあり得るかという点です。一般的には真犯人をかばうために自己犠牲となる虚偽自白が考えられま
すが、「真犯人をかばう必要もない無実の人が虚偽の自白をする」ということは一般的に考えられないとされています。
しかし、浜田教授の論考は、そのような虚偽自白は冤罪事件において示されるように頻繁に起きてしまうということを分析されて
います。無実の人の自白が客観的証拠と合わなくなって虚偽であることが判明する場合を「無実の人の『無知の暴露』」と言いま
す。
3、平成30年8月3日東京高裁(刑事)判決での「栃木小1女児殺害事件」(事件発生:平成17年12月1日、栃木県今市市(現日光
市)で下校途中の小学1年女児A=当時(7歳)=が行方不明となり、翌2日、茨城県常陸大宮市の山林で遺体が発見された。
約8年半後の26年6月、栃木、茨城両県警がK被告を殺人容疑で逮捕した事件(なお、凶器のナイフは見つかっていない。K被告
は捜査段階で自白したが、公判では否認している。)の有罪判決を問題としています。
(1) まず、この東京高裁判決では、一審判決(宇都宮地裁判決―無期懲役)で認定した公訴事実が、被告人の捜査段階での自白
どおりに「被告人は、平成17年12月2日午前4時頃、茨城県常陸大宮市甲字乙丙番丁所在の山林西側林道において、A(当時
7歳。以下「被害者」という。)に対し、殺意をもって、ナイフでその胸部を多数回突き刺し、よって、その頃、同所において、同人を
心刺通(心臓損傷)により失血死させた」というものであるのを、東京高裁判決は、控訴審での審理を通じて検察官の訴因変更
による殺害の日時を『平成17年12月1日午後2時38分頃から同月2日午前4時頃までの間に』と、場所を『栃木県内、茨城県
内又はそれらの周辺において』とそれぞれ改めた犯罪事実を認定して、一審判決を破棄しながらも、K被告が犯人であることは
間違いないとして一審判決と同様に「無期懲役」の有罪実刑判決をしています。
殺害時間については約13時間の幅が生じており、殺害場所も当初の茨城県常陸大宮市だけでなく、茨城県内どころか栃木県
内まで広げられた形の事実認定に変わっています。
(2) この点をわかりやすく説明するとすれば、控訴審判決は次のように言っている判決なのです。すなわち、刑事裁判では、本件
の場合、被害女児Aを「だれが、いつ、どこで、どのようにして」殺害したかという犯罪事実が認定される必要がある。第一審判決
はこの「誰が」という犯人性の部分は被告人が自白しているとおり正しく認定しているが、「いつ、どこで、どのようにして」という殺
害の日時、場所、態様については、被告人の自白を鵜呑みにしてこれを認定したために、本来なら「客観的に裏付ける証拠、そ
の信用性を支える事情の有無について検討すべき」ところを、それが不十分であり、犯人性の判断の中に埋没するようなことに
なって、結果的に殺害の日時、場所、態様に関して被告人が語った自白内容が客観的事実と矛盾することを見抜けなかったの
で、改めて、控訴審で客観的証拠の範囲内で殺害の日時、場所、態様に関して広い範囲での事実認定をして、有罪(無期懲役)
判決を維持したというわけです。
(3) このような控訴審の判断手法に対して、浜田教授は心理学的な視点から、また、自白調書を「証拠」として見るのではなく、取調
べの場における人間現象を記録した「データ」と見るという視点から、大きな疑問を呈しています。「裁判官たちは、無実の人が自
白に落ち、虚偽の自白を語っていく、語らざるを得なくなるその心理過程を正しく理解しているのだろうか。」という疑問です。
そして、自白調書に犯行事実に関して客観的証拠と明らかに異なる虚偽の事実が入っている場合に、法律的には「真犯人が
『作出した虚構』」という方向へ評価されるのか、それとも無実の人が『作出せざるを得なかった虚構』(このことを浜田教授は「無
知の暴露」と呼ばれている)という方向へ評価されるのかの問題になります。
4、「殺害の日時、場所、態様」に関する自白と客観的証拠の不一致をどのように評価するかについて
(1)弁護人は「本件自白供述のうち殺害の日時、場所、態様等に関する部分が、遺体発見現場付近や遺体の客観的状況と矛
盾するのは、被告人が取調官の追及により実際には体験していないこと(知らないこと=無知)を誘導や想像で供述させら
れたからである。被告人が真犯人でないことを示している。」という評価をしています。
(2)これに対して、控訴審判決では「本件自白供述のうち、殺害犯人であることを自認する部分を超えて、本件殺人の一連の
経過や殺害の態様、場所、時間等に関する部分にまで信用性を認めた原判決の判断は是認することができない。」
ただし、「本件自白供述における殺害の経緯及び態様は、通常想定されるものとはいえないし、遺体に認められる創傷か
らそのような犯行態様が推認されるものではなく、その他、本件の関係証拠の中にそのような経緯や殺害態様であったこと
を示すものがあるわけでもない。したがって、本件自白供述が取調官の誘導に基づくものとは考えられないし、そのような
状況をうかがわせる証拠もない。以上のとおり、被告人が供述しようとしても、犯行の体験がないために、具体的な供述が
できず、捜査官から与えられた情報に基づいて本件自白供述が構成されたというような状況は認められず、弁護人の所論
は、根拠を欠くものである。」とし、犯人性の認定には影響を与えないとした。他方、「状況証拠から認められる間接事実を
総合すれば、被告人が本件殺害犯人であることが合理的な疑いをさしはさむ余地なく認められる。」「原審判決は、(客観的
証拠との不一致の犯行日時・場所・態様等は)被告人の作出した虚構である可能性に思い至らなかった(にすぎない)」とし
ています。
(3)その点につき、浜田教授は、自白供述過程の心理学的視点から、無実の人は、取調官の誘導で事実を語るのではなく、自
分が犯行事実については「無知」であるからこそ、事実を想像して語るのであるということを指摘されています。
論考では「虚偽自白は、一般に取調官が把握した客観的事実から犯行筋書きを想定して、その想定に沿って無実の人を意
図的に誘導して出来上がるものだと考えられやすいが、実態はそういうものではない。むしろ、無実の人が自白に落ちてし
まった後は、自ら「犯人になり」「犯人を演ずる」形で、取調官の追及に沿いつつ、犯行の筋書きを自分から想像して語り出
していくほかない。」「そして、自白内容が後の捜査あるいは検証過程で客観的証拠と合致しないと判明したとき、それは無
実の人が想像で語ったためだという可能性が浮かび上がる。
そのことを私は『無知の暴露』として犯行の非体験者の自白の証拠であると指摘してきている。」「無知の暴露は、被告人
のみの無知ではなく、被告人と取調官の両者の無知なのである。」と説明されています。
5、無実の人の犯人性の虚偽自白後の犯罪事実に関する自白供述過程について
犯罪事実は、犯人と被害者と神のみが知っている事実です。取調官も裁判官も証拠から犯人性を推認できるだけです。そこで、
真犯人以外の無実の人は本当は知らないのにどのような心理過程を経て自白調書ができ上がるのでしょうか。論考で説明され
ているその心理過程をまとめてみますと、
(1) 無実の人が取調べが苦しくなって「自分が犯人である」と自白した。
(2) 取調官は、犯人が「落ちた」ということで無実の人を犯人だと確信を強める。
そして、取調官は「犯行内容は犯人しか知ら
ないから、自白した者自身の口で語ってもらうしかない」と考える。
(3) 無実の人は、実際には犯行は体験していないのだから、取調官から質問されても「知らない」と答えるしかないが、犯人性を自
白した以上は、取調官は「分からない」では済ませないだろうと考えてしまう。そこで犯人になった場合を想像して考えていくこと
にする。
(4) 想像した話をしてみる。
(5) 取調官は客観的証拠に合致する話であれば調書へ記載する。合致しない話は再度質問を繰り返し、客観的証拠と反しない話
が出るまで取調べを続ける。取調官に客観的証拠が得られていない事実内容については、不自然なものでない限りそのまま無
実の者の供述が受け入れられていく。(無実の人と客観的証拠の無い取調官双方の「無知」)
(6) その繰り返しで、徐々におおよそ客観的証拠と矛盾しない自白調書全体が作られていく。
(7) 一旦、自白調書が出来上がった後に、事後の捜査や弁護人の反証によって、客観的事実と合致しない自白調書であることが判
明する(無知の暴露)場合が起こる。
(8)被疑者・被告人が全面自白した後に、真犯人がもはや嘘を言う理由もなく、記憶違いをする可能性もない部分について、客観的
証拠と決定的に食い違う自白が語られたとき、それは無実の人がその犯行を知らないこと(真犯人ではないこと)を示している。
とされています。このような「無実の人」が「真犯人を演じて」「犯罪事実を語る」という自白供述の心理過程は、裁判員の方々に
も基本的な知識として必要だろうと思います。
6、控訴審判決の手法への批判
栃木小1女児殺害事件控訴審判決は、「被告人の自白と客観的な事実との不一致が確認できた場合に、もっぱら有罪を前提
に、その不一致に関して真犯人である被告人の「作出した虚構」である可能性のみを考え、その不一致が「無実の人の虚偽自
白」であった可能性を検討すらしようとしていない」(浜田教授見解)と非難されているように、本来の刑事司法での「無罪推定の
原則」を理解しない不当な判決だと批判されてもやむを得ないものと思われます。
以 上
ゴミ袋のゴミの所有権は誰にあるの?
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
「ゴミの所有権」って??
そもそも、みんなが不用なものとして捨てる物、又は、ゴミ回収に出す物などに「所有権」という法律上の権利が問題になんかなるの?と思われるでしょうね。
しかし、次のような法律相談を法律的にご回答する場合には、「ゴミの権利」「ゴミの所有権」から考えないと解決できないのです。
〇(相談Ⅰ)市町村のゴミステーション(集積所)に廃棄排出されたゴミや、回収日に道路脇に出された資源ゴミが、廃品回収業者などに
勝手に持ち去られてしまいます。
勝手に持ち去る業者に刑事上の処罰を受けさせることはできないのでしょうか。
○(相談Ⅱ)市町村としては、ゴミステーションに出されたゴミ袋が廃棄区別をしていないものも多く、廃棄基準や選別基準に合っていないゴミは排出者に返還する対応をしたいが、市町村(担当職員・委託を受けた者)が排出者特定のためにゴミの中を勝手に調べてよいのでしょうか?
○(相談Ⅲ)市町村は警察が求めて来た1軒ごとに回収したゴミ袋を他のゴミ袋と混ざらないように回収して欲しいとの要請を受け、回収した特定の1軒のゴミ袋を警察が任意提出を求めてきたので提出したがそのゴミの付着物から刑事犯罪の犯人のDNAが検出された。警察へのゴミの任意提出及び領置は、本来、特定の1軒に存置する物(ゴミ)を捜索差押令状で取得すべきものであり、令状主義違反の手続きではないでしょうか?
(参照条文:刑事訴訟法第221条:(領置)検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑
者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。)
(ご説明)
この相談例を考える場合、冒頭に申しましたように、そもそもゴミステーションやゴミの回収場所に置かれたゴミについて、そのゴミの所有権は誰にあるのでしょうか、それとも捨てられた物「無主物」として、誰の所有権もないのでしょうか、ということを考える必要があります。
○≪回答≫
1、ゴミの所有権の帰属について―対外関係について
物に対する所有権は、「所有権絶対の原則」から所有権放棄をすることもでき(無主物となる)、他に処分をする(所有権移転等)ことも所有者が自由にできるというのが原則です。しかし、ゴミについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第16条(投棄禁止)で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」との法律による制限規定があるので、勝手に所有権放棄(廃棄)はできないことになっています。
そうなると、条例の定めるゴミ出し日に、ゴミステーション等に出された(ゴミ出し者の)ゴミ袋、及びその中のゴミの所有権は、「所有権放棄ではなく、所有権が移転する」という形で出されていること」になります。
この点、判例上は、ゴミステーションに出されたゴミ袋から目ぼしいものを勝手に持ち去った行為が遺失物横領罪又は窃盗罪になるかどうか、又は条例の罰則適用は合法かという観点で、ゴミの所有権の帰属を判断した例があります。以下のとおり、対外的な第三者に対する関係では、所有権放棄ではなく、地方公共団体か、ゴミ排出者のどちらかに所有権はあるとの判例上の判断が出ています(下記(1)(2)(3)の判例)。
なお、ゴミステーションではなく、公道上の集積場所に置かれたゴミについては、下記(4)の判例があり、判例上は遺留物とされています。また、ゴミステーションのゴミは一般的には「無主物(所有権放棄された物)」とは言えないとしても、住居者が廃棄したという意思を明確に有する場合には、民法上は「無主物」とせざるを得ないとした判例(平成19年12月13日東京高裁判決)もあります。
(1)平成19年12月13日東京高裁判決(世田谷区清掃・リサイクル条例違反事件)
区民が集積日に集積所へ排出した古紙や缶等の資源廃棄物については、区が回収することを前提に集積されるもので、区民
が集積所に排出したからといって所有の意思を放棄したものではなく、むしろほとんどの場合は、区によって回収されるまでは区
民によって所有・占有されており、区が回収することによってその所有権や占有権が区に移転、承継されるものと考えるのが相
当である。したがって、集積所の資源廃棄物は、一般的には無主物ではないというべきである。
(2)平成19年12月26日東京高裁判決(世田谷区清掃・リサイクル条例違反事件)
区民は、行政回収のために区に引き渡す意図で集積所に古紙等を置き、区側は、程なくこれを必ず回収することになるのである
から、古紙等が集積所に置かれることによって、民法第239条第1項の無主物の状態が出現するということ自体が、甚だ疑問で
あり、むしろ、行政回収システムに基づき集積所に置かれた古紙等は、民法の解釈としても、その置かれた時点から区の所有に
属することになり、
同項の定める所有者のない動産には当たらないと解するのが相当である。
(3)平成20年1月10日東京高裁判決(世田谷区清掃・リサイクル条例違反事件)
区民が、古紙等の資源を収集日に資源・ごみ集積所に排出するのは、これを再生利用の目的となる有価物のものとして、
区の収集、回収によるリサイクル事業に委ねるためである
から、区又はその委託を受けた収集運搬業者が資源・ごみ集積所からこれを収集してその占有下に収めるまでは、一般に、
区民は、なお継続してこれを所有占有している
ものとみるべきである。
(4)平成20年4月15日最高裁判決
公道上の集積場所に置かれたゴミの領置について「ゴミ処分者は、その占有を放棄していたものであり、排出されたゴミが通常
収集されて他人にその内容が見られることはないという期待があるとしても、捜査の必要がある場合には、刑事訴訟法第221条
によるこれを遺留物として領置することができる。
2、ゴミの所有権の帰属について―内部関係について
しかし、ゴミステーションのゴミの所有権が、回収する市町村か、ゴミ排出者のどちらかにあるかという内部関係での所有権の帰属を直接判断した判例は見当たりません。
ゴミ廃棄は、法律的には、ゴミ排出者とゴミを回収する市町村との間にゴミ廃棄委託契約があると思われますので、暗黙に、「①ゴミ排出基準に合ったゴミについては、ゴミの所有権は回収する市町村に所有権及び処分権を移転させ市町村が廃棄する。②ゴミ排出基準に合わないゴミについては、市町村は引き取らずに所有権も移転させない。」という合意のある制度になっていると解釈することが可能だと思います。
また、ゴミ廃棄委託契約においては、黙示の契約として、「廃棄排出基準に合うかどうかの審査のために、回収する市町村はゴミ排出者の所有権の下にある間でも、ゴミステーションの置かれたゴミの検査・調査ができる権限を与えられている」と言える(合理的解釈)と思われますが、明確な口頭合意があるわけでもないし、個々の住民との間で委託契約書を取り交わすことも不可能ですので、市町村は条例でその旨(ゴミ所有権の移転時期の定めと、ゴミ所有権が移転しない場合でも排出基準検査のための検査権を有するとの定め等)を規定することが望ましいと考えます。
そうすれば、市町村及び市町村から管理委託された自治会役員等が、違法なゴミ排出者特定のためにゴミの中を勝手に調べても、原則として、プライバシーの侵害等にはならないということになります。(注意:違法なゴミ排出者の特定又は基準違反かの判断に必要な範囲での調査が許されるだけで、そのような調査に不必要なゴミの内容・不必要な個人情報にまで調査してしまうと、プライバシーの侵害となるので、その点は注意する必要があります。)
3、(相談Ⅰ)の回答
条例の定めるゴミ出し日にゴミステーション等に出された(ゴミ排出者の)ゴミ袋の所有権は、所有権放棄ではなく、回収側の市町村かその回収業務担当
者へ所有権が移転する形で出されていることになります。
この点、判例上も、ゴミステーションに出されたゴミ袋から目ぼしいものを勝手に持ち去った行為が、遺失物横領罪又は窃盗罪になるとしていますので、勝手にゴミを取っていく行為は刑事上の処罰を受ける可能性があります。また、条例に定められた「持ち去り行為禁止違反」として処罰される場合もあります。
4、(相談Ⅱ)の回答
市町村(担当職員・委託を受けた者)が排出者特定のためにゴミの中を調べることは、原則として許されます。しかし、調べる範囲は違法なゴミ排出者の特定又は基準違反かの判断に必要な範囲に限定されますし、それらに不必要なプライバシ―を侵害するような内容の調査や方法を採ると違法な行為となる場合がありますので、その点を留意して下さい。
5、(相談Ⅲ)の回答
この相談事例は、東京高裁平成29年8月3日刑事判決で問題となった事案です。問題点としては、①警察がゴミ収集での協力を依頼してきたのは、1軒毎回収方式でまだ犯人の屋敷の中のゴミ回収場所に置いてあるゴミ袋についてのことであったこと(この時点で警察が領置するには捜索差押令状が必要になると思われる。)、②市町村はゴミ収集目的で各軒の屋敷に立入りゴミ袋を回収ができる契約(合意)になっていたことに基づき、ゴミ袋を回収した時点でゴミ所有者は市町村になるので、その時点で市町村からの任意提出を受け領置させるのは、市町村に立入許容範囲外の立入をさせており、市町村の屋敷立入行為の違法性があり違法なゴミ回収になるのではないか、という点です。
東京高裁判決では「本件ゴミ袋は、被告人宅敷地内の木箱の中に置かれていたものであって、その時点においては、被告人に物理的な管理支配関係としての占有が残っており、刑訴法第221条にいう遺留物には当たらないと解される(領置はできない)」「しかしながら、本件ゴミ袋は、被告人宅敷地内の木箱の中に置かれた時点で、市のごみ収集担当職員に対しゴミとしての収集が委ねられたものであり、同職員としても通常業務の一環として本件ゴミ袋を被告人宅敷地内から収集したものであって、遅くとも同職員において敷地内から搬出した時点で本件ゴミ袋について正当に物理的な管理支配としての占有を有するに至ったというべきである。
その上で、その後、運搬先で警察官に本件ゴミを任意提出したものにすぎず、本件は住居侵入及び強盗強姦という重大事件の捜査に必要なものであり、高度の捜査の必要性が認められる(領置は違法ではない)」としています。
しかしながら、個人的見解ですが、この判例の結果には違和感があります。
犯罪捜査であるとしても、一般人を基準としたプライバシーの権利を不当に侵害するものであってはなりません。相談Ⅱで述べましたように、ゴミ収集委託についての常識的な解釈としては、一般人がゴミ袋に入れたゴミを収集担当職員に引き渡すのは、最終的な焼却・廃棄まで内容物が何人の目にも触れないで処理されるという合理的な期待をしていると解することになるのではないかと思います。このプライバシーの保護の観点から言えば、本件事案のように、ゴミ収集職員は収集後に警察がゴミの内容を捜査するということを事前に知りながらゴミ収集をしているのだとしたら、仮に「物理的な管理支配としての占有」を取得したとしても、他人に内容捜査をさせてもいいという意味での収集委託は受けていないと解釈できますので、市町村及びその担当者においては、警察捜査機関からの任意提出の求めに応じる権限まで有しないのではないでしょうか。
その意味で、任意提出権限のない市町村担当職員からの任意提出に基づく領置は、法的根拠を欠く違法な手続きとなる可能性があるようにも考えられます。この点は、警察の捜査手続きの違法性に結果的に関与してしまう可能性があるという意味で、市町村のゴミ収集業務としては、プライバシーの保護という観点は留意しておくとよいでしょう。
以 上
ジョギングも気をつけて走りましょう!(犬にぶつかりそうになって転倒)
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
(問題)ある日の午前中、町内の公道を、Xはジョギングをしており、Yはミニチュアダックスフンド(犬)を散歩させていたところ、Yの飼い犬が他の犬に興奮して強く走り出してしまったためYは、リードから手を放してしまい、Yの飼い犬が勝手に前の通行人Aの後ろへ走り出してしまった。他方Xは、かまぼこ型に曲がっていた公道の反対側から時速約10km程度のスピードでジョギングしていたが、曲がり終わった地点で、通行人Aを急に発見する状態になって、Aとの距離約2m手前で衝突を避けるために右側にAを避けたところ、丁度その右側後方からYの犬が走ってきていたのでそれに驚き、その犬を更に避けようとして転倒してしまい、右手前腕の骨折、顔面挫創(入院9日・通院54日)のけがを負ってしまった。このけがについての法的責任(賠償責任)は誰が負うのでしょうか。
逆に、この事案で、Xが対向歩行者のAにぶつかってしまい、Aが転倒してけがを負った場合は、誰がその責任を負うことになるでしょうか。
(解説)健康志向の世の流れに沿って、日本のお家芸であったマラソン競技や駅伝競技がスポーツとして人気を得るばかりか、市民マラソンが隆盛となり、日常生活での趣味としてのマラソン、ジョギングが庶民の健康方法として定着しています。お正月も初走りということでジョギングを楽しんだ方も多いことでしょう。走ることに苦しみではなく、快感を覚えている人たちが多くなっているのでしょうね。ただし、公道をジョギングする場合には、自転車の速度に近い状態で走っているわけですから、通常の歩行とは異なり、その速度に伴う交通上の危険を内在していることを、ランナー(走者)の方々は認識しておく必要があります。本件は、その点を法律的に検討しようというものです。
1、賠償責任とは?
賠償責任とは、民事上の責任であり、債務不履行(民法第415条)の場合の賠償責任と不法行為(民法第709条)の場合の賠償責任の二つがあります。本件では、けがをしたXと関係者のYやAとは契約関係はなく、債務不履行責任は問題になりませんので、不法行為責任としての賠償責任(民法第709条、民法第718条等)がAにあるのか、Yにあるのか、それともXの自己責任で終わってしまうのかが問題になります。(ちなみに、動物であるYの犬は「物」であり、権利主体又は責任主体となる「人」ではありませんので、犬自体に責任を負わせることはできません。犬の管理責任として飼い主のYが責任主体となるだけです。(民法第718条参照)賠償責任とは、民事上の責任であり、契約不履行(民法第415条)の場合の賠償責任と不法行為(民法第709条)の場合の賠償責任の二つがあります。本件では、けが怪我をしたXと関係者のYやAとは契約関係はなく、債務不履行責任は問題になりませんので、不法行為責任としての賠償責任(民法第709条、民法第719条等)がAにあるのか、Yにあるのか、それともXの事故責任で終わってしまうのかが問題になります。(ちなみに、動物であるYの犬は「物」であり、権利主体又は責任主体となる「人」ではありませんので、犬自体に責任を負わせることはできません。犬の管理責任として飼い主のYが責任主体となるだけです。(民法第718条参照)
2、不法行為責任の主体は?
不法行為責任は、①損害を与えた人の行為に「故意又は過失」があること、②損害が生じたこと、③行為と損害発生との間に相当因果関係があることが必要とされています(民法第709条)
(1)本件では、②の損害(けが)がXに生じていますので、その原因と考えられる人の行為に「故意又は過失」があることが必要です。Xのけがの原因は誰の行為にあるでしょうか?
(2)故意とは、けがの発生を認識しながら、けがが生じても良いと認容したことです。過失はけがを予見しなければいけなかったのにそれを怠ってけがをさせた場合を言います。過失はそもそも予見できない場合には責任を認めることはできません。
ア それでは、「Aさんが公道を歩いていたこと」が、故意又は過失になるでしょうか。
Aさんの立場からは、公道を歩いていて、見えない曲面の先から結構早いスピードでジョギングをしてぶつかりそうになる人がい
ることを予想できるでしょうか?あるいは予想しながら慎重に歩くことが求められるでしょうか?一般的には、故意又は過失は社
会的に違法(法益侵害をする危険性のある行為)と思われる行為についての主観的要件として認められる場合が多いことからし
ますと、そもそも公道を歩くことが違法又は危険な行為とは評価できないでしょうし、常に誰かが危険な行為をすることを予想し
ながら歩かなければならないとすることは不可能を強いることになります。歩道を単に歩いているAさんには故意又は過失の責
任を認めることはできません。
イ それでは、Yさんはどうでしょうか?Yさんは、自分の飼っているミニチュアダックスフンド(犬)を散歩させていましたが、ここまで
は社会的に許される行為です。
犬のリードから手を放してしまったという行為には、何か落ち度(過失)がありそうですが、その原因は、自分の飼い犬が他の犬
を見て興奮して強く走り出したことが原因なのですが、そういう場合を想定して犬の急激な行動を制御するためのリードですか
ら、強く走り出したことが原因なのですが、そういう場合を想定して犬の急激な行動を制御するためのリードですから、それを手
放してしまったことは、犬が走り出して人に対して危険なことをする可能性を作り出してしまったことになり、管理ミス(管理過失)
を認めざるを得ません(要件①)。
しかし、その犬は、実際には、被害者のXに飛びかかったわけでもなく、咬んだわけでもなく、Xのけがとの間に相当因果関係
はあるのでしょうか?(要件③)その検討が必要です。
ウ 最後に被害者であるXの行為はどうでしょうか?ジョギングを公道で行なうことは社会的に許される行為でしょう。早いスピード
でジョギングすることも本来は社会的にも許されている範囲でしょう。ただし、見通しの悪いかまぼこ型曲面の公道を走るという
場合には、先方の見通しも悪く、対向歩行者の存在の可能性を予想することは必要でしょう。その意味では、公道上の対向者に
ぶつからないように注意して走るという結果予見義務も回避義務もこのような場合には求められるだろうと思われます。Xは曲が
り終わった時点ですでに対向歩行者のAとぶつかりそうになっていますので、その予見義務を怠ったと認められると考えます。そ
れを避けるために右側に避けているのですが、その避けた先にYの飼い犬が足元近くまで走ってきていたので、それに驚いて転
倒した。Xの転倒はXの不注意だけでなく、「Yの飼い犬が足元近くまで走ってきていた」ということも原因の一つになっている
ようなので、Xの自己責任ということにもならなさそうです。
3、判例の見解(大阪地裁平成30年3月23日判決―判例時報2386-47)
問題の事案について、大阪地裁判決は、「Yが特別な状況でもないにもかかわらず、突然、飼い犬が走り出したことにより手を放してしまい、飼い犬が単独で道路を進行したことにより、本件事故(Xのけが)が発生したものであって、事故の主たる原因は,Yが飼い犬を係留しない状態にしたことにある」として,Yの不法行為責任(民法第718条動物管理責任)及び相当因果関係を認めました。更に、被害者Xにおいても、「ジョギング中において前方確認や進行速度を適切に調整することにが不十分」であり、これが事故の発生に影響していることも否定できないので、一割の過失相殺を認めるとしています。
この判決は、控訴されています。YはXの過失は3割を認めるべきであると主張していましたので、もう少しXの過失性が高いと判断される可能性が残っています。。
4、最後に、この事案で、Xが対向歩行者のAにぶつかってしまい、Aが転倒してけがを負った場合の責任問題についてはどうなるでしょうか。
公道の利用方法としては、歩行者Aには何ら過失的要素はありませんし、逆に、結構速い速度で走って来ていたXには判例でも認められているように、「ジョギング中において前方確認や進行速度を適切に調整することにつき不十分である」という過失責任が認められ、その結果、歩行者Aがけが(損害)を負っていますので、相当因果関係も認められ、Xが不法行為としての損害賠償責任を負うことになります。
自分の健康管理のためであれ、ジョギングも人に迷惑をかけたりしないような配慮は必要です。ジョギングする人は、公道を利用する以上は車と同じような「前方確認や進行速度を適切に調整する義務」があることを十分に自覚されるほうがよろしいかと思います。気をつけて走りましょうね。
以 上
お正月と法律(その⑤)~天皇即位によるカレンダーと休日~
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
あけましておめでとうございます。
新元号の年を迎えています。お正月になると、新しい年の「年神様」をお迎えし、全てが改まった新鮮な気分になります。その一つとして、暦やカレンダーが新しくなっていることに気を留めてみてはいかがでしょうか。
第一、今年のカレンダーの作製の苦労について
今年(平成31年?)の新春のカレンダー作りは大変だったろうと思います。なぜなら、今上天皇(継宮明仁天皇・つぐのみやあきひと)陛下が退位されるので、元号の「平成」は30年で終わり、次の元号の発表に合わせて作製することが求められますし、新たな天皇(浩宮徳仁殿下・ひろのみやなるひと)の即位による国民の休日を定める予定があったからです。
1、新元号はいつから?
一昨年(平成29年)退位期日の政令公布日の政府発表では、「天皇陛下の退位日を平成31年(2019年)4月30日とし、皇太子様は翌日5月1日に即位する」と決定されています。新元号は、今年(平成31年)5月1日から適用される予定です。
2、新元号の発表時期は?
政府発表では、新元号の発表は、上記元号改元の1ケ月前の今年(平成31年)4月頃としてますが、平成31年2月24日に天皇陛下在位30年記念式典が実施される予定であり、それ以降の天皇陛下の公務に区切りがついた適切な時期に公表する方針であるとも言われています。
3、カレンダー製作時期と元号表示不能
他方、新年のカレンダー作製は、前年の10月には始められますので、今年(2019年)のカレンダーは、その作製時期において「新元号」の表示はできないことになりましたし、元号を使うとしたら「平成31年」の表示、使わないとしたら西暦での表示のみがなされたカレンダーもあるようです。
4、休日の記載について
問題は、新元号表示の問題だけではありません。天皇退位・天皇即位により、天皇誕生日等の「国民の休日」がどのように改正されるかの問題もありました。
この点、昨年の内に安倍総理大臣が、「皇太子様が即位される2019年5月1日、即位を公に宣言する「即位礼正殿の儀」が行われる2019年10月22日を、1年限りの祝日とする検討を進めている。」と明らかにしましたが、天皇誕生日としての休日は、今年(2019年)は現行の12月23日の天皇誕生日には、今上天皇は天皇ではないので休日にならないでしょうし、新たな天皇(現皇太子)の誕生日の2月23日にはまだ天皇ではないので、2月23日を天皇誕生日にすることもできないという状況になりますので、今年(2019年)は「天皇誕生日」の休日はないということになります。
5、春の連休は10連休?
ところで、今年(2019年)4月及び5月のゴールデンウィークは10連休になるという話はご存知だったでしょうか。そのことを「国民の祝日に関する法律」から説明しておきます。
(1)第2条で「国民の祝日」として、4月29日(昭和の日)、5月3日(憲法記念日)、5月4日(みどりの日)、5月5日(こどもの日)が定めてあります。
(2)第3条第2項で「「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。」第3条第3項で「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る )は、休日とする。」と定めています。
(3)今年(2019年)は天皇の退位。新天皇の即位があるので、5月1日を1年限りの祝日とする法律(改正)がなされました。そこで今年のゴールデンウィークのカレンダーの一覧を作製してみますと、次のようになります。
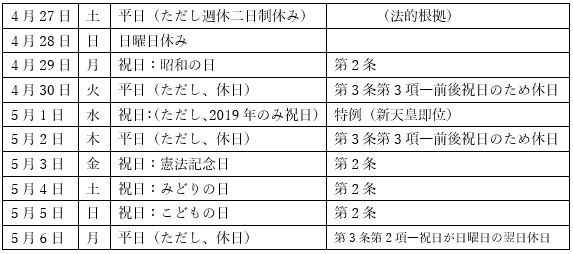
つまり、通常暦の5月1日の平日を「1年限りの休日」としたことにより、祝日で挟まれた平日の4月30日と5月2日が「休日」扱いになる(第3条第3項)ことから、10連休となるゴールデンウィークが生まれるわけです。
第二、正月休日で問題になる「期間の数え方」
天皇の退位・即位と「休日」に関連して、特に正月休日で問題になる「期間の数え方」を話させていただきます。
世の中の契約や約束などの法律行為では、「○○日までに支払います。」とか「一月後に支払います。」との期限(最終期日を定めた約束をする場合が多くあります。また法律の定め方でも、判決や行政処分などに対して「二週間(又は14日)以内に控訴申立てができる」「3ケ月以内に異議申立ができる。」等と定めている場合が多くあります。
1、この期間の数え方についても、民法という法律が次のとおり定めています。
民法第138条(期間の計算の通則)
期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この
章の規定に従う。
民法第139条(期間の起算)
時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
民法第140条(暦法的計算による期間の起算日)
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、こ
の限りでない。
民法第141条(期間の満了)
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
民法第142条(期間の満了の特例)
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるとき
は、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
民法第143条(暦による期間の計算)
(1)週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
(2)週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応
当する日の前日に満了する。
ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了
する。
2、休日と最終期限の確定
例えば、平成30年12月15日(土)に敗訴判決書を郵便で受け取ったとして想定事例を考えてみます。民事裁判の判決に対しては、民事訴訟法の定めにより「判決を受領した日から2週間以内に控訴申立てができる」と定められていますので、2週間の最終期限日は、次のような計算をしていきます。
(1)「判決を受領した日」は、平成30年12月15日(土)です。
(2)それでは、「2週間」というのはどういう計算でするのでしょうか。
ⅰ>まず、民法第140条「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。」(初日不算入の原則
といいます)との定めがありますから、期間算定の初日は「12月16日(日)」になります。
ⅱ>次に、民法第143条1項で「暦に従って計算する」わけですが、これは、例えば、2ケ月という場合に、1ケ月31日の場合と
1ケ月30日の場合と日数が異なることが考えられます。日数の多寡にかかわらず、月数で単純に計算するという意味で考え
ていただければいいのですが、2週間の場合には、民法第143条第2項「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、
その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。」ということで、暦を見てみれば、
起算日の12月16日(日曜日)の二週間後の応当日は「平成30年12月30日(日曜日)」であり、「前日」は「平成30年12月29
日(土曜日)」になります。
ⅲ>そうすると、本来は、判決不服申立てとしての控訴申立ては「「平成30年12月29日(土曜日)」の24時になる前(民法第141
条の「末日の終了」)まで可能ということになります。
ⅳ>しかしながら、この場合、12月29日は年末休日ではないかという問題がありますので、最後に、民法第142条「期間の末
日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるとき
は、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。」の定めがあり、この「平成30年12月29日(土
曜日)」が、この「期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たる」のではないかと
いうことを検討することになります。
国民の祝日に関する法律には「12月29日、30日、31日」の年末休日の定めはありませんが、行政機関の休日に関する法律第1条第1項3号により「12月29日、30日、31日、1月2日、3日」を行政機関の休日としていますので、民法第142条の「その翌日」というのは、休日が1月3日まで続きますので、「平成31年1月4日」となり、控訴はその日まで可能であるという算定になります。
(3)なお、今年(2019年)4月及び5月のゴールデンウィークは10連休になるということを述べましたが、その場合にも、仮に、最終期限日が2019年(平成31年又は○○元年)4月27日(土曜日)」である事案であった場合には、その最終期限は、それから10日後の「5月7日(火曜日)」まで伸びる結果になります。
期間の進行も、期限の最後の日については、「人の休みのときは、期間の進行も休んでいる」ということです。
以 上
遺言書の訂正・変更・撤回
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
私の叔母(夫死亡、子供はなく相続人は甥A・姪B・姪Cの三人だけ)の遺言書(叔母の自筆証書)が次のようになっていた場合、誰が財産を受け取ることができるでしょうか?
遺言書の内容は、最初は「私の全財産は、姪のCに全部贈与する。日付・自筆署名・押印」となっていました。
☆設例(1):遺言書の内容のうち、「姪のC」の部分が二本線が引かれて押印して消してあり、姪のBと横に書いてあって、遺言書の末尾に、「姪のCを姪のBに変更した。日付・自書署名・印」と書き加えられている場合。
☆設例(2):遺言書の内容のうち、「姪のC」の部分が二本線が引かれて消してあり(押印なし)、姪のBと横に書いてあったが、遺言書の末尾にも何も付記されていない場合。
☆設例(3):遺言書は1枚だけの用紙に書かれていたが、その一枚に赤色ボールペンで、左上から右下にかけて一本の線が引かれていて、末尾にも何も付記されていない場合。
<解 説>
高齢社会になると高齢者の多くが通帳に預金が残っていたり、つつましく老後を過ごされ蓄財された財産が残されていたりして、相続人間で遺産分割等の争いになる例も増えています。そのような争いを避けるために「遺言書」を作成されている高齢者の方々も多くなりつつありますが、遺言書自体が争われる場合もあり、人の紛争は絶えることがないのだろうかと考えたりします。そこで、今回は、その遺言書をめぐる解釈の争いの事案を説明していきます。
1、遺言書の訂正・変更については厳格な様式が定められています。
遺言書は、遺言者自らが自書する方法でも認められていて、自筆証書遺言又は自筆遺言書は、要式行為であり、民法第968条で、「1、自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。2、自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」と定められています。
そこでは、自筆遺言書についての加除訂正や変更方法も様式が定められていますので、その様式に従わない場合には、加除訂正や変更の効力が認められないことになります。
本件の相続は、いわゆる第三順位相続(兄弟・甥姪相続で遺留分はない:民法第1028条)ですので、遺言書で相続人や第三者の一人に全部相続又は遺贈させる旨の遺言がなされると、その相続人等の一人だけが遺産全部を取得することができますので、遺言書の解釈は大きな意味を持つことになります。
さて、本件の当初の遺言書では、相続人姪Cが遺産全部を取得する内容でしたが、その後、訂正されて、相続人姪Bが遺産全部を取得する内容になっています。
設例(1)の場合には、書き間違いであれば訂正、相続人自体を変えたのであれば変更になりますが、いずれにしても、民法第968条第2項の遺言書の訂正・変更の様式にしたがった変更がなされていますので、「姪のC」から「姪のB」への有効な変更がなされたことになりますので、設例(1)の場合には、相続人姪のBが遺産の全部を取得することになります。
これは、被相続人の叔母が、自分の意思で法律上の様式を守って変更したという結果の表れであり、その変更した理由がわからなくても、変更は有効となります。
それに対して、設例(2)の場合には、遺言書変更の様式を守っていませんので、誰が二本線を引いたのか(最初は、相続人姪Bと相続人姪Cの二人とも書いてあって、後で誰かが姪Cのみ二本線で消したのではないかも含む)も分かりません。したがって、被相続人の叔母が自分の意思で消したとの判断もできないことから、二本線の訂正・変更は民法第968条第2項により無効となります。
この場合、「姪のB」が最初から書いてあったのか、最初は書かれておらず二本線の抹消時に書かれたものかを確定する必要があります。この判断は、書かれた位置(横の位置か、縦の位置か)や字体や使用した筆記用具の違いの有無等で判断されることになりますが、通常の経験則としては、横にはみ出して書いてある場合には、後に書かれた変更分とされて、加筆部分の「姪のB」は無効となり、遺産の相続対象者にはならないだろうと思われます。したがって、設例(2)の場合には、相続人姪Cが遺産の全部を取得することになります。
2、遺言書の撤回(破棄)は、どういう場合まで含めることができるのでしょうか。
設例(3)の場合は、民法第968条第2項の、一本の赤線で抹消され加筆部分がないまま全部の訂正又は変更という形で検討するのか、又は民法第1024条「遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。」との規定の「遺言書の破棄」として検討すべきかという問題になります。
「訂正又は変更の問題」だとすれば、民法第968条第2項の様式に従っていないので、変更行為(一本の赤線で抹消行為)は無効となり、元の遺言内容(姪Cへの全部相続)が有効となり、他方「破棄の問題」だとすれば、元の遺言自体が撤回されて遺言がない状態となり、相続人甥A、姪B、姪Cが各自、法定相続分(各1/3)を相続する可能性が出てくるという違いが生じるのです。
(1)そもそも、民法第1024条の「遺言書の破棄」は書面の破棄と目的物の破棄という物理的破棄を想定しているかのような定めになっていることから、自筆証書遺言の全文に斜線を引く行為が「遺言書の破棄」に当たるかどうかが問題になります。
学説上は、破り捨てるか燃やすなどの有形的破棄のみならず、遺言書自体は形として残っていても遺言書の内容を抹消して内容を識別できない程度にすることも含まれるとする通説と、同様に有形的破棄に限定しないが、元の文書が判読できる状態であっても、全体が塗抹されたり斜線で消されたりした遺言書はそれが遺言者のせいでなされた以上は加除変更の方式や撤回の方式に即していない場合でも破棄されたと認める少数説があります。
(2)判例
ア、実際の裁判例では、最高裁平成27年11月20日(民集69-7-2021)は、少数説の立場での判断をしています。
事案は、医師である被相続人(遺言者)が医師しか開閉できない麻薬保管庫に遺言書を保管しており、他の誰にも遺言書の出し入れはできない状態だったという事案で「本件のように赤色のボールペンで遺言書の文面全体に斜線を引く行為は、その行為の有する一般的な意味に照らして、その遺言書の全体を不要のものとし、そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であるから、その行為の効力について一部抹消の場合と同様に判断することはできない。」としています。
イ、しかしながら、上記最高裁判決事案の第一審、第二審判決(広島高裁判決平成26年4月25日金融判例1485号12頁)は、通説の立場を採用して「民法第968条第2項は、遺言の効力を維持することを前提に遺言書の一部を変更する場合を想定した規定であるから、遺言書の一部を抹消した後にもまだ元の文字が判読できる状態であれば、民法第968条第2項所定の方式を具備していない限り、末梢の効力を否定することとなり、本件遺言書は斜線が引かれた後も判読可能な状態であるから、民法第1024条前段の「故意に遺言書を破棄したとき」には該当しない。」としていました。
ウ、このような判例の事案(単に自筆証書遺言に斜線が書かれているだけの事案)では、その斜線を誰が入れたかの確定が非常に困難な場合もあります。第三者でも入れられる可能性がある場合には、被相続人(遺言者)の意思は、元の文字には署名押印もあるので表れているが、斜線には表れていない可能性もあるので、元の文字の遺言書を有効にする解釈(下級審判例・通説)が妥当となることもあってよいと思います。本件事案は、その点、「遺言者(医師)しか開閉できない麻薬保管庫に遺言書を保管しており、他の誰にも遺言書の出し入れはできない状態だった」ことから、遺言者自身が斜線を入れたことは確定できる事案であったからこそ、遺言者の意思が「破棄」の意思だったと解釈できる事案だったという例外的な判例として位置づける方が妥当だろうと思います。
以 上