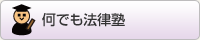掲載された文章・画像等の無断転載を禁止します。著作権は宮崎県町村会またはその情報提供者に属します。
カスタマーハラスメントと法的問題(2)
(刑事問題、民事賠償問題、労働問題)
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
前回に引き続き、今回は、カスタマーハラスメントについて、どのような法的責任が生じるかについてご説明します。
1~4は前回に説明済み
5.カスタマーハラスメントと刑事問題(★カスハラは、どんな刑事罰を受けるの?)
カスタマーハラスメントは、次の態様で行われた場合には、刑法上の犯罪になる可能性が高くなりますので、警察への相談対応もできることになります。
◆ 店員が「お引き取りください」と要求しても帰らなければ
→ 「不退去罪(刑法第130 条)」
◆ 店内で、店員の制止に従わず、大声を出し続けると
→ 「威力業務妨害罪(刑法第234 条)」
◆ インターネット上に評判を貶めるような嘘の書き込みをしたり、無言電話をかけ続けるなどして営業を妨害すると
→ 「偽計業務妨害罪(刑法第233 条)」
◆ インターネット上などで「店員の〇〇という人の態度が最悪!皆も利用しないように!」と言いふらすと(それが事実だとしても)
→ 「名誉毀損罪(刑法第230 条)」
◆ 「俺を怒らせたら何するか分からないぞ!」「お前ん家に、後で若い衆をよこすからな!」などと言って脅すと
→ 「脅迫罪(刑法第222 条)」
◆ 店員に無理矢理土下座させたり、謝罪文を書かせたりした場合は、
→ 「強要罪(刑法第223 条)」
◆ 「ネットに書き込むぞ!黙っててほしいならそれなりの誠意を見せろ!」などと過剰な見返りや金品を要求すると
→ 「恐喝罪(刑法第249 条)」
6.カスタマーハラスメントに対する会社の対応―労働問題(★会社には、従業員を守るためにどういう責任があるの?)
(1)反社会的勢力による企業への不当要求行為への対策については、すでに弁護士会の民事介入暴力対策委員会の弁護士(いわゆる「ミンボー弁護士」)において、「不当要求対応マニュアル」が活用されてきています。(各都道府県暴追センター「暴力団等反社会的勢力からの不当要求に対する対応マニュアル(基本的対応要領16か条)」「不当要求対応ガイド」等)。その要点だけ示します。
○ 反社会的勢力による不当要求がなされた場合には、当該情報を、速やかに反社会的勢力対応部署へ報告・相談し、さらに、速やかに当該部署から担当取締役等に報告する。
○ 反社会的勢力から不当要求がなされた場合には、積極的に、外部専門機関に相談するとともに、その対応に当たっては、暴力追放運動推進センター等が示している不当要求対応要領等に従って対応する。要求が正当なものであるときは、法律に照らして相当な範囲で責任を負う。
○ 反社会的勢力による不当要求がなされた場合には、担当者や担当部署だけに任せずに、不当要求防止責任者を関与させ、代表取締役等の経営トップ以下、組織全体として対応する。その際には、あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずるとともに、刑事事件化を躊躇しない。特に、刑事事件化については、被害が生じた場合に、泣き寝入りすることなく、不当要求に屈しない姿勢を反社会的勢力に対して鮮明にし、更なる不当要求による被害を防止する意味からも、積極的に被害届を提出する。
○ 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合には、反社会的勢力対応部署の要請を受けて、不祥事案を担当する部署が速やかに事実関係を調査する。調査の結果、反社会的勢力の指摘が虚偽であると判明した場合には、その旨を理由として不当要求を拒絶する。また、真実であると判明した場合でも、不当要求自体は拒絶し、不祥事案の問題については、別途、当該事実関係の適切な開示や再発防止策の徹底等により対応する。
○ 反社会的勢力への資金提供は、反社会的勢力に資金を提供したという弱みにつけこまれた不当要求につながり、被害の更なる拡大を招くとともに、暴力団の犯罪行為等を助長し、暴力団の存続や勢力拡大を下支えするものであるため、絶対に行わない。
(2)カスタマーハラスメントへの会社の対応策
カスタマーハラスメントは、一般人としての顧客への対応なのですが、要求内容や要求態度が「不当要求」である点では、反社会的勢力からの「不当要求」への対応策と同様の対応策が採られるべきです。一般人だからといって許す必要はありません。
問題は、職場の上司及び企業管理職等の「カスタマーハラスメントへの対応意識」の無さです。反社会的勢力による場合には、現場の一従業員に対応させることは困難であるため組織的な対応を取ることは意識できても、一般人によるカスタマーハラスメントは、単なるクレーム処理として現場の一従業員に対応させておけばよいという意識になってしまっています。
しかしながら、2020年に労働施策総合推進法が改正・施行された際の「パワハラ指針」において、カスタマーハラスメントについても記載され、労災認定基準(精神障害認定基準)にカスタマーハラスメント記載が追記され、2023年12月には旅館業法改正によりカスタマーハラスメントを行う客の宿泊を拒否できる定めもされました。更に、2025年6月11日公布(公布の日から起算して1年6月以内に施行予定)された改正労働施策総合推進法第33条及び第44条に、カスタマーハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、カスタマーハラスメントに起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務を明確化しました。
従って、カスタマーハラスメントに対しては、企業者(使用者)が次のような法的義務を負っていることになります。
<1> 行政法上の義務
労働施策総合推進法上の使用者義務としてパワハラ防止・措置対応義務と同様に、カスタマーハラスメント防止・措置対応義務を負います。
<2> 民事上の義務
民事上の義務としては、使用者は労働者に対して労働契約法第5条による安全配慮義務を負っていますが、その義務の中にカスタマーハラスメント防止・措置対応義務が含まれることになり、カスタマーハラスメントを行う顧客に対して、組織的対応をせず、現場の一従業員に任せるだけで放置していた場合に当該従業員が精神的疾患になったり、職場環境の不備で退職したりした場合には、賠償責任等を負うことになります。
以上のとおり、カスタマーハラスメントは、単なるクレームではなく、悪質なクレーマー対策と同じ方策を取ることが求められます。上述した「不当要求対応マニュアル」に従った対応策や管理職等への対策の周知を行うことを講じておく必要があります。
最後になりますが、私たちは、無意識に、取引事業者又は顧客としての不満を相手に強くぶつけてしまうことがあるのかも知れません。常に、自分の言葉や行動を相手がどう感じて受け止めているかを、自ら想像して気付くように心がける必要があるように思います。
以 上
カスタマーハラスメントと法的問題(1)
(刑事問題、民事賠償問題、労働問題)
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
1.「カスタマーハラスメント」(Customer harassment)とは、Customer=顧客、 harassment=いじめや嫌がらせ、と訳されるもので、顧客や消費者からの度を超えた又は悪質なクレーム・要求のことです。略称で「カスハラ」と呼ばれることもあります。
このカスタマーハラスメントは、顧客においては、顧客の権利というよりも、逆に、顧客が刑事責任や民事賠償責任を負わされたり、職場環境を維持すべき会社が労働問題としての責任を問われたりするということへ繋がっていく問題となっています。
2.具体例(★どのようなことがカスハラになるの?)
カスタマーハラスメントには複数のパターンがあります。次のいずれかの特徴に当てはまった場合は、カスタマーハラスメントと判断してよいという例示が、多くのマニュアルで示されています。
| 類型 |
発言や行為の例 |
| 優位的地位の乱用(顧客や消費者として不合理な優遇を求める言動等) |
・「俺は客だ」「お客様は神様だぞ!」「あなたの対応次第では出るところに出る」などの発言
・ネットに書き込むなどネット炎上をちらつかせて、値引きやサービスを要求する
・企業や店舗側の人間が質問した際に「客の話が信用できないのか」「俺がお金を払っているのだから、質問する前に俺のためにやって当然だろ!」などの言いがかりで質問を遮断する |
| 不当・過剰・法外な要求・社会通念上相当の範囲を超える対応の強要・コンプライアンス違反の強要等 |
・安価な購入商品への高額な修理要求等、対価的に相当な範囲を超えた要求
・特別の利益や便宜の供与を求める要求
・法令違反の内容への対応要求
・暴行・傷害・強要・恐喝・脅迫・不退去・器物破損・威力・偽計業務妨害・侮辱・名誉棄損などの刑法違反
・一方的な主張の繰り返し(長時間又は多数回の渡る) |
| 職務妨害行為(就業環境または業務推進阻害行為等) |
・長時間にわたる担当者の拘束
・その場で解決できない事象への即時対応要求
・正当性のない担当者の交代要求
・虚偽の申し立て又は威圧的な申し立て
・就業時間後の担当者の拘束
・義務なき文書の提出要求(お詫びの書面を今すぐに書けという要求)
・大声を出す・暴れるなどの施設の平穏を害する言動
・同一・類似案件への執拗な対応(回答)要求や電話架電
・業務上必要な機器などを奪う・破壊する行為
・従業員の警告を無視する |
| 担当者の尊厳を傷つける行為(人格否定・意思決定権の侵害等) |
・暴言・誹謗中傷・侮辱
・個人的な責任追及(賠償・補償要求)
・「ネットに書き込むぞ」と言ったり、「今の時代はネット情報に上がると大変だぞ」というなど、個人情報のさらしなどをちらつかせること
・無許可での撮影や録音
・土下座や人格・尊厳を傷つける行為の強要(セクハラ・性的自由の侵害を含む)
・担当者の意に沿わないSNSなどによる連絡・返信の要求
・職場・通勤経路・自宅での「待ち伏せ」や「付きまとい」をはじめとした恐怖を与える行為
・必要以上の連絡先・個人情報などの開示要求
・嫌がらせ行為 |
3.クレームとの差異(★カスハラは、普通の苦情・クレームと、どう違うの?)
(1)高度成長・バブル期の昭和後半頃には、「お客様は神様」とのチャッチ・フレーズに象徴されるように、商品を買ってお金を出してくれる顧客は、企業者にとっては唯一の利益提供者であり、企業者は顧客の要求には従うべきであるという考え方や、商売において顧客満足を利益・採算などよりも重視すべきであるという顧客満足度を追及する考え方などの「顧客第一主義」が流行した時期がありました。
それは、近江商人が商売理念としてもっていた「三方良し」(買い手よし、売り手よし、世間よし)を元に、商売はまずは最初に買い手(顧客)のことを一番先に考えてあげよう(「お客様の喜びをまず生み出すことで社会に貢献しながら、我が社も潤う!」)という考え方であったにすぎません。
そのような場合には、顧客からの「クレーム」(和製英語Claim=自身の被った損害を説明して、その損害に対して責任のある相手に、損害の補償を要求することを意味する)にも、企業の改善点への貴重なご意見と捉える風潮もありました。
しかし、その後、そのような考え方を顧客側で「悪用」する例(客に刃向かうな。客の言うことは絶対に聞け。等)が増えてきました。
そもそも、顧客第一主義は、顧客が、消費契約取引上のルールや常識を守る顧客であることを想定していたものですが、消費契約取引上のルールすら守れない顧客層が出現するようになりました。
(2)厚生労働省は2022年に「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を作成しており、企業が従業員を守るために対応するべき課題の1つとしています。
そこでは、カスタマーハラスメントの定義として「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・様態が社会通念上不相当なものであって、当該手段・様態により、労働者の就業関係が害されるもの」と定められています。
このように定義上は、クレームとカスタマーハラスメントは、共通の場面ではありますが、社会通念上の妥当性・相当性の有無で区別される点で本質的には全く異なることになります。
① クレームは商品の向上・改善を目的とします。商品やサービスに対する『要求』や、『依頼』の形をとって伝えられる行為ですが、クレームは、商品やサービスをよりよいものにするために役立つ意見であり、正しく対処すれば顧客と企業の両方にメリットをもたらします。また、顧客の要求を受け入れることで解決できます。
② カスタマーハラスメントは、『嫌がらせ』を目的としています。どれも理不尽な嫌がらせや悪質ないじめ又は不当な要求行為になります。カスタマーハラスメントの場合には、顧客の要求を通せば通すほど次々と不当要求が続き、悪化していくので、初期の段階から拒否対応をするなどの適切な対処が求められることになります。
4.カスタマーハラスメントが生じる現代的背景(★なぜ、顧客の苦情が非常識になったの?)
(1)反社会的勢力と一般人のボーダレス化
社会的なルールを逸脱する犯罪的な不当要求を行うのは、従来は、暴力団や社会ゴロ集団などの反社会的勢力の暴力プロの連中が企業や商店に強硬な態様で行うことが多かったのですが、昨今は、反社会的勢力への取り締まりが強化され、そのような事案が少なくなった半面、一般人による過剰な態様や内容の不当要求が法的問題として多く生じるようになってきています。
一般人と反社会的勢力の区分け(線引き)ができなくなってきており、カスタマーハラスメントが生じる原因の一つとなっております。(これを「ボーダレス化」と言います)。
(2)SNSの普及による言いたい放題の風潮
SNSの普及で、それまでは公の場で自分の主張を発表する手段がなかった個々人が、「ものを言う」手段(携帯ネットワーク)を手に入れたことから「ものを言う社会」になっており、自分の主張や感覚を前面に押し出すことに慣れてしまい、逆にそれを受け入れてもらえないときには怒りが大きくなる傾向が出ていることもカスタマーハラスメントが生じる原因の一つです。
(3)接客側と顧客側の意識のずれ
企業で働く側に居る場合には、お客様第一で職務を遂行していた者が、定年退職して顧客側に回った場合に、自分の経験した接客レベルの対応を求めてしまう又は、顧客に苦労して対応した経験を忘れてしまうという問題があるようです。カスタマーハラスメントの相談を多く担当しているある弁護士の見解として「学者、上場企業役員又は管理職、弁護士、医師等、社会的地位の高い業務に携わった人ほどカスタマーハラスメントをしやすい傾向がある。」「高学歴の高齢者の方がカスタマーハラスメントをしやすい傾向がある。」という論評もあります。周囲から敬意を払われることになれている人が、そうでない扱いを受けた際に不満を感じ、カスタマーハラスメントに発展する例が多いようです。
それでは、次回に、カスタマーハラスメントについて、どのような法的責任が生じるかについてご説明することにします。(次回に続く)
以 上
「なるほど!」と思わせる裁判の判決(4)‐②
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
(僕の子じゃない事件)
事案の概要は、前回記載分を参照してください。
1.僕の子じゃない事件(前回)
2.子の認知の制度について(前回)
それでは、裁判例(東京家庭裁判所令和5年3月23日判決)を読んでみましょう。
3.本件の裁判例(東京家庭裁判所令和5年3月23日判決―判例時報2620―48 最高裁確定)
本件事例の裁判では、次のように判断されています。
(1) 被告(花子)は、ベトナム人A(マツ)が、ベトナム人B(タケ)との婚姻期間中に懐胎した子であるから、ベトナム法の規定により、被告(花子)は、ベトナム人B(タケ)の嫡出子であるところ、日本の民法下では、認知は現に父がある子を対象としてはすることができないと解されているから、原告(岩雄)が被告(花子)について行った胎児認知を有効なものと認めることはできない。
(2) また、日本の民法下で認知は、現に父がある子を対象としてはすることができないと解されている(最高裁平成26年1月14日判決寺田逸郎裁判官補充意見)のは、親子関係の公的な秩序として、父が重複することは許されるべきではないとする趣旨から出たものであると解される。
本件の事実関係の下では、実際問題として、ベトナム人B(タケ)が被告(花子)の父として取り扱われる可能性は、今後とも乏しく、原告(岩雄)が被告(花子)についてした胎児認知を有効なものとしたとしても、被告(花子)の父の重複が顕在化する事態が現実に生ずるとは直ちには想像し難い。
さらに、原告(岩雄)が被告(花子)の生物学上の父であることを争うことを明らかにしていないこと、原告(岩雄)は被告(花子)をベトナム人A(マツ)が、ベトナム人B(タケ)との婚姻期間中に懐胎した子であると認識しながら胎児認知の届出をしたと推認されること、原告(岩雄)自身が被告(花子)に対しその父として接してきていたこと、仮に胎児認知が無効であるとされた場合には、被告(花子)は日本国籍を喪失するなどして過酷な状況に置かれると想像されること、原告(岩雄)が被告(花子)に対して、胎児認知が無効であることの確認を求めるに至った動機は、ベトナム人A(マツ)が原告(岩雄)以外の男性との交際に及んだことに対する意趣返しにあったとも疑われることなどの事情を挙げて、原告(岩雄)の被告(花子)に対する胎児認知無効確認請求は、これを許すことには正義公平の観点から見て看過することのできない疑問が残るものであって、権利の濫用に当たり、許されない。
4.「なるほど!」の説明
(1) 親子関係を発生させる認知を無効にして親子関係を失くすには、条文上は「認知について反対の事実があることを理由とすれば」認められることになります。「認知についての反対の事実」とは、認知が親子関係(特に父子関係)を発生させる以上は、生物学上、自分の精子による子ではないとする事実(他の男性の精子による子供であるという事実)が典型的なものになります。
この点、本件判例でも、「被告(花子)はベトナム人A(マツ)がベトナム人B(タケ)との婚姻期間中に懐胎した子であるから、ベトナム法の規定により、被告(花子)はベトナム人B(タケ)の嫡出子である」との認定をしていますから、本来は、「認知について反対の事実」があるわけですから、認知無効の結論になるはずです。
(2) しかしながら、法的な親子関係は、子供の養育・成長を伴う親子間の義務や権利を発生させるものであり、また、他人提供の精子を利用した生殖による親子関係は、婚姻している男女間に発生し、精子提供者との間には親子関係は発生しないとされていること(令和2年12月成立の「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」による)などから、必ずしも遺伝生物学的な親子関係だけで判断されるべきものではないとされています。
そこに、最高裁判所平成26年1月14日判決にいう「認知を受けた子の保護の観点からみても、あえて認知者自身による無効の主張を一律に制限すべき理由に乏しく、具体的な事案に応じてその必要がある場合には、権利濫用の法理などによりこの主張を制限することも可能である」との認知無効の制限がなされる根拠があるわけです。
(3) かかる権利濫用による権利制限として、原告(岩雄)の認知無効の主張が認められなかった理由を整理すると次のようになります。
① ベトナム人B(タケ)はベトナムに帰国したままであり、被告(花子)の父として取り扱われる可能性は今後とも乏しく、被告(花子)の父親が重複する可能性はないこと。
② 原告(岩雄)は、被告(花子)をA(マツ)がB(タケ)との婚姻期間中に懐胎した子であると認識しながら胎児認知の届出をしたこと。
③ 原告(岩雄)が、被告(花子)の生物学上の父であることを争うことを明らかにしていないこと。
④ 従来から原告(岩雄)自身が、被告(花子)に対しその父として接してきていたこと。
⑤ 仮に、胎児認知が無効であるとされた場合には、被告(花子)は日本国籍を喪失するなどして、過酷な状況に置かれると想像されること。
⑥ 原告(岩雄)が被告(花子)に対して、胎児認知が無効であることの確認を求めるに至った動機は、ベトナム人A(マツ)が原告(岩雄)以外の男性との交際に及んだことに対する意趣返しにあったと推認されること。
権利濫用法理は、権利者が違法又は不適切な意思で権利行使をする場合に適用されることが多いのですが、⑥の意趣返し(仕返しをして恨みを晴らすこと)の意図で認知無効の裁判を起こしたのではないかという点は、かなり影響があったのではないかと思います。
また、本件の特殊事情として、被告(花子)は日本国籍を喪失するという不利益を子の保護の観点から回避してあげたということも考えてみると、「なるほど!」と思える判決だと思います。
以 上
「なるほど!」と思わせる裁判の判決(4)‐①
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
1.(僕の子じゃない事件)
(1)ベトナム国籍を有する女性であるA(マツ)は、平成14年から日本に滞在していたところ、平成15年にベトナムにおいて、ベトナム国籍を有する男性であるB(タケ)と婚姻の登録をして、日本でB(タケ)との同居を開始したが、平成17年6月頃にB(タケ)とは別居した。その後、A(マツ)は、同年10月頃までに日本国籍を有する男性である原告(岩雄)との交際を開始し、同年12月頃に原告(岩雄)との同居を開始した。この当時、原告はC(梅子)と婚姻関係にあったが、C(梅子)とは別居していた。
(2)A(マツ)は、平成18年、被告(胎児の花子)を懐胎している旨の診断を受けた。A(マツ)とB(タケ)は同年7月にベトナムの裁判所において合意による離婚の承認を受け、その後、原告(岩雄)は被告(胎児の花子)についての胎児認知の届出をして、受理された。そして、A(マツ)は被告(花子)を出産し、被告(花子)は、戸籍上、原告(岩雄)とA(マツ)との間の長女とされ、日本国籍を有するものとされた。また、B(タケ)は、その数年後に日本から出国した。
(3)被告(花子)は、1歳半になるまでベトナムに居住するA(マツ)の母に預けられていたことがあったほかは、日本で原告(岩雄)及びA(マツ)と同居していた。そうしたところ、A(マツ)は、令和2年6月頃に原告(岩雄)以外の男性との交際を開始し、同年8月頃に被告(花子)とともに原告(岩雄)と別居した。そのことに、原告(岩雄)は憤慨した。
(4)原告(岩雄)は、令和3年5月に被告を相手方とする認知無効確認調停を申し立てたが、調停が成立しないものとして事件が終了したことから、同年7月に本件訴えを提起した。
原告(岩雄)は、「令和3年2月頃になってA(マツ)とB(タケ)が平成18年7月に離婚していたことを知ったが、懐妊時にはA(マツ)は、B(タケ)と婚姻していたから、被告(花子)はB(タケ)の嫡出子であり、そもそも被告(花子)は“僕の子じゃない!”ということで、原告(岩雄)が被告(胎児の花子)についてした胎児認知は無効である」と主張した。
さて、一度、自分の子供であると男性が認知した場合に、その子供は自分の子じゃないと主張して、親子関係を失くすことはできるのでしょうか?
2.子の認知の制度について
(1)子の認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供(いわゆる非嫡出子)を、父(又は母)が、血縁上自分の子であると認めることです。実際には、父親が血縁上自分の子と認める場合が多いです。母親の場合は、裁判例で、原則として子供が産まれた時点で法的な親子関係が生じることになっています。(このことを、「母親であることは事実であるが、父親であることは信じることに尽きる」と表現する人もいます。)
また、認知の方法として、「俺の子だ。」と言っただけでは足りず、役所に認知届を提出する方法、遺言によって子を認知する方法(任意認知といいます)があります。
しかし、父親が任意に認知してくれない場合、母親は、家庭裁判所に認知調停を申し立てることができます。この調停において、当事者双方が、子が父親の子であることについて合意し、家庭裁判所が必要な調査をした上で、その合意が正当であると認められれば、合意に相当する審判が出されます。更に、父親が、調停中から認知に応じておらず、審判に対しても異議を申し立てた場合には、訴訟によって認知を求めることが可能です(強制認知といいます)。
(2)認知の効果
① 任意認知でも強制認知でも認知がなされると、子供の戸籍に父の名前が記載され、法的な父子関係があることになり、子が未成熟子であれば、母親は父親に対し、養育費の支払を求めることができます。
② また、外国籍の母親から生まれた場合には、父又は母が日本国籍である場合には、国籍法第2条で、子供は日本国籍を取得できますが、父親がわからず、外国籍の母親だけの場合には、日本国籍は取得できませんが、日本国籍を有する父親が認知してその子の父親となった場合には、国籍法第2条の定める「父又は母が日本国籍である場合」に該当しますので、子供は日本国籍を有することにもなります。
(3)認知の無効について
① 子の認知については、実際には、自分の子供でない場合であっても、円満な家庭生活を送る目的で、ⅰ)自分の子供だと信じて認知する場合や、あるいは、ⅱ)自分の子供ではないことを分かりつつ、円滑な生活を送ることを優先して、認知する場合などが多くあります。このような場合、逆に、妻と離婚する場合や、内縁を解消する場合に、子供との関係も解消するべく、認知の無効を求める手続きが必要になります。子供との父子関係が継続すると、家庭関係の消滅後の新たな生活を始めようとしても、その後に、養育費の支払い責任や、相続の問題が生じてしまうからです。そこで、民法第786条は、認知の無効の訴えという制度を用意しています。
② 民法第786条(認知の無効の訴え)は次のように定めています。
「次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める時(第七百八十三条第一項の規定による認知がされた場合にあっては、子の出生の時)から七年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができる。ただし、第三号に掲げる者について、その認知の無効の主張が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
一 子又はその法定代理人 子又はその法定代理人が認知を知った時
二 認知をした者 認知の時
三 子の母 子の母が認知を知った時 」
この規定によって、認知をした男性は、「反対の事実があることを理由として」認知の無効の訴えを提起することで、認知が無効であることを判決で確定させ、父子関係が存在しなかったことを確定させられます。
③ ところで、自分の子供ではないことがわかっていながら認知をした場合に、後から認知の無効を主張することは許されるのでしょうか?本件の原告(岩雄)の請求の最も問題とされる点です。
この点については、次のような最高裁判例(最高裁判所平成26年1月14日判決―民集68-1-1、判例時報2226-18)があります。
「血縁上の父子関係がないにもかかわらずされた認知は無効というべきであるところ、認知者が認知をするに至る事情は様々であり、自らの意思で認知したことを重視して認知者自身による無効の主張を一切許さないと解することは相当でない。また、血縁上の父子関係がないにもかかわらずされた認知については、利害関係人による無効の主張が認められる以上(民法第786条)、認知を受けた子の保護の観点からみても、あえて認知者自身による無効の主張を一律に制限すべき理由に乏しく、具体的な事案に応じてその必要がある場合には、権利濫用の法理などによりこの主張を制限することも可能である。」
結局、「自らの意思で認知した」という理由だけで認知無効の主張を許さないということはできないが、認知を受けた子の保護を図る必要があるなどのその他の事情により認知無効の主張を許さないとすることもあるという折衷的な立場です。
どうでしょうか?
次回は、東京家庭裁判所令和5年3月23日判決を紹介して解説をしていきたいと思います。
以 上
「なるほど!」と思わせる裁判の判決(3)‐②
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
前回の見解とは反対の最高裁判例(令和6年3月26日判決)を読んでみましょう。
(2)最高裁令和6年3月26日判決―判例地方自治No514-67)
原審は、犯罪被害者等給金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第5条第1項第1号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」は、婚姻の届出ができる関係であることが前提となっていると解するのが自然であって、婚姻の届け出ができない同性関係にある者に犯罪被害者と同性の者が該当し得るものと解することはできない、と判断しているが、原審の上記判断は是認することができない。
その理由は、次のとおりである。
① 犯給法は、昭和55年に制定されたものであるところ、平成13年法律第30号による改正により目的規定が置かれ、犯罪被害者等給付金を支給すること等により、犯罪被害等(犯罪行為による死亡等及び犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族が受けた心身の被害をいう。以下同じ。)の早期の軽減に資することを目的とするものとされた(平成20年法律第15号による改正前の犯給法第1条)。
その後、平成16年に、犯罪等により害を被った者、及びその遺族等の権利利益の保護を図ることを目的とする犯罪被害者等基本法が制定され(同法第1条)、基本的施策の一つとして、国等は、これらの者が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、給付金の支給に係る制度の充実等必要な施策を講ずるものとされた(同法第13条)。
そして、平成20年法律第15号による改正により、犯給法は、犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族等の犯罪被害等を早期に軽減するとともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため、犯罪被害等を受けた者に対し犯罪被害者等給付金を支給するなどし、もって犯罪被害等を受けた者の権利利益の保護が図られる社会の実現に寄与することを目的とするものとされた(第1条)。また、平成13年法律第30号及び平成20年法律第15号による犯給法の各改正により、一定の場合に遺族給付金の額が加算されることとなるなど、犯罪被害者等給付金の支給制度の拡充が図られた。
以上のとおり、犯罪被害者等給付金の支給制度は、犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族等の精神的、経済的打撃を早期に軽減するなどし、もって犯罪被害等を受けた者の権利利益の保護が図られる社会の実現に寄与することを目的とするものであり、同制度を充実させることが犯罪被害者等基本法による基本的施策の一つとされていること等にも照らせば、犯給法第5条第1項第1号の解釈に当たっては、同制度の上記目的を十分に踏まえる必要があるものというべきである。
② 犯給法第5条第1項は、犯罪被害者等給付金の支給制度の目的が上記①のとおりであることに鑑み、遺族給付金の支給を受けることができる遺族として、犯罪被害者の死亡により精神的、経済的打撃を受けることが想定され、その早期の軽減等を図る必要性が高いと考えられる者を掲げたものと解される。
そして、同項第1号が、括弧書きにおいて、「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」を掲げているのも、婚姻の届出をしていないため民法上の配偶者に該当しない者であっても、犯罪被害者との関係や共同生活の実態等に鑑み、事実上婚姻関係と同様の事情にあったといえる場合には、犯罪被害者の死亡により、民法上の配偶者と同様に精神的、経済的打撃を受けることが想定され、その早期の軽減等を図る必要性が高いと考えられるからであると解される。しかるところ、そうした打撃を受け、その軽減等を図る必要性が高いと考えられる場合があることは、犯罪被害者と共同生活を営んでいた者が、犯罪被害者と異性であるか同性であるかによって直ちに異なるものとはいえない。
そうすると、犯罪被害者と同性の者であることのみをもって「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当しないものとすることは、犯罪被害者等給付金の支給制度の目的を踏まえて遺族給付金の支給を受けることができる遺族を規定した犯給法第5条第1項第1号括弧書きの趣旨に照らして相当でないというべきであり、また、上記の者に犯罪被害者と同性の者が該当し得ると解したとしても、その文理に反するものとはいえない。
③ 以上によれば、犯罪被害者と同性の者は、犯給法第5条第1項第1号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当し得ると解するのが相当である。
以上と異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり、上告理由について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れない。そして、上告人が本件被害者との間において「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当するか否かについて、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。
(判例の解説)
この最高裁判決は、同性婚パートナーが、犯給法に基づく遺族給付を受けられるかが争われた訴訟について、「同性パートナーも犯罪被害者給付金の支給対象になりうる」との判断を示したものであり、「支給対象にならない」とした二審・名古屋高裁の判決を破棄したものです。
それは、犯給法が、遺族給付金の支給対象となる「配偶者」について、婚姻届を出していなくても「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」を含むと定めているが、この規定に同性婚パートナーも含まれうる。」と、最高裁が初めて判断した判例になります。
4 なるほど!と思うための基礎知識
(1)この裁判が提起されるまでのLGBTQに関する考え方(LGBTQとは?)
皆さんは、「LGBTQ」という言葉は聞いたことがあるでしょうか?
従来は、LGBTという単語で略称されていましたが、現在では「LGBTQ」という単語に変わってきています。
さらに、「LGBTQ I(アイ) A+」という言葉も聞かれるようになりました。
因みに、I…Intersex(インターセックス:身体的性において男性と女性の両方の性別を有している)とA…Asexual(アセクシャル:どの性にも恋愛感情を抱かない)が加わってきています。その、LGBTQとは、同性愛者やトランスジェンダーなど性的少数者(セクシュアルマイノリティ)を指す言葉として使われています。
L=レズビアン(Lesbian)、G=ゲイ(Gay)、B=バイセクシュアル(Bisexual)、 T=トランスジェンダー(Transgender)、Q=クィアまたはクエスチョニング( Queer/Questioning)(=性的指向・性自認が定まらない人)、これらの英語の頭文字から構成されている言葉です。
なお、レズビアン(Lesbian)は女性同性愛者、G=ゲイ(Gay)は男性同性愛、バイセクシュアル(Bisexual)は、異性愛や同性愛のように対象となる性別が1つに限定されず、男女両方に魅力を感じる方の場合、トランスジェンダー(Transgender)は、性自認(こころの性)と身体的性(からだの性)が一致していない方の場合ということになります。クィアまたはクエスチョニング(
Queer/Questioning)は、性的指向・性自認が定まらない方を意味する言葉になります。
トランスジェンダー(Transgender)に関して、医療的治療が必要な場合には「性同一性障害者」と呼ばれる場合もありますが、2022年(令和4年)に 性同一性障害という言葉が国際的な医療診断基準から消えており 、病気や障害ではないということにも留意する必要があります。
このような実情において、同性間の婚姻関係への法的保護が図られるかということが法律上の問題として提起されるようになりました。
まず、法的な婚姻届出ができない代わりに、地方自治体からのパートナーシップ証明書の交付して、一定の法的保護を図ろうという動きがあります。
このパートナーシップ証明を受けている場合の同性婚の夫婦の相互の権利が、法的保護の対象になるかという観点で、女性同士の同性婚をして、地方自治体からパートナーシップ証明書の交付を受け、円満な共同生活を続けていたX子とA子に対して、男性BがA子と男女関係を結び、X子とA子との同性婚共同生活が破綻したという事案において、X子から男性Bに対して(不貞行為)慰謝料請求を認めた判例(東京高裁令和2年3月4日判決(原審:宇都宮地裁真岡支部令和元年9月18日判決))があり、同性婚も一定の法的保護を受けられるという傾向にあります。
しかしながら、『公的給付制度における「配偶者」性による受給権まで保障されるかどうか』については、次に示すように肯定説、否定説の両説があります。
A 肯定説(参考)
内縁法理は、単に経済的弱者を保護するための制度と捉えられるべきものではなく、広く、種々の理由から法律上の要件を満たさないために、婚姻の届出をすることができない者に対しても及ぼし得るものとされている。
すなわち、〈ア〉婚姻適齢に達していない場合、〈イ〉再婚禁止期間中である場合といった、時の経過によって婚姻障害事由が消滅する場面において、内縁法理による保護が及ぶのはもとより、〈ウ〉重婚の禁止や〈エ〉近親婚の禁止にそれぞれ抵触する場合など、公序良俗との抵触や倫理性の点に疑義がある場合であっても、少なくとも一定の事例では、内縁法理による保護が及ぶことは判例上確立した法解釈である。
このように、公序良俗との抵触や倫理性の点に疑義がある場合であっても、内縁関係としての保護が及ぼされている状況に照らせば、同性間の共同生活関係についても、公序良俗との抵触や倫理性の点に疑義がない以上、内縁関係として保護されるべきであることは当然である。
なお、内縁関係の定義において「夫婦」という用語が用いられることがあるが、これは、同性婚〔同性間の婚姻〕が想定されていなかった時代の名残であり、また、これまで同性間の共同生活関係が内縁関係に該当するか否かが争われた事例がなかったからにすぎず、同性間の共同生活関係を除外する趣旨ではないとみるべきである。
B 否定論(参考)
「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」とは、いわゆる内縁関係にあった者をいい、具体的には、当事者間に社会通念上夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があり、かつ、当事者間に社会通念上夫婦の共同生活と認められるような事実関係が存在する必要がある。
① 民法においては、婚姻により配偶者の関係にあるものは「夫婦」とされており、同法第739条、第750条等によれば、「夫婦」とは、夫と妻という両性の関係を前提とする概念であると理解されるのであって、現に同法第731条においても「男」、「女」という表現が用いられている。
② 戸籍法第74条に基づく婚姻の届出の様式(戸籍法施行規則第59条、附録第12号様式)においても「夫になる人」、「妻になる人」の記載が必要とされている。
③ これらのことからすると、現行法上、婚姻は異性間で行われることが前提となっているものと解され、犯給法にこれと異なる趣旨の規定は存しない。そうすると、「事実上婚姻関係と同様の事情」として位置付けられる内縁関係も、当然に異性間の関係であることが前提となるから、同性間の関係がこれに包含されることはあり得ず、これに反する立論は、いかに国民の意識等を背景としているとしても、立法政策論の域を出ないというべきである。
現在、種々の形で同性パートナーが異性の場合と同様に保護されている旨を指摘するが、原告が指摘する制度は、同性間の共同生活関係を婚姻関係と同様に扱うというものではなく、事実上の配慮として同性間の共同生活関係について一定の利益を付与するものにすぎないから、同性間の共同生活関係において婚姻の意思や婚姻としての実態が認められるという社会通念が形成されているとはいえない。
<なるほど!と思うところ>
(1)男女の内縁関係も戸籍上の届出の有無という形式的判断ではなく、生活上の実態を見て「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」であるかどうかの判断をしているのであれば、同性婚姻で戸籍上の届け出のできない場合も、事実上婚姻関係と同様の事情が実質的にあるかどうかで判断してよいのではないかと考えています。その意味で、この名古屋地裁・令和2年6月4日判決の結論(その控訴審である名古屋高等裁判所判決・令和4年8月26日判決―法学セミナー68巻1号128頁:―判例地方自治N0499-86も同様の結論)には反対の立場(最高裁の判断を支持する立場)になります。
(2)私が思うには、犯給法第5条第1項には「社会通念」との要件はないのであり、「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」か否かは、その文言どおり、被害者と申請者の関係についての個別具体的な事情に基づいて認定すべき事柄であると思います。「社会通念」によって、個別具体的な事情にかかわらず、同性であることの一点をもって定型的に「事実上婚姻関係と同様の事情」にないなどと判断することは許されないと考えます。
仮に、犯罪被害者給付金制度の保護範囲を画する上で「社会通念」という概念を用いるのであれば、同性事実婚の当事者が「社会通念上、犯罪被害者と親密なつながりを有するものとして犯罪被害者の死亡によって重大な経済的又は精神的被害を受けることが想定されるといえるか否か」という基準によって判断されるべきであるでしょう。
また、仮に同性間と異性間の共同生活関係についての社会通念を問題とするとしても、「同性間の共同生活関係が異性間の共同生活関係と同視し得るものであるとの社会通念が形成されているか否かが問題とされるべきであり、同性パートナーの共同生活関係を異性間の婚姻関係と同視し得るとの社会通念が形成されているか否かという観点で判断すべきではないのではないかと思います。
(3)その点で、最高裁判例が、「事実上婚姻関係と同様の事情にあったといえる場合には、犯罪被害者の死亡により、民法上の配偶者と同様に精神的、経済的打撃を受けることが想定され、その早期の軽減等を図る必要性が高いと考えられるからであると解される。
しかるところ、そうした打撃を受け、その軽減等を図る必要性が高いと考えられる場合があることは、犯罪被害者と共同生活を営んでいた者が、犯罪被害者と異性であるか同性であるかによって直ちに異なるものとはいえない。」している点は、愛する配偶者や家族が死亡した精神的打撃やその後の生活不安が生じることについて、同性婚と異性婚とで差が生じるわけではないことを指摘しているものであり、「なるほど!」と思えるところです。
以 上
「なるほど!」と思わせる裁判の判決(3)‐①
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
1 犯罪被害者給付金とLGBTQ
(事件の概要)
(1)原告(男性)と本件被害者(男性)は、平成6年頃に知り合って交際するようになり、その頃から約20年間同居して生活していた。
(2)(本件殺害行為)原告と交際していた本件加害者は、平成26年▲月▲日、原告と本件被害者との関係が継続しているために、原告を独り占めすることができないなどと考え、本件被害者に対して殺意を抱き、原告及び本件被害者の居宅において、本件被害者の左胸部を、持っていた洋出刃包丁で1回突き刺すなどし、本件被害者を出血性ショックにより死亡させた。
(3)原告は、平成28年12月12日、愛知県公安委員会に対し、「犯罪被害者の配偶者」(犯給法第5条第1項第1号)に当たるとして、犯給法第4条第1号所定の遺族給付金の支給の裁定を申請したが、愛知県公安委員会は、平成29年12月22日付けで、本件申請につき、遺族給付金を支給しない旨の裁定をした。
2 問題点
上記の事案に関しては、法律上、次のような条文の解釈が問題になります。
(1)まず、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「犯給法」という。)という法律があります。犯罪被害者等給付金とは、暴行傷害などの生命や身体を害する犯罪行為の被害に遭い、死亡や重傷病、もしくは後遺障害などの被害を受けた場合で、加害者が無資力であるなどの理由で、正当な損害賠償を受けられない被害者やその遺族は、国からの一時金として「犯罪被害者等給付金」の支給を受けることができます。遺族給付金は、令和6年6月15日以降は、最高額2,964.5万円~320万円の範囲で支給されます(本件事案に適用される、令和6年以前は最高額1,273万円~220万円の範囲での金額になります。)
第五条(遺族の範囲及び順位)
遺族給付金の支給を受けることができる遺族は、犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
二 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
三 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(2)問題は、この第一項の「事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に同性婚の場合も含まれるかという点です。更に、異性間の婚姻ではなく、同性間の婚姻(同性婚)をして婚姻届出を提出していないが、当該地方自治体からのパートナーシップ証明書の交付を受けている場合などがありますが、そのような場合であれば、諸給付を受けられる「配偶者」ということができるでしょうか。
本件の裁判所の判断は分かれました。一審及び二審は、同性婚の場合には犯罪被害者給付金の対象にならないとしましたが、最高裁判所は、同性婚の場合にも犯罪被害者給付金の対象になるとしました。皆さんにはどちらの判例がなるほど!となるでしょうか?
今回は、まず、一審・二審の判決を読んでおきましょう。
3 判例の判断
(1)名古屋地裁令和2年6月4日判決―判例時報2466―13及び名古屋高裁令和4年8月26日判決(控訴棄却―判例地方自治N0499-86)
(地裁判決骨子)
(ⅰ)(同性の犯罪被害者と共同生活関係にあった者が犯給法第5条第1項第1号の「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当し得るか否か)について
ア 犯給法は、犯罪行為により死亡した者の遺族又は重傷病を負い、若しくは、障害が残った者(遺族等)の犯罪被害等を早期に軽減するとともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるようにするため、犯罪被害等を受けた者に犯罪被害者等給付金を支給するものである(第1条、第3条)。
また、重大な経済的又は精神的な被害を受けた遺族等が発生した場合には、当該遺族等を救済すべきとする社会一般の意識が生じるが、他方で実際には、不法行為制度の下での損害賠償等により救済を受けられない場合が多く、その状況を放置した場合には、法秩序に対する国民の不信感が生じる。このことから、社会連帯共助の精神に基づき、租税を財源として遺族等に一定の給付金を支給し、遺族等の経済的又は精神的な被害を緩和するとともに、国の法制度全般に対する国民の信頼を確保することを目的とするものと解される。
イ ① 犯給法第5条第1項は、遺族に支給される遺族給付金の支給範囲を、犯罪被害者の配偶者とした上、その配偶者に「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」を含むものとしている。
このような犯給法第5条第1項の規定内容からすると、犯給法は、民法上は法律婚主義が採用されていることから(第739条第1項)、一次的には死亡した犯罪被害者と法律上の婚姻関係にあった配偶者が遺族給付金の受給権者とされるべきであるものの、前記のような犯給法の目的に鑑み、死亡した犯罪被害者との間において法律上の婚姻関係と同視し得る関係を有しながら婚姻の届出がない者をも保護しようとするものであると解される。
そして、①前記のとおり、犯給法の目的が、社会連帯共助の精神に基づいて、租税を財源として遺族等に一定の給付金を支給し、国の法制度全般に対する国民の信頼を確保することにあることに鑑みると、犯給法による保護の範囲は社会通念により決するのが合理的であること、②犯給法第5条第1項第2号、第3号に掲げられた親子、祖父母、孫や兄弟姉妹といった親族は、社会通念上、犯罪被害者と親密なつながりを有するものとして犯罪被害者の死亡によって重大な経済的又は精神的な被害を受けることが想定される者であり、これらと並んで同項第1号に掲げられている「配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)」に該当する者についても、同様の者が想定されていると考えられることからすると、同性の犯罪被害者と共同生活関係にあった者が犯給法第5条第1項第1号の「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当するためには、同性間の共同生活関係が婚姻関係と同視し得るものであるとの社会通念が形成されていることを要するというべきである。
② この点につき、原告は、重婚的内縁や近親婚的内縁といった、法律上婚姻が認められていない類型における内縁関係にあった者についても「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当し得ることは解釈として確立していることを指摘した。そうである以上、特に法律上禁止されていない同性間の共同生活関係は、当然に内縁関係として保護されるべきであり、同性同士で共同生活関係にあった者は「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当し得るという趣旨を主張する。
確かに、①重婚的内縁の場合、戸籍上届出のある配偶者との婚姻が事実上の離婚状態にあるときや、②近親婚的内縁の場合、近親者間における婚姻を禁止すべき公益的要請よりも犯給法の目的を優先させるべき特段の事情が認められるときには、そのような関係にあった者は、それぞれ「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当する余地があるものと解される(①につき、最高裁昭和54年(行ツ)第109号同58年4月14日第一小法廷判決・民集37巻3号270頁参照、②につき、最高裁平成17年(行ヒ)第354号同19年3月8日第一小法廷判決・民集61巻2号518頁参照)。しかしながら、重婚や近親婚は、婚姻に該当することを前提とした上で、これを認める弊害に鑑み、政策的に法律婚としては一律に禁じられているものである。それゆえ、個別具体的な事情の下で、婚姻を禁ずる理由となっている弊害が顕在化することがないと認められる場合には、法律婚に準ずる内縁関係としての要保護性まで否定する理由はないとの判断が働き、そのような場合の内縁関係は法律婚に準ずるものとして保護されるものと解される。これに対し、同性間の共同生活関係については、政策的に婚姻が禁じられているというのではなく、そもそも民法における婚姻の定義上、婚姻に該当する余地がないのであるから(なお、この解釈自体については、原告も争うところではない。)、重婚や近親婚の場合とは自ら局面を異にしているといわざるを得ない。
したがって、重婚的内縁や近親婚的内縁が一定の場合に内縁関係として保護されるとしても、同性間の共同生活関係が内縁関係に含まれる理由となるとは解されない。
ウ 同性間の共同生活関係に関する理解が、社会一般に相当程度浸透し、差別や偏見の解消に向けた動きが進んでいるとは評価できるものの、同性間の共同生活関係を我が国における婚姻の在り方との関係でどのように位置付けるかについては、同性パートナーシップに関する公的認証制度を設ける地方公共団体は多数に上る。しかしながら、その契機となった渋谷区条例が制定されてから本件処分当時までは、約2年が経過していたにとどまり、現在においても依然として、相当数の地方公共団体においては同性パートナーシップに関する公的認証制度は設けられていない。また、地方公共団体や民間企業における人事関連制度や民間企業における各種サービスの下で同性間の共同生活関係を異性間のものと同様に扱う取組も依然として地方公共団体や民間企業に広く浸透しているとはいい難く、いまだ社会的な議論の途上にある。本件処分当時の我が国において同性間の共同生活関係を婚姻関係と同視し得るとの社会通念が形成されていたということはできない。
エ 結論
本件処分当時の我が国において、同性の犯罪被害者と共同生活関係にあった者が、犯給法第5条第1項第1号にいう「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当するとまではいえない。
どうでしょうか?納得できますか?
次回は、これとは反対の結論を出した最高裁令和6年3月26日判決を紹介して解説をしていきたいと思います。(次号では、LGBTQの説明もいたします。)
以 上
「なるほど!」と思わせる裁判の判決(2)
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
(酔っぱらって内定取消事件)
(1) A男(34歳)は、勤務していた商社を退職した後、転職先を探して、金属材料製品の輸出入・国内販売会社のY社東北支店の採用面接を受け、採用内定通知を受けた。採用前に、転居先を探す目的と勤務予定のY社東北支店見学を兼ねてY社東北支店を訪問した際に、A男が会食での交流を求めたことから、訪問日夕方からY社東北支店従業員等との歓迎食事会(酒席)が一次会、二次会、三次会として準備された。
(2) A男は、以下の時点で次のような発言又は態度であった。
ア 会社訪問時
被告への入社理由について、たまたま引っかかったから、ついでに受けただけである旨の発言をした、③Dが本件支店周辺での住居について話をしようとした際、それは飲み会で話すことであるなどと述べ会話を終わらせたこと、④敬語を使わず話をした。
イ 歓迎食事会時
被告Y会社従業員の肩に手を乗せて、それを支えに立ち上がる動作をし、一次会(座席)において当たり前のように他の社員に酒を作らせていた。二次会(カラオケ付きスナック)において、Dに対して「D」と呼び捨てにし、原告の直属の上司になる予定であった被告従業員E(以下「E」という。)に対しても「E」と呼び捨てにするようになった。
また、前職を退職した理由について、自分としては会社の許可を得て大きな買い物をしたつもりであったが、問題になった際に、常務に全ての責任を押し付けられ、自ら会社を辞める結果となった旨述べ、被告から入社理由について尋ねられると、ついでに受けただけである、たまたま採用までのスピードが早かったため、入社することにした旨の発言をした。原告は、Eに対し、「自分が10億円の買い物をしたいと言った場合、許可してくれますよね」などと述べ、Eが社内決済ルールや意思決定の手順を理解し、遵守することが、組織である以上は重要であり、そのように言われたとしても許可することにはならない旨の説明をすると、原告は「10億じゃなくても1億ならOKですかね」、「とにかく自分はでかいことをやるということしか考えていないんです」などと発言した。
ほかにも、原告A男は、三次会への移動中、従業員Dに対して、「やくざ」、「反社会的な人間に見えるな」と発言した。三次会では、被告Y会社の従業員Eは、もう一人の従業員(G)とともに、原告A男に対して、組織で働くために社内のルールなどを守ること、独りよがりではなく社内で十分に協議した上で決定した会社の方針や、取引先のニーズに合わせて業務を行っていくことの必要性などについて説明したが、原告A男は、会社の方針が自分の考えと異なる場合、自分のやり方を通すのは当然であるという趣旨の発言をした。Eらは、原告A男に対し、被告Y会社にはY会社なりの方針があるが、それを無視してまでも自分のやり方を貫き通すつもりかと質問し、原告A男は「当たり前じゃないですか」と述べた。
このような原告A男の言動に対し、被告従業員が強い口調で叱責し、原告A男は「すみません」と述べて謝罪した。これをもって三次会は終了し、原告A男は宿泊していたホテルに戻った。
(3) 本件歓迎食事会の翌日になって、原告A男は昨夜の食事会で、被告Y会社の従業員から叱責されたことを踏まえ、従業員Dに対して架電し、謝罪するとともに、「昨日の記憶がないが、自分は何をしたのか」を尋ねた。Dは、原告A男に対し、本件会食時、原告A男が会社に言わなくてもいいようなことを言っていたと伝えた。原告A男は、Dに対し、「B支店長に謝罪したいので携帯電話の番号を教えてほしい。」と頼み、Dはこれを教えた。原告A男は、Dとの電話の後、B支店長に架電し、「昨日の記憶がない」旨伝えるとともに、謝罪した。
(4) Y会社では、本件会食時における原告A男の言動を問題視し、本件会食直後から、原告A男の本件採用内定を見直す必要があるのではないかとの協議をしていた。被告Y会社においては、本件支店の訪問及び本件会食に同席した被告従業員が集められて事実関係が聴取され、その結果、本件採用内定を取消すとの結論に至り、本件会食後の1週間後に、本件内定取消をした。
(5) それに対して、原告A男は、酒席でアルコールの影響下になる発言を理由とする内定取消は不当であるとして、労働契約が継続していることの確認を求める裁判を訴えた。
この「酔っぱらって内定取消事件」は、お酒を飲んで言いたいことを言ったら、会社に採用されなくなったという事例ですが、あなたが裁判官だったら、A男を可哀そうだと思いますか?それとも自業自得だと思いますか?
1,契約自由の原則
近代社会の特質として、私有財産の保障と自由経済主義がありますが、そのような特質を支える法原理として、「所有権の絶対の原則」と「契約自由の原則」があります。 「契約自由の原則」とは、当事者同士の自由な意思によって結ばれた契約は、法律に反しない限りその自由を尊重するという原則です。
契約自由の原則には、理念的根拠と実定法的根拠の2つの根拠があります。
1つ目の理念的根拠は、「私的自治」に求められます。人は自由で平等であるという法思想を受け、人は自分のことを自分で決められる社会であることから、誰かと契約を交わすことについても、自分で自分のことを決める「私的自治」が当てはまるためです。
2つ目の実定法的根拠は、民法上の根拠とも呼ばれ、民法第521条(「1 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。」)、民法第522条に由来します。これらの法律に、契約自由の原則は明文化されています。(ただし、すべてにおいて契約を自由にできるというわけではありません。法令に特別な定めがある場合以外について、契約を自由に交わすことができるという内容になっています。)契約自由の原則には、「締結の自由」「相手選択の自由」「内容の自由」「方式の自由」があり、「締結の自由」には、当然、締結しない自由も含まれることになります。
しかしながら、契約自由の原則といえども、一旦有効に契約が成立した後では、一方的に契約を破棄することはできません。有効な契約による拘束力が生じます。契約違反による債務不履行責任を負うことになります(民法第415条等参照)。
2,会社採用内定の法律的意味
(1)「会社に採用される」というのは、どういう契約をするということになるのでしょうか?民法第623条に、「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。」とありますので、会社と採用者との間で雇用契約を締結するという意味になります。さらに、民法の特別法である労働契約法第6条に「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」とありますので、最終的には、会社と採用者との間で労働契約を締結するという意味になります。
(2)会社や企業には労働者を採用する自由があるわけですが、その背景には採用しない自由もあります。採用試験を行って採用する者と採用しない者を区別する自由もあります。「採用内定」とは、一般的には、まだ正式に労働契約を締結する前で将来採用する予定の段階と理解されている面もありますが、労働法で用いられる「内定」とは、採用が内々で(当事者間だけで)決まることを指します。
採用内定通知段階で、内定取消事由が定められている場合もありますが、実際の労働提供が始まる前段階でありながら、労働契約が成立している状態であり、契約が成立している以上は、内定取消事由でもないのに、後で「予定変更で採用しないことになりました」というような、内定の取消は原則としてできないものになります。その意味で、採用内定の法律的性質としては、採用内定は、「採用内定取消事由が生じた場合は解約できる旨(留保解約権)の合意が含まれている就労始期付労働契約」ということになります。
(3)労働契約を締結し、採用された者が労働を提供し、使用者がこれに対して賃金を支払う関係が生じると、その労働契約の使用者側からの一方的解除(「解雇」と言われています)は原則としてできません。労働契約法第16条「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とされており、同法第17条では「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」と解雇の制限規定が定められています。これは、使用者に比べて労働する以外に生活していく手段を持たない労働者の生存の権利をより強く保障しようという法理念に基づくものです。
しかし、労働契約においても、「客観的に合理的な理由があり会通念上相当である場合」や「やむを得ない事由がある場合」には解雇できるということにもなります。
(4)そこで、労働契約が解除権留保状態で成立しているとされる「採用内定」段階においても、事前の内定取消事由に該当しなくても、他に、「客観的に合理的な理由があり社会通念上相当である場合」や「やむを得ない事由がある場合」には解雇に準じた「内定取消」ができるということになります。このことは、最高裁判例昭和54年7月20日判決―大日本印刷採用内定取消事件判決でも、同様に、「採用内定を取消せるのは、内定当時知ることができないか、知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認できるものに限られる。」としています。
そこで、問題としては、翌日になって記憶にないくらい酔って、調子に乗ってしまったA男の言動が、「採用内定を取消せるのは、内定当時知ることができないか、知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認できるもの」なのかどうか、が結論を左右する争点ということになります。
3,判例
東京地方裁判所令和4年9月21日判決では次のように判断されています。
・「原告A男は、本件会食時において泥酔しており、アルコールの影響下にあったから、そのことを考慮すべきである旨主張するが、被告Y会社従業員や二次会の店員が積極的に飲酒を勧めた事実はなく、また、原告A男に酩酊している様子はなかった(原告A男は会話できる状態にあり、一見して酩酊している状態ではなかった旨関係者が供述する上、原告A男は二次会の会場から三次会の会場まで歩いて移動していることを照らせば、原告A男が酩酊状態や、泥酔していたと認めることはできない)から、酩酊・泥酔状態であったかは疑わしい。その点を措くとしても、被告の従業員(特に営業職)に求められる資質等に照らせば、アルコールの影響下での言動であっても、社内ルール及びコンプライアンスを遵守する姿勢に欠ける言動、社会人としての礼節を欠く言動等をすることは、小規模な事業所における従業員同士の協調性を損なわせ、企業秩序の維持を困難なものとし、また営業業務の遂行に支障を来すものである。」
・「①DやEを呼び捨てにしたこと(二次会)、②被告への入社理由について、ついでに受けただけである、たまたま採用までのスピードが早かったため、入社することにした旨の発言をしたこと(二次会。前記のとおり、同旨の発言を本件会食前にもしている。)、③Dに対して、「やくざ」、「反社会的な人間に見えるな」と述べたこと(二次会から三次会への移動中)については、いずれも、被告従業員(上司や先輩に当たる。)に対して礼を失する行為であり、特に上記③の「やくざ」、「反社会的な人間」との表現は侮辱的なものであって、上司や同僚に対する発言として著しく不穏当で不適切であるというべきである。原告がかかる発言をしたことは、それが飲酒の上でなされたものだとしても、従業員同士の協調に反し、職場の秩序を乱す悪質な言動であるということができる。
また、①原告が、「自分が10億円の買い物をしたいと言った場合、許可してくれますよね」などと述べ、Eが社内のルール等を守ることが重要であると説明したことに対して、「10億じゃなくても1億ならOKですかね」、「とにかく自分はでかいことをやるということしか考えていないんです」などと述べたこと(二次会)、②上記発言を問題視したEらが社内のルールを守ることの必要性等を説明したのに対し、原告が、会社の方針が自分の考えと異なる場合、自分のやり方を通すのは当然であるという趣旨の発言をし、Eらが被告の方針を無視してまでも自分のやり方を貫き通すつもりかと質問したことに対しても「当たり前じゃないですか」と述べたこと(三次会)は、いずれも、原告において、被告の会社としての方針に従わない旨の態度を表明するものである。そして、前記のとおり、被告従業員のEらが、かかる言動をたしなめるような発言をしていたにもかかわらず、原告が態度を改めることなく、上記のような発言を繰り返したことを踏まえると、それが飲酒の上での出来事であったとしても、原告の言動は、会社の方針(社内ルール、コンプライアンスを含む。)を遵守して業務を行うという、被告従業員に求められる基本的な姿勢を欠くものであったということができる。
そして、社内ルールやコンプライアンスを遵守する姿勢は、被告の従業員である以上、当然に必要な資質であるといえることに加え、本件支店は18名で構成される小規模な事業所であり、業務の正常な遂行のために従業員同士の協調性が求められること、特に営業職においては、社内外と円滑なコミュニケーションを図る協調性が重要かつ最低限必要な能力として求められる上、取引先との関係性を円滑にするために月に数回の会食の場に参加することがあることから、会食の場での社会人としての最低限のコミュニケーション能力、礼節が求められること、被告においては、上記資質等を原告が備えているものとの判断の下、本件採用内定をしたことがそれぞれ認められ(乙7、証人B。なお、原告もかかる資質が必要なことについて一般論としては認めている。)、これらからすると、原告の前記言動は、これらの基本的な資質を原告が欠いていたことを示すものであって、かつ、被告はかかる資質の欠如を本件採用内定時には知り得なかったといえるから、これらの理由に基づいて本件採用内定を取消すことは、原告がB支店長及びDに対して架電して謝罪したことを踏まえても、解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認することができるというべきである。」
・「本件内定取消は適法である。(A男の敗訴)」
4,「なるほど!」の説明
原告A男は、本件歓迎食事会の翌日になって酔いが醒めて、昨夜の食事会で被告Y会社の従業員から叱責されたことを踏まえ、従業員Dに対して架電し謝罪しているのですが、筆者も過去の筆者自身の失敗例も思い出しながら敢えて言いますが、翌日になって記憶にないくらい酔って調子に乗ってしまって、自分の能力を誇示するために肝心な会社の方針を無視するという考えを吐露したということは、愚の骨頂ともいうべきことでしょう。
日本の社会では「酒の上のことだから許してやって欲しい」という飲酒の抗弁で許されるという考えが残っていますが、この裁判例では「アルコールの影響下での言動であっても、社内ルール及びコンプライアンスを遵守する姿勢に欠ける言動、社会人としての礼節を欠く言動等をすることは、小規模な事業所における従業員同士の協調性を損なわせ、企業秩序の維持を困難なものとし、また営業業務の遂行に支障を来すものである。」とか、「原告が採用内定を受けた営業職においては、会食の場においてもコミュニケーション能力や礼節が求められることは前記のとおりであるところ、飲み会の場において前記のような言動に及んだこと自体問題というべきである。」と厳しく判断されています。
採用すべき会社としては、採用予定者の酒の上での言動は、酒のお陰で当人の本性を知ることができたという意味で良かったのでしょうし、その点は、逆に採用される側からすれば、採用前の会社の接待食事会では、決して歓迎会なのではなく会社による採用適否の補充判断の場として設定されているという警戒心をもって臨む必要があるのではないかと思います。
本件裁判は、日本の社会では「酒の上のことだから許してやって欲しい」という、いわゆる「飲酒の抗弁」で許されるという考えは、もう通じませんよということを知らせる案件として、「なるほど!」と思わせる判決なのではないでしょうか。
以 上
「なるほど!」と思わせる裁判の判決(1)
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
1,(かぼちゃの天ぷら転倒事件)
原告であるA男(33歳)は、ある平日の午後7時頃、勤務先から帰宅途中に夕食を購入するため、当時の自宅から徒歩数分の距離にある本件スーパーマーケットB店舗に立ち寄った。
原告A男は、20分程で買い物を済ませ、2番通路又は3番通路からレジ前通路に向かった。
本件B店舗ではレジ台は1番から7番まであり、それぞれのレジ台の前には利用客が並んでいたが、原告A男から見て右方の1番レジ及び2番レジは比較的空いていたことから、原告は、そちらで精算しようとレジ前通路を歩行中、3番レジ前で床に落ちていた本件かぼちゃの天ぷらを踏んで左足が前に滑り、右膝を床に打ちつける形で転倒し、右膝打撲、膝内障(右膝後十字靭帯損傷、右膝蓋軟骨挫傷)の傷害を負い、これにより、治療費10万円と慰謝料105万円その他弁護士費用等を含めて合計147万0483円の損害を被ったとして、 本件B店舗に対して裁判を提起した。
なお、本件天ぷらは、B店舗のレジ台と反対方向の奥で、かぼちゃの天ぷらを含む惣菜類を種類別に大皿に盛って陳列しており、利用客自身が購入しようとする惣菜をトングで取り、惣菜売場に置かれているプラスチック製パック又は惣菜持ち帰り用袋に詰めてレジまで持参するという方法で販売していた。そのため、本件事故現場付近の床面に本件天ぷらを落としたのは、本件店舗の従業員ではなく利用客であり、それも転倒する直近に落としたものと認められる。本件天ぷらは、縦横それぞれ13cm、10cm程度と比較的大きく、利用客が目視することは容易な大きさであった。
この「かぼちゃの天ぷら転倒事件」、あなたが裁判官だったらB店舗に責任を負わせますか?それとも男性のお客様の不注意によるものとしてB店舗に責任は無いとしますか?
2,そもそも何が問題なのでしょうか?
(1)スーパーマーケットでは、商品販売のために店舗内で商品を自分で手に取って探す行為を認めており、一種の契約関係(商品販売契約と商品販売のための店舗内使用契約)にあります。その場合、スーパーマーケットは、お客様が店舗内で安全に商品を見定めることができるように配慮する義務(安全配慮義務)がありますし、その義務に違反して損害を与えた場合には「本旨に従った履行をしない」という債務不履行(民法第415条)として損害賠償義務を負うことになります。仮に、そのような契約関係がないとしても、スーパーマーケットとして自らの故意又は過失により第三者であるお客様に損害を与えた場合には、不法行為(民法第709条)として損害賠償義務を負うことになります。なお、第三者に安全配慮義務を負うような場合に、その安全配慮義務を怠った場合には、過失があるということになりますが、「過失」(又は「安全配慮義務違反」)が無い場合には、損害賠償責任は負いません。これを「過失責任の原則」(法的責任は故意又は過失がある場合のみに負うという原則)と言います。
(2)不法行為における「故意」と「過失」の意味
「故意」とは、意図してその結果(損害)を発生させることや、発生しても構わないという心理状態を指し、結果(損害発生)を意識的、無意識的に意図している点で過失とは異なります。
「過失」とは、結果(損害の発生)が予見可能であることを前提に、それを回避すべきであったにも関わらず、回避しなかったことをいいます。結果(損害の発生)を認識又は意識していない点で故意とは異なり、また、結果予見が不可能である場合や結果回避が不可能である場合の「結果責任」とも異なります。
そうすると、「過失」が認められるためには、「結果を認識していない」というだけではなく、その責任の前提として、結果が予見できたのに又は結果発生を回避することができたのに、結果発生を認識していなかったということが必要であるということになります。このことを過失責任の「結果予見可能性」「結果回避可能性」と言います。
(3)債務不履行又は不法行為における「過失」=「安全配慮義務違反」
上記(2)の過失の要素は、債務不履行又は不法行為における「過失」が「安全配慮義務違反」である場合も同様です。安全配慮義務違反というためには、安全配慮義務を果たせば結果発生を予見できた可能性があること、安全配慮義務を果たせば結果発生を回避できた可能性があることが必要になります。
これを本件「かぼちゃの天ぷら転倒事件」にあてはめると、「他の客が天ぷらを床に落とし、その天ぷらを他の客が踏んでしまって転倒する」という結果の予見可能性と回避可能性があったか否かが問題ということになります。
それは、細かく分析すると、スーパーマーケットB店舗従業員に、天ぷら販売箇所から離れたレジ前通路の床にかぼちゃの天ぷらが落ちているということの認識が可能であったか、あるいは、天ぷら販売箇所から離れたレジ前通路の床にかぼちゃの天ぷらが落ちるという予測可能性があったか、そのためのレジ前通路に従業員を常駐させ掃除、除去するという方法(回避方法)が可能であったかということを検討するということになります。
3,判例の見解
事例での一審地裁判決と二審高裁判決では結論が分かれています。法律の専門家である裁判官からしても、過失責任の有無の判断は難しいのだろうと思います。
(1)一審(東京地裁 令和2年12月8日判決―判例秘書LO7532011)
・「B店舗の惣菜の販売方法を採用する場合、利用客による惣菜のパック・袋詰めの仕方や運び方等に不備があり、惣菜を持ってレジに向かう途中で、誤ってレジ前通路の床面に惣菜を落とすことがあり得るのは容易に予想される。」
・「本件事故発生時のように、本件店舗が混み合い、相当数の利用客がレジ前通路を歩行することが予想される時間帯については、被告の従業員によるレジ周辺の安全確認を強化、徹底して、レジ前通路の床面に物が落下した状況が生じないようにすべき義務を負っていた。」
・「本件事故当時、本件店舗には26名程度の従業員が勤務しており、手の空いた従業員がレジ周辺の安全確認を行うことが人員不足により不可能であったとは認められないところ、レジ前通路に利用客が並んでいる中、従業員が同所に長時間滞在したり、頻繁に巡回したりすることは困難でも、レジ前通路の端の利用客が並んでいないところや、並んでいる利用客の後方(陳列台によって仕切られた通路の方)等から、レジ前通路の状況を目視により確認することで、利用客の邪魔にならない形でレジ周辺の安全確認を行うことは可能であった。」
・「但し、本件店舗の利用客である原告においても、レジ前通路を歩行するに当たり足元への注意を払うべきであり、そうしていれば、本件事故の原因となった本件天ぷらの大きさや床面の色との違い、原告の年齢(事故当時33歳)等に鑑み、落下物があることに容易に気付いて本件事故を回避し得たといえること、本件事故当時、原告は、鞄と買い物かごを持って両手が塞がった状態であったことなどを考慮すると,本件事故の発生については原告にも過失があり、その過失割合は5割である。」として本件店舗の過失責任を認めた上で、5割の損害だけの負担をさせました。
さてさて、この東京地裁の判断はどう思いますか?「なるほど!」って思われましたか?
次に、この地裁判決の控訴審判決(東京高裁 令和3年8月4日判決―判例タイムズ1501号90頁)を紹介します。
(2) 二審(東京高裁 令和3年8月4日判決―判例タイムズ1501号90頁)
・「要するに、控訴人が顧客に対する安全配慮義務に違反して、本件天ぷらを本件事故現場付近(本件店舗内レジ前通路上)に放置したといえるかが争点である。」
・「本件天ぷらは、縦横それぞれ13cm,10cm程度と比較的大きく、利用客が目視するだけでなく、足に触れたり、カートに当たったりする等して発見しやすい物であることが認められる。しかしながら、利用客からレジ内の従業員等に落下物があるとの申告、苦情等はなかったことからすると、本件天ぷらは、本件事故に近接する時点に落ちたものである可能性が高く、少なくとも長時間放置されていたものとは認められない。争点としては、利用客が本件事故現場(レジ前通路)付近に落とした本件天ぷらを短時間放置させたことが控訴人の安全配慮義務違反といえるかという点に集約される。」
・「本件店舗におけるかぼちゃの天ぷら等の惣菜の販売方法からすれば,惣菜売場においても、青果物売場と同様に落下物が比較的に多くなる可能性はあるが、これは飽くまでも売場付近での話であり、レジ付近の通路とは区別して考える必要がある。」
・「これまで他の店舗も含め、レジ付近で落下物による転倒事故が発生したことはなかったことが認められる。他方、レジ前通路を通行する利用客からは同通路は見通しがよく、同通路上に商品等の落下物があったとしても目に付きやすく、店舗内が混み合っている時間帯でも足下の落下物を回避することは特に困難なことではない。」
・「顧客に対する安全配慮義務として、あらかじめレジ前通路付近において落下物による転倒事故が生じる危険性を想定して、従業員においてレジ前通路の状況を目視により確認させたり、従業員を巡回させたりするなどの安全確認のための特段の措置を講じるべき法的義務があったとは認められない。」
4,「なるほど!」の説明
(1)東京高裁判決は、地裁判決が「レジ前通路の床面に物が落下した状況が生じないようにすべき義務を負っていた」「頻繁に巡回したりすることは困難でも、レジ前通路の端の利用客が並んでいないところや、並んでいる利用客の後方(陳列台によって仕切られた通路の方)等から、レジ前通路の状況を目視により確認することは可能であった」という抽象的な予見可能性等を認定しているのに対して、争点を「本件天ぷらを短時間放置させたこと」(本件事故は、客が天ぷらを落として間もない時間で、他の客が足を滑らせたという具体的な時間性を加えている。)に絞って、その具体的な状態の予見可能性と回避可能性を判断しています。他の客の購入商品が床に落ちたら、店舗従業員が直ちにそれに気づく監視体制や掃除体制を取ることはできない(結果回避可能性がない。)、ということで、B店舗の過失責任を認めなかったわけです。このことは、原告(怪我したお客)にとっては、床に落ちていたかぼちゃの天ぷらに気づかなかったという自分自身の不注意で怪我しただけですよ(本当は、天ぷらを落とした他の客の責任性が問題となる事案)という結論になってしまうわけです。
(2)そもそも、「過失責任の原則」に対しては、その反対概念として、「自己責任の原則」というのがあります。それは自分が怪我した場合には自分の不注意であり、自分だけの責任になるということです。世の中の大原則は、「自己責任の原則」「自己自治の原則」なのです。例外的に他人の責任を追及できる場合(責任転嫁の場合)がありますが、その場合には、他人に過失責任があることが必要になります。それが、「過失責任の原則」=他人過失責任の原則」ということです。
現在の日本においては、このような大原則の位置付けがあまり認識されないまま、他人が少しでも関わった場合には、まずは他人責任を追及するという風潮が見受けられます。法的知識や法的制度をある程度知った人ほどその風潮があるように感じます。世の中の報道も過失責任が認められて多額の賠償金を支払う裁判例のみが多く報道され、庶民の個々人的な賠償問題にレベルで裁判をしてみたけれど認められなかったという裁判例はあまり報道されません。そのことから、まずは他人責任を追及するという風潮が出てきていると思われます。しかし、現実的には、他人の過失責任が認められない裁判例も多くあるのです。
本件裁判は、世の中の危険は、自らの責任で予測し、回避するということを認識させる案件としては、この裁判は「なるほど!」と思わせる判決なのではないでしょうか。
以 上
ETCカードの家族間使用の問題点(その2)
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
4.ETCカードの兄弟間の使用と電子計算機使用詐欺罪の成否(判例)
(1) 大阪地裁判決令和6年5月8日法学セミナー2014-12月号
ⅰ> 事案の概要
暴力団員Aは、弟B(非暴力団員)名義のETCカードを利用して、暴力団員Cが運転する自動車に同乗し、2回に渡り高速道路を利用して高速利用代金の自動支払いをさせた。2回の利用とも、ETCカードは同居する弟Bの承諾を得ており、弟Bは自動車には同乗していなかった。
弟Bは、暴力団員AとCと共謀してETCカードを不正に使用したという電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)で逮捕された。
ところが、裁判では、ABCの弁護人は、電子計算機使用詐欺罪の「虚偽の情報」とは、「料金徴収に関する判断基礎となる重要な事実」であることが必要であり、ETCカードの場合にはその名義人の情報が重要な事実であって、その事実は本件の場合、正確な情報として使用しております。ETCレーン通過時に名義人本人が乗車しているかどうかの確認はされておらず「ETCカードの名義人が乗車しているとの情報」は重要な事実とは言えないので、ETCカード名義人が乗車しているかのように「虚偽の情報」を提供したとしても電子計算機使用詐欺罪は成立しないとして無罪主張をした。
これを、より分かりやすく説明すると、被告人側弁護人は、「家族間のカードの貸し借りは世間でも行われている」ので、車に同乗していない家族のカードを使うことが罪にあたるわけがないという主張を展開したわけです。
ⅱ> 争点
ETCカードを利用する際に、カード名義人Bが同乗していないのに、名義人B以外のA及びCが本件ETCカードを使用した場合には、電子計算機使用詐欺罪の「虚偽の情報」を与えたことになり、有罪として処罰されるか、が問題点として判断されました。
ⅲ> 判決内容(概要)
① 電子計算機使用詐欺罪の「虚偽の情報」とは、電子計算機を使用する当該システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らし、その内容が真実に反する情報をいうとされる。(東京高裁平成5年6月29日判決)
② 高速道路営業規則において、ETCカードによる料金の支払いはクレジットカード会社から貸与を受けている本人が乗車する車両に限られること、ETCの名義人以外によりETCカード使用に対してはETCカードによる支払いの停止等が予定されていることが確認でき、本件ETCカードに附帯されているクレジットカードのETC利用規則では、会員本人のみが利用可能であること、会員は本人以外の者にETCカードを貸与等することはできないことを踏まえると、ETCカードを使用できるのは名義人本人のみであることを明示していることになる。その上、クレジットカードに附帯するETCカードを使用する場合には、所定の審査を経てクレジットカードの発行を受け、ETCカードの貸与を受けた本人との間でのみ電子決済をすることが重要な前提とされていると言える。
③ そうすると、カード名義人である被告人Bが同乗していないのに、被告人A及びCが本件ETCカードを使用したことは、ETCシステムで予定されている事務処理の目的に照らして真実に反するから、『虚偽の情報』を与えたと言える。
④ そして、会員規約では、本件ETCカードの主たるカードであるクレジットカードは、名義人の承諾の有無にかかわらず、名義人でない者が使用することを許しておらず、名義人になりすまして使用した場合には詐欺の罪責を負うものとされており(最高裁平成16年2月9日判決)、暴力団員である被告人A及びCと本件ETCカードを使用させていた被告人Bに関しても共同正犯を認めるものの、主犯格の被告人Aに関しては「暴力団員との取引を拒絶する暴力団排除条項を潜脱するものであり、処罰に値するだけの「虚偽」性を有する(そのため、可罰的違法性が認められる)。」(被告人Aは懲役10ケ月実刑、B及びCは3年間執行猶予)
5.私論
(1) この判決(大阪地裁判決)は、ETCカードの使用につき、承諾を得た同居家族名義のETCカードを利用する場合でも、電子計算機使用詐欺罪になるという結論を導いていることになりますが、被告人弁護側が述べているように、「家族間のカードの貸し借りは世間でも行われているので、車に同乗していない家族のカードを使うことが罪にあたるわけがない。」という私たち一般人の利用実態とは異なるという印象が残ります。
しかし、本件の阪神高速道路は、ETCカードを使った料金の支払いについて、「クレジットカード会社から貸与を受けている本人が乗車する車両1台に限り行うことができる」と定めているということであり、法理論的には、名義人の承諾は、被害者の一人である金銭負担者の諸諾を得ている面はありますが、もう一人の被害者である「被欺罔者(騙された人)」としてのクレジットカード会社や道路管理者(阪神高速道路)の承諾を得ていない面が残っています。その点で、「全ての被害者の承諾」を得ていることにはなりませんので、犯罪成立及び違法性を阻却する事由が成立していることにはなりません。
(2) しかし、この判決(大阪地裁判決)は、最後まで検討すると、暴力団員である主犯格の人物(Aは暴力団組長)と暴力団員でないカード名義人を区別し、暴力団員であることとの関連で「可罰的違法性」を検討しています。
可罰的違法性(かばつてきいほうせい)とは、個別の刑罰法規が 刑事罰 に値するとして予定する 違法性 のことで、このような可罰的な質または量の違法性を有しない行為は構成要件に該当しないか、該当するとしても処罰に値しないというべきであるという刑法理論(可罰的違法性論)ですが、これを検討した結果、可罰的違法性がないということであれば犯罪は成立しないという結論を導くこともできます。
この点を考慮すれば、この判決(大阪地裁判決)は、暴力団員だったから(あるいは暴力団員と共犯だから)有罪として処罰するが、暴力団と関係の無い一般家庭内での承諾の得たETCカードの名義人以外の者の利用の場合には、可罰的違法性は無いとして犯罪不成立(無罪)となる余地を残しているものとも解釈できます。
(3) 最後に
前回の冒頭の検討課題への回答としては、「刑罰法規に違反し、電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)にあたる可能性があります」という結論になります。
ETCカードは、原則、本人名義のカードのみの利用となるため、自分でETCカードを発行しなければ使うことができないため、安易に家族や他人に貸与するという行為は控える必要があります。
また、クレジットカード会社の中には、家族カードと一緒にETCカードを発行する会社もあるようですので、それなりの工夫をしてETCカードを安全に利用することが必要です。
以 上
ETCカードの家族間使用の問題点(その1)
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
○(検討課題)Aさんは、家族のB(妻)名義のETCカードを使用して高速道路を利用して通勤していますが、これは法律違反になるのでしょうか?
1,ETCカードとは?
ETCとは、高速道路などの有料道路を利用する際に、料金所で停止することなく料金支払いが可能なノンストップ自動料金収受システムで、電子決済(キャッシュレス決済)の一種であるとされています。
電子料金収受システム(英語: Electronic Toll Collection System :エレクトロニック・トール・コレクション・システム)の 略称として「ETC」と呼ばれており、自動車にETC車載器を備え付けて、ETC付クレジット契約に基づき発行されるカードを差し込んで使用します。
運転手がクレジットカード会社にETCカードの発行を申請し、申請人名義のETCカードを交付してもらって、自動車のETC車載器に刺し込んだ状態で高速道路を利用すれば、通行料金は自動的にクレジットカード会社を通して、口座から引き落とされる仕組みになっています。
2,電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)
刑法第246条の2には、電子計算機使用詐欺罪として、「人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。」との定めがあります。
例えば、Aが他人(B)のクレジットカードを窃盗して、Aが他人(B)になりすまし、店舗で品物を購入する際に、Bのクレジットカードを使用すると、「Bの事務処理に使用する電子計算機の金銭支払いという事務処理に使用しているクレジットシステム(電子計算機システム)」に、「虚偽の情報若しくは不正な情報を与え(Bが使用していないのに、Bが使用したという虚偽の情報を与え、さらに、Bの電子計算機システムからBのお金を支払うという不正な情報と与え)」、その結果「財産上不法の利益を得た(Aはお金を支払う必要もなく品物を不正に得ることができた)」ということになり、電子計算機使用詐欺罪が成立します。
このことは、AがBのETCカードを窃盗して、B名義のETCカードを勝手に使用し、高速道路利用料金をBの口座から支払うようにした場合でも、同じように電子計算機使用詐欺罪が成立するということは理解できることだと思います。
この犯罪は、被害者Bを直接騙しているという詐欺ではなく、被害者Bとは別な「Bの事務処理に使用する電子計算機システム」を騙している詐欺であるというところに特徴があります。
つまり、欺罔相手と被害者が異なる場合の詐欺罪であるということです。
3,ETCカードの他人使用の問題点
(1)では、被害者(カード名義人)の事前の承諾を得たETCカード使用は、許されるのでしょうか。
皆さんは、家族間や友人間でお互いのETCカードを車に挿入した状態で、自動車自体を貸与したり使用させたりしていることはありませんか。
害悪の告知では、告知者(加害者)がその害悪の発生をコントロールできるものである必要があるかという問題があります。
このような行為は自分名義のETCカードを他人に使用させていることになりますが、法律的に問題はないのでしょうか?
(2)ETCカード利用に関するクレジット契約上での会員保障制度規定から、ETCカード利用に関するクレジット契約では、概ね、次のような規定をしています。
○当社は、会員及び使用者がETCカードを紛失・盗難により他人に不正利用された場合であって、警察並びに当社への届出がなされたときは、これによって会員が被るETCカードの不正利用による損害をてん補します。
○次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
(ⅰ)会員又は使用者の故意若しくは重大な過失に起因する損害。なお、会員又は使用者がETCカードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について、会員又は使用者に重大な過失があったものと見なします。
(ⅱ)会員の役員・社員、使用者の家族・同居人、ETCカードの受領に関しての代理人に よる不正利用に起因する場合
(ⅲ)紛失・盗難又は被害状況の届けが虚偽であった場合
このような定めは、①ETCカードは、本人(名義人)のみが利用可能であること、②会員は本人以外の者にETCカードの貸与等をすることはできないこと、③本人以外によるETCカードの使用についてはETCカードによる支払いの停止等が予定されていること、④ETCカードによる料金支払いはクレジット会社から貸与を受けているカードの名義人本人が乗車する車両に限られていること、が想定されているとされています(参照:大阪地裁判決令和6年5月8日法学セミナー2014-12月号)。
(3)以上の観点から、冒頭の検討課題の夫婦間でのETCカードの貸与や名義人以外の者のETC使用は、ETCクレジット契約上は問題があるということになりますが、「代理人による不正利用」ではなく、承諾を得た範囲での適正な利用の場合も禁止されているのかどうかの検討が必要になります。
そこで、次回は実際の判例を基に検討してみたいと思います。(次回へ続く)
以 上
「天罰が下る」脅迫事件
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
昨今は、SNSを通じて、自分の意見を匿名で自由に発信できる状況になっており、無責任かつ無秩序的な言動や他人への非難中傷の悪質な言葉が飛び交っている現状にあります。
これらは、刑法上の名誉棄損罪(刑法第230条)の他、脅迫罪(刑法第222条)にも該当することになりますので、今回は、葉書や手紙の文章の事案を例に、脅迫罪の基本的な知識についてお話ししたいと思います。
1 事案概要
(1) バイオリニスト(講師)のAは、演奏会を通じて聴講者として知り合った甲(年金受給高齢者)から、10年間程度CDや楽譜を送られたり、話をしたりすることがあったが、令和3年頃から、甲は、経済的に困窮していることをAに話すようになった。
最初に甲は、Aに葉書を書いて「今度の講演会後にお話があります。少し時間をください。」と依頼した後に、さらに手紙に「お金を借用したいと思います。金額は1万円です。いろいろありまして、別紙通帳のコピー(残額4,522円)を見ていただければわかると思います。お金というものがほとんどありません。」「前回は何とか生き延びましたが、今回は、先生の助けなくば生きていくということはまず無理でしょう。」「人間一人の生命を救えば、先生ご自身にも、また、何よりも愛娘のBさんの将来にも必ずや、よき事があるでしょう。」などと書いて送ってきた。
(2) その後、甲は、Aに対し、葉書や手紙などで「NO MONEY HELP ME」と書いて通帳コピー(残額67円)を送ったり、コンサートの後でAに対して、「Do you kill me or help me?」と問いかけたりした。その後、葉書で「もし非業の死に至らば、想像できかねぬような災禍と悲劇が襲うであろう。」とか「私が非業の死を遂げたらば、先生様とご家族が想定をはるかに超えた災難と悲劇に襲われるであろう。予言は必ず実現するものです。」と書き送るようになったが、Aは黙殺して対応することはなかった。
(3) 甲は、令和4年5月21日にAに対して、葉書に「殺害して天罰下る。自業自得。ご一家お揃いで奈落の底へどうぞ。」などと記載して送ったことから、刑法第222条の脅迫罪として取り調べを受け、起訴された。
*刑法第222条
「1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役(2025年6月1日以降は拘禁刑)又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」
2 脅迫罪の説明
刑法第222条による脅迫罪の成立要件は「本人や親族の生命、身体、自由、名誉または財産への害を与えることを告げること(害悪の告知)」と定められています。
例としては、「殺す」などの生命への害悪の告知、「財産を奪う」などの財産への害悪の告知、「公表するぞ」などの名誉への害悪の告知、「子供や家族を誘拐するぞ」などの自由への害悪の告知、「痛い目を見せてやる」「殴ってやる」などの身体への害悪の告知をして、被害者を「畏怖させる」ことが、それに該当します。
しかし、「脅迫」したかという行為面よりも「畏怖させる害悪の告知」といえるかという結果面からの客観的な判断がなされるので、通常の人が恐怖感を覚える程度の害悪の告知であることが必要です。
実際には被害者が恐怖を感じなかったとしても、被害者が害悪の告知の存在さえ認識していれば、「脅迫した」ということの故意の行為としての要件も認められる可能性がありますし、逆に、仲の良い友達同士で笑い合いながら話の流れで「痛め目を見せてやる」「絶対殴る」と言った場合、客観的に恐怖を感じるものではないと判断されます。
3 脅迫罪の解釈上の問題点
害悪の告知では、告知者(加害者)がその害悪の発生をコントロールできるものである必要があるかという問題があります。
たとえば、「1年後地震に巻き込まれて死ぬ」といった脅し文句は、一定の恐怖を感じさせるものの、地震などの害悪を告知者がコントロールできるものではないことから、脅迫罪の要件である害悪の告知とならず、脅迫罪も成立しないとされるのでしょうか。
この点については、刑法学説としては、「脅迫を構成する害悪の告知内容は、告知者が支配し得る将来の害悪であることが必要であり、天災や吉凶禍福の予告は脅迫に当たらない」としています。
判例も、「害悪を与える加害者は第三者であってもよいが、告知者が加害の有無に影響を与えうるものとして告知する必要がある」(最高裁昭和27年7月25日判決)とされていますし、「告知人が左右し得るものとしての害悪の告知内容になっていないから脅迫に当たらない」(広島高裁松江支部昭和25年7月3日判決)としていますので、「害悪の告知では、告知者(加害者)がその害悪の発生をコントロールできるものである必要がある」とする立場だと思われます。
4 本件事案の検討
(1) 一審裁判所(横浜地裁令和5年1月30日判決)
脅迫罪を無罪としています。
理由は、「殺害して天罰下る」の部分は、「Aが甲(被告人)を殺害すればAに天罰が下る」との趣旨であり、甲(被告人)はAに対して害悪を加える意図や認識は無かったし、「自業自得。ご一家お揃いで奈落の底へどうぞ。」の部分も、天罰が下った場合のAやその家族の行く末について述べたものとみるのが合理的であり、甲(被告人)が、Aに害悪を与える意図や認識をもって本件文言を用いたものではない」という理由になっています。
結局、一審裁裁判所は、甲の告知内容は、「天罰が下るという甲のコントロールできるものではないことの告知である」という評価をしているものと思われます。
(2) 二審裁判所(東京高裁令和5年11月28日―判例時報2600-104)
上記の第一審無罪判決を破棄して、有罪(懲役6月・執行猶予3年)としています。
理由は「脅迫の実行行為は、一般人にとって畏怖心を生じさせるに足りる程度の害悪を告知する行為であり、」「本件文言を検討すると、一般人であれば、「殺害」「自業自得」「ご一家お揃いで奈落の底へどうぞ」との文言それ自体により、自身が生じさせる何らかの原因のために家族ごと殺害されるかもしれないと畏怖するのが自然であり、「殺害して天罰が下る」との文言は、日本語の文章としては分かりにくいが、一般人がこれを読めば自身や家族が天罰によって殺害される趣旨と理解することも自然というべきであるからです。
現に、Aも被告人にお金を貸さなかったので、天罰が下って私たち家族全員が被告人甲から殺害されると受け取った旨証言しているし、被告人甲の本件葉書を郵送するまでの経過も考慮すれば、一般人の立場から客観的に見ても、本件行為は「畏怖心を生じさせるに足りる程度の害悪の告知と認められ、脅迫に該当するというべきである。」としています。
結局、二審裁判所は、甲の告知内容は、「天罰が下るという内容ではあるが、甲が何らか作出して甲がコントロールできる何らかの原因で殺害しようとしていることで、甲がコントロールできる害悪の告知」であると評価しているわけです。
5 最後に、
「言霊の幸わふ国」という美しい言葉があります。
万葉の世界の古代の人々は、「日本」を 「言霊(ことだま)の幸(さき)わう国」 と呼んでいました。
万葉集の柿本人麻呂の歌に、「磯敷島(しきしま)の大和の国は 言霊の幸(さき)わふ国ぞ ま幸(さき)くありこそ」という歌があります。これは、「この日本の国は、言葉が持つ力によって幸せになっている国です。これからも幸福であって平安でありますように」という意味ですが、遣唐使を見送る際の相手方の無事を祈る歌だということです。
万葉の世代の人々が言葉で表しているように、古代の人々は、言葉に霊力が宿ると考える 「言霊信仰」 を持っていました。美しい心から生まれる正しい言葉は、その言葉通りの良い結果が実現します。逆に、乱れた心から生まれる粗暴な言葉は災いをもたらします。本論考で説明した事例のように、悪い言葉で人を傷つけようとすると悪い結果としての刑罰を受ける結果になるわけです。
私たちは、美しく優しい言葉を交わして、平穏な「より良き」社会にしていきたいものです。
以 上
(お正月と法律シリーズ)年賀状と法律
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
1,正月には3つの解釈
「正月」とはいつのことを言うのかについて、①「1月の1ヶ月間」、②「三が日の3日間」、③「松の内(1/1~7)の7日間※関西は1/15まで」という解釈がありますが、まず、正月と言えば、初詣をしたり、おせち料理を食べたり、正月飾りを飾ったり年明けの行事を行う期間を指して正月と言います。
そういった意味で、多くの正月行事が行われる②『三が日』(正式には「正月三が日」と言います)を指すのは一般的でしょう。
次に、正月飾りを飾っている間や七草粥を食べたりして年賀状が届くまでの期間という意味では、③『松の内』が正月を指すのでしょう。
最後に、①の「1月の1ヶ月間」は通常の暦歴としてはあまり使用しないかもしれません。
2,年賀状作成と著作権
(1)日本では、正月7日間の松の内で年賀状のやり取りが行われておりますが、最近の携帯電話やインターネットでのメール送信手段が多用されるようになった現代では、紙媒体での年賀状による年賀挨拶は急激に少なくなり、企業では「年賀状じまい挨拶」をしている企業も多くなっているようです。
そのため、郵便局での年賀状売り上げ枚数も2003年の44億5000枚をピークに、2022年では16億8000枚程度に、2023年では14億4000枚程度に激減してきているようです(YahooJAPANニュース参照)。
(2)昨今、権利者やその代理人弁護士から突然損害賠償請求が来るという事例が多くなった「著作権」侵害の問題は、年賀状の場合にも考えられます。
年賀状の干支のイラストや綺麗な初日の出の写真等を、インターネットの「フリー素材」からダウンロードして年賀状に使用する例が多くなっていると思いますが、各企業や地方公共団体の行事案内等に利用したイラスト等に対して、著作権管理法律事務所等から損害賠償請求を受けている例が多く発生しています。
インターネットで検索すると、「無料でダウンロードOK」「編集・商用利用OK」「無料イラスト一覧」等の表示で、素材をたくさん表示しているものがありますが、フリー素材とは言っても、著作権はダウンロードサイト側にある場合が多いため、利用の際はダウンロードサイトまで入って、そこで著作権の表示などが無いかの確認が必要です。
特に、人気キャラクターなどのフリー素材は、「限られた使用にのみOK」と利用の範囲を設けているものも多いようですので、著作権の許可の範囲や利用規約の内容を必ず確認して使用するというのが基本になります。
(3)自分で撮影した家族の写真を転写した年賀状をもらった人は、微笑ましく楽しく頂戴することになりますが、自写ではなく、七五三や成人式に写真館で撮影してもらった写真は、自由に年賀状などに使っていいのでしょうか?
実は、写真を写真館から購入した場合でも、その著作権は撮影した側(写真館の撮影者)にある(著作権法第2条第1項第1号、第2号、第4項、第17条)ため、購入者は自由には使うことはできません。
あくまでも支払った代金は写真に対する代金であり、それを元に複製を行うことの使用料の意味は含まれていませんので、写真館の承諾を得ないで勝手に自分の年賀状に転写することは、原則として禁じられています(データで購入した場合も同様です)。
「私的使用のための複製」は著作権法第30条により法律でも認められているため、自宅用にコピーすることはできますが、年賀状のような多数の他人に印刷して配布する行為は、私的利用に該当しないので、原則的には法律違反になります。(但し、実際には黙認してもらっているのであって、それによって警告を受けたり、告訴されたりするケースは無いと思いますが、厳密にはNGだという認識を持っておいてください。)。
3,家族の年賀状を勝手に読むことは許されるか?
ところで、今度は年賀状を受け取る側での問題ですが、法律上、家族の年賀状を勝手に読むことはどのような問題になるのでしょうか。
(1)刑法第133条は、信書開封罪として「正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以上の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」と定めています。
これによれば、信書開封罪の成立要件は、「信書であること」「封をしてあること」「正当な理由がないこと」「開けたこと」が4つの要件が必要になります。
・「信書」とは、特定の発信人から特定の受信人に宛てた文書をいいます。必ずしも、郵便物として差し出されたことを必要としませんが、意思を伝達する文書であることが必要です。そのため、小包郵便物や単なる図面・写真などは「信書」にあたりませんが、他方、年賀状等の葉書文書は「意思を伝達する文書」ですから「信書」に該当します。
・「封をしてある」とは、封筒に入れて糊で閉じるなど信書の内容を外から分からないように作為して、かつ信書と一体をなした状態をいいます。年賀状等の葉書は該当しません。
・「開けた」とは、封を破って信書の内容を閲読可能な状態に置くことをいいます。現実に閲読したことは必要ではありません。この点で、年賀状等の葉書は該当しません。
・信書開封罪は親告罪です(刑法第135条)。親告罪とは、検察官が起訴するために告訴権者からの告訴を要する犯罪です。つまり、差出人や信書を受け取った後の受取人などの告訴権者が告訴しない限り、起訴されることはなく、刑事裁判にかけられることもありません。
従って、年賀状を親や家族などが勝手に読むことは、刑法上の犯罪にはなりません。
(*参考*)
郵便局配達員やアルバイト職員が、年賀状を盗み読みすることはどうでしょうか?この場合には、郵便法第80条に 『信書の秘密を侵す罪』として、『会社(郵便局)の取扱中に係る信書の秘密を侵した者は、これを1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する』と規定されており、同条第2項に『郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを二年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する』とされています。
信書には葉書も含まれ、「封をしてある」ことは要件になっておらず「秘密を侵した」ことが要件ですので、郵便法第80条違反として刑 事処罰を受けることになります。
(2)民法第709条は不法行為責任として、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定めています。個々人は、個々人として尊重され、自己の個人情報をコントロールする権利としてプライバシー権が認められています。
プライバシー権とは、私生活などの個人情報を、第三者にみだりに公開されない権利のことを指します。第三者には、自分以外の者、親や家族も含まれます。プライバシー権の侵害は、この不法行為に該当する可能性があります。
他人宛の葉書を勝手に読むことは、「他人の権利又は法律上保護される利益」として、このプライバシー権を侵害したことになるのでしょうか?
葉書は封書とは違って、記載された情報が物理的に開示されている方式での文書であることから、事前に他人に読まれることを承諾しているので「法律上保護される利益」とは認めないという考え方もあるでしょうが、必ずしも、他人に読まれることを「承諾している」とまで見做すことはできないと思います。
特に、「自分宛ての葉書は勝手に読まないで」と事前に禁止されている場合に、勝手に読むことは、その人のプライバシー権や保護すべき利益を侵害することになると考えます。
「年賀状」も同様に「誰から来たものか」「どういう内容を伝えて来たか」等はプライバシー性の強い個人情報である場合が多いので、年賀状を勝手に読むことは、不法行為になる可能性が高いと考えます。
4,「お正月の年賀状を楽しむ」方法について
年1回のお便りとして「年賀状」を親しい人たちに出すことで、受け取る人に喜びを与えることは間違いないでしょう。
相手への思いや親しみを込めた年賀状を送ることで、次に会った時の話も弾みます。 自ら相手に個人情報をお知らせするという意味でも「自分や家族の近況を書く」ことは、相手もうれしいことでしょうし、「相手や家族を思いやる言葉」や「お世話になっていることへの感謝」を書き添えるのも良いでしょう。
多くは「ご無沙汰していることのお詫び」の言葉を書き添えることになりますが、年賀状1枚だけでも 許してもらえるのではないでしょうか。
年賀状をもらう側としても、送り主の「健康でいること」「個人的情報を知ること」を通じて、思いが繋がっていることを楽しく思うことで、1年の良き始まりを感じることができるはずです。
「私の年賀状を勝手に見ないで」という言葉を使うことなく、家族団欒で、それぞれの年賀状を見せ合ってあれこれと話しながら、楽しい年の初めを過ごしたらいかがでしょうか。(その意味では法律が入り込む余地はないのだろうと思います。)
以 上
(お正月と法律シリーズ)皇室のお正月と法律
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
1,新年祝賀の儀や新年一般参賀が行われることは、新聞・テレビ等で報道されるので、皆さんにも知られているところですが、一般参賀は、皇居長和殿ベランダに皇族がお出ましになり、手を振られる儀式です。
新年祝賀の儀は、毎年1月1日、皇居において、天皇陛下が皇后陛下とご一緒に、皇嗣殿下をはじめ皇族方、衆・参両院の議長・副議長・議員、内閣総理大臣・国務大臣、最高裁判所長官・判事、その他の認証官、各省庁の事務次官など立法・行政・司法各機関の要人、都道府県の知事・議会議長、各国の外交使節団の長とそれぞれの配偶者から、新年の祝賀をお受けになる儀式です。「国事行為」たる儀式(日本国憲法第7条)とされています。
ところで、その儀式の前に、天皇陛下がどのように年始めを過ごされているかはあまり知られていないと思います。
天皇陛下は、1月1日の夜明け前に起床されて「四方拝」の皇室祭祀を行っておられるようです。四方拝は、夜明け前(午前5時半頃)、皇居の神嘉殿(しんかでん)の前庭において、黄櫨染御袍(こうろぜんのごほう)をお召しになった天皇が出御され、皇室のご先祖(皇祖神)である天照大神をお祭りする伊勢の神宮と四方(よも)の神々、歴代天皇の山陵を拝礼され、五穀の豊穣と国家の安寧を祈られるというものです(NHK出版生活人新書、皇室事典編集委員会編著『皇室事典 文化と生活』角川ソフィア文庫参照)。
四方拝が終わると、次に、宮中三殿に向かわれ、皇祖神である天照大神の分霊とされ、三種の神器の一つである八咫鏡(やたのかがみ)をお祭りする「賢所」、歴代天皇・皇族の霊魂をお祭りする「皇霊殿」、天神地祇をお祭りする「神殿」への拝礼を皇太子(現在は皇嗣)とともに行われますが、その頃、ようやく朝がしらじらと明け始める時間になるようです(京都産業大学・久禮旦雄准教授「News解説」参照)
2,法律上(憲法上)の天皇の行為について
天皇の行為については、憲法学の学説上は、①「国事行為」「象徴としての公的行為」「その他の行為」の三行為説と②「国事行為」「私的行為」の二行為説の争いがあります。憲法第7条第10号で「儀式を行ふこと」が国事行為として定めてあるのですが、皇室が歴史的に継承してきている皇室祭祀(宮中祭祀)の全てが国事行為としての「儀式」に該当するものではないとされています。
政教分離を原則とする日本国憲法の下では、宮中祭祀は天皇の私的行為とされ、政教分離の原則に反するものではないとされています(なお、国事行為として行われる大喪の礼や即位の礼については政教分離に反するという訴訟が起こったりしました)。
憲法学の学説は、「三行為説(通説)」であれ、「二行為説」であれ、いずれの見解に立ったとしても、宮中祭祀は私的行為に分類されており、政府見解は天皇の行為を国事行為、公的行為、その他の行為に分類した三分説ですが、宮中祭祀を「その他の行為」の中の「純粋に私的なもの」に分類しています。
お正月の天皇の宮中祭祀としての「四方拝」は、天皇陛下及び皇室としての純粋な私的行為であり、法律の規制対象ではないということになります。
新年の早朝、天皇陛下が極寒の中で今年1年の国家の安泰を祈られている、という事実はあまり知られてはいません。私たちも寝不足のまま、1月1日遅めに起きてのんびりと正月を迎えるのではなく、せめて、早起きして初日の出を拝むことから新年を始めたいものです。
年末商戦やクリスマスの慌ただしさを楽しんで過ごし、良い新年をお迎えください。
以 上